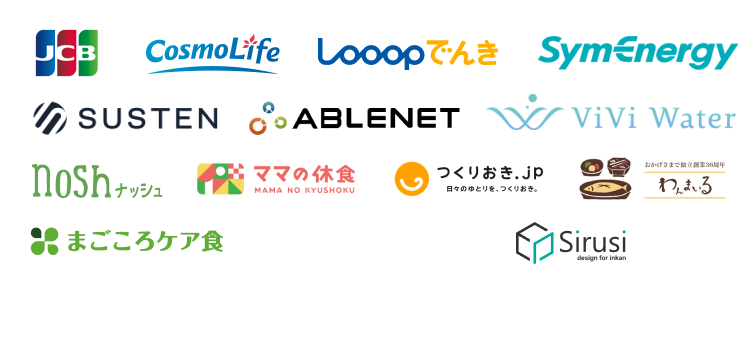-

【はんこプレミアム】「価格の安さ」と「発送の早さ」ならはんこプレミアム
高品質・低価格な印鑑通販サイトとして知られるはんこプレミアム。当編集部は、はんこプレミアムの内部に迫るべくインタビューを実施しました。当ページでは、はんこプレミアムの「おすすめ素材、圧倒的に低価格な理由、評判・口コミ」だけでなく、最新の印鑑業界についても伺いました。 電子化が進み、法人印鑑のニーズが変化? 印鑑定番素材「黒水牛」の品質が劣化してきている? 彫刻機械によって印鑑の値段が大幅に変わる? 上記のような、印鑑業界内部の人のみぞ知る情報満載です。これから印鑑作成を考えている方にはご一読いただきたい内容なので、ぜひ最後までご覧ください。はんこプレミアムってどんな会社?まずは御社の紹介をお願いいたします。はんこプレミアムーはんこプレミアム株式会社と申します。2012年に創業して、最初は印材(印鑑の素材)の卸業者をやっておりました。社長が非常にチャレンジングな人で、印材の卸だけでなく、印鑑の作成もするようになり、その後販売ツールとしてECサイトを立ち上げ今に至ります。御社の「モットー」は何でしょうか。はんこプレミアムー何をするにも「スピード」を重視しています。といいますのも、社長がスピードを重視する人でして。弊社が印鑑の作成を始めたのも、実はスピードが関係しているんです。当時、印鑑を注文してから納品されるまで、1ヶ月もかかっていたんです。 「1ヶ月もお客様をお待たせするなんてありえない」 「弊社ならもっとスピーディーに印鑑をお届けできる」 という想いから、弊社も印鑑の作成を始めました。ですので、弊社は「スピード」を重視しています。ニーズの変化?法人印鑑に人気な素材は「プレミアムウッド」法人印鑑で人気の素材は何になりますか?はんこプレミアムー最近、お客様のニーズが徐々に変わってきているんです。法人のお客様でいうと、 「経費を削減したい」 「使用頻度がそこまで高くない印鑑に関しては、手頃な印鑑が欲しい」 というニーズが増えています。そこで最近は、木材系の素材が人気です。その中でも特に人気な素材が、弊社オリジナルの「プレミアムウッド」。少し前まではチタンが1番人気でしたが、最近はプレミアムウッドがシェアの半分を占めています。価格も安く、耐久性も十分なため非常に人気です。 はんこプレミアムの「プレミアムウッド」木材素材ですと、薩摩本柘も人気な素材かと思うのですが、プレミアムウッドとはどういった点が違いますか?はんこプレミアムープレミアムウッドは樹脂が入っているため、他の木材素材より耐久性が段違いに高いんです。薩摩本柘も適切に使用・保管いただければ長く使い続けられる素材なのですが、適切に使用・保管いただいていないと、少しずつ朱肉の油が印鑑に染み込んでいってしまうんです。油が染み込むと、印鑑が柔らかくなります。適切な力で押印すれば問題ないですが、やはり印鑑を使い慣れていないお客様が多いので、強めの力で押印してしまう。すると、パキッと印鑑が割れてしまうことがあるんです。確かに、押印する機会って多くはないので、適切な力がわからない方も多そうですよね。はんこプレミアムーそうなんです。弊社は事務所の1階で店舗も運営しているのですが、お客様に押印していただくと、グイッと力を込めて押印される方が多いんです。印鑑は軽い力で押印すれば十分なので、誤解されている方も多いなと感じます。そういった意味でも、耐久性の高いプレミアムウッドをおすすめしてますね。 はんこプレミアムの「プレミアムウッド」はこちらから 黒水牛の品質が劣化している?個人実印・銀行印・認印におすすめな印材個人印鑑の人気素材は何になりますか?はんこプレミアムー個人印鑑の人気な素材は、少し前までは定番素材の黒水牛でした。ですが、実は最近の黒水牛の品質があまりよくないんです。少し劣化しているんですよね。黒水牛は保管時の気温に注意しなければいけない素材なのですが、品質が劣化しているために今まで以上に印鑑が変形しやすくなっています。今まで以上にお手入れを念入りにしないといけないので、今は法人印鑑と同様プレミアムウッドをおすすめしています。プレミアムウッドは樹脂が入っているため、変形のリスクも少なく、安定している素材です。実印・銀行印・認印と、印鑑の種類ごとにおすすめの素材は変わりますか?はんこプレミアムー変わります。それぞれおすすめの素材は以下になります。 おすすめの素材 実印:プレミアムウッド 銀行印:チタン 認印:アカネ 実印はあまり使用頻度が高くないので、「プレミアムウッド」がおすすめです。一方、銀行印は使用頻度が実印より高く、印影変形によるリスクも高い印鑑なので「チタン」がおすすめです。認印は安いもので構わないので「アカネ」を選ばれるといいと思います。 銀行印におすすめの「チタン印鑑」はんこプレミアムが選ばれる理由は「価格の安さ」と「発送の早さ」はんこプレミアム様の強みは何でしょうか?はんこプレミアムー価格の安さと発送の早さです。この2つは、かなりこだわっていますね。まず価格の安さに関していうと、値上げをしている印鑑通販サイトが多い中で、弊社は物によっては値下げをしています。印材の卸をしているのもありますが、航空輸送から海上輸送に変更することでさらなるコストカットを実現しています。「高品質な印鑑を低価格でお客様にお届けする」という想いを大事にしているので、価格の安さにはこだわっています。価格の維持だけでなく、値下げまで可能にしているのは大変な企業努力ですね。発送の早さに関してはどうでしょうか。はんこプレミアムー14時までのご注文で、印鑑を当日出荷しています。弊社のモットーとも重なりますが、やはり「スピード」を大事にしています。印鑑は急に必要になるお客様も多いので、当日出荷サービスは大変好評のサービスです。また、当日出荷サービスの料金を300円という低価格に抑えられているのも、弊社の強みです。はんこプレミアムの水晶・パワーストーン印鑑はなぜ安い?自社改良の彫刻機械に秘密がある水晶・パワーストーン系の素材の品揃えが豊富だと思いますが、なぜ水晶・パワーストーン系の印鑑に力を入れているのでしょうか?はんこプレミアムーそもそも水晶・パワーストーン印鑑を始めた理由は、お客様のアイディアなんです。最初は、黒水牛など印鑑の定番素材しか販売していなかったのですが、女性のお客様からもっと「かわいい印鑑」「カラフルな印鑑」の要望を多くいただきました。要望を満たす印材を探す中で、水晶・パワーストーン印鑑にたどり着いたんです。人気の高そうなローズクォーツ・ラピスラズリ・タイガーアイの3種類から販売を始めて、すぐに注文が殺到しました。 ローズクォーツ ラピスラズリ タイガーアイはんこプレミアム様は水晶・パワーストーン印鑑の価格も、他の印鑑通販サイトと比較してとても安いですよね。安く販売できる理由はなんでしょうか。 ローズクォーツ ラピスラズリ タイガーアイ はんこプレミアム 9,000円 8,000円 11,000円 ハンコマン 31,680円 45,100円 45,100円 15.0mmの税込価格 編集部補足 「ハンコマンの印鑑価格自体がそもそも高いのでは?」と思われた方のために、水晶系印鑑以外の価格の比較もしてみましょう。 薩摩本柘 黒水牛 はんこプレミアム 3,280円 4,280円 ハンコマン 4,510円 4,600円 15.0mmの税込価格はんこプレミアムの価格が安いことには変わりませんが、水晶系印鑑ほどの価格差はないことがわかります。はんこプレミアムの水晶・パワーストーン印鑑がいかに安いかおわかりいただけたかと思います。はんこプレミアムーチタン印鑑を安く販売できている理由と同じなのですが、水晶・パワーストーンを削るレーザー(機械)を、自社で改良しているためです。一般的なレーザーですと1日に数本しか彫れないんですが、弊社では改良に改良を重ね、一般的なレーザーの2倍以上の速さで彫ることができるようになったんです。印鑑の作成に時間がかからないので、その分お安く販売できています。実は、弊社では自社で改良している彫刻機械しか使用していません。定番素材だけでなく、チタンや水晶・パワーストーンに至るまで、すべて自社改良の彫刻機械を使用して生産を最適化しています。弊社の強みで「価格の安さ」をあげさせていただきましたが、彫刻機械の改良により価格を安くすることにも成功しています。はんこプレミアム様の価格の安さには、そういった背景もあったのですね。水晶・パワーストーン印鑑の取扱時の注意点などはございますか。はんこプレミアムーやはり割れやすい素材なので、落とさないように注意していただきたいです。以前、パワーストーン印鑑をご購入いただいたお客様が、印鑑が手元に届いた際にうれしくて手が震えて落としてしまったことがあったんです。弊社からも、ご購入いただいたお客様には「割れやすいのでご注意ください」とお伝えしているのですが、水晶・パワーストーン印鑑は割れやすいので落とさないように注意してお使いいただきたいです。 コラム:琥珀樹脂の取り扱いにも注意! 女性に人気の素材に「琥珀樹脂」があります。琥珀樹脂も、水晶・パワーストーン印鑑と同様割れやすい素材になります。そのきれいな見た目から女性人気が高い琥珀樹脂ですが、取扱にはご注意くださいね。はんこプレミアムの評判・口コミは?実際に購入した方の評判や口コミは、どういったものが多いでしょうか?はんこプレミアムーやはり圧倒的に「安くて早い」という評判・口コミが多いです。弊社の強みとしている2つ「価格の安さ」「発送の早さ」をお客様にも評価していただいている印象です。今後はどんな印鑑を販売していきたいですか?はんこプレミアムー実印・銀行印・認印におすすめの素材のところでも申し上げましたが、最近は印鑑へのニーズも変化してきています。「押印機会が多くないので、できるだけ安いものがいい」といった風にですね。ですので、ニーズに応えられるように「実印・銀行印・認印」でおすすめの素材を分ける、それぞれ別の素材で実印・銀行印・認印の3点セットを用意するなどを考えています。それぞれ別の素材で作成すると、見た目で印鑑を判別できるメリットもありますね。注文前に一度電話で確認を!通販サイトでの印鑑購入の注意点についてネット通販サイトで印鑑を購入する際に、気をつけた方が良い点はありますか?はんこプレミアムー印鑑のご注文前に、一度電話で入力内容が正しいか、問題なく作成できるかご確認されることをおすすめします。やはり、印鑑は何度も購入するものではないので、注文の仕方がわからないお客様も多いですよね。弊社であった例ですと、 「最大彫刻文字数が2文字のサイズの印鑑をフルネームで注文される」 「会社名が1文字抜けている」 などがあります。こういったことがあると、お客様の希望の納期に間に合わなくなることもあります。印鑑は急ぎで注文される方が多いので、面倒かもしれませんが、一度店舗に電話でご確認されることをおすすめします。3分程度でご案内も終わります。ありがとうございます。最後に、読者の方へ一言お願いいたしますはんこプレミアムーお客様に今まで以上にご愛用いただけるよう、高品質な印鑑を低価格でスピーディーに良いサービスを提供していきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 低価格・高品質を実現! はんこプレミアム 公式サイトはこちら -

【ハンコマン】大手印鑑通販サイトハンコマンの魅力に迫る!人気の商品・素材など紹介
印鑑業界大手のネット通販サイト「ハンコマン」。当編集部は、ハンコマンの魅力をお伝えするべくインタビューを実施。新型コロナウイルスの影響により印鑑の需要が少しずつ減少している中、人気ネット印鑑通販サイトとして知られるハンコマンの魅力に迫ります。 個人・法人印鑑に人気の商品・素材は? ハンコマンの評判・口コミ ネット通販サイトでの印鑑購入の注意点 インタビューでは、ハンコマンの特徴のみならず、印鑑購入の際に知っておきたいポイントも解説しています。当ページの内容を参考に、納得のいく印鑑を作成してくださいね。ハンコマンはどんなネット印鑑通販サイト?編集部ーまずは御社の紹介をお願いいたします。ハンコマンー真通株式会社と申します。主に通販サイト「ハンコマン」を運営し、印鑑や便利スタンプ等を販売しております。ハンコマンの強みはどういった点でしょうか。ハンコマンー当サービスは、伝統ある印鑑屋さんのノウハウを10年以上に渡り引継ぐ一方、時代に合ったサービスや商品を提供できるよう商品開発も含めて日々取り組んでいます。蓄積したノウハウを最大限に活かしながら、ネット通販の利便性を追求したUIの改善からウェブサービスが苦手なお客様に対しての細かいオペレーションに至るまで全力で取り組んでいます。ハンコマンの人気の商品・素材は?個人・法人印鑑それぞれ紹介個人と法人、それぞれ人気の商品・素材はどちらでしょうか。ハンコマンー個人様と法人様で人気がある商品・素材ですが、「黒水牛」という素材となります。見た目が黒一色という事と、昔から強度や物持ちの良さが有名な事もあり、人気の商品となります。黒水牛ばかりが人気というわけではなく、最近だと個人・法人ともに琥珀の人気も上がってきており、在庫が間に合わない事もあるほどご注文が重なったりもします。ハンコマンの一押し商品は何になりますか。ハンコマンーそれぞれの印材に特徴やおすすめのポイントがあり、一概にどれがおすすめというのは申し上げづらいですが、下記を参考になさってください。 「とにかく値段」重視の方におすすめな素材 アカネ 薩摩本柘 ※リーズナブルな価格帯となっており、薩摩本柘に関しては柘の中でも高級柘を使用しておりまして捺印のしやすさや持った時の馴染みやすさで一押し商品となります。 「値段」「耐久性」重視の方におすすめな素材 彩樺 楓 黒水牛 ※お値段は若干アカネや薩摩本柘より上がってしまいますが、素材自体の強度があり末永くご使用できる素材となっております。滅多に使わない実印だからこそ使用時に「欠け・変形」が起きにくい素材として一押しです。 「耐久性」「高級感」重視の方におすすめな素材 チタン 琥珀 屋久杉 ※価格は上がりますが、物は一級品となります。実印や銀行印等は生活の中で重要な役割がございます。実印は自分を証明する印鑑=自分自身と言われてきたほど人生においても重要な印鑑です。チタンについては、欠けない・サビないという特徴をあてはめ強い人生にする!という意味を込めて購入される方もおられます。一生ものの強い印鑑として一押し素材となります。ハンコマンの評判・口コミはどういうものが多い?実際に印鑑を購入された方の口コミ・評判はどういった内容が多いでしょうか。ハンコマンー弊社の口コミや評判で1番多いのは、やはり注文から発送までの速度です。印鑑を彫って発送するという物理的な事はありますが、お急ぎの内容に関しましては毎日全力でご対応させて頂いておりますので、ご購入者様からの評価をいただいていると感じております。ネット通販サイトでの印鑑購入の注意点についてネット通販サイトでの印鑑購入において、気をつけた方が良い点はありますでしょうか。ハンコマンー基本的にどのサイト様も同じですが、個人情報の取り扱いについては利用者様より運営側が何より重要なものとしておりますので気にせずご利用いただけます。また、価格が安いというだけでモールショップサイトで安易に購入する事はあまりおすすめできない場合があります。価格が低すぎると粗悪品だったり、後々トラブルになりかねないのでご購入時はレビューや運営会社などをご覧いただき判断してください。電子契約への重要が高まる中、この状況をどう捉えているかコロナウイルスの影響もあり電子契約への需要が高まっているかと思いますが、この状況をどのように捉えておりますでしょうか。ハンコマンーいくら歴史ある日本の伝統文化で有ろうと世界情勢や時代の流れに逆らっていては本末転倒です。法の下、印鑑が必要でなくなる日も将来必ず訪れるでしょう。大切なのは皆が安心して個人の生活や法人の資本を守っていく事にあります。その手段の1つであった印鑑という存在も時代と共に変わっていくのは必然であると考えます。ご指摘のように、コロナ禍において電子契約の需要が増え印鑑の需要は減少しております。当社としても早々に電子印鑑のサービスを始め、現在において継続的にご好評をいただいております。さらには今まであまり注目されなかった当社オリジナルのサービス「オンラインプレビュー」は独自開発したもので、印影を自動作成し事前に出来上がりを確認するツールなのですが、コロナ禍においてアクセスが急上昇し需要の高さを実感しております。来店しなくてもデザインの確認が出来ますし、ネットで注文した後のやり取りも無くて済みます。結果、効率よく印鑑の受注から作成、発送がスムーズに構築できていることは大きいと思います。今は個人印鑑と角印のみですが法人実印やデータ入稿が可能がゴム印のオンラインプレビューを開発中でございます。 「個人印影」自動作成はこちら「角印印影」自動作成はこちら今後のハンコ文化について今後のハンコ文化はどのようになっていくとお考えでしょうか。またハンコ文化への想いがあればお伺いできますと幸いです。ハンコマンー先ほどのコロナ需要の返答に重複しますが、実用としてのハンコは減少を辿りいずれ無くなる流れとなるでしょう。こればかりはルールに従うしかありません。そもそもがコロナ禍で働き方が変わり、1人1人がそれぞれの生活を求め選択することがスタンダードとなり価値観や生き方など多様化する社会においては、当然サービスや商品も変化していかなければ生き残っていけないと考えます。今後販売予定の印鑑について今後はどのような印鑑を販売していきたいとお考えでしょうか。ハンコマンー今までのサイト構成やプロモーション方法、プロダクト全て見直す必要があります。「日本文化」としてハンコを世界にどうPRするかという課題に取り組んでいます。プロモーションにおいてはSEOにおける対策はもちろん、モール、SNSを積極活用しています。また、2022年10月に合わせて、ヤフーショッピングとLINEショッピングの強化を図りました。SNSショッピングでは主に当社サービス「印影プレビュー」を活かしたサービスを目指しております。ハンコマンYahoo!ショッピング:Yahoo!ショッピングはこちらハンコマンinstagram:@hankoman_instaハンコマンから読者のみなさまへ一言最後に、読者の方へ一言お願いいたします。ハンコマンー最後までご覧いただき心より感謝申し上げます。「印鑑=時代遅れ」という発想から、これからを生きる私たちがどう向き合うべきかを考えインタビューを受けさせていただきました。時代はデジタルがメインとなることは間違いありません。6Gやメタバースの未来が私たちを待っています。ただ実際問題、実績のあるSE(システムエンジニア)の不足により経験を十分に積んでいないSE人材がキャパ以上の仕事をさせられ、リスクヘッジに対応しきれていないという現状も良く伺います。ウイルスにより情報漏洩のあった企業(特に中堅企業)の話を聞くことがずいぶんと増えました。ならば原点回帰で印鑑が安全、、とも言い難いこの時代においてすべては自己責任というのも愛の無いようにも感じられます。私たちは印鑑を販売していますが固定概念にとらわれることなく、どのようなサービスが求められているのか、またどんなアイデアなら喜んでもらえるのか日々葛藤しています。印鑑が将来どのような形で残るかそれとも消失してしまうかは分かりませんが、少なくともより良いサービス体験やプロダクトをご提供できるよう、日々尽力して参りたいという思いで過ごしております。どうもありがとうございました。 即日発送が可能! ハンコマン 公式サイトはこちら -

【シン・エナジー】シン・エナジーだからできる“選べる自由”:エネルギーで未来をつくる
電気料金の高騰が続く中、新電力への切り替えを検討している方は多いではないだろうか。しかし、「新電力は本当に電気料金が安くなるのか?」という疑問や、料金体系やプラン選びに不安を感じている人もいるだろう。そこで、今回は再生可能エネルギーの開発も手掛けながら電力販売を行う「シン・エナジー」に注目。プランの魅力から電気料金の仕組み、電気を効率よく使うためのコツなどについて話を伺った。取材日:2024年10月4日 当記事は成果報酬型の広告モデルを採用しています。電力の地産地消を推進するサステイナブルな電力会社 シン・エナジー提供まずは、会社概要をお伺いできますか?当社は、1996年に、町の電気工事会社として事業活動をスタートしました。当時は主に省エネ関係の工事を手がけ、お客様に政府の補助金を活用した省エネ対策の提案などを行なってきたんです。その後、2012年から再生可能エネルギーの発電事業に着手し、2015年から電力販売事業を本格的に拡大。2018年に現在の「シン・エナジー」へと社名を変え、電力の創出から販売を総合的に手掛けています。 シン・エナジー提供現在、太陽光をはじめ、バイオマス、バイオガス、小水力、地熱、風力などさまざまな再生可能エネルギーの開発に取り組んでいます。また、電力販売では、個人の家庭や飲食店舗、大規模工場まで、合わせて10万件以上のご利用をいただいています。当社は社員140人規模ながら、多様な再生可能エネルギーを全国開発し、あらゆる施設への電力販売まで手掛けている企業として、業界内でも評価されています。 シン・エナジー提供初期費用や解約金は0円!生活スタイルに合わせて選べるプランが魅力 シン・エナジー提供 一般家庭向けの電気プランの特徴を教えてください。当社の電力プランの大きな特徴は、お客様がご自身の生活スタイルに合わせて、柔軟にプランが選べる点です。多くの電力会社では、そもそもプランが一つしかないとか、プランはいくつかあるものの、後から変更するために手間取ることや、結局最適なプランを選べているのかわからない事態も見受けられるのが現状です。そのため当社では、3つのプランを用意しています。結婚、子育て、老後など、人生のイベントや段階ごとで変わる生活スタイルの変化で、電気の使い方も変わりますよね。そういった生活スタイルの変化にも寄り添うプランをご用意しており、お客様は、毎月プランの見直しができる機能をご利用いただけます。例えば、共働きの家庭で昼間はあまり電気を使わず夜だけ使用する場合、お子さまが生まれて日中に電気を使うようになった場合、お子さまが成長して家を出られて電気を多く使わなくなった場合など、電気の使用時間や使用時期、使用量に合わせたプランを提供しています。一度当社のプランに加入いただければ、そのときの状況に合わせてお得なプランに切り替えることができ、電力会社自体を見直す手間がないところがメリットです。料金体系に関するこだわりやポイントは?やはり電気料金の安さです。お客様にシン・エナジーを選んでよかったと感じていただけるような価格設定を設定しています。また、気軽にお試しいただけるよう初期費用や解約金は0円にしているのが特徴です。 【Pro Tips】 電力会社の中には、一年縛りなどの契約期間の縛りや、解約金が設定されている電力会社もあります。 このような契約期間の縛りがなく、初期費用や解約金がかからないのは非常に親切な料金設定だと言えるでしょう。 引用:シン・エナジー公式サイト正直なところ、料金に関しては悩むこともありました。キャンペーンを利用してすぐの解約が多いこと、料金が安い分広告に使える予算が限られていることも課題です。しかし、そのような状態であっても常にお客様重視の姿勢を大切にしてきました。 【Pro Tips】 電気料金が安いと電力会社の利益率も低くなるため、広告料は自ずと減ります。 広告費が少ないということは、メディア露出が少なくなりやすく、加入者数も増加しづらい傾向があります。 そのような中で、シン・エナジーの契約件数は、10万件を超えています。この契約件数は、決して少なくない数字です。このような結果は、お客様を重視している企業努力の賜物だと言えるでしょう。 お客様が活用できる機能やメニューには、どのようなものがありますか?ライフスタイルに合わせたプランを提案するために、「ぴったりプラン診断」というサービスを提供しているんです。使用実績に応じて最も安い最適なプランを通知しています。また、マイページでは月別、日別、時間帯別の電気の使用状況を確認することができ、夜に多くの電気を使っているとか、昼と夜にバランスよく使っているなどの使用状況がわかる仕様となっているんです。 シン・エナジー提供さらに、マイページ内で省エネや節電に関するコラム、省エネ機器導入支援制度の紹介などを行っており、電気料金を安くするための具体的な提案や省エネの知識をご提供しています。このようにお客様への省エネ等に関するサービスが評価され、経済産業省が実施している「省エネコミュニケーションランキング」において、最大評価である5つ星をいただきました。 【Pro Tips】 全国で700社以上ある電力会社の中で星5つを獲得しているのはわずか30社しかありません。星5つという最大評価を獲得しているのは、非凡な成果だと言えるでしょう。 シン・エナジー提供ありがとうございます。御社が電力プランを展開する中で意識されていることを教えてください。環境の変化にあわせて、常にサービスを見直し続けなければ、電気を最適に利用することができないことです。電力販売事業を開始した当初に、電気を夜に使うお客様向けの「【夜】生活フィットプラン」をリリースしました。当時、全国的に夜間は電気の使用量が少なく、電気が余りがちだったために、夜間の電気料金を安く提供したものでした。しかし、この数年で太陽光発電の普及により昼間の電力供給が増え、逆に昼間の電気があまりがちになってきています。当社も再生可能エネルギーの開発事業者として、昼間に発電した電気を無駄にしたくないという思いから、2020年に「【昼】生活フィットプラン」という昼間の電気代が安いプランをリリースしました。 シン・エナジー提供 エリアと個人か法人か選ぶと上記が表示されます電気を使用する時間帯にとって電気料金が異なるという仕組みは、一見して難しいかもしれませんが、ぜひ認知を広めていきたいと思っています。それによってお客様はお得に電気を使えるようになりますし、限りある大切なエネルギーを効率的に使えるようになります。お客様からの反響や印象に残っているエピソードがあれば教えてください。「生活フィットプラン」を利用されている方からは、例えば、食事の準備や洗濯、掃除など、電力を多く使う家事を、お昼の安い時間帯に行うことで節約できているという声をよく聞きます。電力市場の仕組みを理解して、もっとお得に 引用:シン・エナジー公式サイト電力業界の現状や課題には、どのようなものがありますか?私たちも元々は大手電力会社のプランから、単純に単価だけを安くしたプランを提供していました。しかし、2022年のロシア・ウクライナ情勢の影響などにより燃料価格や電気代が高騰したことを受け、多くの新電力会社が燃料費調整額の請求方法や燃料費を調整する料金体系を大幅に見直し、当社もその流れに沿って、電力市場価格を参照する現在の料金体系に変更しました。 【Pro Tips】 燃料費調整額とは、燃料価格の変動を電気代に反映させた料金で、燃料の需要が高い、もしくは供給が低い場合に高くなります。 ロシア・ウクライナ情勢当初には需給バランスの乱れによって燃料費調整額が高騰し、電気代が高くなりました。 ただ、この燃料費調整額について少し複雑で、理解も難しい部分であると認識しています。料金体系を変更した際にお客様にアナウンスしたときも、ほとんど反応はありませんでした。拠点がいくつもあるような法人さまで、高圧や特別高圧の電力契約を担当している方であれば非常に深い知識を持っておられるのですが、まだまだ一般のお客様には電力市場の存在が浸透した程度なのが現状です。地域電力も苦境に立ち、新規受付を一時的にストップしたり、市場連動メニューを提供せざるを得ない時期があったので、それを経験した法人の電力契約ご担当者は、電力市場や料金メカニズムに対してすごく詳しいんです。お客様にとっては、なかなかわかりにくい領域ですよね。御社がいくら地球や地域の環境に貢献していても、価格が上がったときのネガティブな印象だけが残ってしまうこともあるかもしれないですね。そうなんです。実際に最近、電力市場の影響で料金が高くなった月があったのですが、そのときはお客様から「料金が高くなった」というお問い合わせをいただきました。しかしそうでない月、料金が安くなったときは反応がないんです。なぜ安くなったのかを深く考えることは、あまりないのかもしれません。お客様が電力市場を知るために行っているサービスや取り組みはありますか?法人のお客様向けには、市場価格の変動やその要因をつかむためのレポートを3ヶ月に1回配信し、担当者からの説明も適宜行っています。そのため弊社からは、需要と供給のバランスや燃料価格の動向、今後の価格の見通しをお知らせする―― またお客様が、電力に関する知識をつけ、ご自身で判断できるようになるためのサポート体制の確立にも力を入れていきます。しかし、一般家庭のお客様に対しては、担当者がお客様ごとにご説明できる体制をとれておらず、このような情報提供・ご説明が難しいというのが現状です。なるほど、電気料金の仕組みを理解することは大事ですね。実は、昨年「生活フィットプラン」の料金体系を改定し、夕方の電気料金を高く設定しました。夕方の電力料金を高くした理由は、お客様に「この時間帯はできるだけ電力の使用を控えてほしい」というメッセージを伝えるためでもあります。全国的に、夕方は太陽光発電の供給が減少します。その代わりに主に火力発電等を稼働させて供給量が調整されています。この供給量の調整は、発電所を稼働させたり、停止させたりする際に生まれるコストにより、電気料金がどうしても高くなってしまいます。また、火力発電はCO2の排出量が多いため、この時間帯は環境への負荷が増えることも理由の一つです。電力を使用するタイミングを昼間や夜間にシフトしたり、給湯器や蓄電池をお持ちであればぜひご活用いただければと思います。電力に対するリテラシーを高め、家計にも環境にも配慮した行動を! 引用:シン・エナジー公式サイト今後、挑戦したいことはありますか?お客様が、電力に対するリテラシーや知識を高めるための情報発信をしていきたいと考えています。価格だけに焦点を当てるのではなく、なぜこの時間帯に電力を使ってほしいのか、なぜこの時間帯は控えてほしいのか―― という理由を理解していただき、ご自身の電力の使い方をより深く考え、行動していただくことが必要だと感じています。それが結果的に、地球にやさしい行動にもつながります。そのためにも、お客様が生活を見直すきっかけとなるようなメッセージを伝えていきたいと思っています。地球環境の問題も深刻化する中で、一人ひとりがリテラシーを高めることが求められますね。電気会社の見直しを考えている方にメッセージをお願いします。解約金や契約期間に縛りがなく、月ごとにプランを変更できる点は、迷っている方にとって安心材料になるはずです。「ぴったりプラン診断」でご自身に合ったプランを検討することもできるので、最初の1年間は手探りになってしまうかもしれませんが、2年目以降は楽しみながらプランを見直していただければと思います。当社のサービスは、お客様が安心して切り替えていただけるような内容だと自負しておりますし、3社分に匹敵するくらいの料金プランを取り揃えています。もし迷っているのであれば、悩むよりもひとまず試しに切り替えてみてはいかがでしょうか。 シン・エナジー 公式サイトはこちら シン・エナジーの解説記事を読む -

【ママの休食】ママと家族の未来を支える食事—ママの休食の挑戦とその先
疲労と不安に満ちた産前・産後の日々。その中で、ママたちは自らの健康と赤ちゃんの成長のために奮闘している。「ママの休食」は、そんな彼女たちに寄り添い、手軽に栄養バランスの取れた食事を提供する。本記事では、このサービスの誕生秘話から未来への大胆なビジョンまで、創業者の熱い想いに迫る。そして、現代のママたちの生活をどう変えていくのか、その可能性を探っていく。取材日:2024年10月3日従業員の9割が子育て中のママ!従業員の実体験と思いから生まれた次世代の宅食まずは、御社の概要や提供されているサービスの基本情報について教えてください。当社は2021年に設立され、個人向けには「ママの休食」ブランドによる宅食サービスを提供し、法人向けには企業の従業員の健康管理と働きやすさをサポートする社食サービスを展開しています。さらに、食品開発支援や血液の栄養状態分析とアドバイスを行う栄養解析サービスなど、多岐にわたる事業を手がけているんです。従業員の9割が子育て中の母親であり、全員が女性という独自の特徴がある会社となっています。「ママの休食」サービスの誕生背景について、教えてください。「ママの休食」サービスは、私自身の経験から生まれたんです。事業構想の段階で、健康課題が大きく、かつ健康に対して前向きに取り組むターゲット層を模索していました。管理栄養士としての知識を持ち、前職では女性の月経管理アプリ「ルナルナ」を開発する会社に勤務していた経験から、かねてより女性のヘルスケアには深い関心を持っていたんです。そして、妊娠する時期は健康に目覚めるとても大切な時だと気づきました。この時期にうまく働きかければ、子どもの小さい頃からの食事、そして家族全員の健康的な生活につながると考えました。大人になってからの食育は難しく、子どもの頃から健康的な生活が普通になれば、長い目で見てとても良いことだと考え、妊娠中や子育て中のお母さんたちのための「ママの休食」サービスを始めることにしたんです。そうしたら、「ママの休食」ファンの子育て中のお母さんたちが集まってきて、仲間として、このサービスを支えてくれるようになりました。働くスタッフが出産や育児など、お客さまと同じ経験をしているので、お客さまの気持ちがよくわかり、私たちのサービスにつながっています。 引用:ママの休食 公式ホームページ妊娠期のお母様に寄り添ったサービスを展開する中で感じる社会的な課題は何でしょうか?管理栄養士として妊婦の栄養相談に携わった経験から、妊娠前からの体調管理の重要性を認識しました。日本の健康啓発には課題があり、特に妊娠初期の栄養管理が赤ちゃんの発達に極めて重要であることが十分に理解されていません。妊娠に気づく頃には既に胎児の重要な器官形成が始まっているため、妊娠中期からの栄養管理では遅すぎます。この考え方は「*プレコンセプションケア」として、昨今特に助産師の間で注目されています。2021年、15年ぶりに妊婦の食生活指針が更新され、栄養管理の重要性が再認識されました。多くの研究で、出生時の低体重が将来の健康リスクに繋がることが示されており、「小さく産んで大きく育てる」という従来の考え方の誤りが明らかになっています。日本では妊婦への公的な栄養教育も不十分なため、『10人に1人が低体重児』という先進国の中では特に高い数字を出しているんです。現代の妊婦たちが抱える問題は、SNSの影響も大きいと、私自身は考えています。15年ぶりに妊婦のための食生活指針が改定された背景の一つに、若い女性の「やせすぎ」の問題があります。細身の有名人やインフルエンサーへの憧れから、無理なダイエットをする女性が少なくありません。やせすぎの状態で妊娠すると、妊娠中に必要な栄養が十分に取れず、体重があまり増えないことが、妊婦さんや赤ちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、現在は体重増加の推奨値が引き上げられ、むしろ少し多めに増えることが推奨されています。加えて、妊婦向けの宅食サービスが増えている一方で、必要な栄養素が不足している商品も存在し、「妊婦におすすめ」とされているものもあります。手軽さは魅力ですが、正しい栄養情報の提供も必要です。正しい知識をインプットした後には、「分かってはいるけれど、できない!」といった行動の課題が出てくるので、そのような時に具体的なソリューションとして私たちのサービスを活用してほしいです。 *プレコンセプションケア 女性やカップルを対象とした将来の妊娠のための健康管理のこと。不安な時期だからこそ寄り添いたい。「休む」×「食事」=「休食」への思い「ママの休食」の会員になると無料で使える公式LINE限定サービス「ママ休ほけんしつ」について、教えてください。ママ向けの栄養相談「ママ休ほけんしつ」は、妊娠期間や産前産後も含めて、いつでも何度でも利用できるサービスです。この相談では、体重が増えない悩みから増えすぎる心配まで、個々の状況に応じた多様な問題に対応しており、妊娠中の方にも多く利用されています。妊婦向け栄養相談で私たちが特に強調しているのは、体重管理の本当の目的です。単に体重を気にするのではなく、赤ちゃんの健康的な成長のために管理することが大切なのです。栄養相談では、体重はゴールではなくプロセスの一部だと説明しており、エコー検査も合わせて赤ちゃんの成長を確認しながら、体重管理をおこなってほしいことを伝えています。実は、妊婦さんの栄養管理は、アスリートや持病のある方と同じように、個別の対応が基本です。「ママ休ほけんしつ」は、妊婦の皆様が安心して相談できる場所となることを目指しています。ありがとうございます。「ママの休食」のネーミングにはどのような思いが込められていますか?当初は、妊婦さんの栄養管理や健康課題に焦点を当てることで、妊娠をきっかけに高まる健康意識に訴えかけられると考えていたんです。妊婦さんが抱える最大の課題は何かを探るため、様々なリサーチを行った結果、栄養以前の問題として、時間的余裕の不足が浮かび上がりました。共働きの増加やつわりの影響で、多くの妊婦さんが食事について考える余裕すら持てない状況にあることがわかったのです。この発見から、まず時間的余裕を作ることで、栄養や赤ちゃんのことを考える余裕も生まれるはずだと考えました。そこで、「適切な休養」と「栄養バランスの取れた食事」という二つの要素を組み合わせた「休食(きゅうしょく)」というコンセプトが生まれました。 引用:ママの休食 公式ホームページこのコンセプトは、ブランド名とロゴデザインにも反映されています。ロゴは幾何学模様で表現された栄養素が散りばめられたお弁当箱のような形をしており、よく見ると「休」の字が浮かび上がる仕掛けになっているんです。また、ロゴが旗のような形状をしているのは、次世代の子育てカルチャーを作り上げていくという私たちの意志を表現しています。 引用:ママの休食 公式ホームページ 引用:ママの休食 公式ホームページ自分も体験したからこそ......「ここまで寄り添ってくれる」が生み出す満足感 川端さんとお子さんのお写真「ママの休食」サービスの強みや特徴を教えてください。私自身、管理栄養士としての経験から、「管理栄養士が作った食事」というと「病院食」のようなイメージを持たれがちだと感じております。私たちが目指しているのは、そうした固定観念を覆す商品づくりです。サービス開発のきっかけは、私自身がキャリアと子育ての両立をしようと思った時に「こんなサービスがないと無理だ!」と感じたからです。また、冷凍食品を使うことで「ママとして失格」と思われがちな文化に疑問を感じ、それを変えたいという思いもありました。私たちのサービスの最大の強みは、栄養面での充実です。特に、女性に極めて重要な葉酸や鉄分を1日分の3分の1も摂取できる点が大きな特徴です。 引用:ママの休食 公式ホームページしかし、どんなに健康的な食事でも、美味しくなければ続きません。単なる数字上の健康ではなく、精神的にも楽しめるものでなければならないと考えているため、宅食サービスとして最も重視しているのは「おいしさ」です。添加物に頼らず、様々な野菜や香味野菜、だしなどを使い、見た目も美しく、香りも良く、そして味も深みのある食事を作り上げています。これは、自分の大切な人や妊娠中の自分が毎日食べたいと思えるような食事を提供したいという思いからです。 引用:ママの休食 公式ホームページ多様な食材を使用することで、自然と栄養価も高まり、食物繊維も豊富になり、「美味しさへのこだわり」が栄養バランスの良さにもつながっています。調理方法にもこだわっており、冷凍食品でありながら、煮るタイミングや炒めるタイミングまで細かく指定し、委託工場での製造にも私自身が必ず立ち会っています。例えば、盛り付け方一つとっても、「ぎゅっと詰めすぎるとまずく見えるから、もう少しふんわりと」といった具合に、直接提案を行っています。商品開発では、「おいしさを作るプロ」である元シェフの顧問や元パティシエのスタッフが中心となっています。私の役割は、彼らが作った料理の栄養バランスを確認し、必要に応じて調整することです。 引用:ママの休食 公式ホームページまた、従業員の9割がママであることも、私たちの強みです。従業員の家庭料理をメニューに取り入れたり、新商品の試食会やフィードバック会を綿密に行ったりしています。さらに、私たち独自のサービスの特徴は、実際に妊娠・出産・子育てを経験したスタッフの意見が商品開発に反映されていることです。例えば、私自身が経験したつわりの際の体験が、商品開発に大きな影響を与えました。つわりには、酸味のある食べ物が良いとよく言われることから、トマトやマリネのメニューを商品化したのですが、私は妊娠中酸っぱいものが一切食べられませんでした。つわりの感じ方は人それぞれなのだと実感し、今では酸味にこだわらずに多様な味付けを心がけています。私たちのサービスは単に商品を提供するだけではありません。例えば、つわりの影響で商品が合わなかったお客様に対しても、サービスを終了するのではなく、栄養相談を継続して利用していただくことを勧めています。一度でも商品を購入していただいたお客様は、サービスを停止しても無料で栄養相談を利用できるシステムを設けているんです。また、妊婦さんの辛さを少しでも解消したいという思いから、自社商品だけでなく、他社の優れた商品もセレクトして提供するセレクトショップの運営も行っています。例えば、乳化剤を使用していないアイスクリームなど、私自身が妊娠中に良かったと感じた商品も取り扱っているんです。これは、「ママの休食」サービスを通して、生活全体をどう整えていくかという視点で支援を行いたいという私たちの思いの表れです。サービスを利用された方からのフィードバックや印象に残るエピソードがあれば、教えてください。私たちのサービスで最も嬉しい瞬間は、出産後に料理ができるようになり、サービスを「卒業」されるお客様からの感謝の言葉です。多くの方が、妊娠期間中の不安な時期に私たちのサービスに救われたと仰ってくださいます。また、「野菜嫌いの子供がママの休食の副菜なら喜んで食べます」といった声も多く、家族全体の食生活改善にも貢献できていることを実感します。カスタマーサービス(CS)担当者の多くが子育て中のママであり、お客様に寄り添った対応を心がけているんです。例えば、緊急入院などの予期せぬ事態で、通常のルール外の対応が必要な場合でも、柔軟に対処しています。この「ママの目線」での対応が、単なるサービスへの満足だけでなく、「ここまで寄り添ってくれたから安心して利用できました」というホスピタリティへの高い評価につながっているのでしょう。結果として、クレームはこれまでほとんどなく、お客様からの感謝の声が多く寄せられています。同じママとして、一人の女性として、家事や育児にも生産性を!将来的に挑戦していきたいことや取り組んでいきたい課題を教えてください。私たちの大きな挑戦は、国や企業の支援を活用し、子育て世帯が経済的負担なくサービスを利用できる環境の実現です。現状では、国や自治体の産後ケア支援は主に客観的に見て支援の手が足りていない人を優先しているケースが多いですが、支援の手があったとしても、産後の負担は非常に大きいです。これを改善するため、企業向けの食の福利厚生サービスを通じて、子育て支援の強化や、福利厚生としての両立支援の普及を目指しています。また、産後ケア先進国である韓国や台湾、中国などではすでに一般的なものになっている産後ケアホテルとの提携も重要です。ある産後ケアホテルでは、ママの休食の商品が宿泊中のお食事として提供されています。さらに、より本質的なサービス提供のためには、医療機関との連携も重要です。ある産科病院では、私たちのサービスを入院食として導入していただいています。私が提案するのは、企業、医療機関、行政が一体となって子育て支援に取り組む新しい形です。そのための第一歩として、現状の個人向けのサービスに加え、法人向けのサービスも積極的に展開していきたいと思っています。一方、技術的な課題として解凍ムラの問題があります。一つの食事セットには、主食、主菜、副菜など、形状や素材の異なる様々な食材が含まれ、これらすべてを同じ時間で均等に解凍することは、技術的に大変難しい課題なのです。食材の盛り方や量によっては、厚みのある食材が温まりきらないなどの問題が発生することがあり、食材の盛り付け方や容積にも細心の注意を払う必要があります。解凍ムラの問題も、「手間のない休養をお届けする」という私たちのサービスの本質を見失わないために、取り組んでいきたい課題の一つです。最後に読者の皆様にメッセージをお願いします!現代社会において、ママたちは依然として多くの偏見や制約に直面しており、宅食サービスを利用することに対しても、罪悪感を感じる人が多いのが現状です。「自分が楽をするために買っている」という後ろめたさや、周囲からの批判など、様々なプレッシャーにさらされています。私たちの会社では、このような状況を考慮し、配送箱にサービス名を入れないなどの配慮をしています。しかし、夫や男性パートナーからのプレゼントとして利用される場合では、宅食サービスの利用がポジティブに受け止められるケースがあります。SNSでは、「夫が体調を気遣って注文してくれた」といった投稿が好意的に拡散されています。また、社会には未だに「自炊が最も健康的で栄養バランスが良い」という神話が存在しますが、これは専門家の目から見ても根拠のない考えです。「自炊しないママは“ていねい”ではない」という偏見も、現代の生活スタイルにそぐわないものです。私は、冷凍食品や宅食サービスを上手に活用して家事や生活をこなしていくことが、次世代の子育て世帯にとって重要なスタイルだと考えており、これは、ママに限らず、パパにも当てはまることです。私は、家事や育児といった無償労働にも生産性を求めることが重要だと考えています。効率的に家事をこなし、自分時間や家族時間を確保することは、決して批判されるべきことではありません。私自身、選択的シングルマザーとして、このような課題に日々直面しています。だからこそ、誰もが自由に自分らしく生活を楽しみ、充実させることができる社会を目指したいと強く思っています。私たちは、家庭や仕事、育児において無理なく豊かな時間を過ごせるよう、必要なサポートや選択肢を提供し、柔軟な環境づくりに貢献していきたいと考えています。 ママの休食 公式サイトはこちら ママの休食の解説記事を読む -

【Meals】食卓に変革を: デリッシュキッチンの宅配“Meals(ミールズ)”が届ける、手軽さと健康を両立させた未来の食事
忙しい日常に追われる現代人。栄養と時間の狭間で、毎日の食事に「理想」と「現実」のギャップを感じている人は多い。食のメディア「デリッシュキッチン」から始まったエブリーが、長年の知見を結集し、ついに生み出した新しい食のカタチ。栄養、美味しさ、利便性を兼ね備えた冷凍宅配弁当サービス「Meals(以下:ミールズ)」は、私たちの日常を再定義する。食のプロフェッショナルたちが描く、忙しい現代人の食生活を根本から変える挑戦に迫る。取材日:2024年12月4日レシピメディアから始まった、毎日飽きずに食べられる、罪悪感のない食事体験 引用:ミールズ公式HPミールズが誕生した背景を教えてください。弊社は、もともと「デリッシュキッチン」というレシピメディアから始まった会社です。食に関するコンテンツ配信を中心に、食を通じた課題解決を軸に事業を展開してきました。近年は、「美味しさ」と「健康」をキーワードに事業を拡大しており、ヘルシカというヘルスケアアプリも運営しています。食と健康を結びつけるサービスの展開を模索する中で、宅配弁当事業であるミールズの誕生に至りました。実は、数年前にすでにECへのチャレンジの経験があり、デリッシュキッチンのオリジナルキッチンツールや、お菓子作りキットなどを販売してきたこともあり、食とECに関する知見は蓄積されていました。これらの経験と、食・健康・ECに対する知識とノウハウが、現在のミールズ事業へとつながっています。ミールズの強みや魅力は何ですか?ミールズの強みは、「美味しさ」と「健康」を軸にした商品開発です。特に美味しさへの追求は妥協せず、多くの競合他社がトップシール型(容器とフィルムシール層で剥離する容器)を選ぶ中、真空パックにこだわり続けています。製造コストとしては少々張りますが、冷凍後も水っぽくならず、食材本来の味を損なわない仕上がりが実現されるのです。 真空パックまた、商品化前には必ず試食を重ね、味の質にこだわり、細部までチェックしています。味の追求を軸とした妥協しない姿勢が、私たちの大きな強みです。 引用:ミールズ公式HP 健康面でも、単なるカロリーや糖質管理にとどまらない、より多方面からの栄養アプローチを取っています。他社様の場合では、糖質や塩分のみは配慮しているものの、その他の栄養素は満たしていない商品も存在します。ですが、ミールズでは管理栄養士が監修した栄養バランスを基準に、8つの項目の栄養基準を設けた商品を開発しているんです。一般的に行われている糖質、脂質、塩分、野菜量などの基本的な栄養管理に加えて、エネルギー、タンパク質、糖質、炭水化物、糖質、食塩相当、野菜量、品目数などの項目を設定しています。このような基準を設けることで、栄養基準を総合的にカバーすることが可能です。 引用:ミールズ公式HP「家庭的なおいしさ」の探求の秘密を教えてください。ミールズが目指すのは、毎日の食事を想定した宅配弁当サービスです。デリッシュキッチンを運営する経験から、罪悪感なく、日常的に食べられる味付けにしています。また、デリッシュキッチンは「大根1個で何種類もの料理ができる」といった、少ない材料での多様な料理提案が得意ですが、弁当事業では健康面を考慮し、品目数や栄養バランスをより重視しています。お金を払って購入する弁当だからこそ、「冷蔵庫の中で作れるものではなく、たくさんのものが食べられる」体験を提供したいと考えています。レシピ事業で培ったノウハウを活かしつつ、弁当という新たな形態ならではの価値を模索しています。“あえての真空パック”を採用することで実現した、コンパクト収納と美味しさの両立 引用:ミールズ公式HP冷蔵庫のスペースを圧迫しがちな宅配冷凍食ですが、収納問題へのアプローチや冷蔵庫に収まりやすい商品設計へのこだわりを教えてください。容器設計には徹底的にこだわっています。特に、真空パックを採用し、食材と空気の隙間を最小限に抑えることで、コンパクトで収納しやすい設計を実現しました。 引用:ミールズ公式HP従来のトップシール型と比較して、私たちの容器は非常に薄く、冷凍庫への収納に適しています。しかし、この薄さゆえに、料理の盛り付けには高度な技術が必要です。例えば、ロールキャベツの場合、理想的にはソースをかけたり、下に何かを敷いたりしたいところですが、容器の制約により、そうした細かい盛り付けが難しくなります。食材の配置や盛り付けは、電子レンジでの加熱時間や火の通り具合に大きく影響するため、何度も試作と実験を繰り返してますね。具体的には、様々な配置パターンを試し、レンジで加熱した際に全体に均一に火が通るよう、細心の注意を払っています。さらに、レンジの連続使用による加熱むらも考慮し、ワット数の調整なども行っています。容器は石灰でできており、燃えるゴミとして簡単に処分できます。これにより、環境に優しいだけでなく、料理の後片付けも日常の調理と同じくらい簡単になります。美味しさ、使いやすさ、環境への配慮を兼ね備えた冷凍食品パッケージを創り上げることを目標に、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら、常に改善を続けています。管理栄養士の監修により、美味しさと栄養バランスにもこだわったミールズの宅配弁当。 イメージ画像管理栄養士との協力体制はどのように形成され、どのような影響を与えていますか?ミールズのメニュー開発は、OEM先の管理栄養士と自社の管理栄養士が緊密に連携する、徹底的な試食プロセスを特徴としています。新メニュー開発には3ヶ月から1年以上を要することもありますが、それは試食を何度も重ねることで、より良い商品を追求しているためです。初期段階では金額や取引先の制約を考慮しつつ、最終的にはユーザーに喜んでもらえる商品を目指して、味や栄養バランス、食感など、何度も微調整を行っています。ミールズのメインターゲット層を教えてください。あえて絞ってはいないのですが、結果として40代以上の女性を中心に支持されています。サービス開始当初は、ターゲット層を明確に定めず、オールターゲットでスタートしたのですが、ある程度ユーザー数が蓄積したところでアンケートを取ってみると、40代~60代の方の購入比率が高いことがわかりました。小学生以上のお子様がいる家庭や、子どもと同居していない50代以上の1人もしくは2人暮らしの世帯が中心です。これは、私たちの商品設計、特に栄養バランスや使いやすさが、40代~60代の年齢層のニーズにぴったり合致したためだと考えています。コロナ禍以降に改めてサービスを展開する際に、苦労されたポイントや注力されたポイント、消費者のニーズの変化はありましたか?コロナ禍、特にサービス初期は、プロモーション費をかければある程度の新規顧客を獲得できましたが、継続率の低さが課題でした。そこで、この期間の顧客からのフィードバックを真摯に受け止め、最も多かった「味」への改善に集中的に取り組みました。味の改善により、顧客の継続率が徐々に上がり始め、サービスの質を高めることの重要性を実感したのです。 引用:ミールズ公式HPそして、当初は「おまかせコース」という独自のサービスモデルのみを展開していました。具体的には、食数と配送サイクルのみ指定すれば、毎回異なるメニューが自動的に届くスタイルです。そのため、顧客がマイページを操作する必要がほとんどありませんでした。しかし現在は、若い世代を中心に、自分でメニューを選択したいというユーザーの声も多かったため、2024年8月からメニュー選択機能をリリースし、顧客体験の改善に努めています。より良いサービス提供を目指し、常にユーザーの声に耳を傾け、改善を続けています。サービス開発の過程で、最も難しかったことや克服した課題は何でしたか?サービス開発における最大の課題は、栄養バランスを考慮したメニュー作りの複雑さでした。糖質、塩分、カロリーなど2〜3の栄養要素を調整することは比較的容易でしたが、品目数、タンパク質、野菜の量などを加えると、途端にメニュー開発の難易度が高くなりました。特に、1つの主菜に対して3つの副菜を用意し、それぞれに十分なボリュームを持たせることで、メニュー開発のプロセスはさらに複雑になります。最近、ロールキャベツ、エビクリームコロッケ、水餃子の3つの新メニューをリリースしました。これらは栄養基準を満たしつつ、やや「ジャンク」な印象のある料理で、ユーザーから予想以上に好評を博したのです。この経験から、栄養素の調整だけでなく、ユーザーの期待や満足感を考慮することの重要性を学んだのです。「Meals(ミールズ)」は人の健康をサポートし、食体験を豊かにするツール。 イメージ画像激化する宅配食の中で、どのような位置を確立していきたいですか?私たちの目標は、デリッシュキッチンやヘルシカとも連携した包括的な健康サポートエコシステムを構築することです。ミールズだけでなく、デリッシュキッチン、ヘルシカなど、エブリーが運営する各サービスを連携させ、栄養管理から食事提供、健康管理までをシームレスに行えるプラットフォームを目指しています。現在、デリッシュキッチンは既に一定のユーザー規模を持っていますが、ミールズ事業はまだ小規模です。当面の戦略は、ミールズ単体で事業規模を拡大し、最終的にはデリッシュキッチンと同等の事業規模を確立することです。印象に残ってるエピソードやお客様からの反響を教えてください。私たちのサービスは、多くの30代以上のお客様に毎日利用され、「毎回異なるメニューで飽きない」「美味しい」と喜びの声をいただいています。特に印象的なのは、家族間での利用パターンです。離れて暮らす子供や高齢の両親にミールズの宅配弁当を送っているお客様も少なくありません。例えば、社会人の息子や、70代、80代、90代の親御さんに食事を届けるケースが目立ちます。自分では食べなくても、家族に安心して食事を届けられる点がミールズの魅力です。ミールズを利用する際の理想的なライフスタイルやシチュエーションをどのように想定していますか?デリッシュキッチンやミールズを立ち上げた当初から、私たちは料理をするということに対する社会的な固定概念を変えたいと考えていました。料理や自炊が苦手という方や、仕事や家事に追われて料理が負担に感じている人にとって、料理は”毎日する負担の多い作業”となってしまいます。ですが、私たちの目的は、料理を楽しいものに変え、その楽しさを伝えることでした。デリッシュキッチンで料理の楽しさを感じてもらいつつ、疲れた日や料理する気分でない日には気軽に利用できるミールズがあることで、料理に対する精神的な負担を軽減し、食事の時間をより豊かで楽しいものにしていきたいと考えています。長年築き上げてきた食の世界観ーミールズが描く新しい食体験と未来 引用:ミールズ公式HPまだサービスを試したことのない読者の皆様におすすめのメニューを教えてください。最近リリースしたエビクリームコロッケは、栄養バランスと美味しさの両立を実現した自信作です。カロリー、糖質、タンパク質など、すべての栄養素基準をクリアしながら、塩分2.5グラム以下という制約の中で、豊かな味わいを実現しました。通常、健康的な料理は味や見た目で妥協することが多いですが、このエビクリームコロッケは、そんな常識を覆す一品です。 エビクリームコロッケおまかせコースには入っておらず、自分で選択しなければいけない商品ですが、私たちのメニューの中でも贅沢感のある、少し冒険した商品なので、ぜひ味わっていただきたいと思います。最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします! 引用:ミールズ公式HP私たちのミールズは、特に美味しさに揺るぎない自信を持っています。まだ試したことのない方もたくさんいると思いますが、ぜひ一度、私たちの料理を試していただきたいです。そして先ほどもお伝えしましたが、ミールズとデリッシュキッチンを連携しながら、栄養管理から食事提供、健康管理までを一気通貫して行えるプラットフォームを目指しています。料理からでも、お弁当からでも、デリッシュキッチンのおいしくて楽しい食体験にぜひ一度触れてみてください。 ミールズ 公式サイトはこちら ミールズの解説記事を読む -
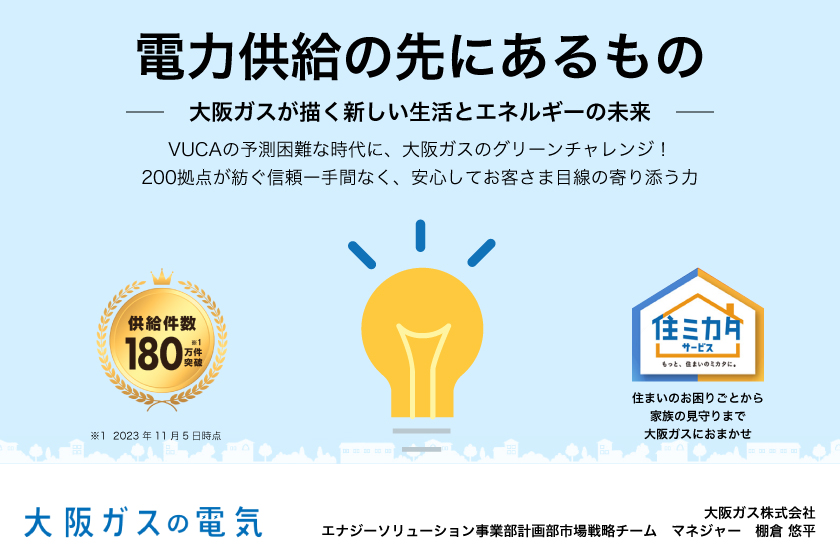
【大阪ガスの電気】電力供給の先にあるもの:大阪ガスが描く新しい生活とエネルギーの未来
私たちの暮らしに欠かせないエネルギー。その供給を担う大阪ガスが、いま新たな挑戦を始めている。140年にわたりガス供給で培ってきた技術とノウハウを活かし、電気事業にも本格参入。ガスと電気を組み合わせることで、より快適で環境にやさしい暮らしを実現する—。そんな大阪ガスの想いと、未来のエネルギー社会への構想に迫る。エネルギー供給の先にある、関西の人々の豊かな暮らしづくりへの取り組みとは?取材日:2024年11月19日 当記事は成果報酬型の広告モデルを採用しています。ニーズに合わせ、お客さまの暮らし回りを丸ごとサポートするという使命「大阪ガスの電気」は電力自由化に伴い誕生しましたが、エネルギー業界の変革期において、御社が電気事業を始めた理由とその背景にはどのような想いがあったのでしょうか?大阪ガスは1990年代後半から、酉島発電所や中山共同発電所での発電事業を手始めに、電気事業への取り組みを開始しました。その後、電力市場の段階的な自由化という時代の流れに応じて、1999年からは工場や病院といった大規模施設向けに電力供給を展開しています。さらに2004年には風力発電事業にも参入し、環境に配慮したエネルギー供給の幅を広げいったんです。そして2016年の電力小売全面自由化を機に、一般家庭向けの電力供給を開始し、電力事業を本格的に拡大しています。創業以来培ってきたエネルギー供給のノウハウを活かし、電気・ガスの両方を安定的に供給することで、お客様の生活インフラを支える総合エネルギー企業としての役割を果たしていきたいと考えています。ありがとうございます。ガスと電気のセットプランによる生活改善への貢献は具体的にどのように感じていますか?その点で最も利用者に伝えたい価値は何ですか?大阪ガスは、「お客さまのライフスタイルや個々のニーズに合わせ、お客さまの暮らし回りを丸ごとサポートする」という使命のもと、多様なニーズに応える料金プランを展開しています。まず、大阪ガスならではの特徴は、ガスと電気をまとめることで料金が割引になる仕組みの提供です。さらに、インターネットサービスとのセット割引も実施しており、複数のサービスをまとめることでガス料金の節約が可能です。また、お客さまの生活スタイルに合わせた電気料金プランも充実させています。たとえば、一人暮らしや二人暮らしの方向けには、新生活のスタートを応援する「新生活応援プラン」※を提供しており、基本料金は無料です。一方、3人以上のご家族向けには「ファミリー応援プラン」※をご用意しており、電気使用量が多いご家庭の負担を軽減できるよう設計しています。さらに、お客さまの多様なライフスタイルに対応するため、Amazonプライムの年会費相当額を大阪ガスが負担するプランや、dポイントが貯まるプランなど、付加価値の高いサービスも展開中です。大阪ガスは、単にエネルギーを供給するだけでなく、お客さま一人ひとりのライフスタイルやニーズに合わせて、暮らし全体の質を向上させる提案を行っています。お客さまにとって最適な料金プランを選択していただくことで、より快適で経済的な生活を実現することができるのです。 新生活を始めるお客さま・使用量が少ないお客さま向け「新生活応援プラン」 公式|大阪ガスの電気 ファミリー応援プラン 電気をたくさん使うご家庭ならおトク/大阪ガス大阪ガスが提供する「環境配慮型エネルギー」の具体的な取り組みや、持続可能な社会への貢献について教えてください。大阪ガスが、カーボンニュートラル社会の実現に向けて取り組んでいることは、ガス事業と電力事業の両面から環境配慮型エネルギーの提供です。ガス事業においては、カーボンニュートラル実現までの移行期間における取り組みとして、天然ガスへの燃料転換やコージェネレーションシステムなどの省エネ技術の導入を通じて、低炭素化を推進しています。さらに、2050年のカーボンニュートラル化を見据えた長期的な取り組みとしては、「e-メタン」という新しい都市ガスの導入への挑戦です。この「e-メタン」は、既存の都市ガスインフラやお客さまの燃焼機器をそのまま活用できる水素キャリアであり、カーボンリサイクル技術により大気中のCO2を増やさないという特徴を持っています。現在、この実用化に向けて技術開発や実証実験を進めるとともに、国内外でのサプライチェーン構築に取り組んでいますね。電力事業では、2030年度までに国内外で合計500万キロワットという具体的な目標を掲げ、再生可能エネルギーの普及に貢献することを目指しており、この目標の達成に向けて、太陽光、風力、バイオマスなど、多様な再生可能エネルギー源の開発を積極的に進めるとともに、再生可能エネルギー由来の電力調達にも注力しています。VUCAの予測困難な時代に、大阪ガスのグリーンチャレンジ!電力事業を展開する中で、特に重視している顧客満足のポイントは何でしょうか?そして、今後さらにどのように顧客体験を向上させていきたいと考えていますか?大阪ガスでは、お客さまの顧客満足を高めるため、個々のライフスタイルやニーズに合わせた柔軟な料金プラン展開を重視しています。たとえば、料金の節約を重視されるお客さまには経済的なプランを、また、自身の生活スタイルに最適なプランを探されているお客さまには、ライフスタイルに応じた選択肢を提供し、お客さまの多様なご要望にきめ細かく対応できるプラン設計を心がけています。現代は、VUCA(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)と呼ばれる予測困難な時代です。このような時代の中でも、大阪ガスは時代の変化や社会のニーズを敏感に捉え、常に新しいプランやサービスを開発・提供することで、お客さまの期待に応え続けたいと考えています。再生可能エネルギーの導入において、御社が特に注力している分野は何ですか?また、今後の成長戦略として見据えている新しいエネルギー技術やイノベーションについてお聞かせください。再生可能エネルギーの分野では、これまで太陽光、陸上風力、バイオマスといった多様な電源開発に取り組んできました。特に今後は、大きな開発可能性を秘めた洋上風力発電に注力していく方針です。ただし、単一の電源に偏ることなく、それぞれの再生可能エネルギー源の特徴を活かしながら、バランスの取れた電源ポートフォリオの構築を目指しています。また、将来に向けた新たな取り組みとして、再生可能エネルギーの開発・調達・販売の強化に加え、革新的な都市ガス「e-メタン」の実用化も進めているんです。この「e-メタン」の社会実装に向けては、技術開発や実証実験を重ねるとともに、国内外でのサプライチェーン構築にも力を入れています。「大阪ガスの電気」を通じて、どのような未来の暮らしやライフスタイルを提供したいと考えていますか?御社の描く理想の顧客像を教えてください。大阪ガスはこれまで、太陽光発電、陸上風力発電、バイオマス発電など、さまざまな再生可能エネルギーの開発に取り組んできました。現在はこれらに加えて、今後の成長が特に期待される洋上風力発電の分野にも力を入れていく予定です。その際、それぞれの発電方式の特徴や長所を最大限に活かせるよう、バランスの取れた開発を心がけています。また、当社の成長戦略は再生可能エネルギーの開発・調達・販売にとどまりません。次世代の環境配慮型エネルギーとして期待される「e-メタン」の実用化も重要な柱としています。この新技術の社会実装に向けて、技術開発や実証実験を進めるとともに、国内外でのサプライチェーン構築も並行して進めています。200拠点が紡ぐ信頼ー手間なく、安心してお客さま目線の寄り添う力。「大阪ガスの電気」を通じて、どのような未来の暮らしやライフスタイルを提供したいと考えていますか?御社の描く理想の顧客像を教えてください。大阪ガスは、長年培ってきたガス事業を基盤としながら、お客さまの暮らし全体をサポートする総合生活サービス企業として発展してきました。ガスや電気の供給にとどまらず、生活に必要な機器の提供やリフォーム、住まいのトラブル解決サービス「住ミカタ」など、お客さまの日常生活における様々なニーズにワンストップでお応えできる体制を整えています。 引用:大阪ガス公式HP 「住ミカタ」ページさらに、未来の暮らしをより豊かにするための革新的な技術開発にも取り組んでいるのです。例えば、CO2と水素から生成する次世代の都市ガス「e-メタン」の開発を進めているほか、エネルギーを使用せずに外気温よりも温度を下げることができる画期的な放射冷却素材「SPACECOOL®」※の開発と実用化にも力を入れています。「SPACECOOL®」は、宇宙空間への熱放出という新しい原理を活用したもので、出資先企業との連携により開発中です。大阪ガスは、お客さまの現在の生活をより快適にするサービスの提供と、環境に配慮した革新的な技術開発の両面から、未来のライフスタイルの創造に取り組み続けることで、より豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。 e-メタンって、「世の中変えちゃうかも」ガス。 SPACECOOL® (炎天下でも宇宙に熱を逃してゼロエネルギーで冷え続ける新素材)今回ホンネのアワード※で、総合評価が最も高い結果がでました。この結果に関して、何か工夫されたことなどはありますか?このような評価をいただけること大変ありがたく思っております。大阪ガスがお客さまから高い評価をいただいている理由は、「WEBからまとめて申し込める」・「検針票がまとめて届く」などの点です。まず、お客さまの利便性を重視したサービス設計が特徴です。大阪ガスのWEBサイトでは、電気・ガス・インターネットの契約をまとめて完了できる仕組みを整えています。また、申込内容に不備があった場合でも、コールセンターや開栓作業員が丁寧にフォローする体制を構築しており、長年のガス事業で培ったノウハウを活かした安心のサポートを提供しているのです。検針票についても、他社が有料のデジタル化を進める中、当社では無料での紙面発行を継続しています。これは、お客さまが日々の使用量や料金を確認し、節電・節約に活用していただきたいという想いからこのようなサービス設計にしているんです。また私たちが、特に力を入れているのが、地域に根差したサポート体制です。大阪ガスの都市ガス供給区域内には200カ所以上のサービスチェーン拠点があり、約1,200名のサービスマンが地域のお客さまのお困りごとに対応しています。ガスや電気の使用開始は、お客さまにとって頻繁に行う手続きではありません。だからこそ、契約から開通までの不安を解消し、スムーズにご利用いただけるようサポートすることが、大阪ガスの重要な使命だと考えています。 HonNe Award(ホンネ アワード)競合他社との差別化ポイントとして、「大阪ガスの電気」が提供する独自の価値や強みは何だとお考えですか?大阪ガスの最大の特徴は、お客さま一人ひとりの生活スタイルに合わせた柔軟なサービス提供にあります。競合他社が従来型の電力供給を主軸としているのに対し、大阪ガスは個々のお客さまのライフスタイル、ニーズ、趣味や嗜好などに細かく対応した多様な料金プランを用意しています。これにより、お客さまは自身の生活パターンに最も適した料金プランを選択することが可能です。さらに、大阪ガス独自の強みとして、地域密着型のサービスチェーン網があります。長年のガス事業で培ってきた地域とのつながりを活かし、単なるエネルギー供給にとどまらない、暮らし全体をサポートするサービスを実現しています。描こう、関西の未来図!変わるエネルギー、変わらぬ想い 引用:Daigas Group 公式HP今後、エネルギー供給の分野で特に力を入れていきたい取り組みや挑戦について、どのようなビジョンを持っていますか?10年後に目指す未来像を教えてください。大阪ガスは、ガス事業と電力事業の両面から、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めています。ガス事業では、2030年度までに次世代の都市ガス「e-メタン」の1%導入が目標です。これは単なる通過点であり、その先の更なる拡大も視野に入れています。また、この目標達成に向けた社会実装の取り組みを加速させていく考えです。さらに、現在進めている天然ガスへの燃料転換と利用拡大を継続しながら、将来的には天然ガスからe-メタンへとスムーズに移行することで、段階的な低・脱炭素化を実現していきます。電力事業においては、2030年度までに二つの具体的な目標を掲げています。一つは、国内外で合計500万キロワットの再生可能エネルギー電源の普及に貢献することであり、もう一つは、国内の電力事業における再生可能エネルギーの比率を50%程度まで高めることです。これらの目標達成に向けて、再生可能エネルギーの電源開発から販売まで、一貫した取り組みを強化していきます。読者の方へメッセージをお願いいたします。大阪ガスの電気は、単なる電力供給を超え、ガスと電気のセット利用による生活の質の向上、さらには環境への配慮を含めた持続可能なエネルギー供給を目指しています。地域に根差して140年、関西の暮らしを支え続けてきた大阪ガスが、より快適な毎日をお届けします。新生活をスタートされる方も、今お住まいの方も、安心と信頼の大阪ガスのサービスで、暮らしをもっと便利に、もっと心地よくしませんか?関西二府四県(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)にお住まいの方、これからお住まいになる方は、ぜひ一度大阪ガスのご利用をご検討ください! 大阪ガスの電気への切り替え を検討の方はこちら 引っ越し先で大阪ガスの電気 を検討の方はこちら 大阪ガスの解説記事を読む -

【パルシステム】忙しい生活に寄り添うパルシステム:ミールキットの可能性
「忙しい毎日の中でも、料理の幅を広げつつ栄養バランスにも配慮した食事を手間なく作りたい」。そんな願いを叶えてくれるのが、パルシステムのミールキット。短時間で本格的な料理が簡単に作れる上、メニューの種類も豊富。厳選された国産野菜や「調味料(アミノ酸等)」不使用の調味料など、食の安全面へのこだわりも徹底しています。食事を準備する負担を減らし、豊かな食卓を提供してくれるこのミールキットの魅力を、本記事で詳しくご紹介します。取材日:2024年12月2日パルシステムならではの食材を詰め込んだミールキット 引用:パルシステム公式HPまずは、パルシステムのお料理セットとはどのような商品でしょうか。黒井さん:お料理セットは、簡単に調理ができるミールキットです。世間的には、「ミールキット」と呼ばれることが一般的ですが、パルシステムでは「お料理セット」と呼んでいます。カット済みの野菜に、肉や魚といった食材、それにプラスして添付調味料とレシピがセットになっています。野菜と肉はすべて国産にこだわり、添付のたれも「調味料(アミノ酸等)」は不使用の商品を取り扱っています。このサービスは2014年にスタートし、2024年で10年目を迎えることができました。サービスを立ち上げた経緯を教えてください。黒井さん:社会的背景としては、共働きの家庭が増えてきていたことが挙げられます。その後、コロナ禍に入ったこともあり、市場全体を見ても宅配食の需要が高まっていきました。またレシピと人数分の必要な食材がセットされているミールキットは、現代のニーズにマッチした商品として様々なところで販売が開始されました。 パルシステムの方針の『組合員のくらしの課題解決』という理念から、共働き世帯をサポートする商品として、2014年から3種類のお料理セットでサービスを開始しました。特に大切にしている価値観や、他社との差別化を図っているポイントは何でしょうか。黒井さん:まず、国産へのこだわりです。肉と野菜は必ず国産のもので、顔が見える生産者(産直)の食材も多く使用しています。2017年には群馬県板倉町に自社工場を建て、子会社の『株式会社パルライン』が運営しています。 自社工場製造分はすべてパルシステムが開発した商品であり、規格外品や余剰となった野菜も積極的に活用しています。パルシステムは生協なので青果の宅配もしていますが、出荷基準があり、産地と作付計画から打ち合わせをする中で、サイズや傷などの理由で規格外品が出てくることがあります。これらはカットして傷を取り除けば食味に問題はありませんし、生産者が作った食品をなるべく無駄にならないように使用しています。このように、生産者の支援にもつながる取り組みも行っています。また、PB(プライベートブランド)商品には調味料からお肉やお魚、カットわかめ、豆腐などの副材まで幅広く揃えており、お料理セットにも取り入れています。組合員にとって普段あまりなじみのない調味料は、大容量だと手が出しにくいと思うんです。そこで、お料理セットに小袋タイプの調味料を内包し、味や使い方を知る機会を作っています。食材を調達する際に重視していることは何ですか?高橋さん:私たちの役割は、全国に広がるネットワークを活用、おいしい食材を安定的に調達することだと考えています。そのため、複数ある産直産地と連携し、それぞれに当会の基準に基づいた方法での栽培をお願いしています。近年、天災などの影響で収穫量が減少することも増えていますが、これまで築いてきた信頼関係をもとに産地の方々と協力しながら供給を維持しています。また、当会では年間契約を行うことで、食材価格の安定化を図っています。お料理セットの販売価格は変動が少ないので、市場で野菜の価格が高騰すると、より多くの組合員の方々にご利用いただける傾向があります。家庭でさまざまな食材を揃えるのは手間もお金もかかりますので、こうしたお料理セットの需要につながっているのではないかと思います。単身世帯にも需要が拡大。野菜価格が高騰しても多種多様な野菜を食卓に 引用:パルシステム公式HPミールキットページサービス開始後から顧客ニーズの変化はありましたか? また、その転機となった出来事は何でしょう。高橋さん:当初は30〜40代の共働きの主婦・主夫を主なターゲットにしていましたが、コロナ禍を機にニーズに大きな変化が見られました。テレワークの普及に伴い、一人暮らしのランチ需要が増加し、それに対応したメニューが伸びています。また、旅行の制限により、郷土料理や世界各国の料理を自宅で楽しめるメニューの需要も高まり、現在も引き続き人気があります。最近では、消費者の深層的にバランスの良い食事、野菜をしっかり摂りたいという気持ちをお持ちです。高齢の方をはじめ、「野菜は食べたいけど、さまざまな種類を買うと高いし使いきれない」というような悩みが増えており、このような方々が徐々にミールキットを利用し始めています。今までは2〜3人前のセットを中心に提供していたのですが、現在は高齢の2人世帯でも食べきれる1.5人前のセットも導入しています。今後も市場動向を見つつ組合員の声を聞きながら、選択肢を増やしていければと考えています。お料理セットの中で特に人気のあるメニューやおすすめは何ですか?また、一番メジャーな商品トマト風味のドライカレーには、国産トマトを濃縮還元したプライベートブランド商品のトマトジュース『濃いトマト(食塩無添加)』を使用しています。このトマトジュースは1本100円ほどですが通常は24本セットでの販売のため、個人で購入するには少しハードルが高いかもしれません。しかし、お料理セットに使うことで、飲むだけでなく調理にも活用できることを知るきっかけになればと思います。 スープ系の料理も人気で、煮込むだけでボリュームがあって栄養価が高い一品を、短時間で用意できるところが高く評価されています。 引用:パルシステム公式HP 商品図鑑高橋さん:有機の若芽ひじきの炒め物もおすすめです。若芽ひじきはお浸しが定番ですが、炒めるとシャキシャキとした食感が楽しめます。若芽ひじきを購入したことがない方や調理法がわからないという方にも試してもらいやすいメニューです。 あとは、「水餃子のジェノベーゼソース(ラビオリ風)」も食べてみてほしい一品です。ジェノベーゼソースと生クリームで餃子を煮込み、ラビオリのように食べるセットで、ジェノベーゼソースの新しい使い方が発見でき、料理の幅が広がるはずです。食材へのこだわりから環境配慮まで、価格以上の価値を提供するパルシステムのお料理セット再生素材を使用したパッケージなど、環境に配慮した取り組みも行われていますよね。黒井さん:当会では環境への配慮を重視しており、特にプラスチック削減を方針として掲げています。ミールキットを始めた当初から再生原料を55%使用したプラスチック製トレイを採用していましたが、2年前にはこのトレイを紙製に切り替えました。 当時、市場には食品用のモールド系紙製トレイがなかったので、たまご用のモールドパックを製造していただいているメーカーに新たに製作してもらったんです。メーカーも初挑戦で、大きさや形などを一緒に考え、何度も試作を繰り返し、強度を確認しながら一緒に作り上げました。 たまご用のモールドパックただ、紙は強度に限界があるので、少量のプラスチックのパルプ繊維を混ぜて強度を上げています。ですので、今は、このパルプ繊維を使用しない、完全にプラスチック使用量ゼロ紙製トレーを目指して頑張っているところです。また、従来のプラスチックトレイのように、回収後に溶かして再利用する水平リサイクルの仕組みを、紙製トレイにも導入することを目指しました。「紙製だから一般の資源ゴミに出せばいいよね」ではなく、リサイクル可能な仕組みを構築していました。コストと品質とのバランスを取るのが難しいところですね。黒井さん:そうなんです。ほかの生協やメーカーと比較すると単価は少し高めかもしれませんが、その分、高品質な商品を提供することにこだわり、環境に配慮した取り組みもおこなっています。忙しい毎日を送るお客様に、ミールキットを使うことは手抜きではなく、むしろ手軽に栄養のあるおいしい食事を作ることができる方法ということを伝えたいですね。御会のサービスについて、「消費者に伝えきれていない」「もっと知ってもらいたい」と感じている点はありますか?高橋さん:学習会などで工場見学をしていただいたり、ムービーで工場の様子をご覧いただくと、食材のカットや袋詰めなどを手作業でおこなっていることに驚かれることがあります。自社工場では、品質や安全性を担保するために機械化はもちろん、人の手で作業する工程も採用することで、より質の高い商品を提供できる体制を構築しています。こうした一手間を知っていただくことで、「この価格は妥当だよね」と言っていただけています。黒井さん:肉や卵の生産においても、餌や飼育環境に気を配り、ストレスを少なくできるよう育てています。このような商品の裏側をもっと多くの方に知ってもらいたいです。 ご利用された方の反響や、特に印象に残っているエピソードについて教えてください。黒井さん:お料理セットはリピート率が高い商品であり、利用した組合員から味や使い勝手も含めて、高く評価されています。学習会などで組合員と話をしていると、「来週のメニューは何にしようか」とお子さんと選んでいるとか、ミールキットを親子で作ったりしているというエピソードをよく耳にします。今まではお母さんがおこなっていた料理に子どもやお父さんも参加するようになったとか、ミールキットを使うことで家事の負担が軽減され、家族で過ごす時間が増えたという喜びの声も寄せられています。また、普段とは違う味付けが楽しめる点も好評です。食卓では「これ初めて見るけど何ていう食べ物?」「この味付けいいね」といった会話も生まれ、家族のコミュニケーションが増えたという話も非常に印象的でした。1週間あたり17万食から20万食へ! 今後は冷凍ミールキットの充実化も視野に入れたソリューションを展開 引用:パルシステム公式HP お料理セットページ10周年を迎えた今、毎週約20万食の注文があるというのは驚異的な数値ですね。高橋さん:10周年を迎えられたことで、利用者の方々に支持いただいていることを改めて実感しています。忙しい日常の中で便利さを求めている方、食品ロス削減を意識している方、産地支援のために選んでいる方など、さまざまな理由により多くの方に使っていただき、徐々に需要が増加したんです。注文数は、昨年は1週間あたり約17万食でしたが、10周年を機に一気に20万食という大幅な伸びを見せました。これは、利用者が商品にそれぞれの価値を見出し、魅力を感じていただいている証拠だと思います。黒井さん:今回、10周年キャンペーンとして、組合員のみなさんが実際にどのように召し上がっているのか、アレンジの仕方などをインスタグラムに投稿していただきました。今まではインスタグラムでキャンペーンを行っても最大100件程度の応募しかなかったのに対し、今回は外部・内部を合わせて500件以上の投稿が集まりました。みなさん思い思いの投稿をされていて、「夏休みにお子さんがおばあちゃんのために作った」とか、働いているお父さん・お母さんの帰りが遅いときにお子さんが作った食事、息子が文句を言わないお気に入りのメニューなど、それぞれの家庭の工夫が見られました。生協はもともと共同購入が目的で、みんなで集まり料理などを教え合う場でもありましたが、ミールキットを通してウェブ上でも教え合う場が作れたのではないかと思っています。今後、挑戦していきたいことはありますか?黒井さん:逆に原点に戻って、一(いち)から丁寧に出汁を取るなど、手作り感を大切にしたメニューの開発を考えています。ミールキットは時短要素が利点ではありますが、時間をかけて煮込む料理やイベント用のローストチキンセットなど、少し手間がかかるけど材料が揃っているから便利、というような商品にチャレンジしてみたいと思っています。あとは、冷凍商品ですね。ストックできる冷凍商品をもっと増やしてほしいというニーズが高まっています。冷凍でも味わいや食感が変わらない野菜の仕様や、冷蔵商品に引けを取らないおいしさとボリュームを実現したいと考えています。ミールキットの購入を検討されている方たちに向けてメッセージをお願いします。高橋さん:私自身、子育てをしながら家事や仕事をする中で、短時間で料理ができるというのは本当に助かっています。普段、自分で作る料理はレシピサイトを参考にしても、どうしても似たような味付けになってしまうのですが、このセットを使うとガラリと料理が変わり、外食気分を味わえるのでコストパフォーマンスの面からもお得感があります。また、ゴミが少なく、トレイの回収サービスがある点も便利だと思います。どんどん共働きの家庭が増えている今、世間的に求められているサービスではないでしょうか。黒井さん:ミールキットを利用することで、おいしさだけでなく、家族と一緒に過ごす楽しい時間を作り出せます。食事は生活の中で大切な時間であり、子どもにとって楽しい記憶として残ることもあるでしょう。豊かな食生活や楽しい時間をサポートする商品として、ぜひミールキットを活用してみてください。 <編集後記>今回、定番メニューの「トマト風味のドライカレーセット」の試供品をいただき、編集部員で料理・実食しました。本当に10分でカレーが作れるんです!1日に余裕ができて、短時間で料理できる魅力を味わうことができました。味に関しては、野菜のカッティングや味付け方法など、普段の料理と異なっているので、お店のカレーを食べているような気分に。また、私はカレーを作るときにトマトジュースではなくてトマト缶を使うタイプなので、こんな料理の仕方もあるんだなと勉強になりました。料理の手間を省きたい方だけではなく、料理に拘りがある方にもぜひミールキットを活用していただきたいです。 パルシステム 公式サイトはこちら パルシステムの解説記事を読む -

【ウェルネスダイニング】食事制限の不安に寄り添う!ウェルネスダイニングが描く未来の制限食文化
「食事制限」という言葉に、何を想像するだろうか?味気ない食事、制限された楽しみ、そして家族との食卓の断絶。そんな固定観念を打ち砕くべくウェルネスダイニングが掲げるのは、「健康管理と美味しさの両立」だ。管理栄養士たちの知恵と情熱が生み出す、驚きの美味しさと栄養バランス。そして何より、背景にある「お客様に寄り添う」という揺るぎない信念。今回の取材では、制限食という枠を超え、新たな食の喜びを創造するウェルネスダイニングの挑戦に迫る。取材日:2024年10月9日ウェルネスダイニングは、創業者の闘病経験と管理栄養士との出会いにより誕生。 左:事業企画部の清水様、右:CS事業部の高木様今回のインタビューでは、ウェルネスダイニングの事業企画部清水様、そしてCS事業部高木様にお話を伺います。まずは、御社の基本的なサービスや企業概要について教えてください。清水:ウェルネスダイニングは、主に食事制限を専門とした宅配食の通販事業を展開しています。当社の主力商品は「気配り宅配食」と呼ばれる、食事制限が必要な方向けの栄養管理された冷凍弁当です。これに加えて、高齢者向けのやわらか食や、塩分を控えた野菜たっぷりの味噌汁なども取り扱っています。気配り宅配食には複数のコースがあり、それぞれご病気と必要な食事制限に合わせて設計されているのです。例えば、腎臓病の方向けにはたんぱく質と塩分調整食、糖尿病の方向けには糖質とカロリー制限食、高血圧や心疾患が不安な方向けには塩分制限食などがあります。さらに、食生活の見直しや予防の観点から栄養バランスを整えた食事も提供しています。 引用:ウェルネスダイニング公式ホームページウェルネスダイニングを立ち上げるに至った背景には、どのような健康に対する問題意識があったのでしょうか?清水:創業の背景には、創業者自身の糖尿病の体験と、ある管理栄養士との出会いがありました。この管理栄養士は腎臓病専門の病院での勤務経験があり、食事制限の重要性について深い知見を持っていたのです。創業者は、自身の経験から食事制限の困難さを理解し、同時に薬物療法だけでは十分な治療効果が得られないことも認識していました。そこで、自宅で適切な食事制限を実践することの重要性と、それをサポートするサービスの必要性を感じたのです。このような経緯から、ウェルネスダイニングは通常の弁当宅配事業ではなく、食事制限を必要とする人々に特化したサービスとして誕生しました。創業者のご経験をもとに生まれたサービスなのですね。特にこだわっている点や、食事の質をどのように維持しているのか教えてください。清水:「美味しさ」と「食事の楽しさ」にはこだわっています。「美味しさ」に関しては、特製のタレや出汁を用いて、制限食とは思えないしっかりとした味付けを目指しています。また、食材の硬さにも注意を払い、実際に召し上がるお客様のことを想像しながら、食べやすさと安全性を確保しています。「食事の楽しさ」では、約90種類のメニューを用意し、常に改良を重ねていることです。特に、お客様へお届けするお食事の内容には特に気を配っております。毎週配送のお客様には、メニューが重複しないよう細かな計画を立てていたり、1回の配送で7食分をお届けする場合は、肉料理、魚料理、卵料理などのバランスを考慮したりしています。高木:さらに、昨年からは食事制限をしながらも季節の食材を楽しんでいただけるように、期間限定で季節メニューの提供を始めました。例えば、夏限定のウナギを使用したメニューがあります。多くのお客様が「制限食ではウナギは食べられない」と諦めていたため、とても好評でした。 引用:ウェルネスダイニング公式ホームページ制限食であっても季節感や豊かな食体験を提供することで、お客様の食生活に楽しみをお届けすることを心がけています。季節限定メニューとして開発され、お客様からの高い評価を受けて通常メニューに昇格したメニューも少なくありません。 社員用の冷蔵庫福利厚生の一環として社員は当社の弁当を食べられますが、皆飽きることなく食べています。食事内容以外にもこだわっている部分はありますか?お客様が商品を開封した際、メニュー名を見て美味しそうだと感じていただけるよう工夫しています。食材は異なっても名称が似ているメニューがあると、お客様には同じように感じられる可能性があるため、メニュー名の選定には細心の注意を払い、社内でも活発なディスカッションをおこなっているんです。また、商品ラベルの設計にも細心の注意を払っています。メニュー名はもちろん、加熱時間や詳細な栄養成分表示など、お客様が知りたい情報をひと目で分かるように工夫しています。特に、タンパク質、糖質、脂質、食塩、カリウムの値に加え、腎臓病の方からのご要望に応じてリンの含有量も表示するようになりました。また、主菜だけでなく副菜のメニュー名も分かりやすく表記し、原材料表示も見やすいように改行を入れるなど、細部にまでこだわっています。長期利用のお客様ほど内容に注目されるため、パッケージを開封せずとも情報が得られるよう心がけています。お客様の年齢層を考慮し、文字の大きさやフォントの選択にも気を配っているのです。 商品ラベルの違い(左:改良前、右:改良後)意外と難しい!直面して初めて分かる健康管理の苦労に寄り添いたいどのようにしてウェルネスダイニングを知るお客様が多いのでしょうか?清水:多くのお客様は、健康診断や血液検査の結果を受けて、医師から食事制限の必要性を指摘されたことがきっかけで、健康に対する意識を高めるようです。お客様の行動パターンとしては、まず自分の症状や疾患に関連する食事情報をインターネットで検索し、制限すべき食品などについて調べます。調べる中で、実際に適切な食事管理の難しさや、自己管理がきちんと出来ているのか不安を感じ、宅配食サービスの存在を知ることが多いようです。制限食に特化した宅食サービスは他にもありますが、ウェルネスダイニングならではの魅力を教えてください。清水:私たちの最大の強みは、お客様の健康をサポートしたいという強い思いです。そのため、当社ではお客様の声を非常に重視しています。毎朝、前日に寄せられたすべての顧客フィードバックを全社員で共有し、迅速に対応する体制を整えているのです。例えば、特定のメニューの味付けに関する指摘があった場合、翌日には製造元に連絡し、サンプルを取り寄せて味の確認をします。お客様からのフィードバックへの対応は、通常1週間以内には必ず改善策を講じています。また、お客様とのコミュニケーション方法も重視しており、インターネットでの問い合わせだけでなく、自分の意見を直接伝えたいという思いに応えるため、電話で声を聞く機会も多く設けています。高木:お客様のお声で多いのは味に関するものです。そのため、ウェルネスダイニングは、美味しさと健康の両立に注力しています。多くの人が制限食を味気ないものと捉える中、当社は塩分2.5グラム以下または2グラム以下のコースを設け、減塩しながらも満足度の高い味付けを実現しているのです。塩分制限下での美味しさを追求するため、出汁の活用や香辛料の工夫、味噌の種類の選定など、様々な技術を駆使しています。調味料室には様々な種類の調味料が揃えられており、同じカテゴリーの調味料でも複数の製品を用意しています。これは、各食材に最適な味付けを見出すためです。実際に試食させていただきましたが、塩分2.5グラム以下とは信じられないくらいしっかりした味付けで美味しかったです。ボリュームも十分ですし、制限食に限らず毎日食べたいと思いました。高木:ありがとうございます。コンビニに売られているおにぎりの塩分量は1個あたり1gほどなので、おにぎり2個分の塩分量と同じくらいなんですよ。ちなみに、ウェルネスダイニングの具体的な味付けの選定は、科学的な数値分析よりも、実際の試食を通じた感覚的な判断に重きを置いています。製造元の管理栄養士と密接に連携し、日々のコミュニケーションと試食によるフィードバックを重視しながら、試行錯誤しています。さらに、視覚的な魅力にも注目し、カラーコーディネーターの助言を取り入れ、弁当の見た目の美しさにも配慮しています。容器の色選びにも細心の注意を払い、食材の色を引き立てる白色のトレーを採用しました。メニューの改良に際しては、味、栄養バランス、見た目の調和を同時に考慮する細やかなアプローチを取っています。例えば、ある魚料理のちゃんちゃん焼きのケースでは、味噌の種類を変更することで複数の課題を解決しました。当初、赤味噌を使用していたため、料理に含まれる赤ピーマンや緑ピーマンの色彩が引き立ちませんでしたが、白味噌に変更することで、主菜の見栄えが格段に向上しました。色味だけではなく、塩分量も抑えることができています。「制限食なのにこんなに美味しい」健康応援団として、お客様に安心感を オフィスの様子。企業理念を中心に、社長室も存在しないフルフラットな空間にすることで、健康応援団としての社員の連携がシームレスにおこなわれているそうです。持病を持つ方々に向けて、安心感を伝えるために工夫していることはありますか?高木:お客様の健康を生涯にわたって応援することが私たちの企業理念です。単なる販売者ではなく、お客様の健康をサポートする「健康応援団」として、食事制限のサポートをおこなっています。多くのお客様が医師とのコミュニケーションに悩んでいたり、クリニックに管理栄養士がいないため栄養相談ができないという課題を抱えているでしょう。当社は38名の従業員のうち半数が管理栄養士の資格を持ち、お客様対応スタッフの過半数も管理栄養士です。これにより、お客様からのお電話に常に専門知識を持ったスタッフが対応できる体制を整えています。例えば、スーパーでの買い物中に「腎臓病の私がこれを食べても良いか」といった相談にも応じています。このような取り組みを通じて、お客様との距離が非常に近く、くだけた会話ができるほど親密な関係を築いているんです。お客様にいつでも気軽に電話していただき、必要なサポートを提供することで安心感を与えられるよう努めています。ご病気を持持つ方に食事を提供する方たちにとっても、魅力的なサービスだと思うのですが、食事を提供する側が抱えている課題やお悩みはどのような点があげられますか?高木:多くの場合、食事制限が必要な方のご家族、特に食事を準備する立場の方が大きな責任感と不安を抱えていると思うのです。例えば、腎臓病患者の食事制限では、塩分制限は比較的イメージしやすいですが、カリウム制限のような専門的な栄養素の管理に関しては多くの方が困難を感じています。病院では「1日の塩分摂取量を6グラムに抑えましょう」という程度の概要的な説明にとどまることが多く、実践的な方法まで踏み込んで指導されることは少ないようです。私たちは、野菜の茹で方など「どうすればいいのか」という具体的な部分をサポートすることで、患者さんやそのご家族の不安を軽減し、実行可能な食事管理を提案しています。ウェルネスダイニングの利用頻度は様々ですが、夕食の置き換えとして利用される方が最も多いです。健康な方なら外食という選択肢もありますが、食事制限のある方にはそういった選択肢が限られているでしょう。そのため、私たちのお弁当を冷凍庫に常備しておくことで、食事準備の負担や精神的なストレスを軽減できると考えています。押し売りはしない!困った時に気軽に頼れる存在でありたい 年に1回社内で発行されるアルバム。アルバムからは社員を大切にする様子が伺えました。食事制限を必要とする方々以外にも、ウェルネスダイニングのサービスを広げるためには、どのようなアプローチが必要だと感じていますか?清水:私たちのサービスを多くの方に知っていただくため、食事制限が必要な方々だけでなく、潜在的な顧客層へのアプローチを強化したいと考えています。当社の強みである栄養相談サービスを活用し、商品購入という従来の入口だけでなく、栄養相談を新たな入口として模索していきたいです。まずは商品を購入せずとも、私たちと対話する機会を通じて、より多くの方々に当社のサービスを知っていただき、興味を持っていただけるきっかけを作りたいと考えています。お客様から寄せられるフィードバックの中で、特に印象に残っているエピソードや改善点はありますか?高木:当社は日々多くのお客様からご意見をいただいていますが、特に印象的なのは手書きのお手紙です。例えば、病気の父親のために娘さんが注文し、料理を準備する母親の負担が軽減されたという喜びの声や、同じ食事制限で悩む方々へのアドバイスを送ってくださる常連のお客様もいらっしゃいます。私たちは単に販売数を増やすことよりも、ウェルネスダイニングのファンを増やすことを重視しています。一方で、お客様の嗜好は様々です。例えば、レモン風味の料理に対して「レモンが強すぎる」という声もあれば「さっぱりして美味しい」という声もあります。改善のつもりが特定のお客様の嗜好に合わないこともありますが、そのような意見も真摯に受け止め、さらなる改善につなげています。 オフィスにいるペットロボット。2体おり社内の雰囲気を和やかにしていました。ウェルネスダイニングが目指す、食事と健康を通じた未来のライフスタイルとはどのようなものでしょうか?清水:当社は食事制限食を提供する会社として、お客様に健康的な食生活を長期的に続けていただくことを重視しています。また、お客様個人だけでなく、ご家族全体をサポートすることも重要だと考えているんです。食事を用意する方の負担を軽減しつつ、食べる方の健康も同時に支援することで、家族全体の健康と生活の質の向上に貢献したいと考えています。最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします!清水:私たちは何よりもお客様に寄り添うことを大切にしているので、商品のご購入の有無にかかわらず、お気軽にご連絡いただきたいと思っています。販売者と顧客という関係性ではなく、、お客様が困ったときに頼れる存在でありたいという思いが一番強いです。特に、健康に不安を感じたり、病気になったと思われたときは、ぜひご連絡ください。私たち管理栄養士が全力でサポートさせていただきます。また、私たちは制限食であっても、日々商品の品質向上に努めています。美味しく、健康的で、お客様の生活に寄り添える食事を提供することを目指しているので、ぜひ一度、私たちの商品をお試しいただければ幸いです。 ウェルネスダイニング 公式サイトはこちら ウェルネスダイニングの解説記事を読む -

【ハミングウォーター】浄水で未来を変える: ハミングウォーターの挑戦と革新
ボトルレスの浄水型ウォーターサーバーとして人気が高い「ハミングウォーター」。飲料水としてだけではなく、1日10ℓも使える圧倒的な浄水力で、料理にもたっぷり使えるのが魅力だ。また、お客様に寄り添った設計により、“使いやすさ”が多くの方に支持されている。家庭のお水の消費を大きく変革するハミングウォーターはいったいどのようにして生まれたのか。誕生秘話から今直面している課題や未来への挑戦まで、開発者にインタビューした。取材日:2024年10月7日レンタル制、月額3,300円のウォーターサーバー 引用:ハミングウォーター公式ホームページ今回はコスモライフ様の浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」について、スペックや機能の概要の他、サービスのこだわり、開発に至った背景や誕生秘話などを深掘りしていきたいと思います。まずは、御社の概要について教えてください。白石さん:株式会社コスモライフは「人を咲かせる」の企業理念のもと、1988年に創業しました。2005年に宅配水ビジネスをスタートし、以降、ウォーターサーバー事業を展開しています。2019年には水道水をろ過する浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」を発売しました。ハミングウォーターの特徴や料金設定について教えてください。白石さん:ハミングウォーターは、水道水をタンクに注ぐだけで安全でおいしいお水を作ることができる、浄水型ウォーターサーバーです。難しい操作も必要なく、ボタン1つで冷水・常温水・温水をいつでもご利用いただけます。料金は月額3,300円(税込)で、ウォーターサーバーのレンタル料と浄水フィルター代、配送料を含んでいます。定額制なので、これ以外の費用はかかりません。シンプルな料金設定になっています。フィルターは6ヶ月に1回、お客様の交換時期に合わせてお届けしています。1日10ℓ使えるフィルターなので、料理やペットの水分補給など、飲み水以外にも気軽にお使いいただけますよ。大原さん:ちなみにフィルターの「浄水能力の高さ」は、ハミングウォーターの大きな特徴の1つといえます。安全でおいしいお水を提供するため、フィルターには徹底的にこだわりました。ハミングウォーターで使用しているのは、活性炭を使用したマイクロフィルターと、細いストローのような形状の中空糸膜を使用したウルトラフィルターです。この2種類の浄水フィルターにより、お水に含まれる微細な物質を最大限まで細かく除去しています。除去項目数も業界トップクラスなので、お客様には安心してお水を飲んでいただけます。白石さん:使いやすさも特徴の1つですね。大きなお鍋が置きやすい水受けトレイや、立ったまま操作がしやすいボタン式パネル、水筒などの背の高い容器もトレイに置いたまま注げる高さ設計など、使いやすさを意識した設計になっています。特にお鍋が置きやすい水受けトレイは大きなポイント。重いお鍋を持ったままお水を注ぐ必要がないので、料理の時に大活躍です。 引用:ハミングウォーター公式ホームページありがとうございます。トレイに大きなお鍋を置けたり、ワンタッチで冷水と常温水が出しっぱなしにできたりと、料理をされる方を意識した設計になっていますね。実際、ユーザー様からは、どのような反響がありますか?白石さん:そうですね。ありがたいことに、数多くのポジティブなお声をいただきました。例えば『お料理にも基本的にはハミングウォーターのお水を使っています。トレイが広いのでお鍋を置いたままお水を注げるのが便利ですね。』というご意見や、『いくつかウォーターサーバーを利用しましたが、一番使い勝手が良かったです。』というご意見をいただいたことがあります。このように、使いやすさにこだわった設計に対してお声をいただけるのは、私たちにとってとても励みになりますね。お客様のお声と水ボトルの配送料高騰をきっかけに浄水型の開発に舵を切る 引用:株式会社コスモライフ公式ホームページ高い機能性を持つハミングウォーターですが、製品が誕生したきっかけは何だったのですか?大原さん:もともと弊社は「コスモウォーター」というブランドで、宅配水の事業を展開しております。コスモウォーターは、天然水を入れた水ボトルを毎月お客様にお届けする宅配型ウォーターサーバーですが、お客様から「水ボトルの持ち運びが面倒」というご意見をいただくことが多かったんですよね。そこで、ボトルレスな浄水型ウォーターサーバーの企画が生まれました。白石さん:運送会社の宅配料金の値上げにより、水ボトルの配送料が高騰したこともありますね。できるだけお客様に負担をかけずに安全なお水を提供するため、「配送機会の少ないエコスタイルなウォーターサーバーを開発しよう」と社内で話をしていた頃でもありました。技術者を悩ませた「女性目線」に立った開発 引用:ハミングウォーター公式ホームページ開発を進める中で、意識していたことはありますか?大原さん:ハミングウォーターは「徹底的に女性目線で作る」という方針のもと、開発がスタートしました。これまで女性は製品開発プロジェクトのメンバーに入っていませんでしたが、開発メンバーに初めて女性スタッフを迎え、男性とは全く違う視点で開発を進めました。操作パネルを例に挙げます。最初は、ウォーターサーバーの上部に操作パネルを水平に配置していました。われわれ男性からすると、高い位置にある方が使いやすいと思っていたのですが、女性スタッフからは「それだと使いにくいよね」という意見が多く出たんですよね。デザインはもちろんですが、このような女性目線での使いやすさにこだわって作りました。白石さん:そこまでこだわったのは、従来製品とは違うコンセプトのウォーターサーバーを作りたい、という意識が強かったからだと思います。その背景には、ハミングウォーターは飲料用としてだけではなく、料理に特化したウォーターサーバーにしたいという想いがありました。 細部までこだわった設計 引用:ハミングウォーター公式ホームページ女性向けのデザインを目指しつつ、使いやすさと機能面を担保するのは、開発までの障壁も多かったと思います。特に開発するうえで難しかったのは、どのような点ですか?大原さん:デザインと実際に必要な機能を両立させる難しさはありました。われわれ技術者としては、「機能を増やせば、本体サイズも大きくなる」と考えますが、「できるかぎり本体サイズは小さくしてほしい」と意見が出たり...衝突は数えきれないぐらいあったと思います。白石さん:確かに数多くの議論が事業部を横断して行われましたね...例えば、水受けトレイにお鍋が置ける仕様になっていますが、この部分は技術部に頑張ってもらいました。お鍋を置けるスペースを確保するために、本体を限界まで削りましたね。また、操作パネルの高さも、小さな子供には届きにくく、かつ女性が使いやすい角度に傾けるなど、細かい部分までこだわりました。大原さん:企画の段階では、操作パネルをタッチパネル式にすることも検討していましたね。操作パネル自体も折りたためたり、指をかざしたらこちらを向いたりするなど、ハイスペックなものはどうかと協議しました。常に技術側と企画側でお互いの意見を戦わせ、機能とコストのバランスを図りながら、最適なゴールを目指して作り上げました。 コロナ禍で広がった浄水型ウォーターサーバーの市場 引用:ハミングウォーター公式ホームページウォーターサーバー市場の変化について教えてください。また、利用者のニーズの変化はありましたか?白石さん:時系列で振り返ると、2011年の東日本大震災直後、お水に対する意識が高まりました。当時は天然水の宅配型ウォーターサーバー市場が伸びた時期で、いわゆるペットボトルのお水が主流でした。しかしコロナ以降は、水道水を使う浄水型ウォーターサーバーへと、ユーザー様のニーズが変化していると感じます。ちなみにハミングウォーターの発売後、浄水型ウォーターサーバーの市場が一気に拡大しました。ボトルレスのウォーターサーバーの先駆けといえます。「ボトルレス」は水ボトルを受け取る必要がないので、ユーザー様にとって大きなメリットですね。そう考えると、ボトルレスの需要は今後も伸びていくのでしょうか?大原さん:ウォーターサーバー市場において、浄水型の需要は拡大傾向にあります。特にコロナ禍の影響が大きいですね。在宅時間が延びたことでお水を使う機会が増えましたが、ペットボトルのお水を買いに行く、水ボトルを宅配してもらう、というのは「手間がかかる」と考えるようになる時期だったのかなと思います。浄水型なら、水道水を注ぐだけで安全でおいしいお水が飲めます。その利便性の高さがハミングウォーターの需要拡大につながったのかもしれません。お客様の声に寄り添い、生活を豊かに 引用:ハミングウォーター公式ホームページその一方で、ウォーターサーバーをまだ利用したことがなく、どの製品を選んだらいいのかわからない、という層もいるはずです。御社のハミングウォーターを導入することで、生活にどのような新しいストーリーを提供できると考えますか?「こんな人におすすめです」といったポイントがあれば教えてください。白石さん:毎日飲むお水を安心・安全に使いたい方や、料理でお水を頻繁に使用する方におすすめのウォーターサーバーだと思います。例えば、料理に水道水を使っている方は今でも多いと思いますが、なぜ水道水を使うのかというと、「沸騰したら大丈夫だ」という漠然とした認識が強いからだと考えています。しかし、健康リスクについて度々議論されている、水道水に含まれる「PFAS(有機フッ素化合物)」は煮沸消毒しても除去されません。もちろん水道局も安全面には配慮していますが、ハミングウォーターはPFASをはじめとする多くの不純物が除去できますので、より安心してお水をご利用いただけます。飲み水だけではなく、料理にも安全なお水を使えるのは嬉しいですね。ウォーターサーバーをお持ちでいない方だと、ケトルでお湯を沸かしている方も多い印象です。大原さん:電気ケトルをお持ちの方は多いと思うのですが、電気ケトルはお湯を沸かすのに意外と時間がかかってしまうんです。一方、ウォーターサーバーだと、温水がすぐに使えるのがメリットです。お客様からは『すぐに温水が出るから、料理でお湯を沸かす時間が短縮できる。』『カップラーメンやスープもすぐ作れて便利。』というお声をいただいています。今後、浄水型ウォーターサーバー市場での競争が激しくなると予想されますが、御社はハミングウォーターをどのように差別化していこうと考えていますか?白石さん:まずは、「女性目線の使いやすさ」を意識して作られていることが最大の強みですね。また、料金プランは月額3,300円(税込)の定額制なので、大きな負担がなくご利用いただけます。新規ご契約者様には、ハミングウォーター設置後の1ヶ月間は無料でご利用いただけるサービスも展開しています。こういった料金面の施策も差別化につながると考えています。引っ越し時に無料で回収し、新品を届ける「安心サービス」 引用:ハミングウォーター公式ホームページこれからハミングウォーターが目指したいこと、より強化していきたいことを教えてください。大原さん:ハミングウォーターは細部までこだわって作った製品ですが、お客様の中には使いづらい部分や不便に感じているところがあるかもしれません。お客様から使い勝手に関するフィードバックをいただき、多くの方に便利と感じていただけるよう、機能改善に努めていきたいと考えています。白石さん:弊社では月額定額制の他、オプションで「安心サービス」を提供しています。これはお客様の暮らしの変化や予期せぬ事態に寄り添うサービスと、ハミングウォーターを利用していただくうえでのトラブルをケアする補償がセットになっています。例えば引っ越し時には、ご利用中のウォーターサーバーを無料で回収し、新しいウォーターサーバーを無料でお届けします。今後も、お客様に便利にサーバーを継続して使っていただけるようなサービスを検討していきたいと思います。ハミングウォーターのお客様は現在、どういったお悩みを抱えているのでしょうか?白石さん:メンテナンスに関しては、お客様自身でクリーン作業をするのですが、作業がやりにくいという部分があるようです。また、排水経路はお客様から目に見えないので、「本当に綺麗で安心なの?」という不安があるかもしれません。大原さん:給水タンクの中には、雑菌の繁殖を防ぐためUV照射をしています。ただ、お客様からはUV照射している部分は見えません。殺菌効果が目に見えないため、不安を感じているお客様は一定数いらっしゃると思いますが、しっかりと殺菌処置をしているので安心して使っていただけたら嬉しいです。毎日使うものだからストレスのないものを 引用:株式会社コスモライフ公式ホームページ今後、ハミングウォーターを通して、消費者にどのようなライフスタイルの変化をもたらしていきたいと考えていますか? 御社が目指している理想の生活のビジョンについて教えてください。大原さん:私が入社した頃は、東日本大震災の発生直後で、当時はお水への不安が叫ばれていた時期でした。ハミングウォーターをより多くの方に使っていただき、安心、安全なお水が飲めることを実感してほしいですね。それによって生活も豊かになるはずです。私自身も自宅でハミングウォーターを使っていますが、こんなにも便利なのかと驚きましたね。特に子育てでミルクを作る時に役に立ちました。ハミングウォーターは水道水に含まれている不純物をしっかり除去できるので、赤ちゃんに使っても安全なお水です。また、温水をすぐに使うことができるので、沸騰までの時間を待たなくていい。貴重な時間を節約できます。同じような想いをされている方は多いと思うので、お客様の豊かな生活につながったらいいな、と思いますね。最後に、これからハミングウォーターを契約しようか迷っている読者に向けてメッセージをお願いします。大原さん:飲料用としてだけではなく、料理でもハミングウォーターを利用してもらうことで、ちょっとした調理中のストレスから開放されるはずです。お水を沸騰させたり、お鍋にお水を注いだりする作業自体は、大した作業ではないかもしれません。ですが、この小さなストレスが毎日積み重なると自炊の負担も増加すると思います。ハミングウォーターはそんな毎日の小さなストレスを少しでも軽くするため、徹底的に設計にこだわりました。日々のストレスが軽減することで、毎日の生活が便利で豊かになるはずです。 まだ利用したことがない方は、ぜひ一度ハミングウォーターがある生活を体験してほしいと思います。白石さん:ハミングウォーターは使いやすさにとことんこだわったウォーターサーバーです。特に、フィルターのろ過能力が高く、水道水に含まれる不純物をしっかり取り除くことができます。ウォーターサーバーは毎日使うものなので、使っていてストレスを感じないことが大事だと考えています。その点ハミングウォーターは不便を感じない設計になっているので、すぐに日常生活に溶け込むと思います。数あるウォーターサーバーの中でも、使いやすさと性能にこだわった自信作ですので、ぜひお試しください。 ハミングウォーター 公式サイトはこちら ハミングウォーターの解説記事を読む -

【まごころケア食】誰もが安心して歳を重ねられる社会へ:まごころケア食で創る未来
「誰もが安心して歳を重ねられる社会の実現」――。人生100年時代といわれる現代、この理念を掲げ、食を通じて人々の健康な暮らしを支える企業がある。株式会社シルバーライフは、高齢化社会における食の課題に挑戦を続けている。健康的な食生活の維持が困難になりつつある現代社会。管理栄養士による徹底した栄養設計、素材へのこだわり、そして長年研究され抜いた調理技術を駆使することで、「まごころケア食」は、手軽さと栄養バランスを両立した画期的な食のソリューションを実現してきた。今回は、急速な高齢化という社会課題に挑戦し続ける「まごころケア食」の誕生秘話から、その独自の品質へのこだわり、そして未来への展望までを紐解いていく。取材日:2024年10月30日築き上げた技術で食卓に安心を。「まごころ」と「ケア」に込めた想いまずは、企業概要や提供サービスについて教えて下さい。田村:2007年に創業した株式会社シルバーライフは、高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営を主軸とし、フランチャイズ加盟店などへの調理済み食材の販売を行っています。この事業を通じて培った製造技術やノウハウを生かし、冷凍弁当のEC販売や施設向け食材の販売にも事業を拡大しています。現在、当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、2024年7月末時点で売上規模は約135億円に達し、順調な成長を続けています。冷凍弁当のEC販売では主に「まごころケア食」を展開しており、自社サイトを中心に大手ECモールにも積極的に出店し、多様なお客様のニーズに応える形で事業を拡大しています。まごころケア食の開発に至ったきっかけや、誕生までの経緯をお聞かせください。島倉:まごころケア食は、弊社が長年の配食サービス事業で培ってきた強みを最大限に生かして生み出されたサービスです。配食サービス事業から生まれた数百種類におよぶ惣菜のレシピを活かし、お客様に飽きのこないメニューバラエティを提供することができると考えました。また、配食サービスの事業で培った大量調理の技術により、安全で美味しい食事を、リーズナブルな価格でお客様に提供することも可能になりました。「まごころケア食」という名前にはどのような意味や思いが込められているのでしょうか?田村:「まごころ」という言葉は、配食サービス「まごころ弁当」で培ってきた商品開発のノウハウや、お客様への真摯な姿勢を受け継いだものです。我々の原点である「心のこもったサービス」との想いをそのまま名前に込めました。さらに、「ケア」という言葉には、ただ食事を提供するだけではなく、お客様一人ひとりの健康的な暮らしを支えたいという願いが込められています。日々の食生活を丁寧にサポートし、心も体も満たしていくようなサービスでありたいと考えています。「薄味でもおいしく」の追求は妥協しない!品質と美味しさを守る知恵メニュー開発のプロセスの中でどのような点に注力されていますか?島倉:メニュー開発にあたっては、管理栄養士が、「薄味でもおいしく」「食事として満足できる内容」の実現に注力しています。多くの日本人が1日当たり10.1gを超える食塩を摂取している中*1、「まごころケア食」のメニューでは食塩相当量が1食あたり2.0g以下に抑えられているのです。減塩では薄味に感じられてしまう可能性を配慮し、旨味や酸味を上手く取り入れることで「薄味でもおいしく」感じられるよう、レシピ開発には工夫を凝らしています。また、メニューでは4種類の惣菜が組み合わされていますが、「こってりした主菜にはあっさりした副菜を組み合わせる」など、食べやすさにも配慮した献立作りを行っています。メニュー開発では、まず、何を目的としたレシピなのかを企画し、その後、商品開発室で少量の試作をおこない、品質の確認をおこないます。次に、大鍋やスチームコンベクションオーブンなどを使ったラインテストを実施し、大量調理を想定した調理工程の確認を行います。その後、栄養計算をおこない、バランスの取れた献立の作成に取り組み、本製造に至るという流れです。それぞれの段階で必要に応じて社内での承認を得ながら、各段階で徹底的な検証を重ね、お客様に満足していただける商品を生み出すべく、丁寧なプロセスを経ています。 日本生活習慣病予防協会『食塩摂取量の平均値は10.1g、男性10.9g、女性9.3g 令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」より』サービス開始から、最も苦労されている課題についてお聞かせください。島倉:まごころケア食を運営する上で、私たちが最も苦労している点は原料の安定供給です。原料の調達は、自然災害や天候不順による不作、また国際的な情勢の影響で価格が高騰するなど、私たちの力ではどうにもならない外部要因に大きく左右されます。例えば、大雨による野菜不作や漁獲量の減少などが起こると、原材料価格の高騰などを理由に使用していた食材を完全に変更せざるを得なくなります。そうすると、これまで提供していた惣菜のバリエーションが減ってしまうという課題に直面します。そのため、急いで代替できる原料を探したり、新たな惣菜の開発に取り組まなければなりません。特に、毎月数トンものボリュームで使用する主要な原料が手に入らなくなると、大変な混乱を来たします。加えて近年の食材高騰の影響もあり、「クオリティを落とさず価格も上げずに」対応することが大きな課題となっています。この課題に立ち向かうために、常に食材の状況をリサーチすることが欠かせません。「今年はこの食材の品質が良い」「今後はこの食材が使えそう」といった情報をもとに、献立の見直しを定期的におこなっています。大量調理において、これまで使ったことがない食材を使うことには臆病になりがちですが、積極的に「この食材は使えるだろうか?」と検討し、チャレンジしていく精神が大切です。「毎日」という価値を食卓へ。健康と簡単の両立で、明日の食を応援高齢化社会の中で、どんな未来を描いていますか?また、まごころケア食が果たすべき役割とは何でしょうか?島倉:多くの人々が「調理の手間をなくしたい」一方で、「でも健康的な食事がしたい」というニーズを抱えているのが現状です。まごころケア食は、このニーズに応えるべく事業を展開しています。簡単に調理できる冷凍弁当を提供しつつ、その中に十分な栄養を確保し、健康志向のニーズに応えることができる点が私たちの強みです。企業理念にも掲げているとおり、私たちは誰もが安心して歳を重ねていける社会の実現を目指しています。調理時間をかけずに済む食事の提供を通じて、皆様の健康維持に貢献していきたいです。田村:私たちは、冷凍弁当が一過性のブームにとどまらず、健康的な食生活を支える定番商品として、社会の中で広く受け入れられる存在になると考えています。自炊や食事準備の負担が増加する中、便利で栄養バランスの取れた冷凍弁当の需要は、今後ますます高まると予想されます。忙しい現代社会において、どの年代の方々にも、手軽に健康的な食事を提供できる選択肢として「まごころケア食」が広く選ばれるよう、私たちは商品開発や広告宣伝に力を入れていきます。利用者の声をどのようにサービスに反映していますか?田村:お客様から頂いたご要望は、常に商品開発の貴重な参考とさせていただいています。食の好みは人それぞれで異なりますので、すべてを一度に反映することは難しいですが、より美味しい商品をお届けするために、使用する食材や調味料の選定・調整を丁寧に行い、改良を重ねています。また、定期的なリニューアルや新メニューの開発にも積極的に取り組んでいます。まごころケア食は「ごちそう」を目指すのではなく、栄養バランスが良く、毎日食べても飽きない優しい味わいを実現することを目標としています。これにより、特別な日だけではなく、日常の食生活に自然と溶け込む存在でありたいと考えています。外食や自炊と組み合わせながら、まごころケア食を気軽に取り入れていただけるよう、今後もお客様の声を丁寧に汲み取りながら、商品改善を進めてまいります。世代を超えて広がる、健康という選択ー安心して歳を重ねられる未来へ今後、サービスをどのように拡大・進化させていく予定ですか?田村:まごころケア食は、業界でも最安値級の価格設定を実現しており、幅広い年代のお客様に気軽にお試しいただける商品です。現在、多くのお客様にご支持いただいており、特に健康を気遣いながらも手軽さを求める方々に選ばれています。どの世代の方にもご満足いただけるよう、バランスのとれた商品内容にこだわっています。今後も、さまざまなライフスタイルやニーズに寄り添う形で、より多くの方々にご利用いただけるような取り組みを進めていきたいと考えています。その上で、競合他社の参入が活発化しており知名度の向上が重要な課題となっています。これに対応するため、さまざまな企画を通じて「まごころケア食」のブランド力を高め、より多くのお客様に選ばれる存在を目指していきます。まごころケア食、最終的にどのような社会や未来を実現したいと考えていますか?田村:弊社の経営理念は、「食の観点から誰もが安心して歳を重ねていける社会の実現」です。この理念のもと、私たちは冷凍弁当を通じて、食事に関するさまざまな社会課題の解決に貢献したいと考えています。たとえば、ライフステージや生活環境の変化に伴う食生活の悩みを解消するための手助けを目指しています。まごころケア食は、栄養バランスに優れ、毎日でも取り入れやすい商品を提供することで、健康的な生活をサポートする存在でありたいと考えています。特に、忙しい方や食事の準備が負担に感じられる方にとって、気軽で便利な選択肢として広く活用いただけるよう努めています。これからも、お客様一人ひとりのニーズに寄り添いながら、日々の食生活をより豊かにし、誰もが安心して年を重ねていける、そんな社会の実現に向けて挑戦を続けていきます。 まごころケア食 公式サイトはこちら まごころケア食の解説記事を読む