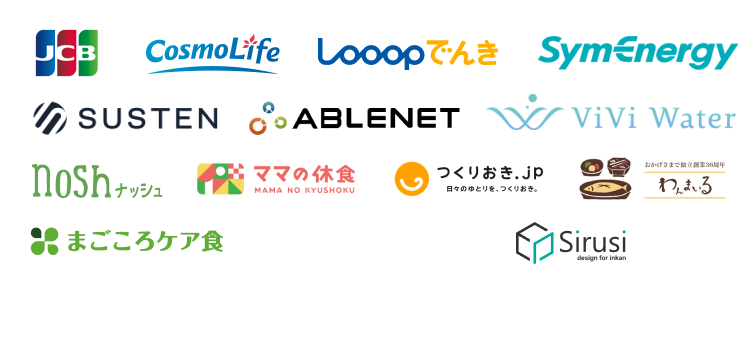-

【三ツ星ファーム】美味しさと健康の三ツ星基準:宅配弁当の新常識
健康と美味しさは両立できるのか。その問いに、三ツ星ファームは冷凍宅配弁当で挑戦を続けている。毎日の食事を、ただの栄養補給ではなく、喜びと元気の源にしたい。健康と美味しさを両立させた冷凍弁当は、従来の宅配食のイメージを根本から覆す可能性を秘めている。健康的でありながら本格的な味わいを追求する三ツ星ファームの挑戦の全貌を明らかにする。取材日:2024年11月28日手軽で健康な美味しい食事!特別で非日常の食体験という想いを込めて 引用:三ツ星ファーム公式HP三ツ星ファームのサービスが誕生したきっかけについて教えてください。三ツ星ファームのサービスは、2020年、コロナ禍の真っただ中に誕生しました。外出制限により外食が難しくなる中、多くの人々が自宅での食事を余儀なくされていた時期です。当時、私たちは市場に出回る宅配食サービスを丁寧に調査しました。その結果、まだまだ世の中では「冷凍食品=あまり美味しくない」というイメージが多いことに気づいたのです。おいしい宅配弁当を提供することで、外食の代替となり得るサービスを創りたい。そんな想いから、味にこだわった冷凍宅配食の提供を決意しました。コロナ禍の困難を、美味しい食事を通じて少しでも解消できないかという思いが、私たちのサービス立ち上げの原動力だったのです。ブランド名「三ツ星ファーム」に込められた意味や願いは何ですか?「三ツ星ファーム」というブランド名には、わたしたちの食へのこだわりと想いが込められています。ライフスタイルが多様化する現代社会において、忙しい毎日の中、食事に費やす負担はとても大きなものです。サービスの誕生当時からわたしたちが大切にしているのは、「食」を通じて皆さまの日常に寄り添い、幸せな気持ちになったり、ほっと安心したり、ワクワク感を感じたり、そんな情緒的な体験をご提供することです。一流シェフの監修のもと、食欲そそる色とりどりの見ても美味しい食べても美味しい味の追求。そして管理栄養士監修でたくさんの食材で栄養バランスの整ったお食事を提供しています。しかも、買い出しや調理や後片付けの負担を減らしてくれるお手軽に食べられる食事を厳選しています。なので、趣味や家族との団欒の時間も与えてくれます。「三ツ星」という言葉には、そんなわたしたちの商品へのこだわり、クオリティの高さへの自信が込められています。また、「ファーム」という言葉には、「ゴロゴロ野菜」がたっぷりと使われたナチュラル感や、ひとつひとつの商品を心を込めておつくりしている想いを表しています。「三ツ星ファーム」は、わたしたちの提供する食を通じて、皆さまの食体験がより豊かになるよう、そして、その食体験が皆さまの生活全体をより良いものにするお手伝いになってくれたら嬉しい、そんな願いが込められたブランド名なのです。三ツ星ファームの強みや特徴を教えてください。三ツ星ファームの強みは、おいしさだけではありません。現在100種類以上のメニューを展開し、お客様のニーズに幅広くお応えしています。特に注目すべきは、栄養面への徹底したこだわりです。すべてのメニューが管理栄養士監修となっております。メニューも原則1食あたりカロリー350kcal以下、糖質25g以下、たんぱく質15g以上という明確な基準を設けています。これは、健康を意識しながらも、美味しさを妥協しないという私たちの姿勢の表れです。美味しさに加え、豊富な種類と栄養バランスという点が、三ツ星ファームの大きな特徴となっています。ミシュランシェフが監修し、工場では涙の試作。情熱のメニュー開発 引用:三ツ星ファーム公式HP一流シェフ監修のメニューを提供する上でのこだわりは何でしょうか?三ツ星ファームのシェフ監修には、明確な基準があります。最も大切にしているのは、私たちの理念に共感し、高い技術と実績を持つシェフを選ぶことです。現在メインで監修いただいているのは、ミシュランで1つ星を獲得した四谷の割烹「鈴なり」のオーナーシェフです。村田シェフが監修したメニューは、今も多くのお客様に支持され、人気メニューの1つとなっています。私たちは、一流シェフの知恵と技術を通じて、お客様に本格的な味わいをお届けすることにこだわり続けています。 引用:三ツ星ファーム公式HPメニュー開発において、苦労した点は何ですか?メニュー開発における私たちのこだわりは、単に新メニューを増やすことではありません。毎月4〜5種類の新メニューを出すことを目指していますが、数を追うことで本来の目的を見失わないよう注意しています。開発プロセスは徹底的で、工場と何度も試作を重ね、管理栄養士に確認し、社内でも繰り返し試食を行います。味付けや食感の細部にまでこだわり、時には1年近くかけて一つのメニューを完成させることもあるのです。お客様の好みは様々ですが、全てのメニューに対して妥協のない姿勢で臨んでいます。「OK」が出た時には、スタッフが感極まって喜ぶほど、一つ一つのメニュー開発に情熱を注いでいるんです。食材については、なるべく国産のものを使用しながら健康に良いものを選ぶよう工場と連携しています。利用者に飽きがこないようにするための工夫を教えてください。各料理は、メニュー全体のバランスを見て食感や味付けが均一にならないように細心の注意を払っています。メニュー開発では、宅配弁当だけでなく、ピザ、冷凍ホットサンド、スイーツ、冬は鍋など、幅広いジャンルに拡大し、多様な選択肢を提供しています。加えて、特に注力しているのがメニュー名の工夫です。単なる「ハンバーグ」ではなく、味や雰囲気を想起させるメニュー名にしています。例えば「濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ」や「ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン」 「濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ」 (引用:三ツ星ファームメニューページ) 「ナポリの風香る チーズをまとったトマトチキン」 (引用:三ツ星ファームメニューページ) そして、和食メニューであれば「丹波の西京味噌の 銀鮭焼き弁当」、中華メニューであれば「天津風卵の 贅沢紅ズワイガニの白雲あん」など思わず食べてみたくなるようなようなメニュー名にするように心がけています。 「丹波の西京味噌の 銀鮭焼き弁当」 (引用:三ツ星ファームメニューページ) 「天津風卵の 贅沢紅ズワイガニの白雲あん」 (引用:三ツ星ファームメニューページ) 料金設定やキャンペーンに関するこだわりを教えてください。三ツ星ファームの料金設定には、新規のお客様を大切にする思いが込められています。初回は1食500円以下に抑え、できるだけ多くの方に試していただけるよう工夫しています。味へのこだわりからどうしても原価は高くなってしまいますが、、初回は赤字覚悟でのサービスです。それでも、興味を持っていただいた方が始めやすい料金設定にしております。しかし、私たちは味と品質への自信と、継続的なキャンペーンの充実により、ほとんどのお客様に2回目以降もご利用いただけると確信しています。競合他社が1食あたり300円前後で提供する中、私たちの初回メニューは1食あたり467円(税込)と、やや高めの設定です。ただし、その分の価格差は、確かな品質と栄養面で必ず還元できると自負しています。「安さ」だけを追求するのではなく、真に価値のあるサービスを提供することを大切にしています。三ツ星ファームで人生が変わった!諦めていた美味しい食事を再発見 引用:三ツ星ファーム引用画像現在の利用者層について、メインターゲットについて教えてください。三ツ星ファームのメインターゲットは、おいしさと健康を大切にし、忙しい日常の中で質の高い食事を求める方々です。具体的には、30代から50代の女性、特に子育てや仕事に忙しい方がメインの利用者層です。当初は女性をターゲットに開始しましたが、意外にも男性からの反響も大きく、コンビニ弁当に飽きた男性や、多様で美味しい食事を求める男性にも一定数ご利用いただいています。全体の比率としては女性の方が高いものの、性別を問わず、「おいしく」「健康的に」食べたいという方々に支持されているサービスです。利用者層に関しては、私たちが意図したわけではなく、お客様の口コミはもちろん、最近では、メディアや雑誌から女性向けのおすすめサービスとして紹介したいという声をいただくことも増えています。コロナ禍以前とその後で、利用者のニーズの変化はありましたか?コロナ禍前は事業を展開していませんでしたが、パンデミック中は外出困難による食事の代替として利用する方が多くいました。コロナ明け後は、利用者のニーズが変化し、時間がない、食事制限がある、といった具体的な課題解決を求める30〜40代の女性が主な顧客層となっています。今後は、これまでのターゲット層を継続しつつ、50〜60代の男女にも積極的にアプローチしていきます。子育てが一段落した世代や、忙しい20代の男女など、幅広い層に向けて、各世代や性別に応じたコミュニケーション戦略でプロモーションを展開する方針です。お客様からの印象的な言葉やエピソードを教えてください。お客様から、サービスを通して心温まる声を多数いただいています。特に印象的なのは、「料理が苦手で、毎日健康的な食事を作ることができないので、三ツ星ファームさんを始めました。おいしくて、作ったり買い物に行ったりする手間なしで野菜が摂れて、とてもありがたいです。」というお声や「毎日の献立を考えなくてもよくなり、ストレスが減りました。毎日何をたべるか楽しみになりました。」などのお声です。単なる時間節約だけでなく、諦めていたおいしい食事を再発見し、生活の質を向上させる効果があったと実感しています。 サービスをご利用いただいた方へのアンケートより抜粋を記載課題として感じている点や、特に改善に取り組んでいる課題はありますか?これまで、サービスの使いづらさが大きな課題となっていました。特に、メニュー変更や解約の手続きが複雑で、お客様の使いやすさの観点から改善の余地があったのです。この1年で、顧客体験の向上に注力し、大きな改善を実施しています。新しく開発したアプリにより、メニュー変更、解約手続き、配送日の変更などが非常に簡単になりました。以前と比べて、アプリから簡単に操作できるようになったのです。また、メニュー開発においても大きな変化があります。例えば、お子様が食べられるキッズメニューや、男性向けの量の多い「満腹メニュー」など、より幅広い層のお客様に対応できるメニューを開発しました。従来の60〜70種類のメニューから、より多様で柔軟な選択肢を提供することで、顧客満足度の向上を目指しています。誰かが心を込めて作ってくれた人の手にこだわり、温もりを感じる冷凍食品 引用:三ツ星ファーム引用画像宅配弁当の品質を高めるために活用している技術や工夫、また審査基準があれば教えてください。冷凍食品の課題である「水っぽさ」に対しては、最新の急速冷凍技術を活用しています。工場では、エビマヨなどの人気メニューを、フライヤーでの調理から盛り付けまで、手作業で行っていることが多いです。具体的には、エビを揚げてからマヨネーズをつけるなど、一つ一つの工程を人の手で行い、機械で急速冷凍することでおいしさをそのままお届けしております。機械化によるコスト削減も可能ですが、食品の品質や温かみを優先しております。そこには単なる食品ではなく、「誰かが心を込めて作ってくれた」という温もりを感じていただきたいという思いがあります。盛り付けから調理まで、できる限り人の手でこだわることで、ブランド全体に温かみを感じていただけると信じています。環境に配慮した観点から、注力している点があれば教えてください。三ツ星ファームでは、環境への配慮も意識しております。まず、お弁当のパッケージには環境負荷の低いパルプモール素材を使用しており、通常のプラスチックと比較して環境に優しい選択です。この取り組みは、お客様からも高く評価されており、環境意識の高い方々から好評をいただいています。SDGsの観点からは、食品ロスの削減にも積極的に取り組んでいるんです。余剰在庫については、アウトレット価格での販売や、渋谷区の子供食堂への無償提供など、可能な限り無駄にしない工夫を行っています。子供食堂への弁当提供は、社会貢献の側面からも意義深い取り組みです。このような取り組みを通じて、環境と社会に配慮した事業運営を目指しています。読者の方にメッセージをお願いします!三ツ星ファームの特徴は、味と栄養にこだわった食品づくりです。ここ数年で、宅配食サービスはかなり増えてきました。そういった中で私たちは、社内で徹底的に研究を重ね、満足のいく製品だけを世に送り出しています。特に味の追求には力を入れており、これが私たちの大きな特長です。また、お客様に長く続けていただくための工夫にも注力しています。初回のみならず定期的なキャンペーンや、お客様が飽きないための様々な取り組みを通じて、継続的なご利用をサポートしています。こういった私たちの想いを、より多くの方々に知っていただきたいです。三ツ星ファームは、おいしさと栄養にこだわり、お客様に寄り添うサービスを目指しています。 三ツ星ファーム 公式サイトはこちら 三ツ星ファームの解説記事を読む -

【わんまいる】国産食材100%宅食サービス『わんまいる』:あくなきこだわりの秘密に迫る
「わんまいる」が届けるのは、単なる食事ではない。株式会社ファミリーネットワークシステムズ代表取締役社長の堀田茂の幼少期の祖父母からの教え、自らの料理人としての経験、全国の生産者との絆が生み出した、日本の豊かな食文化の結晶だ。100%国産の誇りと、合成保存料・合成着色料無添加の優しさが織りなす、革新的な冷凍惣菜宅配サービス。手軽さと栄養、美味しさと安心。相反する要素を見事に調和させた「わんまいる」の裏には、日本の食文化を守り抜く熱い想いが隠されていた。「わんまいる」が描く未来図は、私たちの食卓を越えて、日本全国の食材生産者や地方の未来をも変えようとしている。社長が自らの足を運び、目で見て、一人一人と深めてきた絆――。細部にまで宿るこだわりの秘密に迫れば、日本の食文化の未来が見えてくる。取材日:2024年10月1日お客様の忠犬に!国産食材100%、合成保存料不使用で一人一人の生活を豊かに 引用:わんまいる公式ブログ「わんまいる」のサービス概要と特徴について教えてください。まずは、私たちの主力商品である「冷凍ミールキット/わんまいる健幸ディナー」をご紹介します。食材の選定には妥協を許さず、創業者である現社長が自ら日本各地を巡り、自身の目と舌で確かめた上で厳選した国産食材を使用しています。調理においては、「餅は餅屋」の精神で、各料理に特化した専門調理会社に委託製造を行っているんです。例えば、焼魚は創業100年を誇る神戸市中央卸売市場魚河岸の職人が遠赤外線ガス台で焼き上げており、各料理の専門家の技術を活かすことで、高品質な味を実現します。健康面にも配慮し、国産食材100%、合成保存料無添加にこだわっているんです。主菜1品と副菜2品を個包装の真空パックで冷凍し、温かい料理は湯せん、冷たい料理は流水解凍で簡単に調理できるよう工夫しています。お客様からのご要望に応えて開発したのが「美食弁当」です。 引用:わんまいる公式HP美食弁当は、食品添加物無添加、国産食材100%にこだわり、洗い物が不要なワンプレート型の冷凍おかずです。電子レンジで温めるだけで、主菜1品と副菜2品が楽しめる手軽さが好評で、日々お客様が増えています。さらに、お客様の多様なニーズに応えるため、味噌汁、シチュー、麺類、米飯など、様々な冷凍惣菜を単品でも購入できるよう豊富に取り揃えているんです。販売チャネルとしては、ネット通販を主軸としつつ、創業時から続けているカタログ宅配事業に加え、百貨店や通販事業者向けの卸事業も展開しています。最近では、東京電力ホールディングス株式会社と協業し、国産お魚料理の定期便「和・洋・中」冷凍サブスクリプションサービスを開始しました。サービスの開始に合わせて専用サイトを立ち上げ、食に関する催事の運営も行っています。わんまいるのサービスを始める際に、最も大切にした理念や価値観は何ですか?私たちが最も大切にしている理念は、「わんまいる」という名前に込められています。この名前は、「一品からお届け(参る)」という意味と、「お客様の忠犬(ワン)」になるという二つの意味から名付けました。2005年に伊藤忠商事と業務提携し、「わんまいるシステム」を開発しました。わんまいるシステムは、一品から受注し、一品からお届けするという、現在では当たり前になっていますが、当時としては画期的なシステムだったのです。私たちは食材の調達から洗浄、カット、最終調理の「ラストワンマイル」まで、自分達で担っています。 引用:わんまいる公式HP特に力を入れているのが、高齢者や出産・育児中の方、親の介護をされている方、働く主婦の方々への支援です。これらの方々の家事負担を軽減し、簡単に作れて美味しく、かつ健康的な食事を提供することで、豊かな暮らしを実現することを目指しています。さらに、私たちは生産・加工・流通・販売まで一貫した取り組みを行うことで、日本の農業・漁業の振興にも貢献したいと考えています。わんまいるの理念は、お客様一人一人の生活を豊かにすることと、日本の食産業全体の発展に寄与することの両立にあるのです。お客様の身近な存在として、そして日本の食を支える企業として、日々サービスの向上に努めています。田畑の土から動物の飲む水までー社長自らが細部までこだわり抜いた36年間 引用:わんまいる公式HP合成保存料や合成着色料などが無添加の国産食材を用意するには、全国の生産者の方々の協力が不可欠だと思います。全国の生産者とのつながりをどのように築いていったのかを教えてください。1988年に独立して以来、私は食材の仕入れ方を大きく変えました。市場での仕入れをやめ、直接産地に足を運んで漁協や水産会社から買い付けるようになりました。それ以来36年間、稚内から沖縄まで日本中を訪れ続けています。日本各地には、「ポツンと一軒家」のようなまだ全国的に知られていないこだわりの生産者や、地元で長年食べ継がれてきた食材、郷土料理が数多く存在します。長年の経験から、土を見るだけで作物の質が分かり、畑を見るだけで生産者の努力が感じられるようになりました。農作物の品質は、同じ畑でも日当たりや育ち方で大きく変わります。畜産においても、飼育環境が重要です。清潔で広々とした環境で育った動物は質の良い肉になります。特に興味深いのは、生後間もない動物を女性が育てると肉質が良くなることです。鶏の処理方法も重要で、ストレスを与えずに処理すると肉質が良くなります。また、自動化された工場よりも、一羽ずつ丁寧に解体する方が品質が高くなります。美味しい料理には、何よりも食材の質が重要です。こだわりの生産者や加工会社と良好な関係を築くには、利益よりも品質を重視する姿勢と、その生産者と対等に会話ができる十分な知識と経験が必要です。36年間にわたる全国各地の訪問と生産者との直接的な交流を通じて、私たちは単なる取引先以上の信頼関係を築いてきました。実際に自分の足で出向き、目で見てつないだ絆こそが、合成保存料や合成着色料を使用せず、国産100%にこだわった安全で美味しい食材を安定して提供できる基盤となっています。保存方法や調理方法にもこだわられているそうですが、真空調理や急速冷凍技術を採用した背景にはどのような理由があるのでしょうか?元々は、お客様から冷凍保存ができる真空パック商品の要望を受け、開発を始めました。私たちはそんな中で、真空調理の第一人者である石川シェフと出会いました。石川シェフは阪急ホテルの料理長時代にフランスで真空調理を学び、日本で普及に貢献された方です。私たちは石川シェフと顧問契約を結び、指導を仰ぐことにしました。石川シェフから学んだ重要なポイントは、真空圧力によって調味料や出汁が食材に染み込むため、通常の3分の1の調味液で十分な味が出せること、そして食材本来の旨味を引き出せることでした。また、主菜・副菜・副副菜を別々に個包装し真空パック冷凍することで、手間と包材のコストはかかりますが、料理に合わせた最適な解凍方法を選べることがわかったのです。暖かい料理は湯せん、冷たい料理は流水解凍と、解凍する時間も個別にできることで、料理に合せた解凍でそれぞれ最適な食感と味を楽しめます。一方、電子レンジ解凍は、主菜も副菜も同じ時間で高温加熱するため、残念ながら作りたての料理と同じクオリティを保つのは難しいと考えています。手間はかかりますが、大切な家族と食べる夕食には、お客様自身で盛り付けていただくことで、出来立ての手料理の味わいを楽しんでいただけるでしょう。そして、急速冷凍と一口に言っても、さまざまなタイプの凍結機が有り、何を冷凍するかによって向き不向きがあります。大きくはアルコール凍結機と冷風凍結機の二種類に分かれ、それぞれにさらに多くの種類があります。また、全ての料理が急速冷凍に適しているわけではありません。お客様のニーズにお応えしたことから始まった真空調理と急速冷凍技術の採用でしたが、料理の食感と味わいを最大限に引き出す最適なアプローチとなりました。食の質にとことんこだわることが、地方を創生し、次世代につながるわんまいるのサービスはどのようなお客様に向けて、作られているのでしょうか?わんまいるは、お客様の多様なニーズに応えるため、2種類の冷凍おかずセットを用意しています。 引用:わんまいる公式HP一つは「冷凍ミールキットタイプ」の健幸ディナーで、湯せんまたは流水解凍して盛り付けて楽しむスタイルです。これは主に家族と一緒に食事を楽しむ世帯向けとなっています。 引用:わんまいる公式HPもう一つは「レンジ解凍の冷凍美食弁当」で、洗い物不要のワンプレート型となっており、一人暮らしの方に特に適しています。両タイプともに、主菜はもちろんのこと、副菜にもこだわりを持って調理しています。国産食材を厳選し、品質と美味しさを徹底的に追求しているため、輸入食材に不安を感じる方にも安心してお召し上がりいただける商品です。わんまいるの商品をお選びいただくことは、単に美味しい食事を楽しむだけでなく、日本の農業・漁業・食産業の振興、ひいては地方の活性化にもつながる取り組みです。今わんまいるが抱えている課題は何ですか?特に、今後どのように解決していきたいと考えていますか?紛争や気候変動などの世界情勢の変化により、世界的なインフレが起こり、日本国内においても、食材価格の高騰や人件費の上昇が顕著となっています。国内外の物価上昇の状況下で、わんまいるは品質と美味しさの向上に注力し、付加価値を高めることで、食の質にこだわる、違いのわかるお客様にご利用いただきたいと考えています。同時に、わんまいるは企業の福利厚生の一環としての活用も提案しているんです。具体的には、社員食堂の代替や補完として、また出産・育児・親の介護に携わる従業員、さらにはテレワーク中の従業員の食生活サポートとして、わんまいるの商品をご活用いただけます。企業様に一部費用負担をいただくことで、従業員様の健康的な食生活を支援し、ワークライフバランスの向上にも貢献できると確信しています。わんまいるを通して、食卓にどのような価値を提供したいと思っていますか?将来的にどのような食の未来を描いていますか?わんまいるは、一日の疲れを癒す大切な時間である夕食を、より豊かで意義深いものにすることを目指しています。そのために、日本各地の魅力的な食材を贅沢に使用した献立メニューを提供し、美味しさと楽しさを通じて、日本の食文化の素晴らしさを体験していただけるよう努めています。さらに、私たちにとって、日本の豊かな食文化を次世代に継承することも重要な使命です。お客様からは、「普段自分ではなかなか作れない各地の郷土料理も楽しめる」というお声をいただいており、こうしたニーズにも応えるべく、新たな商品開発にも力を入れています。地域の特色ある食材や調理法を活かした郷土料理を通じて、日本の食の多様性と奥深さを感じていただくことができるでしょう。わんまいるは、こうした取り組みを通じて、単なる食事の提供にとどまらず、日本の食文化の豊かさを体験し、継承する機会を提供することを目指しています。「学歴より食歴」ー日本全国の美味から紡ぐ、未来につながる食事わんまいるの利用を迷っている読者に向けて、サービスの魅力やメッセージをお聞かせください。私の食へのこだわりの原点は、祖父母から受け継いだ日本の伝統的な食文化にあります。祖父母は季節の行事食を大切にし、栄養バランスを重視した食事を教えてくれ、化学調味料を使わず、和食の基本調味料でシンプルに味付けし、食材本来の味を活かす調理法を学びました。この教えは、23歳で居酒屋の店長になった時に実践しました。毎朝市場で新鮮な食材を仕入れ、丁寧に下処理をし、注文を受けてから調理したのです。この経験から、国産食材100%と無添加にこだわるようになりました。このこだわりは、現在のわんまいるの「健幸ディナー」と「美食弁当」に受け継がれています。これらの商品は、単においしいだけでなく、科学的な裏付けのある健康増進食として認められつつあります。「健幸ディナー」は、医療情報サービス最大手の企業と筑波大学付属病院との連携により、糖尿病重症化予防の臨床試験で採用されました。その成果は権威ある学術集会で発表され、高い評価を受けています。「美食弁当」も同様に、某自治体の成人病予防・健康改善プログラムの夕食として採用されており、効果が期待されているのです。私たちは「食歴は学歴より大切である」という信念のもと、お客様の健康と幸せを追求しています。実際に、私自身も「健幸ディナー」を継続して食べることで、好き嫌いが減少し、多様な食材を受け入れられるようになりました。わんまいるは、祖父母から受け継いだ伝統的な食の知恵と、現代の科学的知見を組み合わせることで、おいしさと健康の両立を実現しています。質の高い食材と丁寧な調理法へのこだわりが、お客様の健康と幸せにつながると信じています。 わんまいる 公式サイトはこちら わんまいるの解説記事を読む -

【nosh】ナッシュが届ける本当の価値:健康的な食事への想いと未来への約束
日本人の三大死因である「悪性新生物(がん)」「心疾患」「脳血管疾患」は、「生活習慣病」と呼ばれている。「東京都保健医療局 人口動態統計年報(確定数)令和4年」の調査結果によると、生活習慣病による死亡者数は、死亡者全体の半分以上を占めており、三大生活習慣病が*全体の46.6%を占めているという結果を発表している。生活習慣病は、食事、運動、休養(睡眠を含む)、喫煙・飲酒などの生活習慣と深いかかわりがあり、食生活における栄養の偏りも大きな影響を与えているのだ。日本に蔓延する生活習慣病だが、食事から健康へアプローチする企業が、今回紹介する「ナッシュ株式会社」だ。ナッシュ株式会社は、宅配食「nosh(ナッシュ)」の販売を通して、人々が意識せずとも自然と健康になれる社会の実現を目指している。今回の取材では、健康的な食事への情熱、ユーザーへの想い、そしてサステナビリティへの取り組み......ナッシュの情熱と未来へのビジョンを紐解いていく。取材日:2024年10月9日生きている間により健康的で幸せな時間をー「健康」×「手軽さ」の価値まずは、ナッシュのサービスの概要や提供価値などについて教えてください。ナッシュ株式会社は冷凍宅配弁当のサービスを通じて、「健康」と「手軽さ」という二つの重要な価値をお客様に提供しています。健康面では、1食あたり糖質30グラム、塩分2.5グラム以下の基準を設け、日々の食事の一部を当社の弁当に置き換えることで、健康的な食生活を応援しています。主に単身の方や忙しい20代から30代の方々に使っていただいており、時間がない中でも、簡単に栄養のバランスが取れた食事を提供することで、自分で料理をする難しさや、コンビニの食事で栄養を摂りすぎてしまう問題を解決しています。当社のサービスの特徴は、冷凍という形で、健康的で手軽な食事を提供していることです。これにより、将来的な生活習慣病の危険性を減らすことにつながり、忙しい現代人の生活スタイルに合った食事の選択肢を提案しています。一般的に考えられる競合は、同じ食や健康分野でBtoCサービスを展開している会社ですが、実は本当の競合はファストフードやスーパーのお惣菜となります。現代の生活様式は健康とやや相反する面があり、生活習慣病のリスクがある食事は、満腹感や幸福感を得やすいという印象があります。しかし、好きなものを食べ続けるだけでは長生きはできず、健康な社会も作れません。そこで私たちは、適切な食生活とは何かを改めて考え直し、提案しています。コンビニなどで手軽に食事が手に入る現代の日本社会において、いかに健康的な選択肢を提供し、社会全体の健康を向上させるかという観点から事業に取り組んでいます。 引用:nosh公式HPナッシュのサービスを始めるきっかけや背景は、何ですか?現在の社長である田中が立ち上げた葬儀比較のサービス業が、ナッシュ創業の原点となります。前職では、葬儀の価格を100万円から200万円程度かかっていたものを最適化し、より安価にすることを目指していました。しかし、その過程で亡くなってから悲しむよりも、生きている間により健康的で幸せな時間を過ごすことの方が大切ではないかと考えるようになりました。人生の最後を飾る「エンディング」だけでなく、そこに至るまでの「プロセス」にも注目すべきだという気づきでした。この考えが、現在のナッシュというサービスにつながっています。死は避けられませんが、そこに至るまでの過程をいかに健康的に、幸せに過ごすかが重要です。健康的な生活を送り、周りの人々と長く幸せな時間を過ごせる社会を作ることこそが、私たちが取り組むべき本当の社会的課題だと理解しています。コロナ禍を境として、ユーザーのニーズの変化などは感じていますか?コロナ禍は、予想外にも当社にとって追い風となり、約8倍の売り上げアップとなりました。在宅勤務が一般化し、外食の機会が減少したことで、自宅での食事に対する需要が高まりました。健康意識の向上以上に、自宅で簡単に健康的な食事を摂れることや、買い物などで外出しウィルスに感染するリスクを軽減できる点が、お客様に選ばれる大きな要因となりました。コロナ後の現在でも、完全に以前の生活様式に戻ったわけではありません。リモートワークは新しい働き方の一部として定着し、これが当社の売上やシェアの拡大につながっています。大手企業も続々とこの業界に参入してきていますが、当社が先駆者として市場を開拓してきたことが、現在も選ばれ続ける理由の一つだと考えています。世界中の人々を健康にしたい。だからこそ、多くの人に選んでほしい。 引用:nosh公式HPナッシュのサービスの強みを教えてください。健康的で手軽な食事を提供するサービスが増える中、当社の最大の強みは価格にあります。これは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションに基づいています。社会を健康にするためには、多くの人に選んでもらい、実際に食べてもらう必要があるからです。現在、物価上昇と原材料費の高騰で多くの企業が値上げする中、当社はこれまでに3回も価格の値下げに成功しています。価格戦略を実現するために鍵となるのは、「インハウス化」です。マーケティングから製品の設計、製造、物流に至るまで、可能な限り自社で行っています。例えば、マーケティングでは、SNSやYouTubeでの広告動画制作も社内で行っており、お弁当製造会社でありながら、クリエイティブな面でも自社の力を活かしています。外部委託に伴うマージンを削減し、自社で製造工場や物流拠点を持つことで、コストを抑え、そのメリットをお客様に還元しています。インハウス化へのこだわりは、当社のカルチャーとして深く根付いており、新しいサービスや戦略を検討する際も、最終的にはインハウス化できるかどうかが重要な判断基準となります。外部サービスを使うのは、スピーディーに実証実験を行う場合などに限られ、長期的にはすべてを自社で行うことを目指しています。 noshの工場メニュー開発のこだわりや強み、開発のプロセスについても教えてください。当社のサービスにおいて、美味しさは絶対的な条件です。この背景には、当社の「顧客中心主義」があります。安価で健康的であり、私たちがどれほど良いと思う商品でも、味が美味しくお客様に選ばれ続けなければ意味がありません。そのため、常にお客様の声に耳を傾け、それを製品開発に反映させる仕組みが確立されています。当社の商品開発プロセスは非常に厳格で、企画担当者と専属シェフが毎週新しい商品の開発を行います。そしてサンプルを作成し、社内で厳しい試食テストを実施しています。毎週新メニューを導入し、同時に人気のないメニューは廃止するというサイクルを継続しているのです。具体例として、お客様からの要望を基に、通常のメニューとは異なる価格帯の「プレミアムライン」を2022年12月から展開しました。 引用:nosh公式HP Premiumメニューページこれは、日常的な食事の中に特別感を求める声に応えたものです。また、今年の4月から、量が少ないという意見を受けて、ボリュームを増やした商品の開発や、既存商品の見直しも行っています。プレミアムラインは、通常メニューとは異なりますが、長年ナッシュを利用しているお客様からは、新しいジャンルとして歓迎の声をいただいています。ただし、原材料費の上昇により価格が若干高くなっているため、味や品質の改善を求める声も寄せられているので、こういったフィードバックを真摯に受け止め、常に改良を重ねているんです。このようなお客様の声に応え続けるという取り組みの背景には、「お客様に選ばれることが美味しさの証」という考え方があります。お客様からの反響やフィードバックで印象に残っているものがあれば、教えてください。カスタマーサポートを通じて、お客様から多くの声をいただく中で、特に印象的だった話があります。ナッシュは単身者の方々に広く利用されていますが、あるご夫婦の利用例が、私たちのサービスの価値を再認識させてくれました。このご夫婦の場合、旦那さんが仕事で外出している間、奥様がナッシュを利用していました。以前は、子育てや家事の合間に食事を作ることに時間を取られ、自分のための時間を持つことが難しかったそうです。そのため、夫婦間で衝突することも多かったとのことでした。ところが、ナッシュを利用し始めてからは、料理の手間が省け、食事にかける時間が大幅に短縮されたことで、奥様は自分の時間を持てるようになりました。その結果、健康面での改善だけでなく、夫婦関係も良好になったというのです。この話を聞いて、ナッシュが提供している価値が、単なる時短や健康面だけでなく、利用者の生活の質や人間関係にまで良い影響を与えていることに気づかされました。私たちのサービスが、思いがけない形で人々の幸せに貢献できているという実感を得られ、非常に嬉しく感じました。現代社会では、人々の生活がますます忙しくなっています。スマートフォンなどの新しい技術が登場し、コミュニケーションツールが増えたことで、かえって時間に追われる日々を送っているように感じます。心の余裕を持つためには、時間的な余裕が不可欠であり、ナッシュが提供する価値は非常に大きいと考えています。ナッシュは単に健康的な食事を提供するだけでなく、食事の準備や片付けにかかる時間を大幅に削減することで、利用者に貴重な時間を還元しています。お客様とのコミュニケーションを重ねることで繋がる持続可能な食事ナッシュが理想とする「持続可能な食事」に向けた取り組みについても教えてください。ナッシュでは、環境に配慮した素材を使用することで持続可能性に貢献しています。同時に、お客様にとって使いやすく、廃棄しやすい容器を選んでいます。これは商品提供が食後も続くという観点から重要な課題です。容器やパッケージのデザインには、特にこだわりを持っています。インハウスのデザイナーが試行錯誤を重ね、様々な意見を取り入れながら改良を続けています。8食や10食セットで届く商品の中から、パッケージを見て「これが美味しそう」と感じていただけるようなデザインを目指しています。その理由の一つは、お客様が冷凍庫から商品を選ぶ際の体験を大切にしているからです。今後、ナッシュが目指すビジョンやアプローチしていきたい課題について教えてください。ナッシュは、市場シェアと売上の成長に恵まれ、多くのお客様に選ばれています。しかし、私たちの本当の目標である「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」という観点では、まだ成長の余地があると認識しています。現在のコアターゲットは、忙しい単身者の方々です。時間を節約したいというニーズに応えることで、支持を得ていますが、私たちのMission を実現するためには、より幅広い世代や多様な生活環境の方々にもサービスを利用していただく必要があります。例えば、家族で暮らす方々、高齢者、子供たちなど、それぞれの世代や生活スタイルに応じたニーズがあると思います。現状では、ナッシュの提供する価値がこれらの多様なニーズと完全に合致していない部分があると考えています。そのため、単身世帯以外の方々にもナッシュを選んでいただけるよう、製品を進化させていきたいです。具体的な戦略はまだ明かせませんが、それぞれのターゲット層が求めるものを理解し、その形に製品を適応させていくことが重要だと考えています。ユーザーとのコミュニケーションを重視しているナッシュですが、どのようなお取り組みをされていますか?ナッシュでは、お客様の声を非常に重視しています。現在も定期的なアンケートや商品に関する感想を収集し、それらを単に集めるだけでなく、確実に製品改善に反映させており、この姿勢は今後も変わらず継続していく方針です。さらに、今後はお客様とのコミュニケーションをより進化させる計画があります。具体的には、既存商品への感想だけでなく、「こんな商品があったら嬉しい」といった新しいアイデアや要望もお客様から積極的に聞き取り、それらを基に新製品開発を進めていきたいと考えています。また、商品やサービスに関する意見はもちろん、ナッシュに関するあらゆる側面についてお客様からフィードバックをいただき、それに対して私たちが誠実に応答する双方向のコミュニケーション環境を整備する予定です。一食が作る健康な未来ーナッシュが描く、気づかぬうちに健やかな明日このインタビューを読んで、ナッシュに興味を持った読者の皆様にメッセージをお願いします!ナッシュの提供する冷凍弁当は、まだ馴染みのない方もいるかもしれません。私たちが目指しているのは、人々が意識せずとも自然と健康になれる世界です。健康を維持することは難しいものですが、それを日々意識する必要がない社会こそが理想的だと考えています。私たちのサービスの価値は、単に健康的な食事を提供することだけではありません。時短や利便性といった側面から始まり、結果として健康的な生活が手に入るという体験を提供したいと考えています。冷凍食品や宅配食に抵抗がある方も、一度試していただくことで、その価値を実感していただけると信じています。ナッシュは常にお客様の声を大切にし、製品改善に活かしています。私たちの利益よりもお客様の利益を優先し、価格設定においても、お客様が選びやすい価格を維持するために企業努力を続けています。私自身、この会社で働きながら、これほどまでに顧客中心のサービスを提供している企業は珍しいと感じています。ぜひ一度、ナッシュの食事を試していただき、その味わいとともに、私たちのサービス理念も感じ取っていただければ幸いです。一人ひとりがナッシュを利用することが、社会全体の健康につながる一歩になると信じています。最後に、これだけは食べてほしいというおすすめのメニューを3品教えてください。ナッシュの商品ラインナップで、個人的に特に気に入っているものがいくつかあります。例えば、「ゆず香る!さっぱりおろしポン酢カツ」は非常に美味しいです。 ゆず香る!さっぱりおろしポン酢カツまた、プレミアムラインの鰻を使った「ひつまぶし」も最近登場し、絶品です。 鰻の出汁茶漬け〜ひつまぶしの3杯目〜そして、当社で圧倒的な人気を誇るのが「チリハンバーグステーキ」になります。 チリハンバーグステーキ私自身、最初はなぜこれが1位なのか疑問に思っていましたが、実際に食べてみてその理由がよく分かりました。ナッシュの商品ランキングは、ほぼ間違いなくお客様の好みを反映しています。これらの人気商品を食べていただくと、健康的な食事でありながら、決して味を犠牲にしていないことがお分かりいただけると思います。一般的に、健康食は味が薄かったり、美味しくないのではないかという先入観があるかもしれません。しかし、ナッシュの商品はそのイメージを覆すもので、しっかりとした味付けがあり、これが本当に健康的な食事なのかと驚くほどです。まだナッシュを利用したことがない人は、ぜひ一度商品を体験してほしいですね。まずナッシュの商品を味わってもらい、宅食の便利さはもちろん、“意識せずとも健康的な食生活が送れる”という新しいライフスタイルを体験してほしいと思います。 nosh(ナッシュ) 公式サイトはこちら noshの解説記事を読む -

【ママの休食】ママと家族の未来を支える食事—ママの休食の挑戦とその先
疲労と不安に満ちた産前・産後の日々。その中で、ママたちは自らの健康と赤ちゃんの成長のために奮闘している。「ママの休食」は、そんな彼女たちに寄り添い、手軽に栄養バランスの取れた食事を提供する。本記事では、このサービスの誕生秘話から未来への大胆なビジョンまで、創業者の熱い想いに迫る。そして、現代のママたちの生活をどう変えていくのか、その可能性を探っていく。取材日:2024年10月3日従業員の9割が子育て中のママ!従業員の実体験と思いから生まれた次世代の宅食まずは、御社の概要や提供されているサービスの基本情報について教えてください。当社は2021年に設立され、個人向けには「ママの休食」ブランドによる宅食サービスを提供し、法人向けには企業の従業員の健康管理と働きやすさをサポートする社食サービスを展開しています。さらに、食品開発支援や血液の栄養状態分析とアドバイスを行う栄養解析サービスなど、多岐にわたる事業を手がけているんです。従業員の9割が子育て中の母親であり、全員が女性という独自の特徴がある会社となっています。「ママの休食」サービスの誕生背景について、教えてください。「ママの休食」サービスは、私自身の経験から生まれたんです。事業構想の段階で、健康課題が大きく、かつ健康に対して前向きに取り組むターゲット層を模索していました。管理栄養士としての知識を持ち、前職では女性の月経管理アプリ「ルナルナ」を開発する会社に勤務していた経験から、かねてより女性のヘルスケアには深い関心を持っていたんです。そして、妊娠する時期は健康に目覚めるとても大切な時だと気づきました。この時期にうまく働きかければ、子どもの小さい頃からの食事、そして家族全員の健康的な生活につながると考えました。大人になってからの食育は難しく、子どもの頃から健康的な生活が普通になれば、長い目で見てとても良いことだと考え、妊娠中や子育て中のお母さんたちのための「ママの休食」サービスを始めることにしたんです。そうしたら、「ママの休食」ファンの子育て中のお母さんたちが集まってきて、仲間として、このサービスを支えてくれるようになりました。働くスタッフが出産や育児など、お客さまと同じ経験をしているので、お客さまの気持ちがよくわかり、私たちのサービスにつながっています。 引用:ママの休食 公式ホームページ妊娠期のお母様に寄り添ったサービスを展開する中で感じる社会的な課題は何でしょうか?管理栄養士として妊婦の栄養相談に携わった経験から、妊娠前からの体調管理の重要性を認識しました。日本の健康啓発には課題があり、特に妊娠初期の栄養管理が赤ちゃんの発達に極めて重要であることが十分に理解されていません。妊娠に気づく頃には既に胎児の重要な器官形成が始まっているため、妊娠中期からの栄養管理では遅すぎます。この考え方は「*プレコンセプションケア」として、昨今特に助産師の間で注目されています。2021年、15年ぶりに妊婦の食生活指針が更新され、栄養管理の重要性が再認識されました。多くの研究で、出生時の低体重が将来の健康リスクに繋がることが示されており、「小さく産んで大きく育てる」という従来の考え方の誤りが明らかになっています。日本では妊婦への公的な栄養教育も不十分なため、『10人に1人が低体重児』という先進国の中では特に高い数字を出しているんです。現代の妊婦たちが抱える問題は、SNSの影響も大きいと、私自身は考えています。15年ぶりに妊婦のための食生活指針が改定された背景の一つに、若い女性の「やせすぎ」の問題があります。細身の有名人やインフルエンサーへの憧れから、無理なダイエットをする女性が少なくありません。やせすぎの状態で妊娠すると、妊娠中に必要な栄養が十分に取れず、体重があまり増えないことが、妊婦さんや赤ちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、現在は体重増加の推奨値が引き上げられ、むしろ少し多めに増えることが推奨されています。加えて、妊婦向けの宅食サービスが増えている一方で、必要な栄養素が不足している商品も存在し、「妊婦におすすめ」とされているものもあります。手軽さは魅力ですが、正しい栄養情報の提供も必要です。正しい知識をインプットした後には、「分かってはいるけれど、できない!」といった行動の課題が出てくるので、そのような時に具体的なソリューションとして私たちのサービスを活用してほしいです。 *プレコンセプションケア 女性やカップルを対象とした将来の妊娠のための健康管理のこと。不安な時期だからこそ寄り添いたい。「休む」×「食事」=「休食」への思い「ママの休食」の会員になると無料で使える公式LINE限定サービス「ママ休ほけんしつ」について、教えてください。ママ向けの栄養相談「ママ休ほけんしつ」は、妊娠期間や産前産後も含めて、いつでも何度でも利用できるサービスです。この相談では、体重が増えない悩みから増えすぎる心配まで、個々の状況に応じた多様な問題に対応しており、妊娠中の方にも多く利用されています。妊婦向け栄養相談で私たちが特に強調しているのは、体重管理の本当の目的です。単に体重を気にするのではなく、赤ちゃんの健康的な成長のために管理することが大切なのです。栄養相談では、体重はゴールではなくプロセスの一部だと説明しており、エコー検査も合わせて赤ちゃんの成長を確認しながら、体重管理をおこなってほしいことを伝えています。実は、妊婦さんの栄養管理は、アスリートや持病のある方と同じように、個別の対応が基本です。「ママ休ほけんしつ」は、妊婦の皆様が安心して相談できる場所となることを目指しています。ありがとうございます。「ママの休食」のネーミングにはどのような思いが込められていますか?当初は、妊婦さんの栄養管理や健康課題に焦点を当てることで、妊娠をきっかけに高まる健康意識に訴えかけられると考えていたんです。妊婦さんが抱える最大の課題は何かを探るため、様々なリサーチを行った結果、栄養以前の問題として、時間的余裕の不足が浮かび上がりました。共働きの増加やつわりの影響で、多くの妊婦さんが食事について考える余裕すら持てない状況にあることがわかったのです。この発見から、まず時間的余裕を作ることで、栄養や赤ちゃんのことを考える余裕も生まれるはずだと考えました。そこで、「適切な休養」と「栄養バランスの取れた食事」という二つの要素を組み合わせた「休食(きゅうしょく)」というコンセプトが生まれました。 引用:ママの休食 公式ホームページこのコンセプトは、ブランド名とロゴデザインにも反映されています。ロゴは幾何学模様で表現された栄養素が散りばめられたお弁当箱のような形をしており、よく見ると「休」の字が浮かび上がる仕掛けになっているんです。また、ロゴが旗のような形状をしているのは、次世代の子育てカルチャーを作り上げていくという私たちの意志を表現しています。 引用:ママの休食 公式ホームページ 引用:ママの休食 公式ホームページ自分も体験したからこそ......「ここまで寄り添ってくれる」が生み出す満足感 川端さんとお子さんのお写真「ママの休食」サービスの強みや特徴を教えてください。私自身、管理栄養士としての経験から、「管理栄養士が作った食事」というと「病院食」のようなイメージを持たれがちだと感じております。私たちが目指しているのは、そうした固定観念を覆す商品づくりです。サービス開発のきっかけは、私自身がキャリアと子育ての両立をしようと思った時に「こんなサービスがないと無理だ!」と感じたからです。また、冷凍食品を使うことで「ママとして失格」と思われがちな文化に疑問を感じ、それを変えたいという思いもありました。私たちのサービスの最大の強みは、栄養面での充実です。特に、女性に極めて重要な葉酸や鉄分を1日分の3分の1も摂取できる点が大きな特徴です。 引用:ママの休食 公式ホームページしかし、どんなに健康的な食事でも、美味しくなければ続きません。単なる数字上の健康ではなく、精神的にも楽しめるものでなければならないと考えているため、宅食サービスとして最も重視しているのは「おいしさ」です。添加物に頼らず、様々な野菜や香味野菜、だしなどを使い、見た目も美しく、香りも良く、そして味も深みのある食事を作り上げています。これは、自分の大切な人や妊娠中の自分が毎日食べたいと思えるような食事を提供したいという思いからです。 引用:ママの休食 公式ホームページ多様な食材を使用することで、自然と栄養価も高まり、食物繊維も豊富になり、「美味しさへのこだわり」が栄養バランスの良さにもつながっています。調理方法にもこだわっており、冷凍食品でありながら、煮るタイミングや炒めるタイミングまで細かく指定し、委託工場での製造にも私自身が必ず立ち会っています。例えば、盛り付け方一つとっても、「ぎゅっと詰めすぎるとまずく見えるから、もう少しふんわりと」といった具合に、直接提案を行っています。商品開発では、「おいしさを作るプロ」である元シェフの顧問や元パティシエのスタッフが中心となっています。私の役割は、彼らが作った料理の栄養バランスを確認し、必要に応じて調整することです。 引用:ママの休食 公式ホームページまた、従業員の9割がママであることも、私たちの強みです。従業員の家庭料理をメニューに取り入れたり、新商品の試食会やフィードバック会を綿密に行ったりしています。さらに、私たち独自のサービスの特徴は、実際に妊娠・出産・子育てを経験したスタッフの意見が商品開発に反映されていることです。例えば、私自身が経験したつわりの際の体験が、商品開発に大きな影響を与えました。つわりには、酸味のある食べ物が良いとよく言われることから、トマトやマリネのメニューを商品化したのですが、私は妊娠中酸っぱいものが一切食べられませんでした。つわりの感じ方は人それぞれなのだと実感し、今では酸味にこだわらずに多様な味付けを心がけています。私たちのサービスは単に商品を提供するだけではありません。例えば、つわりの影響で商品が合わなかったお客様に対しても、サービスを終了するのではなく、栄養相談を継続して利用していただくことを勧めています。一度でも商品を購入していただいたお客様は、サービスを停止しても無料で栄養相談を利用できるシステムを設けているんです。また、妊婦さんの辛さを少しでも解消したいという思いから、自社商品だけでなく、他社の優れた商品もセレクトして提供するセレクトショップの運営も行っています。例えば、乳化剤を使用していないアイスクリームなど、私自身が妊娠中に良かったと感じた商品も取り扱っているんです。これは、「ママの休食」サービスを通して、生活全体をどう整えていくかという視点で支援を行いたいという私たちの思いの表れです。サービスを利用された方からのフィードバックや印象に残るエピソードがあれば、教えてください。私たちのサービスで最も嬉しい瞬間は、出産後に料理ができるようになり、サービスを「卒業」されるお客様からの感謝の言葉です。多くの方が、妊娠期間中の不安な時期に私たちのサービスに救われたと仰ってくださいます。また、「野菜嫌いの子供がママの休食の副菜なら喜んで食べます」といった声も多く、家族全体の食生活改善にも貢献できていることを実感します。カスタマーサービス(CS)担当者の多くが子育て中のママであり、お客様に寄り添った対応を心がけているんです。例えば、緊急入院などの予期せぬ事態で、通常のルール外の対応が必要な場合でも、柔軟に対処しています。この「ママの目線」での対応が、単なるサービスへの満足だけでなく、「ここまで寄り添ってくれたから安心して利用できました」というホスピタリティへの高い評価につながっているのでしょう。結果として、クレームはこれまでほとんどなく、お客様からの感謝の声が多く寄せられています。同じママとして、一人の女性として、家事や育児にも生産性を!将来的に挑戦していきたいことや取り組んでいきたい課題を教えてください。私たちの大きな挑戦は、国や企業の支援を活用し、子育て世帯が経済的負担なくサービスを利用できる環境の実現です。現状では、国や自治体の産後ケア支援は主に客観的に見て支援の手が足りていない人を優先しているケースが多いですが、支援の手があったとしても、産後の負担は非常に大きいです。これを改善するため、企業向けの食の福利厚生サービスを通じて、子育て支援の強化や、福利厚生としての両立支援の普及を目指しています。また、産後ケア先進国である韓国や台湾、中国などではすでに一般的なものになっている産後ケアホテルとの提携も重要です。ある産後ケアホテルでは、ママの休食の商品が宿泊中のお食事として提供されています。さらに、より本質的なサービス提供のためには、医療機関との連携も重要です。ある産科病院では、私たちのサービスを入院食として導入していただいています。私が提案するのは、企業、医療機関、行政が一体となって子育て支援に取り組む新しい形です。そのための第一歩として、現状の個人向けのサービスに加え、法人向けのサービスも積極的に展開していきたいと思っています。一方、技術的な課題として解凍ムラの問題があります。一つの食事セットには、主食、主菜、副菜など、形状や素材の異なる様々な食材が含まれ、これらすべてを同じ時間で均等に解凍することは、技術的に大変難しい課題なのです。食材の盛り方や量によっては、厚みのある食材が温まりきらないなどの問題が発生することがあり、食材の盛り付け方や容積にも細心の注意を払う必要があります。解凍ムラの問題も、「手間のない休養をお届けする」という私たちのサービスの本質を見失わないために、取り組んでいきたい課題の一つです。最後に読者の皆様にメッセージをお願いします!現代社会において、ママたちは依然として多くの偏見や制約に直面しており、宅食サービスを利用することに対しても、罪悪感を感じる人が多いのが現状です。「自分が楽をするために買っている」という後ろめたさや、周囲からの批判など、様々なプレッシャーにさらされています。私たちの会社では、このような状況を考慮し、配送箱にサービス名を入れないなどの配慮をしています。しかし、夫や男性パートナーからのプレゼントとして利用される場合では、宅食サービスの利用がポジティブに受け止められるケースがあります。SNSでは、「夫が体調を気遣って注文してくれた」といった投稿が好意的に拡散されています。また、社会には未だに「自炊が最も健康的で栄養バランスが良い」という神話が存在しますが、これは専門家の目から見ても根拠のない考えです。「自炊しないママは“ていねい”ではない」という偏見も、現代の生活スタイルにそぐわないものです。私は、冷凍食品や宅食サービスを上手に活用して家事や生活をこなしていくことが、次世代の子育て世帯にとって重要なスタイルだと考えており、これは、ママに限らず、パパにも当てはまることです。私は、家事や育児といった無償労働にも生産性を求めることが重要だと考えています。効率的に家事をこなし、自分時間や家族時間を確保することは、決して批判されるべきことではありません。私自身、選択的シングルマザーとして、このような課題に日々直面しています。だからこそ、誰もが自由に自分らしく生活を楽しみ、充実させることができる社会を目指したいと強く思っています。私たちは、家庭や仕事、育児において無理なく豊かな時間を過ごせるよう、必要なサポートや選択肢を提供し、柔軟な環境づくりに貢献していきたいと考えています。 ママの休食 公式サイトはこちら ママの休食の解説記事を読む -

【Meals】食卓に変革を: デリッシュキッチンの宅配“Meals(ミールズ)”が届ける、手軽さと健康を両立させた未来の食事
忙しい日常に追われる現代人。栄養と時間の狭間で、毎日の食事に「理想」と「現実」のギャップを感じている人は多い。食のメディア「デリッシュキッチン」から始まったエブリーが、長年の知見を結集し、ついに生み出した新しい食のカタチ。栄養、美味しさ、利便性を兼ね備えた冷凍宅配弁当サービス「Meals(以下:ミールズ)」は、私たちの日常を再定義する。食のプロフェッショナルたちが描く、忙しい現代人の食生活を根本から変える挑戦に迫る。取材日:2024年12月4日レシピメディアから始まった、毎日飽きずに食べられる、罪悪感のない食事体験 引用:ミールズ公式HPミールズが誕生した背景を教えてください。弊社は、もともと「デリッシュキッチン」というレシピメディアから始まった会社です。食に関するコンテンツ配信を中心に、食を通じた課題解決を軸に事業を展開してきました。近年は、「美味しさ」と「健康」をキーワードに事業を拡大しており、ヘルシカというヘルスケアアプリも運営しています。食と健康を結びつけるサービスの展開を模索する中で、宅配弁当事業であるミールズの誕生に至りました。実は、数年前にすでにECへのチャレンジの経験があり、デリッシュキッチンのオリジナルキッチンツールや、お菓子作りキットなどを販売してきたこともあり、食とECに関する知見は蓄積されていました。これらの経験と、食・健康・ECに対する知識とノウハウが、現在のミールズ事業へとつながっています。ミールズの強みや魅力は何ですか?ミールズの強みは、「美味しさ」と「健康」を軸にした商品開発です。特に美味しさへの追求は妥協せず、多くの競合他社がトップシール型(容器とフィルムシール層で剥離する容器)を選ぶ中、真空パックにこだわり続けています。製造コストとしては少々張りますが、冷凍後も水っぽくならず、食材本来の味を損なわない仕上がりが実現されるのです。 真空パックまた、商品化前には必ず試食を重ね、味の質にこだわり、細部までチェックしています。味の追求を軸とした妥協しない姿勢が、私たちの大きな強みです。 引用:ミールズ公式HP 健康面でも、単なるカロリーや糖質管理にとどまらない、より多方面からの栄養アプローチを取っています。他社様の場合では、糖質や塩分のみは配慮しているものの、その他の栄養素は満たしていない商品も存在します。ですが、ミールズでは管理栄養士が監修した栄養バランスを基準に、8つの項目の栄養基準を設けた商品を開発しているんです。一般的に行われている糖質、脂質、塩分、野菜量などの基本的な栄養管理に加えて、エネルギー、タンパク質、糖質、炭水化物、糖質、食塩相当、野菜量、品目数などの項目を設定しています。このような基準を設けることで、栄養基準を総合的にカバーすることが可能です。 引用:ミールズ公式HP「家庭的なおいしさ」の探求の秘密を教えてください。ミールズが目指すのは、毎日の食事を想定した宅配弁当サービスです。デリッシュキッチンを運営する経験から、罪悪感なく、日常的に食べられる味付けにしています。また、デリッシュキッチンは「大根1個で何種類もの料理ができる」といった、少ない材料での多様な料理提案が得意ですが、弁当事業では健康面を考慮し、品目数や栄養バランスをより重視しています。お金を払って購入する弁当だからこそ、「冷蔵庫の中で作れるものではなく、たくさんのものが食べられる」体験を提供したいと考えています。レシピ事業で培ったノウハウを活かしつつ、弁当という新たな形態ならではの価値を模索しています。“あえての真空パック”を採用することで実現した、コンパクト収納と美味しさの両立 引用:ミールズ公式HP冷蔵庫のスペースを圧迫しがちな宅配冷凍食ですが、収納問題へのアプローチや冷蔵庫に収まりやすい商品設計へのこだわりを教えてください。容器設計には徹底的にこだわっています。特に、真空パックを採用し、食材と空気の隙間を最小限に抑えることで、コンパクトで収納しやすい設計を実現しました。 引用:ミールズ公式HP従来のトップシール型と比較して、私たちの容器は非常に薄く、冷凍庫への収納に適しています。しかし、この薄さゆえに、料理の盛り付けには高度な技術が必要です。例えば、ロールキャベツの場合、理想的にはソースをかけたり、下に何かを敷いたりしたいところですが、容器の制約により、そうした細かい盛り付けが難しくなります。食材の配置や盛り付けは、電子レンジでの加熱時間や火の通り具合に大きく影響するため、何度も試作と実験を繰り返してますね。具体的には、様々な配置パターンを試し、レンジで加熱した際に全体に均一に火が通るよう、細心の注意を払っています。さらに、レンジの連続使用による加熱むらも考慮し、ワット数の調整なども行っています。容器は石灰でできており、燃えるゴミとして簡単に処分できます。これにより、環境に優しいだけでなく、料理の後片付けも日常の調理と同じくらい簡単になります。美味しさ、使いやすさ、環境への配慮を兼ね備えた冷凍食品パッケージを創り上げることを目標に、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら、常に改善を続けています。管理栄養士の監修により、美味しさと栄養バランスにもこだわったミールズの宅配弁当。 イメージ画像管理栄養士との協力体制はどのように形成され、どのような影響を与えていますか?ミールズのメニュー開発は、OEM先の管理栄養士と自社の管理栄養士が緊密に連携する、徹底的な試食プロセスを特徴としています。新メニュー開発には3ヶ月から1年以上を要することもありますが、それは試食を何度も重ねることで、より良い商品を追求しているためです。初期段階では金額や取引先の制約を考慮しつつ、最終的にはユーザーに喜んでもらえる商品を目指して、味や栄養バランス、食感など、何度も微調整を行っています。ミールズのメインターゲット層を教えてください。あえて絞ってはいないのですが、結果として40代以上の女性を中心に支持されています。サービス開始当初は、ターゲット層を明確に定めず、オールターゲットでスタートしたのですが、ある程度ユーザー数が蓄積したところでアンケートを取ってみると、40代~60代の方の購入比率が高いことがわかりました。小学生以上のお子様がいる家庭や、子どもと同居していない50代以上の1人もしくは2人暮らしの世帯が中心です。これは、私たちの商品設計、特に栄養バランスや使いやすさが、40代~60代の年齢層のニーズにぴったり合致したためだと考えています。コロナ禍以降に改めてサービスを展開する際に、苦労されたポイントや注力されたポイント、消費者のニーズの変化はありましたか?コロナ禍、特にサービス初期は、プロモーション費をかければある程度の新規顧客を獲得できましたが、継続率の低さが課題でした。そこで、この期間の顧客からのフィードバックを真摯に受け止め、最も多かった「味」への改善に集中的に取り組みました。味の改善により、顧客の継続率が徐々に上がり始め、サービスの質を高めることの重要性を実感したのです。 引用:ミールズ公式HPそして、当初は「おまかせコース」という独自のサービスモデルのみを展開していました。具体的には、食数と配送サイクルのみ指定すれば、毎回異なるメニューが自動的に届くスタイルです。そのため、顧客がマイページを操作する必要がほとんどありませんでした。しかし現在は、若い世代を中心に、自分でメニューを選択したいというユーザーの声も多かったため、2024年8月からメニュー選択機能をリリースし、顧客体験の改善に努めています。より良いサービス提供を目指し、常にユーザーの声に耳を傾け、改善を続けています。サービス開発の過程で、最も難しかったことや克服した課題は何でしたか?サービス開発における最大の課題は、栄養バランスを考慮したメニュー作りの複雑さでした。糖質、塩分、カロリーなど2〜3の栄養要素を調整することは比較的容易でしたが、品目数、タンパク質、野菜の量などを加えると、途端にメニュー開発の難易度が高くなりました。特に、1つの主菜に対して3つの副菜を用意し、それぞれに十分なボリュームを持たせることで、メニュー開発のプロセスはさらに複雑になります。最近、ロールキャベツ、エビクリームコロッケ、水餃子の3つの新メニューをリリースしました。これらは栄養基準を満たしつつ、やや「ジャンク」な印象のある料理で、ユーザーから予想以上に好評を博したのです。この経験から、栄養素の調整だけでなく、ユーザーの期待や満足感を考慮することの重要性を学んだのです。「Meals(ミールズ)」は人の健康をサポートし、食体験を豊かにするツール。 イメージ画像激化する宅配食の中で、どのような位置を確立していきたいですか?私たちの目標は、デリッシュキッチンやヘルシカとも連携した包括的な健康サポートエコシステムを構築することです。ミールズだけでなく、デリッシュキッチン、ヘルシカなど、エブリーが運営する各サービスを連携させ、栄養管理から食事提供、健康管理までをシームレスに行えるプラットフォームを目指しています。現在、デリッシュキッチンは既に一定のユーザー規模を持っていますが、ミールズ事業はまだ小規模です。当面の戦略は、ミールズ単体で事業規模を拡大し、最終的にはデリッシュキッチンと同等の事業規模を確立することです。印象に残ってるエピソードやお客様からの反響を教えてください。私たちのサービスは、多くの30代以上のお客様に毎日利用され、「毎回異なるメニューで飽きない」「美味しい」と喜びの声をいただいています。特に印象的なのは、家族間での利用パターンです。離れて暮らす子供や高齢の両親にミールズの宅配弁当を送っているお客様も少なくありません。例えば、社会人の息子や、70代、80代、90代の親御さんに食事を届けるケースが目立ちます。自分では食べなくても、家族に安心して食事を届けられる点がミールズの魅力です。ミールズを利用する際の理想的なライフスタイルやシチュエーションをどのように想定していますか?デリッシュキッチンやミールズを立ち上げた当初から、私たちは料理をするということに対する社会的な固定概念を変えたいと考えていました。料理や自炊が苦手という方や、仕事や家事に追われて料理が負担に感じている人にとって、料理は”毎日する負担の多い作業”となってしまいます。ですが、私たちの目的は、料理を楽しいものに変え、その楽しさを伝えることでした。デリッシュキッチンで料理の楽しさを感じてもらいつつ、疲れた日や料理する気分でない日には気軽に利用できるミールズがあることで、料理に対する精神的な負担を軽減し、食事の時間をより豊かで楽しいものにしていきたいと考えています。長年築き上げてきた食の世界観ーミールズが描く新しい食体験と未来 引用:ミールズ公式HPまだサービスを試したことのない読者の皆様におすすめのメニューを教えてください。最近リリースしたエビクリームコロッケは、栄養バランスと美味しさの両立を実現した自信作です。カロリー、糖質、タンパク質など、すべての栄養素基準をクリアしながら、塩分2.5グラム以下という制約の中で、豊かな味わいを実現しました。通常、健康的な料理は味や見た目で妥協することが多いですが、このエビクリームコロッケは、そんな常識を覆す一品です。 エビクリームコロッケおまかせコースには入っておらず、自分で選択しなければいけない商品ですが、私たちのメニューの中でも贅沢感のある、少し冒険した商品なので、ぜひ味わっていただきたいと思います。最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします! 引用:ミールズ公式HP私たちのミールズは、特に美味しさに揺るぎない自信を持っています。まだ試したことのない方もたくさんいると思いますが、ぜひ一度、私たちの料理を試していただきたいです。そして先ほどもお伝えしましたが、ミールズとデリッシュキッチンを連携しながら、栄養管理から食事提供、健康管理までを一気通貫して行えるプラットフォームを目指しています。料理からでも、お弁当からでも、デリッシュキッチンのおいしくて楽しい食体験にぜひ一度触れてみてください。 ミールズ 公式サイトはこちら ミールズの解説記事を読む -

【パルシステム】忙しい生活に寄り添うパルシステム:ミールキットの可能性
「忙しい毎日の中でも、料理の幅を広げつつ栄養バランスにも配慮した食事を手間なく作りたい」。そんな願いを叶えてくれるのが、パルシステムのミールキット。短時間で本格的な料理が簡単に作れる上、メニューの種類も豊富。厳選された国産野菜や「調味料(アミノ酸等)」不使用の調味料など、食の安全面へのこだわりも徹底しています。食事を準備する負担を減らし、豊かな食卓を提供してくれるこのミールキットの魅力を、本記事で詳しくご紹介します。取材日:2024年12月2日パルシステムならではの食材を詰め込んだミールキット 引用:パルシステム公式HPまずは、パルシステムのお料理セットとはどのような商品でしょうか。黒井さん:お料理セットは、簡単に調理ができるミールキットです。世間的には、「ミールキット」と呼ばれることが一般的ですが、パルシステムでは「お料理セット」と呼んでいます。カット済みの野菜に、肉や魚といった食材、それにプラスして添付調味料とレシピがセットになっています。野菜と肉はすべて国産にこだわり、添付のたれも「調味料(アミノ酸等)」は不使用の商品を取り扱っています。このサービスは2014年にスタートし、2024年で10年目を迎えることができました。サービスを立ち上げた経緯を教えてください。黒井さん:社会的背景としては、共働きの家庭が増えてきていたことが挙げられます。その後、コロナ禍に入ったこともあり、市場全体を見ても宅配食の需要が高まっていきました。またレシピと人数分の必要な食材がセットされているミールキットは、現代のニーズにマッチした商品として様々なところで販売が開始されました。 パルシステムの方針の『組合員のくらしの課題解決』という理念から、共働き世帯をサポートする商品として、2014年から3種類のお料理セットでサービスを開始しました。特に大切にしている価値観や、他社との差別化を図っているポイントは何でしょうか。黒井さん:まず、国産へのこだわりです。肉と野菜は必ず国産のもので、顔が見える生産者(産直)の食材も多く使用しています。2017年には群馬県板倉町に自社工場を建て、子会社の『株式会社パルライン』が運営しています。 自社工場製造分はすべてパルシステムが開発した商品であり、規格外品や余剰となった野菜も積極的に活用しています。パルシステムは生協なので青果の宅配もしていますが、出荷基準があり、産地と作付計画から打ち合わせをする中で、サイズや傷などの理由で規格外品が出てくることがあります。これらはカットして傷を取り除けば食味に問題はありませんし、生産者が作った食品をなるべく無駄にならないように使用しています。このように、生産者の支援にもつながる取り組みも行っています。また、PB(プライベートブランド)商品には調味料からお肉やお魚、カットわかめ、豆腐などの副材まで幅広く揃えており、お料理セットにも取り入れています。組合員にとって普段あまりなじみのない調味料は、大容量だと手が出しにくいと思うんです。そこで、お料理セットに小袋タイプの調味料を内包し、味や使い方を知る機会を作っています。食材を調達する際に重視していることは何ですか?高橋さん:私たちの役割は、全国に広がるネットワークを活用、おいしい食材を安定的に調達することだと考えています。そのため、複数ある産直産地と連携し、それぞれに当会の基準に基づいた方法での栽培をお願いしています。近年、天災などの影響で収穫量が減少することも増えていますが、これまで築いてきた信頼関係をもとに産地の方々と協力しながら供給を維持しています。また、当会では年間契約を行うことで、食材価格の安定化を図っています。お料理セットの販売価格は変動が少ないので、市場で野菜の価格が高騰すると、より多くの組合員の方々にご利用いただける傾向があります。家庭でさまざまな食材を揃えるのは手間もお金もかかりますので、こうしたお料理セットの需要につながっているのではないかと思います。単身世帯にも需要が拡大。野菜価格が高騰しても多種多様な野菜を食卓に 引用:パルシステム公式HPミールキットページサービス開始後から顧客ニーズの変化はありましたか? また、その転機となった出来事は何でしょう。高橋さん:当初は30〜40代の共働きの主婦・主夫を主なターゲットにしていましたが、コロナ禍を機にニーズに大きな変化が見られました。テレワークの普及に伴い、一人暮らしのランチ需要が増加し、それに対応したメニューが伸びています。また、旅行の制限により、郷土料理や世界各国の料理を自宅で楽しめるメニューの需要も高まり、現在も引き続き人気があります。最近では、消費者の深層的にバランスの良い食事、野菜をしっかり摂りたいという気持ちをお持ちです。高齢の方をはじめ、「野菜は食べたいけど、さまざまな種類を買うと高いし使いきれない」というような悩みが増えており、このような方々が徐々にミールキットを利用し始めています。今までは2〜3人前のセットを中心に提供していたのですが、現在は高齢の2人世帯でも食べきれる1.5人前のセットも導入しています。今後も市場動向を見つつ組合員の声を聞きながら、選択肢を増やしていければと考えています。お料理セットの中で特に人気のあるメニューやおすすめは何ですか?また、一番メジャーな商品トマト風味のドライカレーには、国産トマトを濃縮還元したプライベートブランド商品のトマトジュース『濃いトマト(食塩無添加)』を使用しています。このトマトジュースは1本100円ほどですが通常は24本セットでの販売のため、個人で購入するには少しハードルが高いかもしれません。しかし、お料理セットに使うことで、飲むだけでなく調理にも活用できることを知るきっかけになればと思います。 スープ系の料理も人気で、煮込むだけでボリュームがあって栄養価が高い一品を、短時間で用意できるところが高く評価されています。 引用:パルシステム公式HP 商品図鑑高橋さん:有機の若芽ひじきの炒め物もおすすめです。若芽ひじきはお浸しが定番ですが、炒めるとシャキシャキとした食感が楽しめます。若芽ひじきを購入したことがない方や調理法がわからないという方にも試してもらいやすいメニューです。 あとは、「水餃子のジェノベーゼソース(ラビオリ風)」も食べてみてほしい一品です。ジェノベーゼソースと生クリームで餃子を煮込み、ラビオリのように食べるセットで、ジェノベーゼソースの新しい使い方が発見でき、料理の幅が広がるはずです。食材へのこだわりから環境配慮まで、価格以上の価値を提供するパルシステムのお料理セット再生素材を使用したパッケージなど、環境に配慮した取り組みも行われていますよね。黒井さん:当会では環境への配慮を重視しており、特にプラスチック削減を方針として掲げています。ミールキットを始めた当初から再生原料を55%使用したプラスチック製トレイを採用していましたが、2年前にはこのトレイを紙製に切り替えました。 当時、市場には食品用のモールド系紙製トレイがなかったので、たまご用のモールドパックを製造していただいているメーカーに新たに製作してもらったんです。メーカーも初挑戦で、大きさや形などを一緒に考え、何度も試作を繰り返し、強度を確認しながら一緒に作り上げました。 たまご用のモールドパックただ、紙は強度に限界があるので、少量のプラスチックのパルプ繊維を混ぜて強度を上げています。ですので、今は、このパルプ繊維を使用しない、完全にプラスチック使用量ゼロ紙製トレーを目指して頑張っているところです。また、従来のプラスチックトレイのように、回収後に溶かして再利用する水平リサイクルの仕組みを、紙製トレイにも導入することを目指しました。「紙製だから一般の資源ゴミに出せばいいよね」ではなく、リサイクル可能な仕組みを構築していました。コストと品質とのバランスを取るのが難しいところですね。黒井さん:そうなんです。ほかの生協やメーカーと比較すると単価は少し高めかもしれませんが、その分、高品質な商品を提供することにこだわり、環境に配慮した取り組みもおこなっています。忙しい毎日を送るお客様に、ミールキットを使うことは手抜きではなく、むしろ手軽に栄養のあるおいしい食事を作ることができる方法ということを伝えたいですね。御会のサービスについて、「消費者に伝えきれていない」「もっと知ってもらいたい」と感じている点はありますか?高橋さん:学習会などで工場見学をしていただいたり、ムービーで工場の様子をご覧いただくと、食材のカットや袋詰めなどを手作業でおこなっていることに驚かれることがあります。自社工場では、品質や安全性を担保するために機械化はもちろん、人の手で作業する工程も採用することで、より質の高い商品を提供できる体制を構築しています。こうした一手間を知っていただくことで、「この価格は妥当だよね」と言っていただけています。黒井さん:肉や卵の生産においても、餌や飼育環境に気を配り、ストレスを少なくできるよう育てています。このような商品の裏側をもっと多くの方に知ってもらいたいです。 ご利用された方の反響や、特に印象に残っているエピソードについて教えてください。黒井さん:お料理セットはリピート率が高い商品であり、利用した組合員から味や使い勝手も含めて、高く評価されています。学習会などで組合員と話をしていると、「来週のメニューは何にしようか」とお子さんと選んでいるとか、ミールキットを親子で作ったりしているというエピソードをよく耳にします。今まではお母さんがおこなっていた料理に子どもやお父さんも参加するようになったとか、ミールキットを使うことで家事の負担が軽減され、家族で過ごす時間が増えたという喜びの声も寄せられています。また、普段とは違う味付けが楽しめる点も好評です。食卓では「これ初めて見るけど何ていう食べ物?」「この味付けいいね」といった会話も生まれ、家族のコミュニケーションが増えたという話も非常に印象的でした。1週間あたり17万食から20万食へ! 今後は冷凍ミールキットの充実化も視野に入れたソリューションを展開 引用:パルシステム公式HP お料理セットページ10周年を迎えた今、毎週約20万食の注文があるというのは驚異的な数値ですね。高橋さん:10周年を迎えられたことで、利用者の方々に支持いただいていることを改めて実感しています。忙しい日常の中で便利さを求めている方、食品ロス削減を意識している方、産地支援のために選んでいる方など、さまざまな理由により多くの方に使っていただき、徐々に需要が増加したんです。注文数は、昨年は1週間あたり約17万食でしたが、10周年を機に一気に20万食という大幅な伸びを見せました。これは、利用者が商品にそれぞれの価値を見出し、魅力を感じていただいている証拠だと思います。黒井さん:今回、10周年キャンペーンとして、組合員のみなさんが実際にどのように召し上がっているのか、アレンジの仕方などをインスタグラムに投稿していただきました。今まではインスタグラムでキャンペーンを行っても最大100件程度の応募しかなかったのに対し、今回は外部・内部を合わせて500件以上の投稿が集まりました。みなさん思い思いの投稿をされていて、「夏休みにお子さんがおばあちゃんのために作った」とか、働いているお父さん・お母さんの帰りが遅いときにお子さんが作った食事、息子が文句を言わないお気に入りのメニューなど、それぞれの家庭の工夫が見られました。生協はもともと共同購入が目的で、みんなで集まり料理などを教え合う場でもありましたが、ミールキットを通してウェブ上でも教え合う場が作れたのではないかと思っています。今後、挑戦していきたいことはありますか?黒井さん:逆に原点に戻って、一(いち)から丁寧に出汁を取るなど、手作り感を大切にしたメニューの開発を考えています。ミールキットは時短要素が利点ではありますが、時間をかけて煮込む料理やイベント用のローストチキンセットなど、少し手間がかかるけど材料が揃っているから便利、というような商品にチャレンジしてみたいと思っています。あとは、冷凍商品ですね。ストックできる冷凍商品をもっと増やしてほしいというニーズが高まっています。冷凍でも味わいや食感が変わらない野菜の仕様や、冷蔵商品に引けを取らないおいしさとボリュームを実現したいと考えています。ミールキットの購入を検討されている方たちに向けてメッセージをお願いします。高橋さん:私自身、子育てをしながら家事や仕事をする中で、短時間で料理ができるというのは本当に助かっています。普段、自分で作る料理はレシピサイトを参考にしても、どうしても似たような味付けになってしまうのですが、このセットを使うとガラリと料理が変わり、外食気分を味わえるのでコストパフォーマンスの面からもお得感があります。また、ゴミが少なく、トレイの回収サービスがある点も便利だと思います。どんどん共働きの家庭が増えている今、世間的に求められているサービスではないでしょうか。黒井さん:ミールキットを利用することで、おいしさだけでなく、家族と一緒に過ごす楽しい時間を作り出せます。食事は生活の中で大切な時間であり、子どもにとって楽しい記憶として残ることもあるでしょう。豊かな食生活や楽しい時間をサポートする商品として、ぜひミールキットを活用してみてください。 <編集後記>今回、定番メニューの「トマト風味のドライカレーセット」の試供品をいただき、編集部員で料理・実食しました。本当に10分でカレーが作れるんです!1日に余裕ができて、短時間で料理できる魅力を味わうことができました。味に関しては、野菜のカッティングや味付け方法など、普段の料理と異なっているので、お店のカレーを食べているような気分に。また、私はカレーを作るときにトマトジュースではなくてトマト缶を使うタイプなので、こんな料理の仕方もあるんだなと勉強になりました。料理の手間を省きたい方だけではなく、料理に拘りがある方にもぜひミールキットを活用していただきたいです。 パルシステム 公式サイトはこちら パルシステムの解説記事を読む -

【ウェルネスダイニング】食事制限の不安に寄り添う!ウェルネスダイニングが描く未来の制限食文化
「食事制限」という言葉に、何を想像するだろうか?味気ない食事、制限された楽しみ、そして家族との食卓の断絶。そんな固定観念を打ち砕くべくウェルネスダイニングが掲げるのは、「健康管理と美味しさの両立」だ。管理栄養士たちの知恵と情熱が生み出す、驚きの美味しさと栄養バランス。そして何より、背景にある「お客様に寄り添う」という揺るぎない信念。今回の取材では、制限食という枠を超え、新たな食の喜びを創造するウェルネスダイニングの挑戦に迫る。取材日:2024年10月9日ウェルネスダイニングは、創業者の闘病経験と管理栄養士との出会いにより誕生。 左:事業企画部の清水様、右:CS事業部の高木様今回のインタビューでは、ウェルネスダイニングの事業企画部清水様、そしてCS事業部高木様にお話を伺います。まずは、御社の基本的なサービスや企業概要について教えてください。清水:ウェルネスダイニングは、主に食事制限を専門とした宅配食の通販事業を展開しています。当社の主力商品は「気配り宅配食」と呼ばれる、食事制限が必要な方向けの栄養管理された冷凍弁当です。これに加えて、高齢者向けのやわらか食や、塩分を控えた野菜たっぷりの味噌汁なども取り扱っています。気配り宅配食には複数のコースがあり、それぞれご病気と必要な食事制限に合わせて設計されているのです。例えば、腎臓病の方向けにはたんぱく質と塩分調整食、糖尿病の方向けには糖質とカロリー制限食、高血圧や心疾患が不安な方向けには塩分制限食などがあります。さらに、食生活の見直しや予防の観点から栄養バランスを整えた食事も提供しています。 引用:ウェルネスダイニング公式ホームページウェルネスダイニングを立ち上げるに至った背景には、どのような健康に対する問題意識があったのでしょうか?清水:創業の背景には、創業者自身の糖尿病の体験と、ある管理栄養士との出会いがありました。この管理栄養士は腎臓病専門の病院での勤務経験があり、食事制限の重要性について深い知見を持っていたのです。創業者は、自身の経験から食事制限の困難さを理解し、同時に薬物療法だけでは十分な治療効果が得られないことも認識していました。そこで、自宅で適切な食事制限を実践することの重要性と、それをサポートするサービスの必要性を感じたのです。このような経緯から、ウェルネスダイニングは通常の弁当宅配事業ではなく、食事制限を必要とする人々に特化したサービスとして誕生しました。創業者のご経験をもとに生まれたサービスなのですね。特にこだわっている点や、食事の質をどのように維持しているのか教えてください。清水:「美味しさ」と「食事の楽しさ」にはこだわっています。「美味しさ」に関しては、特製のタレや出汁を用いて、制限食とは思えないしっかりとした味付けを目指しています。また、食材の硬さにも注意を払い、実際に召し上がるお客様のことを想像しながら、食べやすさと安全性を確保しています。「食事の楽しさ」では、約90種類のメニューを用意し、常に改良を重ねていることです。特に、お客様へお届けするお食事の内容には特に気を配っております。毎週配送のお客様には、メニューが重複しないよう細かな計画を立てていたり、1回の配送で7食分をお届けする場合は、肉料理、魚料理、卵料理などのバランスを考慮したりしています。高木:さらに、昨年からは食事制限をしながらも季節の食材を楽しんでいただけるように、期間限定で季節メニューの提供を始めました。例えば、夏限定のウナギを使用したメニューがあります。多くのお客様が「制限食ではウナギは食べられない」と諦めていたため、とても好評でした。 引用:ウェルネスダイニング公式ホームページ制限食であっても季節感や豊かな食体験を提供することで、お客様の食生活に楽しみをお届けすることを心がけています。季節限定メニューとして開発され、お客様からの高い評価を受けて通常メニューに昇格したメニューも少なくありません。 社員用の冷蔵庫福利厚生の一環として社員は当社の弁当を食べられますが、皆飽きることなく食べています。食事内容以外にもこだわっている部分はありますか?お客様が商品を開封した際、メニュー名を見て美味しそうだと感じていただけるよう工夫しています。食材は異なっても名称が似ているメニューがあると、お客様には同じように感じられる可能性があるため、メニュー名の選定には細心の注意を払い、社内でも活発なディスカッションをおこなっているんです。また、商品ラベルの設計にも細心の注意を払っています。メニュー名はもちろん、加熱時間や詳細な栄養成分表示など、お客様が知りたい情報をひと目で分かるように工夫しています。特に、タンパク質、糖質、脂質、食塩、カリウムの値に加え、腎臓病の方からのご要望に応じてリンの含有量も表示するようになりました。また、主菜だけでなく副菜のメニュー名も分かりやすく表記し、原材料表示も見やすいように改行を入れるなど、細部にまでこだわっています。長期利用のお客様ほど内容に注目されるため、パッケージを開封せずとも情報が得られるよう心がけています。お客様の年齢層を考慮し、文字の大きさやフォントの選択にも気を配っているのです。 商品ラベルの違い(左:改良前、右:改良後)意外と難しい!直面して初めて分かる健康管理の苦労に寄り添いたいどのようにしてウェルネスダイニングを知るお客様が多いのでしょうか?清水:多くのお客様は、健康診断や血液検査の結果を受けて、医師から食事制限の必要性を指摘されたことがきっかけで、健康に対する意識を高めるようです。お客様の行動パターンとしては、まず自分の症状や疾患に関連する食事情報をインターネットで検索し、制限すべき食品などについて調べます。調べる中で、実際に適切な食事管理の難しさや、自己管理がきちんと出来ているのか不安を感じ、宅配食サービスの存在を知ることが多いようです。制限食に特化した宅食サービスは他にもありますが、ウェルネスダイニングならではの魅力を教えてください。清水:私たちの最大の強みは、お客様の健康をサポートしたいという強い思いです。そのため、当社ではお客様の声を非常に重視しています。毎朝、前日に寄せられたすべての顧客フィードバックを全社員で共有し、迅速に対応する体制を整えているのです。例えば、特定のメニューの味付けに関する指摘があった場合、翌日には製造元に連絡し、サンプルを取り寄せて味の確認をします。お客様からのフィードバックへの対応は、通常1週間以内には必ず改善策を講じています。また、お客様とのコミュニケーション方法も重視しており、インターネットでの問い合わせだけでなく、自分の意見を直接伝えたいという思いに応えるため、電話で声を聞く機会も多く設けています。高木:お客様のお声で多いのは味に関するものです。そのため、ウェルネスダイニングは、美味しさと健康の両立に注力しています。多くの人が制限食を味気ないものと捉える中、当社は塩分2.5グラム以下または2グラム以下のコースを設け、減塩しながらも満足度の高い味付けを実現しているのです。塩分制限下での美味しさを追求するため、出汁の活用や香辛料の工夫、味噌の種類の選定など、様々な技術を駆使しています。調味料室には様々な種類の調味料が揃えられており、同じカテゴリーの調味料でも複数の製品を用意しています。これは、各食材に最適な味付けを見出すためです。実際に試食させていただきましたが、塩分2.5グラム以下とは信じられないくらいしっかりした味付けで美味しかったです。ボリュームも十分ですし、制限食に限らず毎日食べたいと思いました。高木:ありがとうございます。コンビニに売られているおにぎりの塩分量は1個あたり1gほどなので、おにぎり2個分の塩分量と同じくらいなんですよ。ちなみに、ウェルネスダイニングの具体的な味付けの選定は、科学的な数値分析よりも、実際の試食を通じた感覚的な判断に重きを置いています。製造元の管理栄養士と密接に連携し、日々のコミュニケーションと試食によるフィードバックを重視しながら、試行錯誤しています。さらに、視覚的な魅力にも注目し、カラーコーディネーターの助言を取り入れ、弁当の見た目の美しさにも配慮しています。容器の色選びにも細心の注意を払い、食材の色を引き立てる白色のトレーを採用しました。メニューの改良に際しては、味、栄養バランス、見た目の調和を同時に考慮する細やかなアプローチを取っています。例えば、ある魚料理のちゃんちゃん焼きのケースでは、味噌の種類を変更することで複数の課題を解決しました。当初、赤味噌を使用していたため、料理に含まれる赤ピーマンや緑ピーマンの色彩が引き立ちませんでしたが、白味噌に変更することで、主菜の見栄えが格段に向上しました。色味だけではなく、塩分量も抑えることができています。「制限食なのにこんなに美味しい」健康応援団として、お客様に安心感を オフィスの様子。企業理念を中心に、社長室も存在しないフルフラットな空間にすることで、健康応援団としての社員の連携がシームレスにおこなわれているそうです。持病を持つ方々に向けて、安心感を伝えるために工夫していることはありますか?高木:お客様の健康を生涯にわたって応援することが私たちの企業理念です。単なる販売者ではなく、お客様の健康をサポートする「健康応援団」として、食事制限のサポートをおこなっています。多くのお客様が医師とのコミュニケーションに悩んでいたり、クリニックに管理栄養士がいないため栄養相談ができないという課題を抱えているでしょう。当社は38名の従業員のうち半数が管理栄養士の資格を持ち、お客様対応スタッフの過半数も管理栄養士です。これにより、お客様からのお電話に常に専門知識を持ったスタッフが対応できる体制を整えています。例えば、スーパーでの買い物中に「腎臓病の私がこれを食べても良いか」といった相談にも応じています。このような取り組みを通じて、お客様との距離が非常に近く、くだけた会話ができるほど親密な関係を築いているんです。お客様にいつでも気軽に電話していただき、必要なサポートを提供することで安心感を与えられるよう努めています。ご病気を持持つ方に食事を提供する方たちにとっても、魅力的なサービスだと思うのですが、食事を提供する側が抱えている課題やお悩みはどのような点があげられますか?高木:多くの場合、食事制限が必要な方のご家族、特に食事を準備する立場の方が大きな責任感と不安を抱えていると思うのです。例えば、腎臓病患者の食事制限では、塩分制限は比較的イメージしやすいですが、カリウム制限のような専門的な栄養素の管理に関しては多くの方が困難を感じています。病院では「1日の塩分摂取量を6グラムに抑えましょう」という程度の概要的な説明にとどまることが多く、実践的な方法まで踏み込んで指導されることは少ないようです。私たちは、野菜の茹で方など「どうすればいいのか」という具体的な部分をサポートすることで、患者さんやそのご家族の不安を軽減し、実行可能な食事管理を提案しています。ウェルネスダイニングの利用頻度は様々ですが、夕食の置き換えとして利用される方が最も多いです。健康な方なら外食という選択肢もありますが、食事制限のある方にはそういった選択肢が限られているでしょう。そのため、私たちのお弁当を冷凍庫に常備しておくことで、食事準備の負担や精神的なストレスを軽減できると考えています。押し売りはしない!困った時に気軽に頼れる存在でありたい 年に1回社内で発行されるアルバム。アルバムからは社員を大切にする様子が伺えました。食事制限を必要とする方々以外にも、ウェルネスダイニングのサービスを広げるためには、どのようなアプローチが必要だと感じていますか?清水:私たちのサービスを多くの方に知っていただくため、食事制限が必要な方々だけでなく、潜在的な顧客層へのアプローチを強化したいと考えています。当社の強みである栄養相談サービスを活用し、商品購入という従来の入口だけでなく、栄養相談を新たな入口として模索していきたいです。まずは商品を購入せずとも、私たちと対話する機会を通じて、より多くの方々に当社のサービスを知っていただき、興味を持っていただけるきっかけを作りたいと考えています。お客様から寄せられるフィードバックの中で、特に印象に残っているエピソードや改善点はありますか?高木:当社は日々多くのお客様からご意見をいただいていますが、特に印象的なのは手書きのお手紙です。例えば、病気の父親のために娘さんが注文し、料理を準備する母親の負担が軽減されたという喜びの声や、同じ食事制限で悩む方々へのアドバイスを送ってくださる常連のお客様もいらっしゃいます。私たちは単に販売数を増やすことよりも、ウェルネスダイニングのファンを増やすことを重視しています。一方で、お客様の嗜好は様々です。例えば、レモン風味の料理に対して「レモンが強すぎる」という声もあれば「さっぱりして美味しい」という声もあります。改善のつもりが特定のお客様の嗜好に合わないこともありますが、そのような意見も真摯に受け止め、さらなる改善につなげています。 オフィスにいるペットロボット。2体おり社内の雰囲気を和やかにしていました。ウェルネスダイニングが目指す、食事と健康を通じた未来のライフスタイルとはどのようなものでしょうか?清水:当社は食事制限食を提供する会社として、お客様に健康的な食生活を長期的に続けていただくことを重視しています。また、お客様個人だけでなく、ご家族全体をサポートすることも重要だと考えているんです。食事を用意する方の負担を軽減しつつ、食べる方の健康も同時に支援することで、家族全体の健康と生活の質の向上に貢献したいと考えています。最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします!清水:私たちは何よりもお客様に寄り添うことを大切にしているので、商品のご購入の有無にかかわらず、お気軽にご連絡いただきたいと思っています。販売者と顧客という関係性ではなく、、お客様が困ったときに頼れる存在でありたいという思いが一番強いです。特に、健康に不安を感じたり、病気になったと思われたときは、ぜひご連絡ください。私たち管理栄養士が全力でサポートさせていただきます。また、私たちは制限食であっても、日々商品の品質向上に努めています。美味しく、健康的で、お客様の生活に寄り添える食事を提供することを目指しているので、ぜひ一度、私たちの商品をお試しいただければ幸いです。 ウェルネスダイニング 公式サイトはこちら ウェルネスダイニングの解説記事を読む -

【まごころケア食】誰もが安心して歳を重ねられる社会へ:まごころケア食で創る未来
「誰もが安心して歳を重ねられる社会の実現」――。人生100年時代といわれる現代、この理念を掲げ、食を通じて人々の健康な暮らしを支える企業がある。株式会社シルバーライフは、高齢化社会における食の課題に挑戦を続けている。健康的な食生活の維持が困難になりつつある現代社会。管理栄養士による徹底した栄養設計、素材へのこだわり、そして長年研究され抜いた調理技術を駆使することで、「まごころケア食」は、手軽さと栄養バランスを両立した画期的な食のソリューションを実現してきた。今回は、急速な高齢化という社会課題に挑戦し続ける「まごころケア食」の誕生秘話から、その独自の品質へのこだわり、そして未来への展望までを紐解いていく。取材日:2024年10月30日築き上げた技術で食卓に安心を。「まごころ」と「ケア」に込めた想いまずは、企業概要や提供サービスについて教えて下さい。田村:2007年に創業した株式会社シルバーライフは、高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営を主軸とし、フランチャイズ加盟店などへの調理済み食材の販売を行っています。この事業を通じて培った製造技術やノウハウを生かし、冷凍弁当のEC販売や施設向け食材の販売にも事業を拡大しています。現在、当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、2024年7月末時点で売上規模は約135億円に達し、順調な成長を続けています。冷凍弁当のEC販売では主に「まごころケア食」を展開しており、自社サイトを中心に大手ECモールにも積極的に出店し、多様なお客様のニーズに応える形で事業を拡大しています。まごころケア食の開発に至ったきっかけや、誕生までの経緯をお聞かせください。島倉:まごころケア食は、弊社が長年の配食サービス事業で培ってきた強みを最大限に生かして生み出されたサービスです。配食サービス事業から生まれた数百種類におよぶ惣菜のレシピを活かし、お客様に飽きのこないメニューバラエティを提供することができると考えました。また、配食サービスの事業で培った大量調理の技術により、安全で美味しい食事を、リーズナブルな価格でお客様に提供することも可能になりました。「まごころケア食」という名前にはどのような意味や思いが込められているのでしょうか?田村:「まごころ」という言葉は、配食サービス「まごころ弁当」で培ってきた商品開発のノウハウや、お客様への真摯な姿勢を受け継いだものです。我々の原点である「心のこもったサービス」との想いをそのまま名前に込めました。さらに、「ケア」という言葉には、ただ食事を提供するだけではなく、お客様一人ひとりの健康的な暮らしを支えたいという願いが込められています。日々の食生活を丁寧にサポートし、心も体も満たしていくようなサービスでありたいと考えています。「薄味でもおいしく」の追求は妥協しない!品質と美味しさを守る知恵メニュー開発のプロセスの中でどのような点に注力されていますか?島倉:メニュー開発にあたっては、管理栄養士が、「薄味でもおいしく」「食事として満足できる内容」の実現に注力しています。多くの日本人が1日当たり10.1gを超える食塩を摂取している中*1、「まごころケア食」のメニューでは食塩相当量が1食あたり2.0g以下に抑えられているのです。減塩では薄味に感じられてしまう可能性を配慮し、旨味や酸味を上手く取り入れることで「薄味でもおいしく」感じられるよう、レシピ開発には工夫を凝らしています。また、メニューでは4種類の惣菜が組み合わされていますが、「こってりした主菜にはあっさりした副菜を組み合わせる」など、食べやすさにも配慮した献立作りを行っています。メニュー開発では、まず、何を目的としたレシピなのかを企画し、その後、商品開発室で少量の試作をおこない、品質の確認をおこないます。次に、大鍋やスチームコンベクションオーブンなどを使ったラインテストを実施し、大量調理を想定した調理工程の確認を行います。その後、栄養計算をおこない、バランスの取れた献立の作成に取り組み、本製造に至るという流れです。それぞれの段階で必要に応じて社内での承認を得ながら、各段階で徹底的な検証を重ね、お客様に満足していただける商品を生み出すべく、丁寧なプロセスを経ています。 日本生活習慣病予防協会『食塩摂取量の平均値は10.1g、男性10.9g、女性9.3g 令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」より』サービス開始から、最も苦労されている課題についてお聞かせください。島倉:まごころケア食を運営する上で、私たちが最も苦労している点は原料の安定供給です。原料の調達は、自然災害や天候不順による不作、また国際的な情勢の影響で価格が高騰するなど、私たちの力ではどうにもならない外部要因に大きく左右されます。例えば、大雨による野菜不作や漁獲量の減少などが起こると、原材料価格の高騰などを理由に使用していた食材を完全に変更せざるを得なくなります。そうすると、これまで提供していた惣菜のバリエーションが減ってしまうという課題に直面します。そのため、急いで代替できる原料を探したり、新たな惣菜の開発に取り組まなければなりません。特に、毎月数トンものボリュームで使用する主要な原料が手に入らなくなると、大変な混乱を来たします。加えて近年の食材高騰の影響もあり、「クオリティを落とさず価格も上げずに」対応することが大きな課題となっています。この課題に立ち向かうために、常に食材の状況をリサーチすることが欠かせません。「今年はこの食材の品質が良い」「今後はこの食材が使えそう」といった情報をもとに、献立の見直しを定期的におこなっています。大量調理において、これまで使ったことがない食材を使うことには臆病になりがちですが、積極的に「この食材は使えるだろうか?」と検討し、チャレンジしていく精神が大切です。「毎日」という価値を食卓へ。健康と簡単の両立で、明日の食を応援高齢化社会の中で、どんな未来を描いていますか?また、まごころケア食が果たすべき役割とは何でしょうか?島倉:多くの人々が「調理の手間をなくしたい」一方で、「でも健康的な食事がしたい」というニーズを抱えているのが現状です。まごころケア食は、このニーズに応えるべく事業を展開しています。簡単に調理できる冷凍弁当を提供しつつ、その中に十分な栄養を確保し、健康志向のニーズに応えることができる点が私たちの強みです。企業理念にも掲げているとおり、私たちは誰もが安心して歳を重ねていける社会の実現を目指しています。調理時間をかけずに済む食事の提供を通じて、皆様の健康維持に貢献していきたいです。田村:私たちは、冷凍弁当が一過性のブームにとどまらず、健康的な食生活を支える定番商品として、社会の中で広く受け入れられる存在になると考えています。自炊や食事準備の負担が増加する中、便利で栄養バランスの取れた冷凍弁当の需要は、今後ますます高まると予想されます。忙しい現代社会において、どの年代の方々にも、手軽に健康的な食事を提供できる選択肢として「まごころケア食」が広く選ばれるよう、私たちは商品開発や広告宣伝に力を入れていきます。利用者の声をどのようにサービスに反映していますか?田村:お客様から頂いたご要望は、常に商品開発の貴重な参考とさせていただいています。食の好みは人それぞれで異なりますので、すべてを一度に反映することは難しいですが、より美味しい商品をお届けするために、使用する食材や調味料の選定・調整を丁寧に行い、改良を重ねています。また、定期的なリニューアルや新メニューの開発にも積極的に取り組んでいます。まごころケア食は「ごちそう」を目指すのではなく、栄養バランスが良く、毎日食べても飽きない優しい味わいを実現することを目標としています。これにより、特別な日だけではなく、日常の食生活に自然と溶け込む存在でありたいと考えています。外食や自炊と組み合わせながら、まごころケア食を気軽に取り入れていただけるよう、今後もお客様の声を丁寧に汲み取りながら、商品改善を進めてまいります。世代を超えて広がる、健康という選択ー安心して歳を重ねられる未来へ今後、サービスをどのように拡大・進化させていく予定ですか?田村:まごころケア食は、業界でも最安値級の価格設定を実現しており、幅広い年代のお客様に気軽にお試しいただける商品です。現在、多くのお客様にご支持いただいており、特に健康を気遣いながらも手軽さを求める方々に選ばれています。どの世代の方にもご満足いただけるよう、バランスのとれた商品内容にこだわっています。今後も、さまざまなライフスタイルやニーズに寄り添う形で、より多くの方々にご利用いただけるような取り組みを進めていきたいと考えています。その上で、競合他社の参入が活発化しており知名度の向上が重要な課題となっています。これに対応するため、さまざまな企画を通じて「まごころケア食」のブランド力を高め、より多くのお客様に選ばれる存在を目指していきます。まごころケア食、最終的にどのような社会や未来を実現したいと考えていますか?田村:弊社の経営理念は、「食の観点から誰もが安心して歳を重ねていける社会の実現」です。この理念のもと、私たちは冷凍弁当を通じて、食事に関するさまざまな社会課題の解決に貢献したいと考えています。たとえば、ライフステージや生活環境の変化に伴う食生活の悩みを解消するための手助けを目指しています。まごころケア食は、栄養バランスに優れ、毎日でも取り入れやすい商品を提供することで、健康的な生活をサポートする存在でありたいと考えています。特に、忙しい方や食事の準備が負担に感じられる方にとって、気軽で便利な選択肢として広く活用いただけるよう努めています。これからも、お客様一人ひとりのニーズに寄り添いながら、日々の食生活をより豊かにし、誰もが安心して年を重ねていける、そんな社会の実現に向けて挑戦を続けていきます。 まごころケア食 公式サイトはこちら まごころケア食の解説記事を読む -

【つくりおき.jp】冷蔵で届ける手作りの味—つくりおき.jpが叶える家庭の食のニューノーマル
「毎日の食事づくりに追われる生活から、もっと大切なことへ時間を使ってほしい」そんな想いから誕生した宅配食サービス「つくりおき.jp」が、いま注目を集めている。共働き世帯の増加とともに「作りたくても作れない」「あと一品欲しいのに...」という声は切実さを増すばかり。プロの料理人が手がける本格的な作り置きを、LINEという身近なツールで注文できる。仕事の合間でも注文できる利便性、栄養バランスへのこだわり、そして何より確かな品質。日本の食卓の未来を見据えた、その誕生秘話から将来の展望まで、サービスの全貌に迫る。取材日:2024年10月24日環境が変われば、人生が変わる!幼少期の体験が生んだ宅配食サービス 引用:株式会社Antway 公式ホームページつくりおき.jpの開発の背景について教えてください。つくりおき.jpは、代表の前島の幼少期の経験から事業構想を得て、一人で立ち上げたところからスタートしました。熊本出身の前島は、小学生時代に集団行動が苦手で不登校を経験しましたが、関東への転居を機に新しい環境で活き活きと過ごせるようになりました。この経験から、その人自身が変わっていなくても、置かれた環境によって人生が大きく変わり得るという気づきを得たそうです。事業のもう一つの原点は、前島が子どもの頃に経験した家庭環境です。父親がうつ病で一時期働けなくなった際、母親が家計と家事の両方を担わねばならない状況を目の当たりにしました。この体験から、特に女性に偏りがちな家事負担によって、本来なら仕事や家族との時間、趣味などに使えるはずの時間が制限されている社会課題に着目したそうです。ユーザーリサーチを通じて、家事の中でも特に料理が時間的にも精神的にも大きな負担となっていることが判明し、その解決策としてつくりおき.jpを立ち上げました。つくりおき.jpのサービスの強みや特徴は何でしょうか? 引用:株式会社Antway 公式ホームページ当社のサービスの最大の特徴の一つは、家事における義務的なタスクを徹底的に削減して、とにかく楽であるという点です。例えば、通常のミールキットの場合、最後の調理や後片付けまで、合わせて20分程度必要でしょう。また、冷凍弁当でも4人分を温めるとなると同様に20分ほどかかってしまいます。一方、私たちのサービスは冷蔵配送で、おひたしなどの冷菜は、受け取ってすぐに食べられ、温める必要のある主菜も3〜4分程度で準備できます。冷菜、温めた主菜、ご飯、味噌汁を組み合わせれば、わずか5分程度で食事の準備が完了します。さらに、調理器具を使用しないため、洗い物も食器類のみで済み、容器は捨てるだけです。もう一つの強みは、お客様の精神的な負担を解消する点にあります。冷凍弁当やコンビニ弁当は一時的な利用であれば問題ありませんが、毎日家族に提供することには少なからず罪悪感や抵抗感が伴うと思います。特に栄養バランスの面で不安を感じる方もいらっしゃいます。つくりおき.jpでは、管理栄養士が栄養バランスを考慮してレシピを作成し、プロの料理人が手作りした料理を冷蔵のままお届けします。自分で作るには少し手間がかかる料理を、大人も子供も一緒に食べられる薄味で、丁寧に手づくりしています。冷蔵でのお届けなので、出来立てそのままの美味しさで、夕食以外にも朝昼の1品にしたり、アレンジも自由自在です。さらに、メニューが週替わりで変化するため、日々の食卓に変化をつけることができます。このような特徴から、長期的な利用を前提としたサービスとして、多くのお客様から支持をいただいています。プロの料理人や管理栄養士と協力して作られたというメニューのこだわりのポイントや、開発過程でのエピソードについて教えてください。当社は、お客様からのフィードバックを基に、常に迅速な商品開発を行っています。毎週実施しているアンケートを通じて、お客様からの生の声や満足度、継続率などのデータを即座に分析し、チーム全体で商品改善に活かしています。他社でもお客様の声を商品開発に反映させる取り組みは行っていると思いますが、当社ほど迅速かつ直接お客様の意見を収集し、開発に活かしている例は少ないでしょう。顧客起点の開発サイクルの速さが、当社のメニュー開発のこだわりの一つです。例えば、魚料理は、家庭での調理に手間がかかる一方で、市販の惣菜は揚げ物が中心となっており、焼き魚や煮魚といった日常的な魚料理を手軽に楽しむ選択肢が限られているというお客様からの声がありました。そこでつくりおき.jpでは、フライなどの一般的な惣菜メニューに加えて、家庭的な焼き魚や煮魚などの料理も提供しています。例えば魚料理は、魚を捌いたり、骨を取ったりする調理工程を考えると調理のハードルが高くなりがちです。そのため、家庭料理としては浸透しているものの、調理の負担が高かったり、スーパーや市場で入手しづらかったりする魚を使用した魚料理も積極的に開発しています。メニュー開発の課題の一つは、子供から大人まで、家族全員が同じ食事を楽しめるための幅広い年齢層に対応しているかどうか、ということです。別々の食事を用意する手間を省くため、幼児向けすぎず、かといって大人向けすぎない、バランスの取れたメニュー作りを追求しています。例えば、豚骨ラーメンのように大人には美味しくても子供には適さない料理もあり、全年齢層が満足できるメニューの開発には試行錯誤しているんです。また、一つのメニューを開発する際には、最低3〜4回の試作を重ねています。これは、テストキッチンと実際の工場では、調理器具のサイズや食材の状態が異なるためです。家庭での調理以上に大規模な食品工場での生産には独自の課題があり、その都度最適な味と品質を実現するために、何度も試作を続けています。以前は問題なく提供できていたメニューでも、規模が大きくなることで様々な制約が生まれ、提供が難しくなるケースが発生するんです。また、お客様の増加に伴って、より多様なニーズへの対応も求められるようになってきました。メニュー開発においては、事業の拡大とともに日々新たな課題が生まれ、その解決に向けて努力を重ねている状況です。ありがとうございます。その上で、おすすめのメニューを3品あげるとしたら、何でしょうか? 引用:株式会社Antway 公式ホームページ当社の一番の人気メニューは、トマトハンバーグです。ハンバーグ系のメニューは、子供から大人まで幅広い年代に人気があります。また出汁を使った煮物系の料理も人気です。作り置きという形式と相性が良く、時間とともに味が染み込んでより美味しくなる特徴があり、プロの料理人による絶妙な味付けが好評です。これから冬に向けて提供予定のチーズフォンデュのような、家族で楽しめるメニューも用意しています。温めて最後にチーズをつけて食べるという、食事の楽しさも演出できるメニューとなり、おすすめの一品ですね。家事の外注に罪悪感はいらない!時間の余裕が作る心の余裕 引用:つくりおき.jp 公式ホームページプランや料金体系でのこだわりを教えてください。ユーザーリサーチを通じて、共働き世帯や子育て中の家庭が最も苦労しているのは、日々の食事の準備であることが分かりました。そこで、週の半分以上の食事を賄える量と、継続利用しやすい価格設定を重視しています。1食あたり700円台という価格は、2,000円近くかかるデリバリーサービスと比べても、かなり手頃な価格設定となっているでしょう。この価格を実現できている主な理由は、サブスクリプション型のビジネスモデルにあります。お客様が継続的に利用してくださることで、需要予測が立てやすく、食材の廃棄ロスを最小限に抑えることができているんです。一般の飲食店では来客数の予測が難しく、食材の廃棄が避けられない面がありますが、当社では大規模な運営にも関わらず、廃棄をほとんど出さない効率的な運営が可能となっています。このような無駄を省いた運営により、適正価格でのサービス提供を実現しています。忙しい方が使いやすいサービスを提供されているという印象を受けます。特にLINE登録して注文する仕組みを導入したのはなぜでしょうか?当社では創業当初から、忙しい顧客層の利便性を考慮し、LINEでの注文システムを導入しています。新たにアプリをダウンロードする手間を省き、日常的に使用しているLINEを活用することで、友達登録だけで簡単にサービスを利用開始できる仕組みを整えました。また、お客様の都合に合わせて注文でき、休会や解約は無料です。毎週の注文を義務付けることなく、柔軟に利用期間を調整できる点も、働きながら家事をこなす方々から好評を得ています。お客様の声で特に印象に残っているエピソードはありますか?以前、お客様へインタビューをした機会がありました。その際、特に印象に残っているエピソードがあります。ある女性のお客様は、当初、家事の外注に対して罪悪感があり、つくりおき.jpの利用を躊躇していたそうです。しかし、周囲に当たり前のようにサービスを活用し、時間を有効活用している友人たちがいることに気付き、自分の考えが変わったと言うお客様がいました。実際にサービスを利用し始めてからは、以前は時間が取れなかった小説執筆の時間が確保できるようになり、生活に余裕が生まれたそうです。その結果、家族への接し方にも良い変化が現れ、むしろ早く利用を始めておけばよかったと感じたとのことでした。当社のサービスが目指す理念が、お客様の体験として実現された好例だったので、このお客様のエピソードは特に印象深いものとなりました。また、私たちのサービスを通じて、食を介した家族の新たな発見や成長の瞬間を共有できたことを、多くのお客様からお喜びの声としていただいています。例えば、お子様が今まで苦手だと思っていたナスを美味しく食べていたり、普段は避けていた煮物を進んで口にしたりする姿に、保護者の方々も驚きと喜びを感じられるようです。普段苦手だと思って、食卓に出さなかったものの、つくりおき.jpで届いた料理がきっかけで、お子様にとっては新しい味との出会い、保護者の方にとってはお子様の未知の一面を発見できる機会を提供できたことは、当社としても嬉しい限りです。楽になる×楽しさ。「日々のゆとりを、つくりおき。」に秘められた思い 引用:つくりおき.jp 公式ホームページここ数年で、人々の食のニーズはどのように変化していますか? また、昨今では特にどのようなニーズが多いのでしょうか?コロナ禍とその後の変化によって、食生活に関する消費者の意識と行動が変わった部分があります。在宅勤務中は自炊の時間も確保できていましたが、出社勤務が再開してからは、多くの人が出社し、通勤時間や仕事量の増加など、全体的な忙しさが増えるようになりました。その過程で、コロナ禍に普及したデリバリーサービスの利便性を実感した人が増え、食事の準備に掛かる時間と手間を省くための選択肢として、こうしたサービスを積極的に活用する傾向が強まっています。まだ完全な定着とは言えませんが、日常的な食事をデリバリーで賄うという習慣は、少しずつ社会に浸透しつつあるように感じます。「つくりおき.jp」が目指す未来の食生活とは何ですか?弊社のキャッチコピーである「日々のゆとりを、つくりおき。」には、「楽になる」と「楽しむ」という二つの意味が込められています。昨今、完璧な栄養バランスを謳う食品が増えていますが、その多くは味わいの面で物足りなさを感じさせます。一方、弊社が目指すのは、食事の手間を減らすだけでなく、食卓の豊かさも同時に提供することです。普段目にしないような野菜や魚を使った料理、その食材にまつわるストーリーなどを通じて、家族の会話が弾むような体験を創出したいと考えています。効率や利便性だけでなく、食事本来の楽しみも大切にした、より豊かな「ゆとり」を提供できるよう、今後もサービスの品質強化に努めていきたいです。一人一人の「良かった!」が変えていく社会。家事を背負いこむ義務感を手放して。最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします!休日など時間に余裕がある時の料理は、趣味や楽しみとしていいのですが、毎日の食事の支度が義務的な負担になっているのであれば、その時間を家族との時間に使うこともひとつの選択肢ではないでしょうか。両親が心に余裕を持って穏やかに過ごせることは、子供たちにとっても嬉しいことだと思うのです。家事を自分で完璧にこなそうとするのではなくて、日常の料理という義務的なタスクを外部に任せることで、新しいライフスタイルが見えてくるかもしれません。まずは一週間でも、義務のタスクを任せてしまうという暮らし方を試してほしいと思います。初めての方におすすめのプランは、最も利用しやすい3食プランです。平日が忙しい方であれば週の前半に、また週末に料理から解放されたい方は木曜日や金曜日に料理を受け取っていただくことで、土日のお昼などにも活用できます。また、朝昼晩の全ての食事を手軽に済ませたい方にも多く使っていただいているんです。ライフスタイルに合わせて柔軟な使い方が可能なので、ご自身に合った活用方法を見つけていただければと思います。共働き世帯の増加や女性の社会進出が進む中、私たちのサービスも日本社会の変化に応じた支援的なサービスとして、メディアでも積極的に取り上げていただけるようになりました。一方で、「家事は全て自分でやらなければならない」と考えている方はまだ多くいらっしゃいます。このような状況を変えていくために、サービスを利用して良かったという経験を、SNSや口コミで周りの方々にお伝えいただけると嬉しいです。一人一人の「良かった!」という声が、社会の意識を少しずつ変えていくきっかけになるのではないでしょうか。 つくりおき.jp 公式サイトはこちら つくりおき.jpの解説記事を読む