-

倉敷芸術科学大学・楢村友隆氏が語る、美容脱毛の現状と未来とは?
昨今、男女問わず脱毛を経験する人が増え、都市部では脱毛サロンの数も増加している。インターネット広告やテレビCMでも頻繁に見聞きするようになった脱毛サロンだが、増加と共に脱毛に関する事故や金銭トラブルも増えているのが現状だ。脱毛についての適切な情報収集が重要になる一方で、適切な情報がインターネット上では不足しており、脱毛に関する知見が乏しい人はどのように脱毛サロンを選択したら良いのかわからない方も多いのではないだろうか。そこで、『よくわかる脱毛 後悔しないサロン選び』の著者である倉敷芸術科学大学の楢村友隆准教授に、美容脱毛の現状と将来の可能性について取材しました。倉敷芸術科学大学・楢村友隆准教授が取り組む脱毛の研究とは?まずは研究概要について教えてください。元々私の主な研究テーマは、人工透析治療でした。特に人工臓器を使用した治療技術に焦点を当てて研究を行ってきました。私は臨床工学技士という医療系国家資格を有しており、大学教員になるまでは病院で臨床業務に従事してきたんです。近年は病院で使用される人工臓器や医療機器のみならず、美容機器の研究にも力を入れています。美容機器は、超音波やレーザーなどの物理的エネルギーを用いて体を美しくするというコンセプトが基盤にあります。実は、このエネルギーの利用原理と生体への作用機序は私が以前から研究していた医療機器と非常によく似ているんです。脱毛の研究に没頭した契機は、私自身がレーザー脱毛器による医療脱毛を受けたことでした。あまりの痛みに耐えられず、数回施術に通っただけで脱毛通いをやめてしまいました。痛くない脱毛方法は他にないのかということで美容サロンでの光脱毛に関心を持ったんです。後ほどブロードバンド光脱毛のお話もしますが、現在はこの技術に関する研究を行っています。技術進化により、光脱毛でもレーザー脱毛と同様の脱毛効果がある!?なるほど、脱毛機自体の調査なども担当されているのでしょうか?毎年毎年新たな脱毛器が市場に出てきますので、全てを把握しているわけではありませんが、国内で販売されている脱毛機の殆どは調査してきました。脱毛技術は最近どのように進化していますか?脱毛技術に関して言えば大幅な進化を遂げているわけではありませんが、軽微な改良や快適性の追求は続いています。基本的な原理、すなわち皮膚と毛に光を当てることで脱毛を実現するという点は変わっていません。しかし、より効果的に、より肌に優しくという点で、時代と共に新しい工夫が取り入れられています。例として、現在ではすでに主流となっていますが、ハンドプローブの先端が冷えており、皮膚表面を冷やしながら光照射を行うことができるようになりました。これにより、従来よりも施術の痛みが大きく軽減され、火傷のリスクも低減しています。また、根深い毛の脱毛効果を高めるために、従来よりも少し波長の長い光を照射できる装置なども誕生しています。なるほど一方で、ブロードバンド光の脱毛・美容医学における最新の研究成果は何かありますか?最近の研究では、光脱毛機を使用することで、皮膚に優しく、痛みが少ない状態での永久脱毛が可能であることが確認されました。私自身は、皮膚への負担が少なく、効果的な光脱毛機の方が将来的にはより多くの方に選ばれると考えており、その研究を現在進めています。光脱毛でも永久脱毛ができるんですね! 自分も脱毛に通っているのですが、完全に毛を無くしたいのであれば、レーザー脱毛しか方法がないと思っていました。確かに多くの人が、「永久脱毛をするためには医療脱毛が必要」という先入観を持っていると思います。ですが「永久脱毛」という言葉の意味を正しく理解できている方は殆どいないのではないかと思います。医学的にいう「永久脱毛」とは、最終脱毛日から1ヵ月後の毛の再生率が20%以下の状態をさします。つまりおおよそ80%の毛が1ヵ月以内に、生えてこなくなる状態が永久脱毛と定義されています。実際にはレーザー脱毛を受けたとしても、一部の毛は再び生えてくることがあります。それでも、サービスを提供している側からすれば、“永久脱毛が完了した状態”と言うことができるのです。現在の光脱毛でも回数は医療脱毛より多くかかりますが、「80%の毛が1ヵ月以内に生えてこなくなる状態」は十分に達成可能です。また、サロン側も「永久脱毛」という言葉は誤解を招きやすい用語ですので、個人的にはあまり使わない方がいいのではと思っています。多くの方は、永久脱毛は永遠に毛が生えてこなくなると思っていますよね。医療脱毛でも一部の毛は生えてくることがありますので、医療脱毛でも光脱毛でも、「永久減毛」といった方が現実には見合っていると思います。なるほど…自分もレーザー脱毛か光脱毛か迷っていたので、今のお話を聞いて安心しました!脱毛機から毛へ照射されるのは、レーザーや光です。人間が色を認識できるのは、太陽からの光が「波」として目に入ってくるからです。人間の目が感じることができる光の波長は(波1つ分の距離)は、約400nm~780nmという限られた領域です。たとえば、波長が短いと青紫色だと認識し、波長が長いと赤色だと認識します。その波長がさらに短くなると紫色から外れるので紫外線(400nm未満)、長くなると赤色から外れるので赤外線(780nm以上)と呼んでおり、波長が極端に短いものや長いものは人の目では見ることができません。ブロードバンド光脱毛は、特定の波長に固定されていないという特徴があり、500~1000nm程度の光を広範囲に照射することができます。一方で医療脱毛機(レーザー脱毛)は、アレキサンドライトレーザーは755nm、ダイオードレーザーは810nm、というように波長が決まっています。それぞれのイメージとしては、レーザー脱毛機は、レーザーポインターのように特定の方向に強いエネルギーが飛び、光脱毛機は電球のように光が拡散します。そのためレーザー脱毛は、強いエネルギーで照射するため痛みがある一方、光脱毛は痛みが少なく、効果はやや弱いと言われています。レーザー脱毛の方が、強いエネルギーのレーザーを使用するので、脱毛も早く完了するんです。また消費者の方は、医療脱毛の意味をしっかりと理解できていない方も多いと思います。医療行為である医療脱毛とは、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」と定義されています。そのため、病院で行うから医療脱毛、レーザー脱毛器を使用すれば医療脱毛、といった分類ではないわけです。レーザーであっても弱いレベルであれば医療脱毛に相当しませんし、光脱毛であっても毛乳頭や皮脂腺開口部等が破壊されるレベルの照射を行えば医療脱毛となります。またレーザー脱毛器ではなく出力の高い光脱毛器を医療脱毛としてクリニックで使用されている先生もいらっしゃいます。より安全・安心な脱毛のために、私たちが知るべきこと―――昨今脱毛をする方は、男女共に増えていると思います。一方で事故や施術期間中にサロンが倒産して施術料金が返金されないなどのトラブルも増加している気がします… 脱毛業界の課題や動向で特質している点はありますか?脱毛業界の視点から見れば、大手脱毛サロンが国内での店舗拡大を続けていますが、美容脱毛市場そのものは飽和状態に近づいてきているように感じます。その結果、顧客の取り合いや他社との競争はより一層激化しており、新しい技術や手法の名前を活用したマーケティング戦略が目立っていますね。例えば、従来の脱毛技術と大差がない施術方法であっても、一般的な技術名称に名前を付け加えてあたかも新技術を開発・導入しているかのような宣伝をしている脱毛器メーカーやサロンも存在します。また、サービス面では、都度払いよりお得なまとめ払いプランを採用して、複数回の施術費用を先払いするプランが多くの消費者に支持されています。しかし、この制度を導入している脱毛サロンの中には経営難から突如として閉店するケースもあり、多くの消費者が被害を受けている実態が明らかになっています。特に、ローンやカード決済を選択している消費者は、返金問題などのトラブルに巻き込まれるリスクもあるので注意が必要です。なるほど…私も施術期間中に倒産してしまった脱毛サロンから、顧客へお金が返金されないというニュースを拝見しました。倒産している脱毛サロンの問題は業界では深刻なんです。つい先日も大手サロンが倒産し、全国で一斉に閉店しましたよね。多くの方がご存知の大手脱毛サロンでも、過去に数回の倒産歴があり、別の企業に買収されて経営を継続しているケースなどもあります。買収されたことはラッキーで、そのお蔭でなんとかサービスが継続できているという状態です…このような背景情報は、一般の消費者にはあまり知られていないのが実情です。特に若い世代の方々は、ローンを組むと月々の支払いは安価になりますので、それを魅力と感じて契約を結んでしまうケースが多いです。しかし、実際にはかなりの金額の借金を背負ったということを自覚していないケースが少なくありません。また、とある脱毛サロンでは「激安」「通い放題」で人気を集めていますが、全身を50パーツ程に分割して1ヶ月に最大5カ所までしか脱毛できないという制限を設けています。そして、中々予約も取れず…全身脱毛を終了するまでいったい何年かかるのだろう…というケースもあります。そこでは、予約が取りやすくなり、1度の来店で全身の脱毛をしてくれるというオプションプランを用意しており、高額なオプション料金を支払えば一般的な期間で脱毛が終了します。結局、最終的に支払う金額は他のサロンと変わりないといったこともあります。なるほど…ここまでのお話を聞いていると、サロン側の事情が先行して、顧客側への配慮がされていないような印象を受けました…。とある脱毛サロンでは、単純にスタッフ不足や施術の部屋が足りないことが原因で予約が取れないという部分を隠しているケースもあります。「最適な脱毛間隔は3ヵ月に1回です!」と消費者に説明し、あたかも次の脱毛までの最適間隔は3ヵ月は空けなければならないという間違った認識を消費者に伝えているケースもあります。本当ですか…今のお話を聞いていると、脱毛に関する知識が乏しい人の場合、サロン側の事情で間違った選択をしてしまうリスクが高まるというか…おっしゃる通りです。そのため、安易な契約は後々のトラブルの原因となる可能性がありますので、十分な情報収集と冷静な判断が必要ですね。ここまでのお話を聞いていると、脱毛に対する誤解や根拠がないのに情報だけが一人歩きしている状況のように思いました… このような原因を招いてる要因は、何かあるのでしょうか?大手脱毛サロンや大手脱毛器メーカーの宣伝広告が目を引きますが、必ずしも大手だからといって信頼性が高いというわけではありません。多くの人が、「大手の脱毛サロンならば安心!」と考えているかもしれませんが、大手の脱毛サロンは店舗数が多く、施術を行うスタッフの研修体制が不十分な場合もあります。実際に施術の経験が乏しい新人が、短時間の研修を受けたのみで現場に配属され施術に携わるケースも少なくありません。サロンのみならず美容クリニックでも同様ですが、脱毛のことを正しく理解できている経営者・施術者は少ないと思います。なので、ホームページ等の広告媒体に間違ったことが記載されていたり、かなり誇大広告となっていたりしても気付かないのだと思います。なるほど…数ヶ月前にあった、施術後の火傷の事故がニュースになっていたのも、経験が乏しい故のヒューマンエラーだったんですね…。そうですね…施術中のミスによる事故が発生するのは大手サロンに限ったことではありません。先日関西のサロンで起きた施術中の火傷の事故は、装置のメンテナンス後の確認ミスが原因でした。これは施術技術の問題ではなく、単純な作業ミスによって発生したんです。美容機器に関する専門教育の不足も深刻な問題です。一般的な美容系の専門学校では、美容機器の原理や操作方法、施術のテクニックに関する授業は行われていません。また、専門教育を受けていなくても脱毛サロンは開業できます。サロンでは医療従事者がいないため、より安全な施術を行うことが求められます。また、医療従事者が働いている美容クリニックでも安全とは言えません。医療スタッフが機器の操作方法を正確に理解していないケースが散見されているんです。看護師さんも医療機器の専門教育は受けていませんから。このような状況は非常に危険であり、医療機器の専門職である臨床工学技士の配置が必要だと私は提案しています。現在の美容医療や美容施術に美容機器は欠かせません。我々の大学では日本で唯一、美容機器の仕組みや取り扱いなどに関する専門教育を受けることができるコース(生命科学科美容コース)を開講しています。ここまでのお話を聞いていると、各サロンの問題というよりは、業界特有というか、業界全体に根深い課題があるような印象を受けました…そうですね… 医療脱毛では、看護師さんたちは医学的な知識は持っていますし、美容クリニックでの注射や点滴なども行えます。ですが特定の美容機器を使用する際の施術は、看護師さんにとっても経験が乏しかったり、そもそも機器の使用に不慣れだったりするケースがあるんです。使用する機器に突然エラーが出たり、いつも通りに使用していたのに突然装置が不具合を起こしてしまうと看護師さんも困惑してしまいます…実は過去に、心臓の手術や人工透析治療の分野でも同様の問題があって、それが我々の職種(臨床工学技士)が生まれた契機にもなっています。現場で機器を使用する人が不慣れというのは、施術を受ける側からするととても不安ですね…。そうですよね。そのため、業界全体の改善に向けて何かを変えたいけど、業界同士の反発が発生するケースも多いんです。既得権益を守ろうとする団体もあり、仕組み作りの変革に賛同しない傾向があったりします。そう考えると、業界全体を変えていくのには5年や10年といった長期戦になるかと思っています。でも、「必要は発明の母」ということわざがありますが、同じような感じで必要であればいつかは変革される時期がくるものと思っています。美容脱毛の未来は、多岐にわたるニーズに応えるための技術進化によって加速する美容脱毛の未来は、非常に多岐にわたる可能性を秘めていると感じます。まず、歴史を振り返ると、脱毛という概念は紀元前から存在し、海外では紀元前4000年頃から脱毛剤による脱毛が行われていたという記録が残っているそうです。日本に初めてレーザー脱毛器が輸入され、レーザー脱毛が行われるようになったのが1997年頃、もっと安く、もっと痛みのない脱毛を目指して光脱毛器が開発され使用されるようになったのは2000年頃からです。近年では美容目的だけでなく、アスリート脱毛といって、テレビカメラの高解像度化によりアップで映し出されるとスポーツ選手の毛穴までがくっきりと映るため、多くのプロスポーツ選手が脱毛を希望するようになっています。また、スポーツのパフォーマンスを向上させるため、水泳選手は水の抵抗を減少させるために、競輪選手は風の抵抗を減らすために、クライミング選手はテーピングの浮きを防ぐために、といった目的で脱毛を行われる選手も増えています。さらに、近年では子どもさんの脱毛も増加しています。毛が濃く、それがいじめの原因やコンプレックスとなるケースもあり、親御さんが子どもさんの脱毛を希望するケースが増えています。そして、介護脱毛という、将来的に介護される可能性のある40代・50代の特に女性の方が、将来介護して頂く方の負担軽減のためにVIO脱毛をされる方が増えていますね。60代を過ぎてくると体毛の一部も白くなってきますが、白くなってしまうと毛が脱毛器に反応しなくなってしまうため、毛が黒いうちに脱毛しておこうということが重要になるわけです。また、我々の研究室で取り組んでいる医療的ケア児(病気や障害のために特定の医療的ケアが必要な子ども)のための「介護脱毛」という新しい方向性もあります。男女問わず思春期に差し掛かると体毛が濃くなってきますが、その毛の処理は介護されている親御さんの負担となります。男の子の場合は定期的にヒゲを剃ってあげる必要があったり、女の子の場合は生理時や排泄物処理の際にVIOの毛が処理の手間や衛生的な問題を引き起こしたりと、普段から定期的にお子さんの剃毛をされている方も多くいらっしゃいます。そのため、お子さんの脱毛や減毛を希望される親御様が多くいらっしゃいますね。子どもの脱毛となると大人のように痛みに耐えることは困難ですので、我々は痛みを伴わない脱毛技術の提供を目指して日々研究を続けています。技術的な進化では、どうでしょうか?もちろん、技術的な進展も今後期待できます。現在の脱毛は光やレーザーが主流ですが、将来的には他の物理的エネルギーを用いた新しい技術が登場する可能性もありますね。また、最新の研究によれば発毛に関与する幹細胞をコントロールしているのは特定のタンパク質であり、このタンパク質の制御技術を開発すれば、より痛みが少なく肌に優しい効果的な脱毛が可能となるでしょう。総じて、脱毛の未来は多岐にわたるニーズに応えるための技術進化が求められると感じています。それにより、脱毛は今よりもさらに身近なものになってくるでしょう。脱毛の目的やゴールを考えることが重要どのような視点を持ち、私たちは脱毛のサービスや現状と向き合えばよいのでしょうか?まず私たちは、脱毛サロンを選ぶ際、多くの情報源から適切な情報を収集することが大切です。口コミや友人・知人の体験談は、非常に重要な参考となります。しかし、これらの情報だけで判断せず、自分の脱毛に対する目的やゴールをしっかりと考えることが重要です。例としては、脱毛の部位や仕上がり具合を明確にイメージすること―― それが、自己処理が楽になる程度でよいのか、産毛まで取り除きたいのか、毛穴までしっかりと除去したいのかなど、自身の希望を具体的にイメージすることが大切です。このようなイメージをもって、サロンとの契約内容をしっかりと確認することで後悔することなく脱毛サービスを受けることができます。例えば、目的が自己処理を楽にすることだけであれば、永久脱毛相当の回数を契約することは過度かもしれません。サロンのアクセスの良さや施術時間、料金なども考慮して、自分のライフスタイルや予算に合ったサロン選びをすることが重要となります。インターネット広告で見かけたキャンペーンプランが安そうだったから、分割払いで安く施術できそうだから―― などの広告や宣伝を鵜呑みにして、すぐにサロンを決定しないことが失敗しないサロン選びのポイントですね。その場ですぐに契約せずに、色々と比較して冷静に考えられてから契約されるのがよいと思います。 -
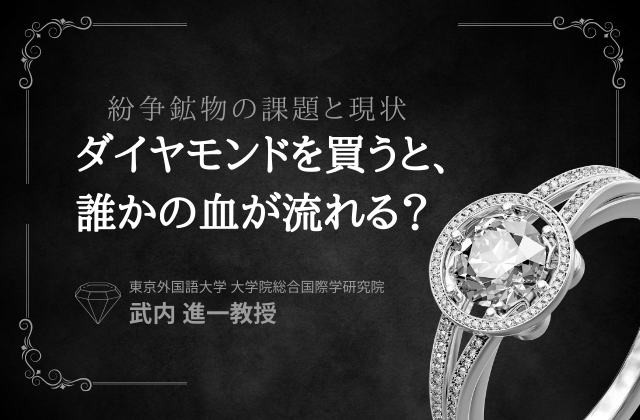
ダイヤモンドを買うと、誰かの血が流れる?〜紛争鉱物の課題と現状〜
ダイヤモンドやスマートフォンを始め、鉱物資源はいまや私たちの生活になくてはならないものになっている。その鉱物資源がどのように採掘され、届けられているかをご存知だろうか?アフリカでは、鉱物資源にまつわる紛争や劣悪な労働環境が今なお続いている。このインタビューでは、「未来の新しい当たり前」をテーマに、紛争鉱物の問題に焦点を当てる。東京外国語大学の武内進一教授との対話を通して、紛争鉱物の現在の状況、課題、未来への展望について深く探求する。紛争が相次ぐ1990年代、アフリカに赴任まずは、研究領域について教えてください。地域研究者として、中部アフリカのフランス語圏地域を専門にしています。具体的には、政治経済分野が専門で、アジア経済研究所で研究を始めた1980~90年代には、主食食料の生産やその都市への流通に関する調査研究を行っていました。1992~94年にコンゴ共和国の首都ブラザヴィルに赴任し、農村に滞在したり、食料を運んでくるトラックに同乗したりしながら、主食食料の生産・流通について調査しました。滞在中にブラザヴィルで武力紛争が起こり、それに巻き込まれたこともあって、食料の生産・流通から政治に関する問題へと、徐々に研究テーマを変えました。紛争に関する研究の一環として、紛争鉱物についても学びました。政治と農村が交わる場としては土地問題が重要なので、最近は土地政策やアフリカの国家による領域統治にも関心をもっています。当時赴任されていた地域で紛争が起こったとのことですが、具体的にどのような紛争が発生したのでしょうか?中部アフリカ・フランス語圏の中で最も大きな国が、現在のコンゴ民主共和国です。私がこの地域について勉強を始めたのは1980年代には、ザイールと呼ばれていました。※1当初はザイールに赴任して調査活動を行うつもりで準備していましたが、ちょうどその時期にザイールの政治情勢が不安定になり、大規模な暴動が勃発して、とても調査ができる状況ではなくなってしまいました。そこでやむなく、1992年に隣国のコンゴ共和国に赴任したのです。しかし、そこでも選挙のやり方や結果をめぐって政治対立が深まり、1993年には政府勢力と反政府勢力が首都で激しく対立する事態となりました。街中を戦車が走り回り、あちこちで銃撃戦が起こるので、何度も自宅から避難しました。この時期、中部アフリカの国々で次々に紛争が起こりました。ルワンダでは1990年から内戦が始まり、1994年にはトゥチ人の大量虐殺(ジェノサイド)が起こっています※2。このルワンダの紛争が波及する形で、隣国のコンゴ民主共和国でも1990年代後半には大規模な武力紛争が勃発しました。中部アフリカの国々で紛争が相次いだのです。 参照:外務省 コンゴ民主共和国(Democratic Republic of the Congo)基礎データ 参照:国際連合広報センター 1994年のルワンダにおけるジェノサイドを考える国際デー(4月7日)に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長メッセージ長引く紛争と劣悪な労働環境、かいくぐられる規制紛争鉱物の問題の背景と現在の状況について、教えてください。紛争鉱物の問題が注目されるようになったのは、1990年代以降です。※1アンゴラやモザンビークなど、アフリカでは冷戦時代にも多くの紛争があったのですが、紛争鉱物をめぐる問題が注目されるようになったのは、主に冷戦終結後のことです。アメリカとソビエト連邦が対立した冷戦時代には、アフリカの紛争の多くは大国間の代理戦争という性格が強く、そうした大国がアフリカの紛争当事者(政府、反政府武装勢力)に直接軍事援助を行っていました。しかし、冷戦終結後にはそうした代理戦争が減少し、アフリカで紛争が勃発すれば、紛争当事者は自ら軍事資金を調達しなければならなくなりました。そこで、紛争鉱物資源を利用して軍事資金を得るという行動が増加したのです。その最初の例として挙げられるのが、シエラオネやアンゴラでのダイヤモンドです。ダイヤモンドは少量でも高い価値がありますから、これを利用して軍事資金を得る行為が増加してきたのです。紛争鉱物問題の背景として重要なことは、鉱物を採掘する方法です。鉱物採掘には二つの方法があります。一つは大規模な機械を使用して行う方法です。もう一つは人力で掘る方法で、例えばダイヤモンドの場合、鉱脈近くを流れる川底の泥をさらい、人力でダイヤモンドを探します。金もこのような形で探すことが多いです。その他の鉱物では、埋蔵していると思われるところを人力で掘っていく、という単純な作業がほとんどです。機械掘りの場合は、高価な掘削機械を使って鉱脈を掘り進めます。この方法は資本が必要で、事実上大企業しか行うことができません。一方、人力で川底をさらったり、埋蔵地を掘り進めたりして、鉱物を探すことは、資本力がなくてもできます。ほとんどの紛争鉱物には、この人力掘りが関わっています。人力に依存した鉱物採掘は、近年アフリカ農村部に急速に広がっています。これは、紛争による治安悪化と相乗的な関係があります。紛争拡大で治安が悪化すると、人々が畑に出て耕作や収穫といった農作業をすることができなくなります。そのため人々は、自分の生計を立てるために小規模な採掘活動に従事することが多くなりました。この状況が最初に顕著に現れたのが、1990年代後半から2000年初頭にかけてのシエラレオネとアンゴラの紛争ダイヤモンドの問題でした。※2シエラレオネとアンゴラはともに2000年代初頭には紛争が終結しましたので、紛争鉱物の文脈では問題が解消されました。しかし、依然として小規模な鉱物資源採掘活動の労働環境は劣悪ですし、他のアフリカでは、ダイヤモンド以外の鉱物に関して紛争鉱物問題が起こっています。最近の例として挙げられるのは、コンゴ民主共和国東部やマリ、ブルキナファソなどのサヘル地域です。特に、コンゴ民主共和国東部のタンタルやタングステン、金などの鉱物は、紛争との関連で注目されてきました。小規模な採掘が広範囲で行われ、武装勢力がこれらの鉱物を売る際に税金を課して、その資金を活動資金として利用する状況が、今日まで続いています。 参照:東京大学未来ビジョン研究センター紛 争鉱物取引規制への対応に関する 提⾔ 参照:武内進一「紛争ダイヤモンド」問題の力学-グローバル・イシュー化と議論の欠落-2000年代には紛争が終わり、2010年頃には鉱物の取引規制の制定により流通が規制されていたにも関わらず、紛争鉱物の問題が一部地域ではまだ続いているというのは、びっくりしました。まず、最初に世界的な注目を集めた紛争ダイヤモンドについては、UNDP※1などの国連機関やNGOが熱心に運動したこともあって、2000年代初頭には、キンバリー・プロセス※2というダイヤモンド流通に関する認証制度が整えられました。ダイヤモンドは採掘量が限られている上、供給チェーンの追跡が比較的容易であることから、最初にシステムが確立された経緯があります。しかし、ダイヤモンド以外の鉱物に関しては、状況がもっと複雑です。2010年にアメリカの国内法であるドッド・フランク法※3が成立してからは、鉱物の調達に関して、紛争鉱物でないかを確認する申告が必要となりました。アメリカの証券取引所に上場している大企業が遵守しなければいけないというインパクトは非常に大きく、日本企業にも影響が及び、紛争鉱物を使用しないよう取り組みが進んでいます。近年、紛争地域からの鉱物を使用していないことや、使用する鉱物の生産地を証明する認証書が必要となるなど、新たな仕組みが導入されました。しかし、この認証制度も、完璧には程遠いことが指摘されています。機械掘りの地域では、紛争鉱物かどうかや、きちんとした労働環境が保障されているかが比較的監視しやすいのですが、小規模な人力掘りの地域ではそうした監視はほとんど期待できません。一般に、人力掘りの労働環境はきわめて劣悪です。機械掘りと人力掘りの採掘地がしばしば接近しており、認証を受けた採掘地といっても、人力掘りの紛争地域から出た鉱物が混ざっていることもあります。また、紛争地域から鉱物を持ち込んで承認を受けた採掘地で販売するなど、不正行為も指摘されています。コンゴ民主共和国東部のように紛争の影響が広大な地域に及び、戦線が常に移動するような状況にあっては、鉱物採掘に関して正確な情報を把握することはきわめて困難です。紛争鉱物の存在は、それに依存して軍事資金を調達している勢力にとって、紛争を長引かせる動機となります。そうしたなか、小規模な採掘者が劣悪な労働環境で鉱物資源を採掘しているのです。鉱物資源は、我々の生活を様々な形で支えていますが、それはここまで述べてきたようなサプライチェーンの上に成り立っている場合もあるということです。 参照:国際連合開発計画 (United Nations Development Programme) 参照:経済産業省 ダイヤモンド原石の輸出入管理 参照:日本経済新聞 ドッド・フランク法とは紛争鉱物をなくすために、私たちができること紛争鉱物の問題に関して、我々消費者には何が出来るでしょうか?我々に製品を提供している企業は、紛争鉱物を使用しない製品を作ろうと努力しています。消費者も同様に、多くの人が紛争鉱物を使用した製品を避けようと意識していると思います。一方で、紛争鉱物ではないとされている製品でも、その実態はかなりグレーで、上流部分で起こっていることは私たちが想像している以上に複雑です。少なくともその事実を理解した上で、ではどうするのか、という問題意識を持つことが必要ではないかと思います。世界的に取り組まれている昨今の紛争鉱物の規制について、現状を教えてください。先ほどお話ししたキンバリー・プロセスやドット・フランク法など、鉱物資源のサプライチェーンをもっと整備しよう、認証システムをもっと精度の高いものにしようという努力は長年にわたってなされてきています。しかし、一方でアフリカの小規模採掘は広がり続け、劣悪な労働環境も拡大しています。小規模採掘に関しては、労働環境の整備への支援など、少しずつ取り組みが始まっています。これまでの調査や研究の中で、色々な現場に足を運び、資料に目を通してきたかと思います。何か印象に残るシーンはありましたか?なかなか立ち入れないので、直接見ることはできていないのですが、目を疑うような採掘現場の写真を多く目にしてきました。例えば、研究書の表紙に使われている写真は、コンゴ東部のルウォウォ(Luwowo)鉱山のもので、コルタン(タンタル)の小規模採掘の現場です。 参考:CHICAGO広大な場所に山のように人が群がり、地下深くまで掘るので、落盤事故も頻繁に起こります。こういった写真に示される状況が、コンゴ東部を筆頭に、西アフリカなどでも広がっているようです。紛争鉱物から脱却して、クリーンかつ持続可能な鉱物産業にしていくために、社会はどのように変わっていくべきなのでしょうか?まずは、紛争を止めることです。この問題は堂々巡りなのですが、先進国で鉱物資源への需要が高まれば、小規模採掘も拡大し、そこから武装勢力が資金を得る機会が生まれます。紛争が続く限り、そのサイクルは続きます。紛争鉱物問題の根本的な要因は武力紛争です。現在のアフリカでは、幾つかの理由から国内統治がうまくいかず、紛争が発生してしまうという状況があります。規制を導入しても、根本的な問題が解決されない限り、紛争鉱物が世界市場に流出する事態が続くので、国際社会として紛争解決に取り組むことが不可欠です。日本政府としても、真剣に取り組んでほしいと思います。我々一人一人にできることとしては、まずこうした事態を知ることが重要です。その上で、自分に近い分野、なじみのある分野で、世界とどのようにつながっているのかを意識することが大切だと思います。今日、世界は様々な形でつながっています。タンタルはスマートフォンに使われていますし、電気自動車に必要なコバルトは、世界生産量の大部分をコンゴが占めています。日常生活で消費する様々な品々が、どんなふうに世界とつながっているのか、そこには人々のどんな暮らしや労働が関わっているのか、意識してほしいと思います。負の側面だけではない、アフリカの魅力ありがとうございます。衝撃的な事実ですが、我々の生活と密接に結びついていて、目を逸らさずに向き合っていかなければいけないと感じます。最後に、読者の方にメッセージをお願いします。アフリカは様々な問題を抱えています。紛争鉱物もその一つですし、そもそも武力紛争は貧困やガバナンスの悪さなど、様々な問題が絡み合って起こります。しかし、同時に言えるのは、アフリカには非常に大きなポテンシャルがあるということです。人々は魅力的で、そこでの生活は楽しく、学ぶことも多いのです。アフリカを自分と関係のない、遠くて恐ろしい場所と捉えずに、その多様性や魅力に目を向けてほしいと思います。現地の実情や人々の暮らしを知ることから始めて、アフリカのことをもっと理解してほしいと強く感じています。 -
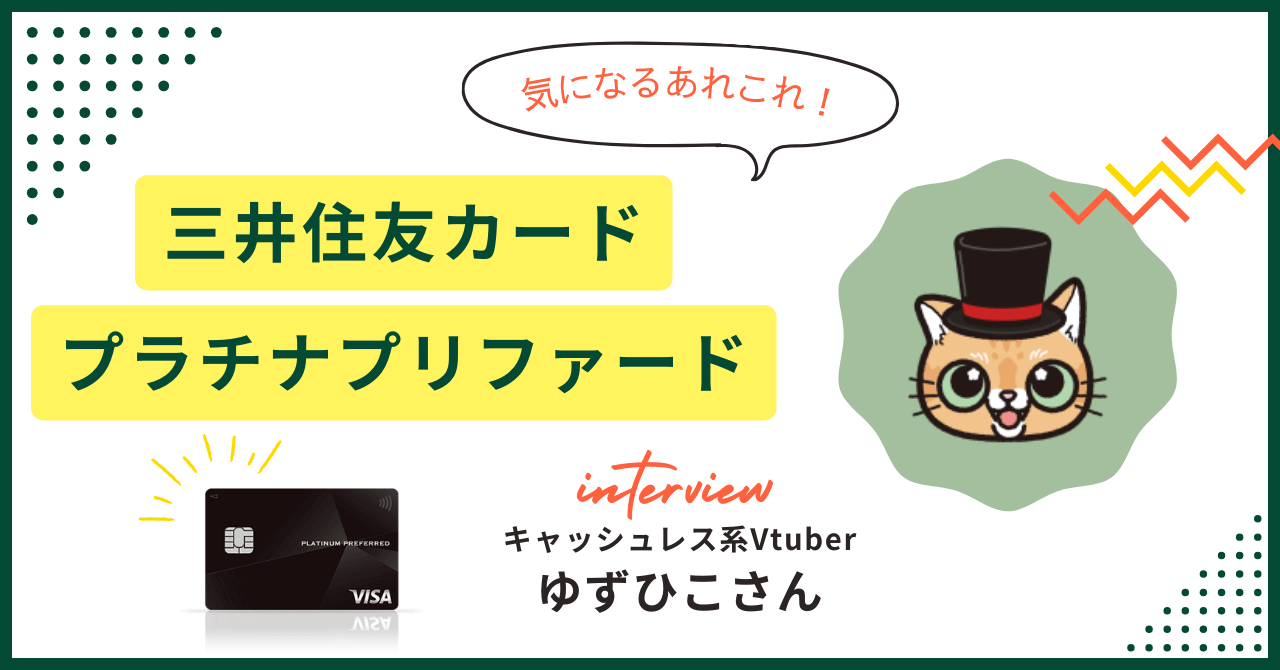
三井住友カード プラチナプリファードインタビュー!リアルな使い方を聞いてみた
ポイント特化型のプラチナカードとして名を馳せる「三井住友カード プラチナプリファード」。高いポイント還元率で有名ですが、年間33,000円(税込)の年会費がかかるため、申し込みに1歩踏み出せない方も多いようです。そこで、実際に三井住友カード プラチナプリファードを利用している人気のキャッシュレス系Vtube「ゆずひこさん」に実際の使い方やお得に利用する裏技をお伺いしました!「年会費がかかるけど、それ以上のメリットはあるの?」「そもそもどんな使い方をするといいの?」など、三井住友カード プラチナプリファードに関する疑問をお持ちの方は必見です。取材日:2024年3月21日三井住友カード プラチナプリファードとは?発行したきっかけ インタビュー時の様子三井住友カード プラチナプリファードの特徴や発行したきっかけを教えてください。三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント特化型のクレジットカードで、何よりあらゆる場面でポイント還元率が高いことが特徴のプラチナカードです。年会費は33,000円(税込)かかるのですが、自分の場合はそれ以上のメリットがあったので申し込みをしました。三井住友カード プラチナプリファードの基本情報 三井住友カード プラチナプリファード基本情報 クレジットカード券面 国際ブランド Visa クレジットカード年会費(税込) 33,000円 家族カード年会費(税込) 無料 ETCカード年会費(税込) 無料 ※初年度無料※前年度に一度もETCカードの利用がない場合550円(税込) クレジットカード総利用枠 〜500万円 ※所定の審査あり ポイント還元率 1〜15% ※プリファードストア(特約店)利用で通常還元率+1~14% 海外旅行傷害保険 最高5,000万円 ※利用付帯 国内旅行傷害保険 最高5,000万円 ※利用付帯 申し込み対象・入会条件 原則として、満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 出典:三井住友カードプラチナプリファード公式サイト 上記クレジットカード情報は2025年4月の情報です。特に、SBI証券での投資信託の積み立てでは5.0%の還元率で利用できる(※)(※2024年3月21日時点)ので、その部分のメリットが大きく申し込みをしましたね。それがなくても、基本還元率が1.0%と高還元率なので、日常的にもすごい使いやすいので。あとは、三井住友カード プラチナプリファードに限った話ではないですが、PayPayや楽天Payに紐づけることでクレジットカードが利用できない店舗でもキャッシュレスで支払いができるので、支払いはほぼ三井住友カード プラチナプリファードです。ポイント還元率がアップする店舗が多い点も日常使いにおすすめですね。 2024年9月10日(火)積立設定締切分(2024年10月1日(火)買付分)までのポイント付与。以降は対象カードごとのカードご利用金額などに応じたポイント付与率になります。 三井住友カードつみたて投資のご利用金額は、プラチナプリファードの新規入会&利用特典、継続特典の付与条件であるご利用金額の集計対象となりません。 クレカ積立上限は10万円三井住友カード プラチナプリファード以外に比較したカードはありますか?そうですね、100万円修行系のカードは結構持っていて、三井住友カード ゴールド(NL)やセゾンゴールドプレミアムなどの修行が終わったので、次どうしようかなと思った時に三井住友カード プラチナプリファードが次の候補になったんですよね。100万円以上の利用で毎年ボーナスポイントがもらえる点が魅力的でした。比較で言うと、同じ修行系のカードでイオンゴールドカードもあったのですが、正直私がイオン自体をあまり利用しないというのがありましたので、今回は三井住友カード プラチナプリファード1択で申し込みをしたという感じですね。ズバリ聞いてみた!三井住友カード プラチナプリファードの実際の使い方 2024年3月21日時点の情報です。三井住友カード プラチナプリファードは基本還元率が高い点が普段使いに嬉しいですね。その他、どのように三井住友カード プラチナプリファードを実際に利用されているんですか?SBI証券での積み立て投資でポイントを貯めるまずいちばんのメリットは、SBI証券での積み立て投資で5.0%付与※があることですね。これは、三井住友カード プラチナプリファードを利用するならマストの条件かもしれないです。 2024年9月10日(火)積立設定締切分(2024年10月1日(火)買付分)までのポイント付与。以降は対象カードごとのカードご利用金額などに応じたポイント付与率になります。 三井住友カードつみたて投資のご利用金額は、プラチナプリファードの新規入会&利用特典、継続特典の付与条件であるご利用金額の集計対象となりません。 クレカ積立上限は10万円今だと最大5万円までの積み立て分が5.0%還元になるので、私の場合は毎月5万円の積み立てをして毎月2,500ポイント※が貯まっています。 積立投資のポイント付与画面年会費は33,000円(税込)かかるけど、現状は積み立てだけで年間30,000ポイント※が戻ってくるし、その他の還元も考えると、正直超お得に利用できてますね。ただ、2024年3月からちょうど内閣府令が改正されて、クレカ積立の上限が10万円までできるようになったんですよね。ただ三井住友カード プラチナプリファードがこのまま10万円まで5%の還元率で積み立てできるかどうかは正直分からないのでどうなるか気になっているところですね。上限5万円まで5%だけでも超お得なので使う価値は高いですが。 クレカ積み立ての上限アップと還元率変更について 2024年4月10日積立設定締め切り分より、クレカ積立の上限金額が5万円から10万円に変更になりました。2024年9月10日積立設定締め切り分まではこれまでと同様に最大5.0%のポイントが貯まりますが、2024年10月10日積立設定締め切り分以降はカードの利用金額に応じたポイント付与率に改定予定です。詳しくは三井住友カードの公式サイトをご確認ください。外貨ショッピング利用時では3%のポイント還元率 引用:三井住友カード プラチナプリファード公式HPなるほど。ポイントが貯まりやすいので年会費のハードルがグッと下がりますね。積み立て以外の使い方ではどんなものがありますか?これも正直めっちゃいいと思っているんですけど、外貨ショッピング時の還元率ですね。要は海外で三井住友カード プラチナプリファードを利用した場合のポイント還元率なのですが、これが通常+2%で3%貯まるんです。3%!超高還元率ですね!そうなんです。ちょうど新婚旅行に行ってハワイで結構三井住友カード プラチナプリファードを使ったんですけど、今円安なのもあってポイントで戻ってくるのはありがたかったですね。 外貨決済時の実際のポイント付与画面外貨ショッピングで3%貯まるというのは、お得というよりは手数料がかからず決済できているという側面が大きいです。というのも、三井住友カード プラチナプリファードに限らずクレジットカードを海外で利用すると外貨決済の事務手数料がかかり、三井住友カード プラチナプリファードでは2.2%なんです。だけど、手数料分におつりがくるくらいのポイントが返ってくるので、実質無料で海外で利用できるのは大きいですね。特に私の場合は海外で利用する予定もあったので、迷わず三井住友カード プラチナプリファードに申し込みました。私も結構海外に行くのでこれはありがたいですね。ライフイベントや仕事の関係で海外が多い方には嬉しいですね。コンビニやファーストフードなどでの利用 引用:三井住友カード プラチナプリファード公式HPそうなんです。あとはこれは結構有名ですが、コンビニとかファーストフードとか、その他ドラッグストアとかスーパーとかにもポイントアップの対象店舗があって、基本対象店舗では三井住友カード プラチナプリファードの利用一択ですね。 特約店利用時の実際のポイント付与画面ただし、スマホのタッチ決済じゃないと最大還元率にならない場合もあるのでそこは注意が必要です。なので基本はスマホでタッチ決済してますね。こんな感じで、使っていると、積み立て投資を除いて年間100万円は利用できる計算で申し込んだんですよね。三井住友カード プラチナプリファードは、継続特典として年間100万円ごとの利用で最大で40,000ポイントももらえるし。そうなると、積み立て投資分で年間30,000ポイント※、全部1%の還元率として計算しても年間100万円で10,000ポイント、継続特典で10,000ポイントはももらえるのでそれだけで50,000ポイントはもらえる。となると年会費の33,000円(税込)は全然ペイできますよね。さらに初年度は期間中のキャンペーンの利用で40,000ポイントももらえるので申し込まない理由がなかったです。(笑)そんな感じでペイできる方なら使った方がいいと思いますね。 クレカ積み立ての上限アップと還元率変更について 2024年4月10日積立設定締め切り分より、クレカ積立の上限金額が5万円から10万円に変更になりました。2024年9月10日積立設定締め切り分まではこれまでと同様に最大5.0%のポイントが貯まりますが、2024年10月10日積立設定締め切り分以降はカードの利用金額に応じたポイント付与率に改定予定です。詳しくは三井住友カードの公式サイトをご確認ください。公共料金の支払いでも変わらず1.0%の還元率後は、電気料金など公共料金の支払いでも三井住友カード プラチナプリファードを利用していますね。楽天カードなど、クレジットカードによっては公共料金の支払いは還元率が下がるカードもある中で、三井住友カード プラチナプリファードは変わらず1.0%なのがいいですよね。楽天カードは、こういった一部の還元率ダウンなどの改悪も続いているのでそういった点でも三井住友カード プラチナプリファードは推せますね。ちょっと私も今すぐ私も三井住友カード プラチナプリファード申し込んできます(笑) 即時発行なら最短10秒! 三井住友カード プラチナプリファード 公式サイトはこちら ※即時発行ができない場合があります。貯めたポイントのお得な使いみち4選と、言いたいところですが、では貯まったポイントどうするのという部分もお伺いしたいです!Tポイントに交換して毎月20日のウェル活で使うぜひぜひこの後申し込んでください(笑)貯まったポイントは個人的に3つの使い方をしています。1つはTポイントに交換をして使ってますね。そのTポイントを、いわゆる「ウェル活」で使ってます。毎月20日のお客様感謝デーだとTポイント1ポイントが1.5円分として使えるんですよ。まさに昨日ウェル活してきたんですけど、例えば1,000ポイントが1,500円分で利用できるので、日用品などはその日にまとめて買ってます。買っていると言ってもポイントなのでただですけどね(笑)ウェル活超魅力的です・・・しかもVポイントとTポイント統合しますね! 公式HPよりそうなんですよ。これまで通りウェル活で利用できるみたいで、さらに使い勝手が良くなりそうなので嬉しいですね。SBI証券のポイント投資2つ目のポイントの使い方も教えてください!2つ目は、SBI証券でのポイント投資に使っています。1ポイント1円分として利用できるので投資信託の購入などに利用してます。ポイントで気軽に運用できるのは魅力ですね。投資初心者で試してみたい方とかにも、ポイントで気軽に投資できるのはよさそうですね。支払いに充当してポイントを使うそうですね。あとは単純にカード支払いにポイントが使えるのでそれで利用したりもします。なので私の場合はTポイントに交換してウェル活、ポイント投資、支払いの充当の3つで時と場合によって使い分けて利用してますね。使い道豊富ですね。では、実質還元率でいくとTポイントに交換してウェル活がいちばんお得ですかね?秘伝のポイント交換先とは。最強のポイント交換先 私の場合ではウェル活がいちばんお得にはなるんですが、実はもっと還元率が高いポイント交換先があります。今すぐ教えてもらっていいですか?はい(笑)ちょっと住んでいる場所とかによって全員使い勝手がいい訳ではないんですけど、ソラシドエアへのマイル交換が個人的にはいいと思います。1ポイント=2マイルとして交換できて、このレートは正直すごいお得だと思います。例えば、シーズンによって必要マイル数は変わるんですが、東京(羽田)⇔沖縄(那覇)だとレギュラーシーズンで往復で13,000マイルで行けるんですよね。となると必要なVポイントは6,500ポイントだけなんですよ。 引用:ソラシドエア公式HP初年度はキャンペーンもあるので、100,000ポイントは貯められそうだと考えると、もう沖縄行き放題って感じです。なんと・・・!これは超お得な使い方ですね。そうなんです。ただ行き際などは限られていたりもするので、対象になっている地域は事前に確認しておいた方が良いです。あとは結構人気で予約取りずらい可能性もありますね。ソラシドエアのマイル交換には、Solaseed Airカードの入会も必要になります。初年度無料で2年目以降も1,375円 (税込)なので、年会費かかるとはいえそれでもお得なので使える人はこの使い方がおすすめです。 即時発行なら最短10秒! 三井住友カード プラチナプリファード 公式サイトはこちら ※即時発行ができない場合があります。実は…三井住友カード プラチナプリファードにはこんないいところも!注意点も紹介もう申し込まない理由がないくらいの感情になっています(笑)その他三井住友カード プラチナプリファードの使い方とか注意点とかありますか?交通系ICや電子マネーへのチャージはポイント対象外!この裏技がおすすめそうですね、1つ注意点は交通系ICや電子マネーへのチャージはポイント対象外という点ですね。私はよく交通系を利用するのですが、まずプリペイドカードにチャージしてから交通系ICにチャージをしています。実際使っているのは「MIXI M」というサービスのプリペイドカードを利用していて、まずそこに三井住友カード プラチナプリファードを紐づけてチャージします。そのあとMIXI Mからsuicaなどの交通系ICにチャージしていますね。 引用:MIXI M公式HP三井住友カード プラチナプリファードから直接交通系ICへのチャージはポイント対象外ですが、MIXI Mなどのプリペイドカードを間に入れることで、手間はかかりますが1.0%還元でポイントが貯められるので私はそうしています。なるほど!もう1ステップ挟むことでメリットがデメリットではなくなるんですね。そうなんです。よく交通系ICを利用する方はこのやり方がおすすめです。継続特典はつみたて投資分は集計対象外その他の注意点としては、SBI証券でのつみたて投資分は、継続特典の集計対象外になることですかね。なので年間100万円の利用で10,000ポイントが継続特典としてもらえますが、その100万円につみたて投資分は入らないです。それをふまえて利用するかどうか、判断するのがいいと思います。ありがとうございます!家族カードで夫婦で利用していくなどの場合は、結構クレカの利用金額大きくはなりそうですよね。そうですね。ちなみに三井住友カード プラチナプリファードは家族カードが無料なんですよ。プラチナカードだと家族カードでも数万円の年会費がかかることもあるので、家族カードを発行して夫婦で利用などができるとハードルもグッと下がりますね。USJのチケットもお得に手に入る!あとは、USJのチケットも日によってはお得にポイント交換ができますね。通常混雑状況などによってチケット代金が変わって高いと大人税込で10,900円ほどするところ、Vポイントが8,500ポイントで交換できるんです。 引用:USJ公式サイト特に金曜日や土曜日が高い傾向があるので、ポイントで交換してチケットをゲットするのもおすすめです。所得税などの国税支払いの裏技あとはこれも三井住友カード プラチナプリファードに限らずではあるのですが、特に個人でやっている人などは所得税を自分で払うじゃないですか。クレカ払いもできるんですけど、金額に応じて手数料がかかるんですよね。実は「スマホアプリ納付」というのもできて、その場合は手数料がかからず納付ができるんです。なので私はAmazonギフト券を三井住友カード プラチナプリファードで購入して1.0%分のポイントをゲットしながら、実際の税金支払いはAmazonPayで支払いしてます。ただし納付金額が30万円を超える場合はスマホアプリ納付が利用できないのでそこは注意が必要です。三井住友カード プラチナプリファードに関していろいろ教えていただきありがとうございます!その他、カードの使い分けなどもしていますか?三井住友カード プラチナプリファードと他のカードとの使い分けはい。メインはプラチナプリファードなのですが、そのほかに2枚カードを利用しています。1枚目が、「JQ CARDセゾンGOLD」です。このカードのいいところはいろいろありますが、ファミリーマートでの決済で使っています。特約店にファミリーマートが入っているのでポイントが5倍で貯まります。三井住友カード プラチナプリファードはメインどころのコンビニでファミリーマートだけポイントアップの対象外なので使い分けをしています。JQ CARDセゾンGOLDは初年度年会費はかかりますが、年間50万以上のご利用で次年度以降年会費永年無料です。私の場合は一般カードのJQ CARDセゾンというカードを使っていて、インビテーションが来たので無料でJQ CARDセゾンGOLDにアップグレードできました。2枚目は、「SAISON GOLD Premium」。こちらも年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費が永年無料で使えます。このカードは主に映画専用で使っていますね。主要な映画館で映画チケットが1,000円になるので。よく映画を観る方にはおすすめできるカードですね。 即時発行なら最短10秒! 三井住友カード プラチナプリファード 公式サイトはこちら YouTube登録者数10万人突破!ゆずひこさんの活動スタンスを聞いてみた本日は、なにからなにまで教えていただきありがとうございます!YouTubeやXなどを拝見させていただき、情報の速さやユーザーに寄り添った発信をされている点が印象的でした。普段どんな想いで発信をされているのですか?大前提として、観てくださっている「お客さんが勝つこと」ですね。観ていただいているかたが困っていることとか損していることとかを、私が実際に体験をしながら具体的に説明することで理解してもらって喜んでもらうことがすごい嬉しいんです。喜んでもらうことはもちろん、今よりもいい経験や得をしてもらうことでファンがついてくるのかなと思いますね。やっぱり自分が儲けたいというのをいちばんに考えたら、もっと他の方法もあるかもしれないですけど、自分だけ得するようなことってあまり長く続けられることでもないのかなと思っています。弊社のメディア「HonNe」もまさにユーザーファーストを大事にしているメディアなので、本日はゆずひこさんにインタビューさせていただき貴重なお話をお伺いできて大変光栄です!ありがとうございました。 当ページ利用上のご注意 当記事の掲載情報は、各金融機関の公開情報を元に作成しておりますが、情報更新等により閲覧時点で最新情報と異なる場合があり、正確性を保証するものではありません。各種商品の最新情報やキャンペーンについての詳細は公式サイトをご確認ください。 当記事で掲載しているポイント還元率は公式サイト情報を元に独自に算出しています。より正確な情報は各カード会社の公式サイトをご確認ください。 -

ウォーターサーバーの導入でSDGsに取り組んでいる大学10選
持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みは、教育機関においても重要なテーマとなっています。特に、プラスチックごみの削減に向けた取り組みとして注目されるのが、ウォーターサーバーの導入です。本記事では、ウォーターサーバーを活用し、SDGs達成に貢献している日本の大学10校を紹介します。これらの大学は、環境への影響を軽減するための施策としてウォーターサーバーを導入し、学生や教職員の意識向上を図りながら、持続可能なキャンパス環境の実現に取り組む先進的な大学です。プラスチックボトルの使用削減からSDGs達成に貢献するこれらの大学の取り組みを紹介し、その効果と今後の展望について探ります。プラスチックごみが環境に与える影響 日常生活のさまざまな場面で使用するプラスチックですが、このプラスチックごみが環境に大きな影響を与えています。現在深刻化しているのが、海洋プラスチックごみ問題。世界中の海に存在しているプラスチックごみは、合計で1億5,000万トン(※)あると言われています。 (出典:McKinsey & Company and Ocean Conservancy)50年後には魚よりプラスチックごみの方が多くなると言われ、生態系に悪影響を及ぼしているのが現状です。例えば、海洋生物が誤ってプラスチックごみを食べてしまったり、水質汚染によって、サンゴの成長を妨げたりすることで、生態系のバランスを崩す原因となります。海洋ごみの約7割は街で排出されたものと言われているため、プラスチックごみ問題は私たちが責任を持って解決しなくてはいけない問題なのです。ウォーターサーバーの導入はSDGsにどう貢献するのかプラスチックごみ問題を解決する方法の1つが、ペットボトルの削減です。ウォーターサーバーを導入することで、ペットボトルの購入頻度が減るため、プラスチックごみの削減に貢献できます。それでは、ウォーターサーバーの導入がSDGsにどう貢献するのか、解説していきます。安全で清潔な飲料水を提供するウォーターサーバーは、安全で清潔な飲料水を提供し、これは目標6「清潔な水と衛生」に貢献します。これにより、水質問題に直面している地域の人々に健康的な生活環境を提供し、公衆衛生の向上に貢献します。日本はすでに清潔で安全な水が供給されている国の1つですが、日本は地震や台風などの自然災害が頻発する国です。災害時には水の供給が途絶えることがあるため、非常時における清潔な水の確保は、公衆衛生の維持に貢献します。ペットボトルの生産や輸送エネルギーの削減SDGsの目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」は、全ての人々に手頃な価格で信頼性の高い、持続可能で現代的なエネルギーサービスを提供することを目指しています。ペットボトルの生産、輸送、冷却に必要なエネルギーは意外に大きく、ウォーターサーバーによる代替は全体的なエネルギー消費を減少させます。環境省によると、500mlのペットボトルを購入した場合と、マイボトル(5年間で700回利用と仮定)を使用した場合の1回あたりのCO2の排出量を比べたところ、ペットボトルと比べてマイボトルは約1/4の排出量(※)であることがわかりました。 (出典:リユース可能な飲料容器およびマイカップ・マイボトルの使用に係る環境負荷分析について)地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らせるため、ウォーターサーバーの導入は、目標13「気候変動に具体的な対策を」にも貢献できます。プラスチック廃棄物の削減ウォーターサーバーは、ペットボトルの使用を減少させることでプラスチック廃棄物を削減し、持続可能な消費パターンを促進します。この取り組みは、資源の有効利用と環境保護に直接貢献し、目標12「責任ある消費と生産」の実現に向けた重要なステップです。清潔な水の確保、エネルギー効率の向上、そしてペットボトルの使用減少は、持続可能な未来への重要な一歩です。大学のような規模の大きな施設が、ウォーターサーバーの導入に取り組むことで、より広範な持続可能性への意識改革に繋がることでしょう。ウォーターサーバーの導入でSDGsに取り組む大学10選ここからは、ウォーターサーバーの導入により、SDGsに貢献している先進的な大学を紹介します。京都大学 出典:https://www.kyoto-u.ac.jp/ja京都大学は、持続可能なキャンパス(サステイナブルキャンパス)の実現を目指し、学生と教職員の有志が「エコ~るど京大」を発足。京都大学のSDGsに関する取り組みについて、インタビューを実施しました。ウォーターサーバー導入は、キャンパス内のペットボトルのごみを減らしたいという思いがきっかけとのこと。2022年までに9台のウォーターサーバーが設置され、構内の学生の利用頻度が多い場所や研究室などに設置されました。この取り組みにより、学内全体で見ると毎月6,000本分(500ml換算)のペットボトル削減が達成され、SDGsに大いに貢献しています。学生からの反応は非常に良く、一方で管理側は費用や衛生面の管理に一定の課題を抱えているようです。さらに京都大学では、大学生や教員だけでなく、地域住民や企業も巻き込みながらSDGsについてのさまざまな企画を行っています。例えば、マイボトルの普及活動やSDGs弁当の販売、YouTubeでのマイボトルダンスの配信を通じ、学内外にサステナビリティのメッセージを広めることに注力しています。京都大学のこの取り組みは、他の大学にも影響を与え、京都薬科大学などがウォーターサーバーの導入を行うきっかけとなりました。これらの活動は、教育機関がSDGsにどのように貢献できるかの素晴らしい例です。 大学コメント 京都大学|エコ~るど京大 ウォーターサーバーはペットボトルの削減などでSDGsに貢献できる反面、設置や管理の手間が生じます。そのため、「ウォーターサーバーを設置したい」という学生からの強い声が重要になってきます。ウォーターサーバーの導入を検討している大学は、施設との調整や安全面の管理を徹底的に行うことが大切です。 上智大学 出典:https://www.sophia.ac.jp/jpn/上智大学はSDGsに関しての情報発信や企画実施などの取り組みを行う「サステナビリティ推進本部」を設置し、SDGsへの積極的な貢献を示しています。ウォーターサーバーの導入も取り組みの一部で、学生、教職員が一丸となって活躍中。上智大学のSDGsに関する取り組みについて、インタビューを実施しました。ウォーターサーバー導入当初は、コロナ禍で多くの学生が登校していなかった影響もあり、なかなか存在を認知されずに悩んでいたそうです。そこで、学生のアクセスが多い場所へサーバーを設置することや、少数色覚者にも見やすいようなマップを作成するなど、ウォーターサーバーを多くの学生に利用されるようなさまざまな工夫を凝らしました。その結果、今では多くの学生に認知され、授業の合間にはウォーターサーバーを利用するための行列ができるほどに。マイボトルの持参率も増え、ペットボトルの削減に大きく貢献しているため、企画に参加した学生職員もやりがいを感じているとのことです。上智大学は、ウォーターサーバーの導入に留まらず、マイ容器の持参を促すキッチンカーでの食事サービスや、ごみの分別を促進するためのごみ箱デザインの改善など、学生がSDGsに貢献するための具体的な取り組みを実施しています。これらの取り組みは、SDGsに関心がない学生でも参加しやすいように設計されており、誰でもSDGsに貢献できるような画期的なアイデアです。このような取り組みは、学生目線で考えられた実践的なアプローチにより、持続可能な未来への貢献だけでなく、学生コミュニティ内での環境意識の向上にも大きく寄与しています。 大学コメント 上智大学|サステナビリティ推進本部 ウォーターサーバーの導入に限らず、何か学生のアイデアで革新を起こしたい場合、残念ながらその声はなかなか教職員まで届きません。そのため、私たちサステナビリティ推進本部のような、学生の声を拾い上げ、議題にあげることができる機関を設置することが重要です。学生職員を採用することで、学生と教職員の橋渡しとなる存在ができ、より良い大学作りに貢献してくれています。 立命館大学 出典:https://www.ritsumei.ac.jp/立命館大学は2019年4月に「立命館SDGs推進本部」を設置し、持続可能な未来に向けて、教育研究機関として幅広い取り組みを学生とともに進めています。立命館大学では、今までも冷水器を設置していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、不特定多数が利用する冷水器の代替機を検討していました。そこで、ウォーターサーバーを設置することで、感染拡大を防止するだけでなく、マイボトルの普及でプラスチックごみの削減を目指しています。学園として、各キャンパスにおいて毎年前年比3%のゴミ削減の実施が決定したことがきっかけで、びわこ・くさつキャンパス(BKC)では2022年9月にウォーターサーバを導入。キャンパス内には合計18台のウォーターサーバが設置されています。学生の満足度も上がり、多い月で80,000L~90,000Lの水を使用しているそうです。学生からの要望もあり、次年度に向けて2台程度の増設を検討中とのこと。立命館大学では、その他にもゴミの排出抑制策として、業務のDX化推進による紙の消費抑制、食品ロスの削減に向けた啓発活動、食品廃棄物の分解処理を実施。地球環境委員会やSDGs推進本部の立ち上げなど、SDGsへの取り組みとして様々な取り組みを行っています。日本大学 出典:https://www.nihon-u.ac.jp/日本大学では、学生が主体となって行動し、各ゼミでの活動やワークショップ型授業、プロジェクトを通して、SDGsの実現に取り組んでいます。コロナ禍を乗り越えキャンパス回帰した学生達へ、熱中症対策という目的と、綺麗で美味しい水をオールシーズンキャンパス内各所でお届けしたいという保護者組織の後援会からのアイデアと支援もあり、2023年7月にウォーターサーバを設置しました。学内5ヶ所にウォーターサーバが設置されており、学生・教職員共に好評でスムーズに利用されているとのこと。日本大学 文理学部ではスポーツ系の学問領域も盛んであることから、特に猛暑時の体育授業や課外活動時に需要が高まっています。学生の中にはマイプロテインをシェイカーで用意し、体作りに励む方もいらっしゃるそうです。慶應義塾大学 出典:https://www.keio.ac.jp/ja/慶應義塾大学は、教職員・学生・生徒・児童が、互いの人格を尊重し多様な価値観を認め協力して生きるための環境を構築し、多様性の受容に関する課題に迅速に対処するため、2018年4月1日に「協生環境推進室」を設置しました。「地球環境との”協生”」をテーマに、「2030年までに、ウォーターサーバーをキャンパス内の全ての施設に設置する」ことを目標に掲げています。目標を達成するために、スタンプラリーの企画を実施。ウォーターサーバーの設置後も、全校生徒にマイボトルの推進活動を積極的に行っています。東北大学 出典:https://www.tohoku.ac.jp/japanese/東北大学は、2019年3月に「プラスチック・スマート」(※)の推進を宣言しました。 (※出典:プラスチック・スマート公式ページ)プラスチック・スマートとは、環境省が実施している、海洋プラスチックごみの削減に向けたキャンペーンの名称のこと。東北大学では、主要会議室にウォーターサーバーを設置し、マイボトルの持参を推進することで、ペットボトルごみの削減に貢献しています。明治大学 出典:https://www.meiji.ac.jp/明治大学は教育と社会貢献のカテゴリーにおいて、英語のクラスで「アイデアから行動へ」プロジェクトを実施し、その一環としてウォーターサーバーの利用を奨励するプロジェクトが進行しています。このプロジェクトでは、生徒たちが泉キャンパスにウォーターサーバーを使用するよう他の生徒を促すためのポスターを作成し、キャンパス内の5か所に設置しました。立教大学 出典:https://www.rikkyo.ac.jp/立教大学は2022年2月にカーボンニュートラル宣言を公表し、「キャンパスのカーボンニュートラル化」を目指しています。その取り組みの一環として、同年11月に、池袋・新座両キャンパスに1台、ウォーターサーバーを設置しました。立教大学は、「トップグローバル大学プロジェクト」の一環として、環境汚染、難民危機、経済的不平等などの深刻なグローバルな課題に取り組む能力を持つ、自由教養知識とスキルを備えたグローバル志向の個人を育成することを目指しています。青山学院大学 出典:https://www.aoyama.ac.jp/青山学院大学は、2023年4月より、学生サービス向上と安全衛生面の観点及び本学におけるSDGs推進活動の一環として、学内のペットボトル削減と学生生活をより快適に整えることを目的に、学内にマイボトル利用式ウォーターサーバーを設置しました。青山学院大学は、教育を通じての取り組みが顕著で、大学全体の教育目標に「愛と奉仕の精神を持って、すべての人と社会に対する責任を果たす人間の形成」を掲げています。この目標は、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念と一致しています。大学は、キリスト教の信仰に基づいた教育を提供し、より良い世界の実現を目指しています。青山学院大学は「青山学院グローバルウィーク(AGGW)」というイベントを通じて、SDGsに関連する活動やプロジェクトを紹介し、学生、教職員、卒業生を含めたコミュニティ全体でSDGsの達成に向けた取り組みを促進しています。このイベントでは、多様な活動やセミナーが実施され、参加者に持続可能性についての理解を深める機会を提供しています。東京農工大学 出典:https://www.tuat.ac.jp/東京農工大学は、2019年8月に「農工大プラスチック削減5Rキャンパス」活動を宣言し、2050年石油ベースプラスチックゼロに向けて、使い捨てプラスチックの削減と、課題解決のための新素材の創生等を含めた研究の推進に取り組んでいます。活動宣言に基づいて、マイボトル用のウォーターサーバーをキャンパス内に設置し、プラスチック削減対策を行っています。以上、ウォーターサーバーの導入でSDGsに取り組んでいる大学を紹介しました。ウォーターサーバーについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考下さい。 関連記事 おすすめウォーターサーバーは、こちらの記事で紹介しています。 -
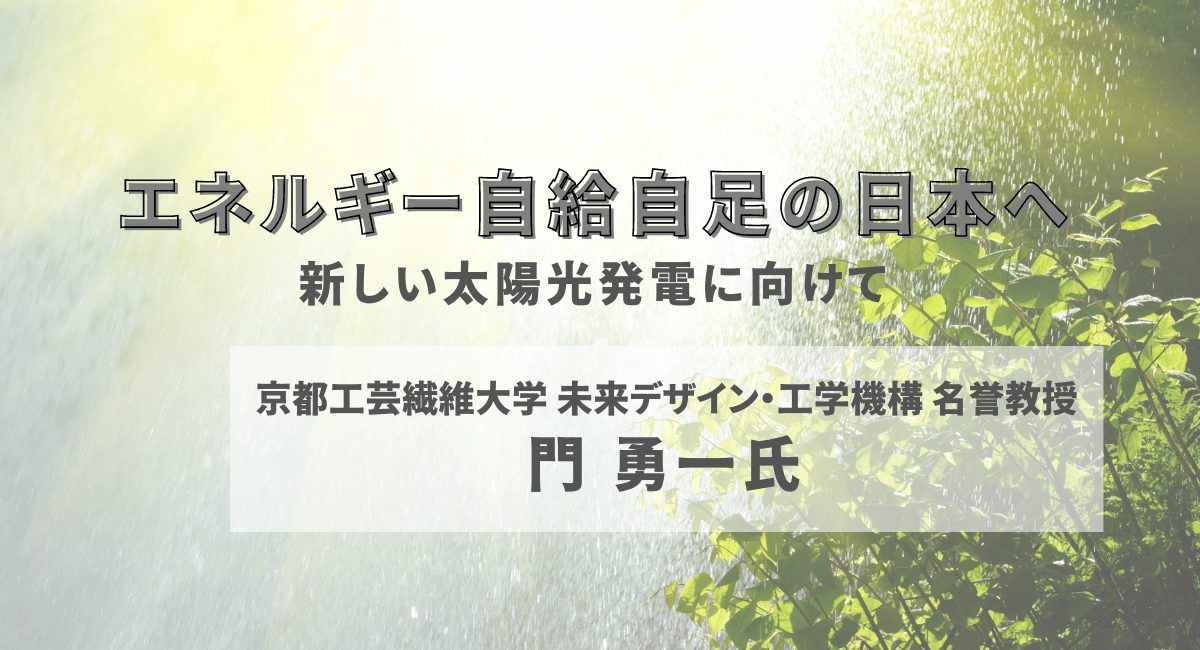
エネルギー自給自足の日本へ: 門勇一教授が実現する新しい太陽光発電
2023年に起きた電気料金の高騰は、日本全体をネガティブな空気に包み込んだ。当たり前に使っていたものに生活がおびやかされ、将来へ不安を感じた人も多いだろう。電気料金の高騰に対応するため、私たちができることの一つに太陽光発電がある。太陽光発電は、自宅の屋根に設置をしておくだけで、電力会社からの供給とは別に電気を使用できる「再生可能エネルギー源」だ。しかし、個人が太陽光発電の導入をすることに、ほとんどの人が一歩踏み出せないのが現状である。設置コストの高さだけでなく、下落を続ける売電価格の影響で、個人だけでなく事業者も導入へのリスクを感じてしまうためだ。今回紹介する京都工芸繊維大学・門勇一名誉教授は、太陽光発電システムを世の中に普及させるため、低コスト化の実現に向けた共同研究を企業と進めている。高コストで電力損失を伴う制御器をシステムから排除して、太陽光パネルと蓄電池を直接接続すれば、蓄電効率が飛躍的にアップし、経済的メリットのある再生可能エネルギーの実現が可能だ。今回は、太陽光発電の可能性を探求し、電力のあり方にゲームチェンジを起こす活動をする門名誉教授に、従来の太陽光発電システムの問題や解決策、再生可能エネルギーが普及した未来についてのお話を伺った。京都工芸繊維大学・門勇一名誉教授が研究する新しい太陽光発電システムはじめに、研究概要を教えてください。現在は、再生可能エネルギーに焦点をあてており、なかでも太陽光発電システムに関する研究がメインです。特に、太陽光パネルと蓄電池を直接接続する方法と、蓄電池に蓄えられた直流電力を交流に変えずに、直流電力のまま近隣でシェアする研究に力を入れています。従来、400Vで5 kW以上の発電をする太陽光パネルと蓄電池を直接接続する事はできませんでした。直接接続出来れば蓄電効率の飛躍的な改善が可能です。また、太陽光パネルで貯めた直流電力を、地産地消で地域でシェアする研究も続けています。具体的には、直流電力を地域でシェアするため直流電力ネットワークを構築します。そのネットワークを構成する「電力ルータ(直流電力分配装置)」の研究開発を進めています。従来の太陽光発電システムのコスト問題を解決し、低コストで高効率な太陽光発電システムが普及すれば、直流電力ネットワークを通して地域で電気をシェアできる世の中が実現可能です。このネットワークは電気自動車(EV)との接続で、シナジー効果が期待され、災害による停電時にはEVの電気エネルギーを活用できます。ありがとうございます。再生可能エネルギーの大量導入をするべきと思った背景を教えてください。これからの日本は、再生可能エネルギーを大量導入して、エネルギーの自給自足をする必要があると感じているためです。エネルギーの自給自足とは、自らのまちで電気をつくり、地産地消で生活ができることを意味します。日本の電力事情を紐解いてみると、火力発電への依存度が約76%(2020年実績)と高く、その燃料には天然ガス、石炭、等が主に使われています。この天然ガスの価格は原油価格に連動しているため、国際紛争等が原因で原油価格が上がると天然ガス価格も上がり、電気料金が高騰しているわけです。こうして、エネルギー源を海外に大きく依存したままだと、世界的な感染症や国際紛争などで日本が孤立した場合、電力をまかないきれなくなることが想像できます。海外に頼っている現状から脱するためにも、日本は再生可能エネルギーを大量導入し、自給自足で電力を作れるようにしなければなりません。実は、日本は再生可能エネルギーの自給自足に向いている国なんです。たとえば、火山大国である性質上、日本は世界第3位の豊富な地熱資源量を持っており、地熱発電のポテンシャルが非常に高い国です。ほか、海に囲まれているため、海上に風車を設置する「洋上風力発電」にも適した国土をもっているんですよね。これらの再生可能エネルギーに加え、大量導入しやすい太陽光発電の研究が進めば、海外に頼らず電力供給ができる未来が待っているはずです。現在の太陽光発電の問題は、導入コストの高さと、売電価格の下落従来の太陽光発電には、どのような問題があるのでしょうか?現状の太陽光発電システムのままでは、発電電力の効率的な蓄電と配電ができておらず、導入・運用コストと見合っていないことが問題です。太陽光パネルが発電した電力を蓄電するには、太陽光パネルと蓄電池の電圧をマッチングさせ、蓄電池が過充電にならないように「DC/DC変換器」等で充電制御をする必要があります。しかし、電気がDC/DC変換器を通るたび、電力ロスが発生します太陽光で発電した電力を蓄電池に貯めて、ユーザに電力を提供するにはDC/DC変換器を2回経由する必要があります。1回通るたびに電力ロスが5%程度おきるため、合計で10%程度の損失が起きてしまっているんです。しかも、直流電力を交流に変換してユーザに提供する場合は更に5%以上の損失が生じ、トータルの損失は20%程度に増えてしまいます。なるほど。太陽光パネル以外にも、太陽光発電に関連して障壁となっているものはありますか?事業者が参入できないほど、売電価格が下がってしまっていることが挙げられます。2010年は、1kWあたり48円で電力の売電ができていましたが、2023年は16円まで下がってしまっているのが現状です。事業者が太陽光発電で利益を得ようとすると、大規模な太陽光パネルを作る必要があり、設備コストが発生しますし、電力会社に売電するため交流への変換設備や接続ポイントまでの電線敷設コストが加わります。売電価格が16円まで下がってしまった現在では、利益を得るのが難しくなっているんですよね。本来の太陽光発電は、家庭用から事業用までさまざまなスケールが可能で、コスト的にも参入しやすいものなんです。実際に、世界を見渡してみると、太陽光パネルによる発電量は右肩上がりになっています。しかし、売電価格の下落が続く現状では、事業者の参入が難しい状態なんです。一方で、電力会社から購入する電気の料金は高騰しています。売電せずに、自ら使うべきなんです。交流から直流接続にシフトすれば、太陽光発電の普及が見えてくる。太陽光発電の問題を解決し、自給自足のエネルギーとして活用するためには、どのような対策が必要なのでしょうか?太陽光発電システムから電力ロスを伴うDC/DC変換器やパワーコンディショナーを排除して、発電した電力を効率的に蓄電池に貯めます。次に、交流に変換することなく直流電力として地域でシェアリングすることが大切です。将来、地方ではEVが地域の足となり、直流電力の給電が必要となりますが、EVの普及とシナジー効果を期待できます。先ず、太陽光パネルと蓄電池を直接つなぐ仕組みをつくり、発電した直流電力を蓄電池に高効率で貯めます。従来の太陽光発電システムからDC/DC変換器等を排除して、太陽光パネルと蓄電池を直接つなぐと、1システムにつき全損失が5%以下で済むことが分っているんです。更に、直流電力を交流電力に変換する時に、5%以上の電力損失が生じて、従来システムではトータルで20%程度のロスが生じます。直流電力のままネットワークで地域に配電する方法が有効です。直流電力を効率的に配電するには地産地消型の「直流マイクログリッド」と呼ばれる電力ネットワークが、直流社会へのシフトにおいて重要なインフラとなっていきます。直流マイクログリッドは、複数の太陽光パネルや複数の蓄電池が接続され、更にEVやLED照明等の電力を消費する負荷が接続された直流のネットワークですね。将来は直流家電も増えていくと考えています。今の白物家電は交流を直流に変換し、更に、直流を交流に変換してモーターを駆動しています。2回ロスが入ります。直流給電であれば、交流への変換だけで済むのでロスが減るからです。このネットワークの重要性は、EVの普及とも関係しています。EV市場の予測を見ると、EVが占める自動車販売市場における割合は、2035年に6割を占めると言われています。EVは動く蓄電池なので直流マイクログリッドに繋がれると、マイクログリッドから充電されますが、逆にEVがもつ直流電力をマイクログリッドに給電できます。例えば、太陽光による発電電力が不足した時や、災害による停電時は、マイクログリッドを介して、複数のEVから地域の家庭に電気を送ることが可能です。このような電気の使い方が現在の交流システムと共存し、将来は主流となることが予想されます。太陽光パネルと蓄電池を直接つなぐ発電システムとマイクログリッドが導入されると電力の損失が減り、エネルギーの単価が下がるとも言いえます。つまり、電気料金が安くなるのと同じ意味なんですよね。さらに、地域で直流を使う技術が確立すれば、ネットワークを介して、地域で電気をシェアリングするインフラを整備できます。電気のシェアリングとは、各家庭に蓄電池と「電力ルータ」を設置し、余った電力をシェアリングする仕組みです。このシェアリング方法が実現すると、電気エネルギーの単価が原油価格に直接依存せずに下がり、高騰している電力会社に支払う電気料金よりも安くなります。つまり、太陽光パネルと蓄電池が直接つなげられるようになれば、太陽光発電の大量導入も現実味を帯びてくるのです。電気料金が安くなる以外に、私たち消費者が感じやすいメリットはありますか?太陽光発電の運用でネックとなりがちな、メンテナンスの手間とその費用が改善されます。既存システムでは太陽光パネルと蓄電池の間に「DC/DC変換器」や「パワーコンディショナー」が入っており、これらを構成する電解コンデンサ等の部品の寿命は、長くても15年程度しかもちません。我々、消費者からすると、太陽光発電システムを導入したら、20~30年は動作し続けて、長くノーメンテナンスであって欲しいですよね。提案システムの様に、高コストでロスを発生するDC/DC変換器を排除すると、20~30年程度はメンテナンス不要で動き続けることが期待されます。また、直流ネットワークの仕組みを使った電気シェアリングが普及していくと、動くエネルギーバンクとも言えるEVを活用して、災害による大規模停電にも対応できるようになります。電力会社からの供給が止まっても、太陽光発電等の再生可能エネルギー源を使い電気を発電し、近隣とシェアしながら使っていく、地産地消型の世の中が実現できます。未来への不安をなくすためにも、再生可能エネルギーの大量導入が必要再生可能エネルギーの大量導入が実現すると、将来的にどのようなことがおきるのでしょうか枯渇する資源を使う火力発電所や、地震のリスクを伴う原子力発電がなくなり、エネルギーの民主化が起きて、真に持続可能なエネルギーシステムが実現すると考えられます。エネルギーの民主化とは、再生可能エネルギーが浸透し、誰もが電力の発電とその取引に参加できる社会状況のことです。これまでの日本は、エネルギーの供給における自主性と平等性がありませんでした。たとえば、原子力発電所が近くにある地域に住む人は、リスクを背負いながら生活をしているといえますよね。誰のための発電なのか?と言う問題意識が益々強くなっていくと思います。再生可能エネルギーの大量導入が成功すれば、誰もが自分と地域のために発電をし、地域へ電力を分け合うような仕組みが実現できます。また、今後普及していく地域の足としてのEVともマッチし、地域の人々がエネルギーとモビリティで繋がり、地産地消型のまちづくりが可能です。おもしろいですね…汎用性が高い印象を受けました!そうですね!太陽光パネルと蓄電池の直接接続は、パーソナルユースが可能なんですよね。例えばパーソナルユースの例では、カーポート型の太陽光発電システムなどがあります。EVをカーポート下に駐車することで、太陽光を使用した充電が可能です。また畑や農園での使用も期待されています。営農型太陽光発電システムと言って、植物に必要な光だけを透過する太陽光パネルの新素材を使用しているんです。つまり畑の上に太陽光パネルを設置しても、果物や野菜の成長を妨げることなく太陽光発電が可能になります。※ 参考資料:農林水産省素晴らしいですね!現段階で、太陽光パネルと蓄電池を直接つなぐ研究はどこまで進んでいるのでしょうか?太陽光パネルと蓄電池の直接接続を可能とする条件を明らかにして、模擬実験で検証している段階です。一方で、直接接続システムでも、電力回路などに短絡などの異常があった時、強制的に電流遮断をする方法が安全の上で必須です。最近、日本が強い分野でもある「シリコンカーバイド」という半導体材料を用いたトランジスタを用いて、直流専用の半導体遮断器を作ることに成功したんです。初期の研究成果を3月の電気学会等で発表予定です。現在、遮断器が確実に動作するかどうか、実際の太陽光パネルを模擬した電源と蓄電池の間に入れて、遮断実験を進めています。良好な結果を得ています。つまり、社会実証試験に向けて前へ進んでいる状態と言えますね。ありがとうございます。最後に、未来を生きていく若者や研究者たちに対してのメッセージをお願いします。これから長い人生を送っていく若者が、未来への漠然とした不安をなくすためには、日常使うエネルギー確保の将来ビジョンが必要です。いまの若者は、自分が将来どのような生活をしているのか、ビジョンが見えていない人が多いのではないでしょうか。世界各国で起きる国際紛争や環境問題などのニュースを見るたび、未来への不安を抱えてしまってもおかしくはありません。不安な気持ちを少しでもなくすためには、生きていくうえで必要不可欠なものだけでも、安定して供給される世の中にしていく必要があります。生きていくうえで必須なものとは、食料や最低限の生活保障に加え、電力などのエネルギーのことですね。つまり、他国に依存せず、自給自足的なエネルギーを確保していくには、地球温暖化防止の観点からも再生可能エネルギーが必要なんです。ただし、世間が動いてくれるのを待つだけでは、安心な未来にはたどりつけません。将来的には、人口減少に伴い、行政サービスの継続が困難な地域が出る予測が出ています。自らの生活基盤を固めていくためには、いまの自分にできることがないかを探し、地域の人々と繋がりながら、地産地消型のエネルギーシステム実現に向けて主体的に動くことが大切だと思うんです。私はこれからも、再生可能エネルギーで自給自足ができる未来への研究と普及を続けていきます。普及する電気自動車とのシナジー効果を模索しながら、エネルギーに関するゲームチェンジに果敢に挑戦する姿勢を若い人達に見せていきたいです。 -

久保博子教授と探る、快適な毎日を手に入れる睡眠、健康の科学
私たち人類は、睡眠という行為と共に進化してきた。つまり人間にとって睡眠は、必要不可欠であり、生理機能として備わっているのだ。睡眠は人類史において、何億年もの間変わらず受け継がれ続けているもので、これから先も睡眠の重要性は変わらない―― しかし、私たちが生活する日本は世界各国の中でも睡眠時間が短い国であり、2021年の調査ではついに世界ワースト1位というランキングも発表された。睡眠不足は、生産性の低下を招き経済活動にも影響があるといわれており、睡眠不足による経済損失は約18兆円と言われている。このような現状を踏まえて、私たち日本人は快適な睡眠とは何かを考える一方で、睡眠の重要性も考えなくてはならない時期を迎えたと言えるのではないだろうか。そこで今回は、人間工学、環境工学の分野を研究し、室温・湿度が与える健康への影響について研究する奈良女子大学研究院工学系・久保教授にお話を伺いました。快適な睡眠のための室温・湿度を研究する奈良女子大学・久保氏まずは、研究概要について教えてください。私は、人間工学、環境工学の分野を研究してきました。なかでも、暑さや寒さといった気温や湿度の環境が住居の中でどのように健康に影響を与えるのかという調査に力を入れています。私が所属していた研究所は1960年代から睡眠研究を行っていました。例えば「扇風機をつけるのは、睡眠に悪影響を及ぼすのかどうか」や「エアコンのタイマー機能を使用することが本当に最適なのか」などの研究です。また、上向き、下向き、横向きなど色々な姿勢で体圧分布を計測して寝心地について検討しています。さらに年代別に睡眠調査をおこない、若い世代、高齢者世代など、年代や性別で調査しています。ずばり質問ですが、快適な睡眠の条件は何でしょうか?快適な睡眠には、布団の中の温熱が影響していきます。例えば、布団の中の環境(寝床内気候)は、33℃±1度、想定湿度55%±5%の範囲が適切だと言われています。そして、35℃を超えると不快感を覚えます。そして夏場は、布団利用する方が少ないのですが、寝床内気候は計測しにくいのですが、タオルケットなど薄手の寝具を使用して、この程度の安協が心地がよいです。シングルが薄いので、だいたい25℃~27℃の室温にすると快眠が得られる環境になります。また夏場の場合は、肌と寝具との接地面も快眠に影響を与えます。例えば、海外のウォーターベッドを湿度の高い日本で使用するとウォーターを包むカバーの上に湿気がたまり、不快感のもとになるということがわかっています。そのため湿度の高い日本の夏場は、ゴザをひくなどの湿気対策も大切になります。快適な睡眠のために夏場のエアコンは冷房と除湿のどちらが正解?「睡眠時の快適さ」と「健康」の関連性を説明していただけますか?睡眠時の布団の温度や室温(暑さ・寒さ)が影響して、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりすることが、結果的に健康への悪影響に繋がることはあるでしょう。冬場の睡眠時は、布団で首から下を保温することができます。つまり布団の中の温度は、保温により保つことが能になる訳です。そのため、布団の中の湿度・温度を調整すれば室温が低い場合でも、それほど悪影響はありません。しかし夏場は、寝具により暑さを防ぐには限界がありエアコンによる室温と湿度の調整が不可欠です。エアコンを使用する場合は、冷房を使用するのがおすすめです。除湿機能を使用して室温を調整するのは、あまりいい方法とは言えません。なぜなら、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」という2つのタイプがあり、使用中のエアコンが「再熱除湿」タイプだった場合は、室内機の中に部屋の空気を取り込み、一旦冷やして除湿して、下がりすぎた空気を温めて室内に戻しています。そのため、十分に温度を下げることはできますが、省エネという観点から言うと、消費電力も多くなってしまうのです。したがって、夏場にエアコンで室温・湿度を調整する場合「冷房」を使用した方が効率的に室温・湿度を調整できるといえるのです。 参照:独立行政法人中小企業基盤整備機構 省エネQ&A『弱冷房除湿と再熱除湿の違いは?』日本人の睡眠時間は世界ワースト1位!睡眠の重要性をしっかりと伝えたい日本は先進国でも睡眠が足りておらず、睡眠不足による経済損失も大きいとも言われていますが、日本特有の睡眠における課題は何でしょうか?日本人の睡眠時間は、世界各国と比べても短すぎるといえるでしょう。実際、経済協力開発機構(OECD)が2021年に33カ国を対象に行った睡眠時間の調査では、日本の1日の睡眠時間は、これまでワースト1位だった韓国を抜き、ワースト1位という結果でした。不眠、睡眠不足は疲れや疲労感を促す原因であり、しっかりと睡眠をとらないと仕事のパフォーマンスも向上しません。不眠状態の人の判断能力は、お酒を飲んで酩酊している状態と同等とも言われています。つまり、不眠状態で仕事をした場合、お酒を大量に飲みながら仕事をしている状態とパフォーマンスは同じになると考えられるでしょう。同じように、不眠状態での運転も飲酒運転の状態と同じといえます。このように、身近なものを挙げるだけでも、睡眠の大切さはわかっていただけると思います。そのため、日本はまず適度な睡眠時間を確保することが課題だと言えますね。 参照:厚生労働省『良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない 睡眠のこと』なるほど……とはいえ、私たちのようなWEB関係や書籍、映像など制作仕事は、締切に追われて寝たいけど寝れない……という人が多いのが現実です。そんな人はどうしたらいいですか?やはり、企業、働く人のマインドセットを変えて、社会の意識も変えていくことが大切だと思います。現場では「できないことはできない」と伝える必要もありますね。アメリカ人の上司をもつと「残業するな」と言われるという話をよく聞くと思います。アメリカでは、優先順位の低い仕事はやらなくていい、本当に重要なことがけをやるというマインドが根付いているのです。逆に日本の場合は、全ての仕事を引き受け、丁寧に仕事をしすぎる人が多い国だと言えます。上司の部下への仕事の割り振りが原因となり、部下のパフォーマンスが上がらなかったり、残業が発生してコスパが悪いといわれたり……悪循環になっているのです。現代の生活環境において、最も注意すべき「快適さ」と「健康」の問題は?そもそも日本人は「睡眠は重要である」という認識が低いことが問題です。人類史において人は、何億年も「夜になったら寝る」という生活サイクルで生きてきました。どんなにテクノロジーが発達しても、6~8時間は眠るという行為をやめるという遺伝子にはなっていないのです。そのため、まずは睡眠の重要性を理解して、しっかり眠ることがとても重要です。また睡眠不足からくる体の不調は、生活習慣や寝具など何か1つを変えるだけでは改善はされません。睡眠不足で、体調に不具合が出ているのなら、その身体のSOSに耳を傾けてあげることも重要ですね。一方で、職業によっては、社会の時間と睡眠の時間が一致しないケースも多いと思います。社会時間とのバランスを取るのが難しい人はどうしたら良いのでしょうか?結論からお伝えすると、自分にとっての最適な睡眠時間を確保していれば睡眠をとる時間が夜22時から朝6時でも、朝5時~昼13時でも特に問題はありません。実は、過去に私の息子の脳波を計測したことがあるんです。当時、浪人生だった息子は、夕方から始まる予備校に通っていました。昼頃起床し、15時頃から予備校、夜遅くまで勉強して、深夜に寝るという生活スタイルでした。こんな生活リズムで、しっかりと睡眠がとれているのかと気になったので、脳波を測っていみたところ、驚きの結果でした。教科書の手本のようなキレイな脳波が計測できたんです!つまり昼に起きて、深夜まで勉強をする(時間外れているけれど、日を浴びて起きて、たっぷり眠る)けど8時間は眠る生活を続けるこれは息子にとっては普通の睡眠だったということです。ここで課題となったのは、大学入試本番は朝からはじまることでした。自分が普段寝ている時間(つまり彼にとっては夜中)に、テストを受けるので、パフォーマンスに影響を及ぼします。多少の時間は誤差かもしれませんが、普通の社会の始業時間と同じ時間に働く必要があるなら、睡眠一覚醒リズムとずれてしまうことで、パフォーマンスの低下を引き起こす恐れがあるので、生活スタイルの改善をおすすめします。自分の身体を知ること。そして睡眠時間を確保すること。それが日本の未来を明るくする第一歩に……。研究の今後の方向性や目標について教えてください。睡眠の質や仮眠という領域については、正確な情報を提示するのに十分なエビデンスが不足している研究領域でもあるんです。今は快眠観葉についても研究を進めています。また「睡眠の質」という領域も、昨今は研究も進んできましたが、さらに調査する必要があります。例えば、就寝前の入浴に関していうと、お風呂上がりの1時間は寝付きが悪い傾向があります。1時間をすぎた後、身体が冷えることで睡眠状態に入っていくと言われているんです。しかし、この就寝前の入浴についても細かく調査すると、何℃のお風呂に何分浸かったのか、シャワーだけの場合、入浴後の寝室の温度・湿度、冬なのか夏なのか様々な要素が複雑に交差して、睡眠に影響を与えているんです。そのため、「睡眠の質」に関しても今後も調査していきたいですね。ありがとうございます。睡眠の質で言うと寝具との関係は?何かありますか?睡眠の質に対する寝具の影響に関しては、これまでの研究では明確な関係はよくわかりません。疲れて寝不足な状態の時は、どんな状況でも寝ますよね? そのため、高いマットレスや枕を使用しても、それだけでは睡眠の質が向上するとは言えないというような実験結果でした。もちろん、自分にとって快適な睡眠環境を作ることは大切です。自分が寝た時に極端な不快感を抱かなければ問題なく、その環境が自分の中で快適ならそれで問題ありません。未来の生活環境を理想的にするために必要なことは?子どもはもちろんですが、大人にも、睡眠教育が重要です。適切な睡眠を取ることが、健康や日中のパフォーマンスにどのように影響を与えるのかを適切に伝える必要があります。睡眠不足を削っての長時間労働は、仕事の生産性を下げるだけです。さらに言うと1人のGDPを低下させることに繋がり、それは日本経済全体に与える悪影響と言っても良いと思います。また、子どもも同じです。学校や家庭でしっかりと睡眠教育をしていくことが大切でしょう。実際に睡眠の時間が短い子どもは、算数の点数が低いという研究データもありますね。久保先生の研究を通して、読者に伝えたい一番のメッセージは?睡眠に関しては、書籍、WEBサイト、SNSで様々な情報が出ています。しかしそういった情報から得た知識よりも先に、自分の身体のコンディションを正確に把握することが重要です。睡眠不足や睡眠に問題があるの場合は居眠りしてしまったり、考えがまとまらずパフォーマンスが上がらなかったり、何らかの影響が出ます。自分自身の身体について知ることで、自分にとって最適な睡眠も知るきっかけになるでしょう。まずは自分の身体に目を向けて、しっかりと睡眠の時間を確保する、そして自分の人生のために、健康に意識を向けるこのように一人ひとりの意識が少しずつ変わっていくことで、健康への配慮に加えて、経済力の向上にも繋がると思います。 -
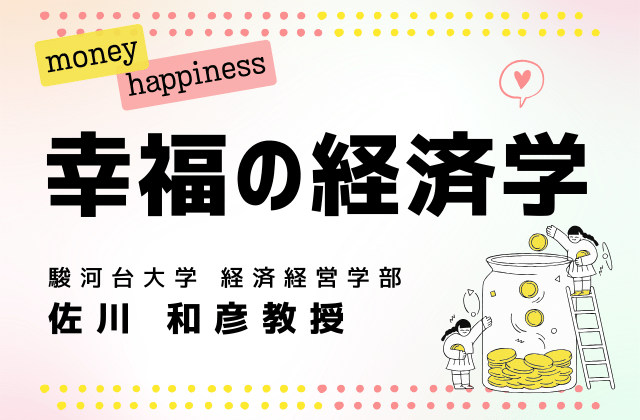
経済学における“幸福”の深層探訪
“お金と幸福”の関係は、資本主義社会を生きる我々にとって、一つの重要なテーマではないだろうか? お金と幸福を考察する際、従来の経済学は客観的な数値を用いて研究していた。ところが近年、経済学に「幸福」を採り入れた「幸福の経済学」が注目を集めている。幸福という、客観的な数値を持たない主観的な感情を、経済学に取り組むことで、経済と幸福の関係値、そしてお金と幸福に関しての一つの答えが出るのではないだろうか―― そこで今回は、駿河台大学経済経営学部・教授・佐川和彦氏を取材した。幸福の経済学とは?先生のご専門についてお教えください。私の専門は医療経済学です。医療経済学と聞くと、特殊な学問に思う人もいると思います。ですが「経済学」という学問は、基本的にお金が関係する現象すべてを対象としているのです。例えば、医療の場合、お医者様が患者を治すことがメインになりますが、新薬開発や医療保険といった医療に関連するものにはお金が絡んでいます。医療の分野でも、経済学は重要な役割を果たしています。私はその分野の研究を行っています。幸福の経済学という学問領域については、3年生、4年生のゼミで指導しています。ゼミ生には、幸福の経済学の分野で学んだことを中心にして、卒業論文を書いてもらいたいと考えています。幸福の経済学を研究していると、人の幸福にはさまざまな要因が絡んでいることがわかるんです。例えば医療や健康は、幸福感に対して大きな影響を及ぼしています。このような医療や健康と幸福感との関連性についても研究しているところです。実は、私は幸福の経済学という分野の研究をずっと続けてきたわけではありません。むしろ最近になって幸福の経済学の重要性を認識するようになったのです。私の専門である医療経済学分野にも、幸福の経済学の考え方を絡めて考えていくことは非常に重要であると考えています。幸福とGDPとの関係性について昨今、こういった幸福の経済学が注目を集めている背景についてお教えください。幸福の経済学について説明をしなければならないのですが、そもそも経済学の究極の目的は、人間を幸福にすることです。ただ、従来の経済学は、幸福は主観的なものであり、それを定義づけることや人と人との幸福を比較することは難しいという立場をとってきました。従来の経済学は、幸福感というあいまいな指標の代わりに、GDPを使ってきました。1人当たりのGDPが大きくなると、それだけ物質的に豊かになるので、皆が幸せになるという考えです。さて、ここでひとつの問いかけが、「私たちは本当に幸せなのか?」なのです。先進国である日本は1人当たりGDPが発展途上国と比べれば大きいので、物質的に豊かな国であるとは言えるでしょう。そのため従来の経済学では、私たちは幸福である、となります。ですが、幸せに対しての根本的な疑問はぬぐいきれません。これは、『幸せはお金で買えるのか----』、と言い換えることも可能です。場合によっては、お金に執着することで、逆に不幸になることだってあるかもしれません。なるほど...『幸せはお金で買えるのか』『お金があれば幸せなのか』というのは永遠のテーマというか...私自身も常に考えさせられますね。そうですね、実際にOECD加盟国における1人当たりのGDPと生活満足度との関係を国際比較したデータがあります。GDPが上がれば、基本的には生活満足度、いわゆる幸福感みたいなものが上がっていく関係が見られます。国際的に見て、1人当たりGDPが増えると幸福感も比例して上がっていくものの、一定のところで頭打ちになるのが全体的な傾向です。一方、日本での1人当たりGDPと生活満足度の関係について時系列で見てみましょう、ここでは通常経済学で用いる実質GDPでなく、名目GDPを使います。なぜなら、日常私たちが目にする数字、例えば給与の明細の数字は名目値だからです。1960年代から1990年代において、名目GDPは増加しましたが、生活満足度は多少の上がり下がりはあるものの、ほぼ横ばいです。つまり、1人当たりのGDPと生活満足度とはリンクしていないのです。このような現象が起きることは、リチャード・イースタリンという学者が発見しました。所得と幸福感が連動しないことは、「イースタリン・パラドックス」と呼ばれています。所得が増えても、幸福感が伸びない理由として3つあります。1つめは、人間の幸福度はその人の周りの人たちとの比較で決まるという点、2つめは比較対象が変わってしまう点、そして3つめはそもそも慣れてしまう点です。では、所得は大事ではないのか、といえばそうではありません―― 所得は絶対に大事です。物質的な豊かさを享受しているので、所得がもたらす幸福感に対する感覚が鈍くなっている方も多いと思いますが、所得がもしなくなった時のことを考えたら、人は幸福ではいられなくなるということは容易に想像できると思います。経済学と幸福の経済学が交わることで、社会はより良い方向へ――所得が上がったとしても、幸福度は伸びないことがある一方で、所得が絶対に大切というお話をしました。所得以外の要因もありますので、人は自分がおかれた状況の中でどれだけの幸せを感じることができるのかということが重要です。私は、従来の経済学を否定しているわけではありません。実際に大学ではマクロ経済学というオーソドックスな経済の理論を教えています。強調したいのは、これまでの経済学では捉えきれなかった「幸福」という側面を、「幸福の経済学」という視点で考察していく従来の経済学と幸福の経済学が合わさり、より良い方向に社会の歩みを進めるということです。話は変わりますが、日本の健康指標についても興味深いデータがあります。1つは、OECDの加盟国それぞれの平均寿命で、客観的な健康の度合いを表すものとして一番有名です。もう1つは、自己報告による、いわゆる主観的な健康度です。これは実際に病院等で行った健康診断の結果のような客観的なデータではありません。1つめのOECDの加盟国それぞれの2019年の平均寿命データですが、日本はトップです。一方、2つめのデータの自己報告による健康度では、低いところから2番目のところに日本があります。両極端な結果となっています。このような結果についてですが、私は日本人特有の国民性みたいなものの影響もあるのではないかと推察します。日本は、昔から災害が多い国、地震や台風が多い国です。いつどこで大きな災害が起きるかわからないことを、いつも意識しながら生活しています。日本人は、今は普通に暮らしていても、いつ健康を害することがあるかわからないと、控え目に考えるようにしているのではないでしょうか。もちろん、実際にデータとしてはないので分析できないのです一方で、日本についての私の最近の研究では、病床数などの医療資源量の違いが主観的健康度と客観的健康度の乖離につながる可能性があることもわかっています。これからの幸福と経済の関係性における推察先ほど、他者との比較が出てきましたが、昔と比べて結構強く出てきている時代ではないかと思います。幸福の考え方みたいな部分だったりと、他者と比べたときの幸福にならないといけない、というハードルが高まっている気がしますが、いかがでしょうか?他者との比較については、2つの例が挙げられます。1つは、デジタルデバイスが普及したことで、色々な情報が一瞬に自分の中に入ってきてしまう状況です。さらに、スマートフォンやコンピューターを通してみる世界は、自分と対象のコンテンツだけの一人だけの世界に入っています。若い子たちが、SNSを通して誰かの幸せそうな情報を見てしまうことで、対象の情報をじっくりと考察する時間がないまま、ストレートに享受してしまう可能性が高いかもしれませんね。情報過多のネット社会においては、情報をうまく取捨選択していかなければなりません。ですが、若い子たちは、情報の取捨選択を上手にできないのが現状です。そのまま間違った情報を受け入れ、取捨選択を誤り、道に外れた場合はその子の人生が悪い方向に進んでしまう可能性がありますね。そして2つ目ですが、親と子どもの関係です。今に始まった話ではありません。昔の親は世間体を気にしていました。世間体も他者との比較なのです。もっとも昔は兄弟姉妹がたくさんいたので、親も1人の子どもだけに構ってはいられませんでしたが...現在は一人っ子が多くなったため、その1人の子どもに一点豪華主義で期待をかけるので、親がよその子どもと比較して、「もっと勉強して」となってしまいます。とはいえ、親であれば皆そう思うのではないでしょうか。ですが、世間体から子どもに過度な期待をかけ、親が理想とする人生のルートを強制しようとすると子どもの視野は狭くなってしまう可能性があります。以前に比べて情報の取捨選択のハードルは上がっている気がしますし、他者と比べるというのは顕著に現れている気がします...。自分のなかで本質的な価値を追求したり、心の器のような精神的な軸をしっかり持っていないと、流せれてしまいますよね...。そうですね、今後一層このような現状は、顕著になるでしょう。情報の入ってくる速度や量が進化しています。昔なら、自分の周りの情報しかなかったので、ある意味幸せでした。昔だったら、たとえ貧しくとも周りの人たちもみんな貧しい状況だったら、自分だけじゃない、と感じられたのです。日本人ならではの、仲間意識の強さみたいなところが経済的な幸福を感じられない要因になっているのではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか?私は徳島県出身なんですが、子どもの頃に、地域では「お念仏」という行事がありました。近所に住む人たちがグループになって、月に1回お経を唱える内容です。終わった後でみんながお茶を飲みながら雑談するんですよ。いわゆる情報交換ですね。このような地域のグループの中に入って交流を持つという風習が、昔からありました。全部自分のことが筒抜けになるので、今の若い人たちからしたら信じられないかもしれませんが私自身、お念仏のような集まりは悪くなかったと思います。周りの人がどのようなことを考えているかがわかります。つまりコミュニケーションロスがなくなるわけですよね。そしてグループの繋がりもあるので、いざ困ったことがあったら助けてくれます。これから世代が変わることで、価値観も変わってくると思いますが、昔だったらそのグループの中にいたら幸福でした。今は、グループの助け合いみたいなのがなくなってきています。今は、人との繋がりが希薄になってきており、幸福の基準もあいまいになってきています。よくいえば、多様化しているのです。人間が幸福になるというのを誘導していくことはすごく難しいです。だからこそ、我々個人個人がどう考えるか、というところに行き着くんだろうと思います。個人的に、お金の価値観はそれほど幸せにつながっていないように思っています。私は、人とのつながりとか、精神的な安定性っていうところに幸せを感じるので、人それぞれですね。 自分にとっての幸せを考えた時には、趣味を持つことがとても大事だと思います。私は音楽が趣味で、なおかつ研究もある意味趣味なのです。教育や校務を行うことが仕事であり、それによって給料をもらい生活しています。個人的にはすごく満足しています。私の父親は現在92歳ですが、80過ぎても自営で菓子屋をやっていました。朝から晩まで働いてました。父にはこれといった趣味がないのですが、決して不幸ではないと思います。人それぞれといえるのではないでしょうか。何から満足感、幸福感を感じるかというのは、私の親のように生まれた世代ごとの価値観もあるかもしれません。言い方を変えると、働きづめの生活が不幸かといえば、まったく不幸ではありません。もちろん先程お話したように、ある程度の経済的な豊かさや所得は、必要不可欠です。ですがお金に人生を振り回せれないように、自分の心を理性的にコントロールするための、人間性や心の器を持っていることはこれからの時代は、とても大切なのかなと思っています。GDPそのものは維持でき、生活水準も維持できる可能性がある?5年後10年後の幸福と経済の世界観について、何かイメージされていることはありますか?今、日本は確実に人口が減少していっています。これから5年10年とか、あるいはそれ以降、10年20年先には人の数が少なくなり、高齢化率が上がり働く人の数も少なくなっていくでしょう。世界の中での日本のGDPの相対的な地位は、今後下がっていく可能性があると思います。しかし、ベースとなる1人当たりのGDPは維持できると考えています。働き手が少なくなっても、代わりにコンピュータや機械に置き換えていくだけの研究開発を進めれば、1人当たりのGDPそのものは維持でき、生活水準も維持していけるだろうと私は思うのです。あとはいかに経済水準をキープするかですが、5年、10年の間で生活水準が急激に悪化することはないと私は考えています。私は、大学院で研究している留学生たちと研究以外でもよく雑談を交わします。彼ら彼女らは、日本は急進的ではなく、戦争をしない国といった印象を持っているようです。今後も特段変わることはないであろうと思ってくれているようです。個人的には、日本人の多くの学生たちは、大学院で研究する留学生たちのような、いい意味での貪欲さがなくなっていると感じています。高度経済成長期の日本人だったら、もう少し泥臭く自分の夢を叶えるために努力する、生活の水準を上げるために行動するような、ある種のストイックさを持っていたと思うんです。一方で留学生たちは、いい意味で貪欲です、学問に対して。学問だからすぐ就職に直結するわけではないですが、貪欲に吸収しようとするのです。もう少し日本人の若い人にも貪欲さを持ってもらいたいと考えています。趣味を持ち、心に余白を持つ。最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。最大限努力して、一生懸命自分の仕事も頑張っていることを前提で申し上げると、趣味を持っていてほしいですね。幸福感にもつながるのですが、仕事に真面目な人ほど、万が一仕事でうまくいかなかったときに絶望します。いい意味での逃げ場を作るためにも、趣味はとても大事です。趣味があれば、切り替えが可能となります。切り替えるものを持って生活していくと、追い詰められることがなくなります。追い詰められたら駄目です。もちろん、趣味を持つことは、限られた時間の中でそのための時間まで確保する必要があるので、体力も使います。大変なのですが、いざというときのシェルターの役割を果たしてくれるでしょう。その意味でも、社会人になってもやっぱり趣味を持ってやってほしいと思います。 -
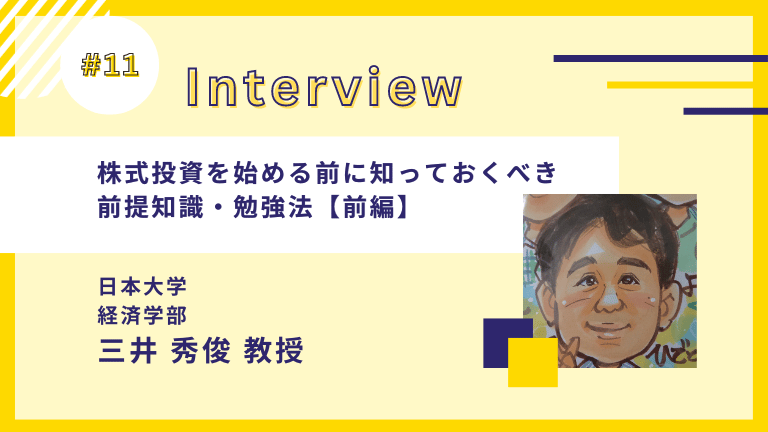
株式投資を始める前に知っておくべき前提知識・勉強法【前編】|日本大学 経済学部 三井秀俊教授
積立投資にある程度慣れてくると、「そろそろ個別株に投資してみたい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。個別株投資には、自分が気になった銘柄を選んで投資できる魅力があります。しかし、投資の方法は人によってさまざま。自分に合った方法がわからず、始めたくても始められないと思っている方もいらっしゃるでしょう。そこで、HonNeでは日本大学経済学部で主に金融データ分析を研究されている、 三井 秀俊(みつい ひでとし)先生にインタビューを実施。先生の研究テーマを踏まえつつ、株式投資の学び方を前編・後編に分けてお聞ききします。これから自分の投資方法を見つけたい方、投資に関する知識を深く学びたい方は、ぜひ当記事をご参照ください。インタビュー日:2023年11月2日株式投資とは何か?始める前の準備 デューク大学 (客員研究員)の時の様子株式投資を始めるとは何か?2024年から新NISAがスタートするように、株式投資を始める人が年々増えていますが、先生はどのような印象を持っていますか?日本政府は国民の資産が金融市場に流れるよう推進していますが、政府が推進しているからと言って、安易に株式投資を始めて欲しくないと思っています。同時に、「株式投資は簡単」と主張する広告や本を見て、真に受けて始めてしまう人がいることも、個人的に心配をしています。株式投資とは、自分が頑張って稼いだお金を使います。他者の意見に影響されて、十分な知識を身に付けずに株式投資を始め、損をするから「株式投資は怖い」というイメージが付いてしまいます。そのため、最初にやるべきことは、株式投資とは何か、どのように行なったら成功するのか、上手くいっている人から話を聞くことです。具体的に、誰から聞けばいいですか?私がおすすめするのは、自分にとって信頼できる人・本音を言い合える人で、自分のお金で実際に株式投資をしている人から聞くことです。親しい間柄だと、相手は本当の株式投資について話してくれます。ご自身も相手の性格をある程度理解した上で聞けるので、相手が嘘や誇張しているかを判断もしやすくなります。まだ距離感がある人に聞くと、「俺はこの方法で儲かった!」といった自慢話を聞かされるだけでしょう。大切なのは、上手くいったことはもちろん、失敗談も聞くことです。失敗談を聞くと、安易な考えで始めては、株式投資は儲からないことが理解できます。もし身近な人で株式投資を続けている人がいなかったら、どうすればいいですか?身近な人の知り合いから、株式投資を行なっている人を紹介してもらってください。その際、謙虚な気持ちで頭を下げるような姿勢で聞きに行くことが大切です。「株式投資で儲けたいから教えて欲しい」といった、安易な気持ちで聞きにいくと、相手も話す気がなくなって、本当のことを教えてくれないでしょう。その際、話した内容をメモするために、必ず筆記用具とノートも持参してください。株式投資で成功している人が書いた本(例えば、マーク・ミネルヴィニ『株式トレード 基本と原則』PanRolling)には、「本気で株式投資を始めたい人は、筆記用具とノートを持ってきて話を聞きに来る」と書いてあります。株式投資ではありませんが、興味深いエピソードがあります。私のゼミ生に、私のアドバイスを聞き、A4ノートを持って就職活動をしていた学生がいます。もちろん、相手の話をメモするために持って行っているわけですが、何と、リクルーターや人事部の方がそのノートに色々と重要なことを書いてくれたと言うのです。人によっては、図まで描いて詳細に説明してくれたそうです。株式投資に限らず、何かしら教えてもらうときに大事なことですね。真剣な姿勢で話を聞く態度を示せば、相手はもっと教えてあげたいって気持ちになりますね。真剣に聞くか、とりあえず聞いてみようか、その姿勢の差は株式投資に限らず、あらゆる物事の結果に大きく影響します。その道のプロの人が話す内容は、本や記事の内容では絶対に知れないものですから、素直に聞き入れる姿勢を持つことから始めましょう。合わせて、事前に予備知識を勉強しておけば、相手も何を話せばいいか判断しやすくなりますし、本気度合いも伝わります。自分が理解できたことと、そうではないことが整理されるので、具体的に聞きたいことも出てくるはずです。何の準備もせずに聞きにいってしまうと、相手も何から話せばいいか、混乱させてしまいます。株式投資を続けることは仕事やスポーツと同じ!株式投資を始める第一歩を話してくれましたが、株式投資を続けるために一番必要なことは何でしょうか?物事を進めるプロセスを理解していることが一番大事ですね。仕事やスポーツ、受験勉強など、なんでもいいので何かしら努力してうまくいった経験を持っている人は、株式投資も努力が必要で時間がかかることを理解してくれます。合わせて、何を聞くべきか判断もできるので、こちらとしても教えやすいんです。そうではない人は、手取り足取り教えてもらおうとするので、教える気もなくなります。極端に言えば、事前に予備知識を学んでいなくても、何か物事を身に付けるには時間と努力が必要なことを体感していれば、株式投資を続けるために必要なことも理解できると思います。もし、何か1つのことを続けた経験がない人が本気で株式投資を始めたい場合は、何から始める必要がありますか?私の場合、そもそもの勉強の仕方やノートの取り方を教えて、知識の身に付け方や情報を整理する方法を理解してもらいます。そうでないと、いくら株式投資のことを勉強しても自分の身にならないからです。例えば、何かスポーツを始めた場合、最後まで試合を続けられる能力と体力はどんなスポーツでも必要ですよね。たまに面倒くさがる人がいますが、「株式投資でうまくいきたいなら、まずは学び方を学びなさい」と、何が何でも理解してもらいます。方法論で株式投資が上手くいくとは限らない 対外経済貿易大学の中国語語学研修引率の様子先生のお話を聞いて、株式投資は安易に手を出せるものではないことが理解できました。続けられる投資家になるには、実際どれくらい時間がかかりますか?少なくとも、2〜3年は見越したほうがいいですね。本やインターネットを見ると、「1年で何億円も儲かった」といった情報に目が行きがちですが、ほとんどが偶然なので長続きしないそうです。そういった人は、儲かったお金をすべて失っている人が多いそうです。株式投資の目的はいくら儲けるかではなく、いくら残せるかです。だから、コツコツ地味に続けているほうが、最終的に大きなお金を残せます。そのため、株式投資では最初の心構えと準備がとても重要です。どれだけ真剣な気持ちで、続けるための準備を整えているかで、株式投資の結果は大きく変わってきます。仮に100%儲かる投資手法を教えたとしても、実際に理解して実行できる人は1割もいないと思います。絶対に儲かる投資手法を知ったとしてもですか?はい。これは、株式投資に限らず、何か新しいことを始めて、成果を出すまでの本質的な考え方だと思います。みなさん、どうやったら上手くいくか方法論を知りたがりますが、実際に実行できるかどうかは自分次第です。確実な方法論を知ったから、上手くいくのではありません。例えば受験勉強の場合、有名大学に合格する方法はある程度確立されています。その方法を最後まで実践できる人が少ないから、有名大学に合格する人が限られるんだと思います。何事も、ある程度のレベルまで行く方法は確立されていて、そのハードルもそこまで高くありません。一部の人が上手くいくのは、上手くいく方法を最後までやり続けたからです。だから、仮に絶対儲かる投資手法を知ったとしても、真剣にやる心構えと身に付けるための準備を徹底しないと、続けることは難しいでしょう。どのような方法論を選ぶかが重要ではなく、本気でやり続ける姿勢が大前提と…。あと、道具等にもこだわって欲しいです。100円ショップで売られている包丁よりも、プロが使っている包丁を使ったほうが食材を美味しく切れ、料理が上手くできるように、株式投資でもプロが読んでいる本や記録の付け方を学ぶことにこだわってください。スーパーで売っているテニス・ラケットで試合に出るプロのテニス選手がいるでしょうか。小さなメモ帳を使用して、上手くいくわけがありません。私個人の意見ですが、スマートフォンの画面で見ても株式投資は上手くいかないと思います。プロは大きな画面を使い、しかも複数の画面を準備しています。株式投資はいろんな情報を見て判断することが多いので、画面が小さいと見れる情報が限られて、効率が悪くなるからです。チャート等も小さい画面では、ただ見てるだけで何もわからないともいます。社会人の方でスマートフォンを使用して、まともな仕事はできないことは理解して頂けると思います。スマートフォンは通信手段などごく限られた分野で使うものです。プロのカメラマンがスマートフォンで写真は撮りませんし、我々研究者もスマートフォンで論文は書きません。私の授業である学生がスマートフォンでノートを取っているのを見て、腰を抜かしたことがあります。そのような学生の成績は察して知るべしです。株式投資では、断片的に入ってくる情報を効率よく集めて整理することも求められます。そのため、情報の集め方や整理する方法も、プロの投資家や経験者から学ぶのがおすすめです。もうみなさんおわかりだと思いますが、株式投資で大事な要素は仕事やスポーツなどと共通します。なので、「株式投資」だからと言って変に身構える必要はありません。株式投資を続ける考え方が、何ら特別ではないことがわかって目から鱗でした。むしろ「自分でも株式投資は続けられる!」と、勇気をいただいた気分になっています。株式投資を知るために読みたい本まず株式投資の心構えが学べる「古典」を読むそれでは、続けられる投資家になるために、最初に何をすべきか教えてください。株式投資について本当のこと知りたいなら、まずは株式投資の世界で「古典」と呼ばれる本を読んでください。世に出ている株式投資の本は、そのほとんどが〇〇業界の立場を配慮して書かれているため、私たち個人投資家にとってあまり参考になりません。私が知っている限り、初めて個人投資家のために本を書いたのは、林輝太郎(はやし てるたろう)さんだと思います。現在でも林輝太郎さんの本は、ECサイトはもちろん、大きな本屋さんでも必ず株式投資コーナーに置かれています。 引用:Amazon「林輝太郎相場選集〈1〉相場金言集」何冊も出版されていますがどれか1冊でもいいので、これから株式投資を始めたい方は、ぜひ林輝太郎さんの本を手に取ってみてください。他に先生が最初に読んで欲しい本はありますか?もう1つ絶対読んで欲しいのは、板垣浩(いたがき ひろし)さんの『自立のためにプロが教える株式投資』(同友館)です。初版は1990年ですが、今でも増刷されているほど、多くの投資家から支持を受けています。 引用:Amazon「プロが教える株式投資: 自立のために」この本は株式投資の心構えや姿勢が書かれており、良い意味で株式投資の現実、厳しさを教えてくれます。本当に株式投資で儲けたいなら、アマチュアではなくプロとして株式投資に臨む必要があるというメッセージが込められています。初めて株式投資の本を読む方からすると、知りたいことが書かれていないかもしれません。しかし、ある程度経験している方にとっては、趣味や片手間といった考え方では甘いと痛感し、身が引き締まる思いを抱くでしょう。そのため、林輝太郎さんと板垣浩さんの本を読むだけでも、株式投資に対する心構えが変わると思います。1冊2,000円程度ですが、1万円以上払ってもおかしくないくらい価値がある本なので、ぜひ読んでみてください。先ほども申し上げたように、株式投資は自分の大事なお金を使います。そのため、最初は腰を落ち着けて勉強する時間を作ることが大切です。心構えを理解してから投資売買の原則が学ぶ先ほど紹介していただいた本は、株式投資の心構えが学べるということですが、その後はどうすればいいですか?株式投資を真剣にやる必要があると理解できたら、株式トレードのパフォーマンスを競い合う「USインベスティング・チャンピオンシップ」の優勝者である、ミネルヴィニさんの本がおすすめです。 引用:Amazon「株式トレード 基本と原則 (ウィザードブックシリーズ) 」 引用:Amazon「ミネルヴィニの成長株投資法 ━━高い先導株を買い、より高値で売り抜けろ (ウィザードブックシリーズ) 」日本語に翻訳されているのは4冊あって、その中でも、前に紹介した『株式投資の基本と原則』と『ミネルヴィニの成長株投資』(PanRolling)の2冊は必ず読んでください。投資対象となる銘柄の条件やリスク管理など、どのような投資手法を行なう場合でも必要な知識が書かれています。ちなみに、プロの投資家といえばウォーレン・バフェットが有名ですが、彼の本を読むのはどうなんですか?個人的な意見としては、ウォーレン・バフェットさんの本は個人投資家にとって、必ず読むべきであるとは思っていません。もちろん、株式投資の本質や哲学に関して、学べることは沢山あると思います。ただ、私たち個人投資家の資金は数百万円、多くても数億円程度ですよね。一方、ウォーレン・バフェットさんは、何千億・何兆という巨額のファンドを数十年単位で運用しています。投資金額と期間が違えば、株式投資の考え方も当然変わります。そのため、彼の書いた本は機関投資家や大口投資家には役立っても、個人投資家にはあまり参考にならないと思います。個人投資家でも、数十億・数百億円を運用している方には参考になるでしょう。地元の八百屋さんと全国展開するスーパーマーケットでは、経営手法は異なります。同じことは、投資手法でも当てはまると思います。このような観点からも、株式投資を勉強するときは、個人投資家の視点に合わせて書かれた本を読むのがおすすめです。ここまで教えていただいた事だけでも、投資に対する考え方が大きく変わると感じました。とはいえ、私が紹介した本を読んで理解できたとしても、株式投資の全体の進捗度合いとしては、せいぜい20%~30%程度です。ここから先は、模擬売買をやってみましょう。証券会社が提供している模擬トレードツールを使って、半年〜1年程度は続けてください。スポーツだと、何日ものトレーニングや多くの練習試合を重ねてから、初めて本番の試合に臨みますよね。株式投資も同様で、いきなり自分のお金を使うのではなく、模擬売買を通じて株式投資をする感覚を養いましょう。ここまでのお話だけでも、株式投資に対する考え方がガラッと変わると感じました。模擬売買以降のお話は、後編でお聞きしたいと思います。株式投資の学び方が知りたい方は、ぜひ後編もご一読ください。後編に進む -
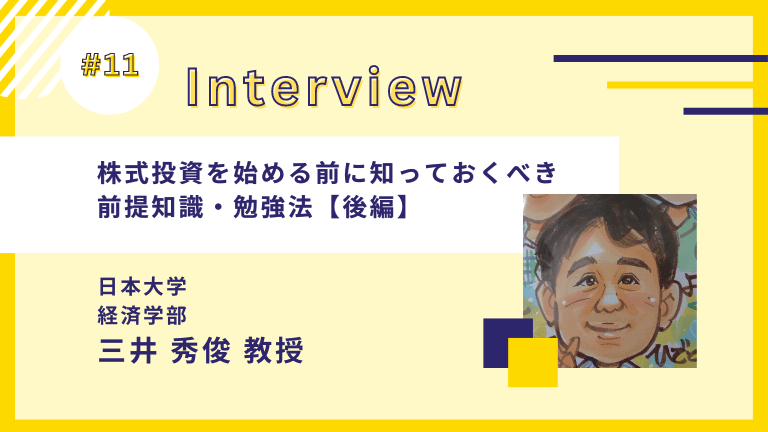
株式投資を始める前に知っておくべき前提知識・勉強法【後編】|日本大学 経済学部 三井秀俊教授
当インタビュー記事は、日本大学で主に金融データ分析を研究されている 三井 秀俊(みつい ひでとし)先生からお聞きした、株式投資の学び方を前編・後編に分けて掲載しています。前編では、株式投資を始める前の心構えや最初に読みたいおすすめの本を解説しています。当記事の後半では、模擬売買や本番の投資で知っておきたいポイント・注意点をまとめています。「これから株式投資を始めたいけど、何から始めたらいいかわからない」という方は、ぜひ前編をお読みになった上で、後編をご一読ください。※前編はこちらへインタビュー日:2023年11月2日模擬売買して投資する感覚を身に付ける 三井秀俊ゼミ:東京証券取引所見学の様子超重要!記録する習慣を身に付けよう模擬売買を始める際、何が一番大事ですか?自分が実行したこと等を記録する習慣を身に付けることです。売買した銘柄はもちろん、日付・売買価格・売買した理由をしっかり「書いて」記録してください。余裕がある方は、日経平均や米ドル・円為替レート等も書いておくと良いと思います。記録する習慣が付くと、自分が上手くいくパターンと失敗するパターンが見分けられ、銘柄の選び方や売買を決める土台になるんです。ほとんどの個人投資家は、この記録の作業をやっていません。株式投資で上手くいっている人が書いた本には、必ず売買を記録していること、また、チャートを手書きで記録していることが書かれています。ミネルヴィニさんの本にも、記録することの重要性が強調して書かれています。私の仮説ではありますが、カルテを書く習慣がある医師は、株式投資が上手くいく傾向があります。患者の身体状況を1人ひとり記録することと、銘柄ごとに重要なことを記録することが共通することから、日々の記録が大事なことをすぐ理解できるからです。習慣化されているので面倒くさいとか言う方はほとんどいません。このような観点からでも、模擬売買を通じて記録する習慣を身に付けることは、株式投資が上手くいくための必須要素だと断言できます。記録を付ければ、自分に合った投資手法は見つけられるのでしょうか?「こういう手法で投資すれば儲かる」と謳っている投資手法を実践したら、確かに上手くいく可能性はあります。ただ、特定の投資手法は、個人の性格が大きく影響することを理解しておいてください。例えば、長期的に運用する投資手法は、短期ですぐに売買する人からすると我慢できないでしょう。逆に、短期的に売買を繰り返す投資手法だと、気長に運用したい人にとっては抵抗を抱くかもしれません。そのため、模擬売買で記録する習慣を身に付けることは、投資における自分自身の性格を理解して、相性の良い投資手法を見つけることにも繋がります。記録は物事を上達させるコツ!有名スポーツ選手も実践している心構えを知ることはあくまで前座で、記録を取ることが投資で一番重要な作業なんですね。記録を取ることは、株式投資に限らず、あらゆる物事に共通して重要な作業です。サッカーの本田圭佑や野球の大谷翔平も、毎回の練習・試合内容をしっかり記録し反省しているそうです。何事もトップレベルに上り詰める人は、何かしら記録する習慣を身に付けています。記録したことを見返すことで、自分が何を考えているのか、何を大事にしているか確認できるからです。自分が積み重ねてきたものを振り返って、失敗しても次はどうするか考えられるから、「もっと続けよう」という粘り強さが芽生えてくるんじゃないでしょうか。ただ、ここまで言っても実際に記録し続けられるのは、10人中1人くらいでしょう。残りの9人は聞いて終わってしまいます。ここが重要です。ほとんどの人が実践しないからこそ、自分はちゃんと記録しながら投資を続けられるかが、株式投資で結果を残せる大きな分かれ目となります。先生も実際に記録を続けてきたからこそ、記録の大事さを確信されているんですね。ちなみに、他にも記録することが大事な理由はありますか?記録することが習慣化すれば、冷静に投資判断しやすくなり、感情的に大きなリスクを取ることも避けられます。感情的になりやすい人は、冷静に判断するための時間を取っていないことがほとんどです。記録することで一旦冷静になり、株価の一時的な値動きに惑わされず、自分がどのような売買戦略にしたがって投資しているか確認できます。個人投資家は、文字通り「個人」で投資する人です。職場の先輩・上司のように、失敗を指摘・修正してくれる人がいません。ということは、自分が実行したことが上手くいったのか失敗したのか、すべて自分自身で判断して修正する「自己管理能力」が必須です。この自己管理能力の大事さって、組織の中で仕事しているとなかなか気付けないと思います。上司や先輩のおかげなのに、「自分が頑張ったから今の自分がいる」と考える人が意外に多いからです。特に、大きな組織に属している人ほどその傾向が強いです。そのため、スポーツや受験勉強、国家試験、個人事業主の経験がある人だと、自己管理の重要さと大変さを理解しやすいでしょう。実際にお金を投じて「土壇場の自分」を知る模擬売買で記録する習慣が出来たら、やっと本場の投資でしょうか?はい。本番の投資ができる準備が整って、株式投資で必要なことの50%まで進んだと言えます。でも、ここからが大変なんです。模擬売買と違って本番の株式投資だと、「違う自分」が出てきます。自分の大切なお金を使っているから、売買する感覚が全然違うからです。模擬売買なら購入した銘柄が50%下落しても気になりませんが、本番だと5%下落しただけでも絶望するでしょう。夜、眠れないこともあるでしょう。人によっては、保有している株が10%下落したら、二度と株式投資はしない、株式投資はギャンブルだと思うかもしれません。ここが、模擬売買との大きな違いであり、越えなければならない壁になります。現実には、一か月で10%以上の上昇・下落は株式市場ではザラにあります。株式投資に関してメンタルに関する本が多く出版されているのもうなずけます。方法論だけでは十分でないことがここからも理解できると思います。ここで、多くの個人投資家は、株式市場から退場することになります。そのため、実際に自分のお金を使った株式投資を始めたら、下落したときの対処方法を身に付けていきましょう。ここがアマチュアとプロの違いです。実を言うと株価の値動きは、一定のパターンの繰り返しが多くみられます。この感覚が体感できれば、下落時の対処方法が見出せて忍耐力が付き、株式投資を続けるモチベーションも保てます。そのためにも、模擬売買で記録する習慣を身に付けることが大事なのです。どの銘柄を選んでいつ売るか、株式投資の醍醐味は最後に控えている 三井秀俊ゼミ:卒業式の様子本番の投資を始めるためにも、どの銘柄に投資するか選ぶ必要がありますが、具体的にどうすればいいでしょうか?ミネルヴィニさん本に、選択する銘柄の最低条件が書かれているので、それらは必ず守って投資してください。株価の値動きは、銘柄によって異なります。一方、人によって投資の仕方も違いますよね。ということは、自分にとって相性が良い値動きをする銘柄があるということです。模擬売買の時点から、自分と相性が良い銘柄を意識しながら銘柄選択をすれば、上手くいく可能性が上がるでしょう。ちなみに、銘柄選定の仕方を身に付ける際の注意点は何でしょうか?いきなり何銘柄も手を出さず、まずは1銘柄だけ選んで売買してください。仕事・スポーツ・料理でも、まずは1つのことをとことん極めた方が、結果的に上手くなりますよね。株式投資も同様で、まずは1銘柄の株価の値動きや事業内容、決算時期など、関連情報を網羅できるまで極めてください。それが出来たら、他の銘柄に手を出しても良いでしょう。「いつ売るか」の見極め、損失を抑え利益を残していく銘柄選定では、自分にとっての得意銘柄を作ることが重要なんですね。あとは、投資した銘柄をどのタイミングで売るかでしょうか?はい。「いつ売るか」とは、ベストな株価で売却できるのはもちろん、損失を抑える「損切り」も含まれます。どれだけ上手くいっている投資家でも、時には失敗します。ということは、損した分を取り戻せないと、株式投資で利益を増やし続けられません。ほとんどの個人投資家は、ちょっと儲かっただけで売ってしまいます。もしくは売るべきタイミングを逃して、そのまま持ち続けて大きな損失を出しています。実際にチャート見たらわかりますが、株価の値動きは一定のパターンを繰り返しているので、長期的に保有しても永遠に上がり続けることはありません。そのため、いつ売るかを見極められて、初めて中・長期的に株式投資を続けられる投資家になります。あとは、別の投資手法を試したり他の銘柄に投資したりして、時には失敗しつつも、少しずつ利益を増やし続けていきましょう。人気を集める投資信託とロボアドバイザー、先生の意見は?ここまで株式投資に関するお話を聞いてきましたが、投資家の中には投資信託を運用したい人もいます。個別銘柄がわからないから投資信託に走る人が多いですが、私からすると投資信託はあまりおすすめしません。長期的に見て、投資信託で利益を得ている人がほとんどいないためです。もし投資信託が気になるなら、リチャード・エリス『敗者のゲーム』(日本経済新聞社)という本を読んでください。この本には、投資信託はどういうものか丁寧に書かれており、投資信託における「古典」に相当します。投資信託に投資するかは、『敗者のゲーム』を読んでから判断することをおすすめします。敗者のゲームというタイトルには、どのような意味があるんですか?敗者のゲームとは、自分のミスを極力減らせば勝てるゲームを指します。例えば、テニスで実力が拮抗している選手同士が試合をすると、相手より素晴らしいショットを打つのではなく、ミスを減らすことが勝利に繋がるということです。下手同士の場合には、ポイントはほとんど相手のミスによるものです。投資信託もテニスと同様で、ファンドマネージャーの実力や得られる情報に大きな差はなく、間違った投資判断を下したファンドが損をする、敗者のゲームとなっています。どうしても購入したければ、株価指数連動型ETFぐらいでしょうか。投資信託を選ぶのも個別銘柄を選ぶのと同じぐらい労力を使うと思います。ちなみに、ロボアドバイザーはいかがでしょうか?一見、ロボアドバイザーやAI投資を利用したら、簡単に儲かるような印象を受けますが、そのようなことはあり得ません。みなさん意外と誤解されていますが、株式市場は売りたい人と買いたい人がいるから成立します。言い換えたら、これから株価が上がると考える人とこれから株価が下がると考える人がいるから、価格が決まって売買できるのです。経済指標が株価を動かしているわけではありません。あくまで株式投資は、商取引の一形態に過ぎません。つまり、ロボアドバイザーやAI投資を利用する人が増えると、同時にそれを逆手に取る投資家が出てきます。それらに使用されているアルゴリズムの戦いになるかもしれません。今はアドバンテージがあっても、いずれは無くなるものも出てきます。また、今度はどのロボアドバイザーやAIを選択するかの問題に直面します。個人投資家にそれらの判断ができるでしょうか。投資信託・ロボアドバイザー・AI投資、いずれにしても利用する際の注意点がありますね。そのため、私が一番お伝えしたいのは、「自分のお金は自分で運用・管理しましょう」ということです。あなたのお金を真剣に増やしてくれる人は、果たしてこの世の中にいるでしょうか?自分で真剣に働いて稼いだお金だからこそ、株式投資も自分で真剣にやらないと増やせません。自分の大切なお金だからこそ、他人に委ねず自分で運用・管理してください。そのためにも、必要なことを正しい手順で学ぶことが大切なのです。株式投資についてお聞きするつもりが、人生で大事なエッセンスをたくさん教えていただきました。投資が上手くいけば、仕事でもスポーツでもうまくいく人になれそうですね。今回はインタビューを受けていただき、本当にありがとうございました!前編を読む -

日本の金融・経済の流れから学ぶ、将来に向けた投資先は?|フェリス女学院大学 国際交流学部 齊藤直教授
皆さんは、これからの日本はどのような道を歩むと考えていますか?人にとっては、あまりポジティブな印象を持てないかもしれません。日本で生活していく以上、少しでも希望を見出し、自分の将来に期待を持てたほうがいいですよね。そこで、今回はフェリス女学院大学で主に経済史を研究されている、齊藤直(さいとうなお)教授にインタビューを実施。これからの日本が何が求められ何が必要なのか、日本の金融・経済史を踏まえつつ、日本の将来についてお聞きしていきます。日本の未来に希望を持ちたい方、日本経済をあらためて理解したい方は、ぜひ当記事をご参照ください。常に変化する世の中で、新たな一歩を踏み出すためのヒントが得られるでしょう。インタビュー日:2023年10月18日戦前・戦時中の金融史戦前の金融市場は世界トップだった?!先生は日本経済史を研究されていますが、具体的にどのような研究をされていますか?日本経済史は、文字通り日本の経済の歴史を指していますが、その研究対象の幅は広くなっています。その中で私は金融史を専門としており、特に1920〜1930年代の企業金融や資本市場を研究中です。今日に生きる私たちのイメージからすると、当時の日本は発展途上で、欧米に追いつけ追い越せという状況にあったと思いがちです。しかし、実際には、当時の日本の資本市場は非常に大きく、特に株式の売買高では圧倒的に世界トップだったんです。当時の米国はもちろん、1990年代の先進諸国と比較しても、上位に入るくらいの規模でした。このようなことから、当時の日本は資本市場中心の金融システムだったと先行研究で言われています。戦前、日本の資本市場は活発だったんですね。これだけ聞くと、当時の日本経済は十分に発展していたという印象を受けますよね。そこで売買高の中身を調べてみると、売買高の大部分が短期清算取引で占められていました。清算取引とは、今で言うところの先物取引を指しており、一定期間先に受け渡しを約束する取引手法です。しかも清算取引では差金決済が行われるのが通常でした。想像されるような、所有権の移転を伴うような取引ではなかったのです。さらに、取引された銘柄を調べてみると、1930年代にはたった3銘柄の売買高だけで短期清算取引全体の7割程度を占めていました。具体的な銘柄は、東京株式取引所新株・大阪株式取引所新株・日本産業旧株です。これに鐘淵紡績新株・帝国人造絹糸旧株などいくつかの銘柄を加えると、8割程度に達します。つまり、1930年代の日本の株式市場は、上記の限られた銘柄の短期清算取引のみで、世界トップの売買高を牽引していたと言えるんです。当時の金融市場は、私たちのイメージと全然かけ離れていますね。多くの人が想像する通り、資本市場は数多くの商品が高い流動性で取引されていて、妥当な価格が形成されているイメージがあると思います。戦前についても、頻繁に取引されている銘柄は限られますが、それらの銘柄については価格形成における情報の効率性が高かったのではないか、という意見もあります。当時から、他の投資家を抜け駆けして自分だけ儲けることは難しいという意味で、公平な市場という面はあったといえるかもしれません。とはいえ、たった数銘柄の売買で世界トップの資本市場だったと評価するのは、いささかの違和感を抱くのではないでしょうか。歴史研究にとって、地道に当時のデータを集めて検証することが重要です。例えば、当時の東京株式取引所の月報は国会図書館で閲覧できるので、足を運んで情報を入力することもあります。他にも、金融市場で今日と違う点はありますか?今日、ニュースや新聞で報道される株価は、1日の終値ですよね。投資をしていなくても、なんとなく終値が重要な情報であることはわかると思います。当時も同様で、終値は重要な情報でしたが、東京株式取引所の売買だと午前中の終値が重要視されていたんです。先ほど紹介した短期清算取引では、1日目の午後と2日目の午前という実質1日間を単位とした先物取引を行っていて、受渡に適用される株価が2日目の午前の終値でした。当時の投資家にとっても、短期清算取引が最も関心が高い取引方法であったため、午前の終値が1日の終値としての意味を持っていました。今ならスマホですぐに株価がわかりますが、当時の人たちが株価を見るには、「株式日報」を取る必要がありました。この日報を見てみると、午前中の終値が記載されています。この日報が夕方に配達されますので、投資家たちは夕方には午前の終値を知ることができたわけです。生活上の1日が終わるタイミングで、最も重要であった短期清算取引の午前の終値を知ることができたんですね。今日の金融市場が形成された背景戦前の株式市場は短期清算取引が中心でしたが、戦後はどのように変化したのでしょうか?株式市場についていえば、戦時統制と戦後改革を経て、取引所での清算取引は廃止されますので、戦前とは全く異なる特徴を持つ市場になります。それに伴って、証券会社についても大きな変化がありました。今日の証券会社といえば、全国に支店を構えている大規模な企業をイメージしますよね。ただ、これらのいわゆる大手証券会社は、戦時中の資本市場の変化に合わせて成長してきました。戦前の証券業の中心は、実は個人商店とでもいうべき小規模な業者が担っていました。先ほども申し上げたように、戦前の株式市場は短期清算取引が中心でした。そして清算取引には取引所集中義務があり、それを担うのは仲買人(後に取引員)と呼ばれる正式な資格を持つ証券業者でした。取引所での売買が認められる仲買人は、最も格式高い業者だったといえます。清算取引の売買高が大きかったこともあり、仲買人は大きな収益を得られます。例えば、東京都文京区の目白台に「小布施坂」という地名がありますが、東京株式取引所の仲買人だった小布施新三郎さんの邸宅があったことが由来となっています。つまり、個人商店と言えるくらいの規模でありながら、大量の取引を担っていたため、地名に影響を及ぼすほどの経済力を持っていたんです。戦前の証券業は個人商店のような業者によって担われていたんですね。では、何がきっかけで今日の大手証券会社が生まれてきたんでしょうか?戦時中、公社債の発行量が増加したことがきっかけです。戦時期には財政赤字の拡大に対応して国債の発行が増加し、国債以外にもさまざまな債券が発行されます。それら大量の債券を消化することが必要になるわけです。先ほど紹介した仲買人(取引員)は支店を設けることが認められておらず、1つの営業所しか持てなかったんです。これは大量の債券を売り捌くうえでは不利な条件になります。一方、今日の大手証券会社と言われる、野村證券・大和証券・SMBC日興証券は、元々公社債を取り扱う証券業者でした。それらの公社債業者は、支店開設を制約されておらず、実際に債券の売り捌きのために複数の支店を有していました。戦時期に大量の債券を投資家に売り捌くためには、全国に支店を構えている証券業者が優位です。必然的に、全国で公社債を販売できる証券業者の地位が高まって、営業所が1つしかない仲買人(取引員)に取って代わりました。そして戦後の大手証券会社へと成長することになります。証券業は、戦後の有力行が戦前から存在していた銀行業とは違う歴史を辿ってきたんですね。そうですね。ただ共通して言えることは、どちらも時代の変化に対応できた企業が生き残っていることです。経済がずっと安定して推移することはなく、どこかで必ず変化が訪れることは、ここまでお話した内容からも理解できるでしょう。戦後の日本経済の変化キャッチアップ型だから機能した銀行中心の経済システムでは、戦後の日本経済が発展したのは、どのような要因があったんですか?さまざまな要因があるのですが、1つ言えるのは銀行中心の金融システムですね。戦後の日本経済は、欧米先進国をモデルとしたキャッチアップ型の成長を実現しました。発展途上段階にあるうちは、海外に自国よりも進んだ技術が多く存在しますので、それを導入し、自国の市場に合うように調整することにより、自前の技術開発に伴うリスクを抑えながら成長することができます。海外からの技術導入に頼る場合、成長軌道はある程度明確になっているので、毎回異なる投資家から資金を集めるよりも、1つの銀行から継続的に融資を受ける方が、効率的に事業を成長させられます。銀行にとっても、企業と長期的な関係を築けば情報が蓄積されるので、融資におけるリスク判断もしやすくなります。このように、銀行を中心とした金融システムがうまく機能したことで、戦後の日本経済は大きく発展しました。銀行中心から資本市場中心の経済システムへ戦後の日本経済が成長できたのは、銀行の存在が大きかったんですね。ただ、今の日本経済は停滞している印象が強くなっています。現在の日本経済は停滞していると言われていますが、そう見えるのはキャッチアップ型で日本経済が十分に成長し、先進国の仲間入りを果たしたからです。先進国の仲間入りを通り越して、衰退する局面に入っていると感じてしまうこともありますが・・・。それはさておき、近年までに日本は技術力において世界のトップランナーとなり、他国からモデルにされる存在となっています。そこからさらに成長するには新たな1歩を進めること、すなわち新しい技術を開発することが求められます。ということは、研究開発への投資が必要不可欠です。当然、成功するかわからない不確実性の高い状況ですので、複数のプロジェクトに投資する必要があります。そのうち1つでも成功するプロジェクトが出れば万々歳というような状況です。このように多くのプロジェクトから勝者となるプロジェクトを選抜する過程を「ウィナーピッキング」と呼びます。つまり、今の日本経済はキャッチアップ型から、数ある投資先から当たりを選ぶ「ウィナーピッキング型」の経済に移行したということです。では、これからは何が日本経済を支えていくのでしょうか?「ウィナーピッキング型」の経済システムを支えるには、銀行よりも資本市場が適しています。なぜなら、これから大きく成長する投資先を見つけるのは、銀行よりも資本市場の方が得意だからです。キャッチアップ型の経済では大きな役割を果たした銀行ですが、何が成功するか不透明な状況で、多くのプロジェクトのなかから適切な案件を見つけ出して融資するのはとても難しいことですよね。それを踏まえれば、1980年代に金融自由化がおこなわれ、資金調達先が銀行である必要がなくなったのは、時代の流れとして自然でしょう。経済の変化に伴う働き方の変化時代の変化に合わせて、私たちの働き方も変化してきました。先生は今の働き方についてどう考えていますか?キャッチアップ型の経済では、ある意味、多くの企業の成長が約束されていたため、従業員の終身雇用が現実的でした。よほどのことがない限り定年退職まで雇用が約束されているから、人生設計もある程度立てやすかったでしょう。しかし、今日ではキャッチアップ段階を終え、ウィナーピッキングという特徴を持つ経済へと移行しています。どの企業が大きく成長するか、確かなことは誰にもわかりません。世間で「勝ち組」と捉えられている企業に勤める人のなかには、「自分はこれから伸びる企業を見抜いて、新卒の段階で就職した」と考えている人もいると思いますが、それはあくまで結果論です。ボタンの掛け違い1つで、「負け組」と捉えられる企業になっていたかもしれません。ひょっとしたら、倒産していたり、他者に買収されたりしていた可能性もあるでしょう。そう考えると、自分自身のキャリアや人生設計に応じて転職するのは、なんら不思議なことではなく、むしろ当たり前だと思います。そうしたことが起こり得ると想定しておくのが当然の世の中になったということでしょう。働き方の変化に合わせて、時間に対する考え方も変わっていますよね。いわゆる「Z世代」と言われる人たちは、自分の時間を大切にすると言われていますが、ここまでの話を踏まえたら当然ですよね。これからの世の中がどうなるかわからないから、将来のために自分の時間を作りたいのは、過去から現在までの経済の流れを踏まえると納得いただけるでしょう。自分自身への投資は手間や体力も必要なので、何かしらのしがらみに囚われず、自分の時間を守ることは、とても大事なことだと思います。これから私たち個人に求められるもの変化が激しくなる時代、最も有効な投資先とは?時代が変化したからこそ、求められるものも変わると思います。おっしゃる通り、「ウィナーピッキング型」の経済だからこそ、自分は何に時間を使うかが重要です。スキルを身につけるのか、資産運用を始めるのか、さまざまな選択肢があるでしょう。ここで重要なのは、「異時点間」の観点から考えることです。異時点間とは、文字通り異なる時点の間を指します。この異時点間での資金の配分は、金融の最も基本的な役割の1つです。投資で考えるとわかりやすいでしょう。例えば、投資信託を30年間運用する場合、30年後の自分に今のお金を渡していると言えます。逆に、将来のお金を今使うことも可能です。貸与型の奨学金で大学に進学したり投資家から資金を借りて起業したりするのは、将来の自分がそれを返済することになりますので、将来の自分からお金を受け取っていることになります。これが借金の本質的な考え方となります。つまり投資とは、異なる時点の自分とお金のやり取りをしているのです。「借金をする」というと、どうしても他者から借りるという発想になるわけですが、その先には将来の自分がいるわけです。いかなる場合にも、この「異なる時点の自分と」という視点は決して忘れてはならない点だと思います。それを踏まえて、先生にとっておすすめの投資先は何でしょうか?将来、何が起こるかわからないので、一般的な投資だと必ず何かしらのリスクは伴います。銀行預金だと銀行の倒産、金融商品だったら価格変動のリスクがありますよね。タンス預金しておいても盗まれてしまうかもしれません。幸い窃盗被害や銀行の倒産がなかったとしても、インフレが起こればタンス預金や銀行預金の実質的な価値は減少します。インフレを恐れて不動産に投資したとしても、土地の価格が将来どうなるかは不確実で、下落することもあり得ます。いずれの選択肢にせよ、あらゆる状況に対応できるとは言い切れません。だから私たちは、自分自身のお金を何に投じるか真剣に考えるわけですよね。では何に投資したら、あらゆる時代の変化に対応できるか。それは人的資本、すなわち自分自身の能力に投資することしかありません。どのように時代が変化しても、その変化を的確に認識し、その都度適応できる力を身に付けることで、新しい環境に応じた稼ぎ方をすればよいのです。資産運用をすることもちろん大事ですし、そこで蓄えた財産がいざという時に自分を助けてくれる、ということもあり得るでしょう。しかし、それだけで不確実性にあふれる将来に十分に備えることは難しいでしょう。やはり最も自分を助けてくれるのは自分の能力なのだと思います。その際、歴史を学ぶことは、ある意味私たちに勇気を与えてくれると思います。過去に起きた変化に対して、世の中はどう対応したのか知ることで、これからの変化を読み解くヒントが得られるでしょう。幕末の開国や明治維新にせよ、太平洋戦争や戦後改革にせよ、それにより社会のあり方は大きく変わったわけですが、人々はその変化に対応して、たくましく生き抜いてきました。決して現在だけが特別な状況ということはないと思います。新しいことを学ぶときのポイントそう考えると、歴史の学び方が大事になってきますよね。おっしゃる通り、歴史に限らず新しいことを学ぶときは、何を基準で学ぶかが大切です。たくさんの時間が残されている若い頃であれば、がむしゃらに学ぶというのもありだと思いますし、その経験自体が人生の糧になり得ると思うのですが、社会人になればなかなかそのような時間はないはずですから。その道の専門家から学ぶことが効果的ですが、その人が偏った考えを持っていたら、適切に学べない可能性があります。あるいは初めて学ぶからこそ、情報の非対称性も課題となります。そうであるからこそ、自分なりの目利きと申しますか、判断力を養っておくことが望ましいわけですが、そのためには日頃から幅広い意見に触れる機会を持っておくことが重要だと痛感します。年齢を重ねて、仕事でそれなりの責任も負うようになってくると、意識してそのための時間を作らなければならないなと感じています。私の場合、他の分野で活躍している同世代の話を聞くことが、意外と有意義な学び方だと感じています。コロナ前くらいの時期に、20数年ぶりに高校の同窓会が開催されたことがありました。私たちの世代は、高校を卒業した時点ではメールも携帯電話もなく、SNSで繋がることもできなかったので、少し大げさですが卒業は今生の別れであってもおかしくないというような感じだったんです。どの同窓会も、高校時代の名簿に記載された実家の電話番号に連絡が来て・・・、という形での開催でした。当然、ほぼ20年ぶりに再会したら、積もり積もった話をします。当然、各々違う道を進んでいるからさまざまな話が聞けますし、特に自分と違う意見や自分よりも深い考えに触れると、「そういう考え方もあるのか」と、学べることがたくさんあったんです。影響力のある人の話を聞くのも大切でしょうが、年齢など自分と条件が近い身近な人の話を聞くことからも、自分にとって大きなヒントが得られるように思います。少なくとも自分が学んでいることや考えていることを相対化するうえで効果的だったように感じます。同年齢の人だからこそ、良い影響が受けられるということですね。同じ経験は、私にもあります。経済史に関するお話を聞くつもりでしたが、これからの時代を生き抜くヒントをたくさんいただきました。今回はインタビューを受けていただき、本当にありがとうございました!





