-
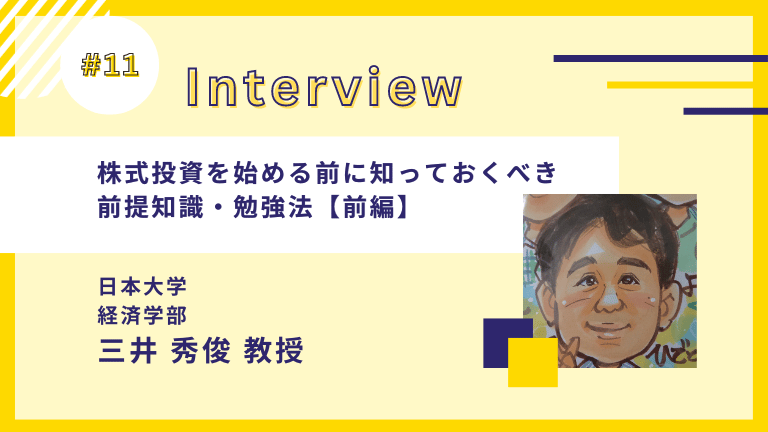
株式投資を始める前に知っておくべき前提知識・勉強法【前編】|日本大学 経済学部 三井秀俊教授
積立投資にある程度慣れてくると、「そろそろ個別株に投資してみたい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。個別株投資には、自分が気になった銘柄を選んで投資できる魅力があります。しかし、投資の方法は人によってさまざま。自分に合った方法がわからず、始めたくても始められないと思っている方もいらっしゃるでしょう。そこで、HonNeでは日本大学経済学部で主に金融データ分析を研究されている、 三井 秀俊(みつい ひでとし)先生にインタビューを実施。先生の研究テーマを踏まえつつ、株式投資の学び方を前編・後編に分けてお聞ききします。これから自分の投資方法を見つけたい方、投資に関する知識を深く学びたい方は、ぜひ当記事をご参照ください。インタビュー日:2023年11月2日株式投資とは何か?始める前の準備 デューク大学 (客員研究員)の時の様子株式投資を始めるとは何か?2024年から新NISAがスタートするように、株式投資を始める人が年々増えていますが、先生はどのような印象を持っていますか?日本政府は国民の資産が金融市場に流れるよう推進していますが、政府が推進しているからと言って、安易に株式投資を始めて欲しくないと思っています。同時に、「株式投資は簡単」と主張する広告や本を見て、真に受けて始めてしまう人がいることも、個人的に心配をしています。株式投資とは、自分が頑張って稼いだお金を使います。他者の意見に影響されて、十分な知識を身に付けずに株式投資を始め、損をするから「株式投資は怖い」というイメージが付いてしまいます。そのため、最初にやるべきことは、株式投資とは何か、どのように行なったら成功するのか、上手くいっている人から話を聞くことです。具体的に、誰から聞けばいいですか?私がおすすめするのは、自分にとって信頼できる人・本音を言い合える人で、自分のお金で実際に株式投資をしている人から聞くことです。親しい間柄だと、相手は本当の株式投資について話してくれます。ご自身も相手の性格をある程度理解した上で聞けるので、相手が嘘や誇張しているかを判断もしやすくなります。まだ距離感がある人に聞くと、「俺はこの方法で儲かった!」といった自慢話を聞かされるだけでしょう。大切なのは、上手くいったことはもちろん、失敗談も聞くことです。失敗談を聞くと、安易な考えで始めては、株式投資は儲からないことが理解できます。もし身近な人で株式投資を続けている人がいなかったら、どうすればいいですか?身近な人の知り合いから、株式投資を行なっている人を紹介してもらってください。その際、謙虚な気持ちで頭を下げるような姿勢で聞きに行くことが大切です。「株式投資で儲けたいから教えて欲しい」といった、安易な気持ちで聞きにいくと、相手も話す気がなくなって、本当のことを教えてくれないでしょう。その際、話した内容をメモするために、必ず筆記用具とノートも持参してください。株式投資で成功している人が書いた本(例えば、マーク・ミネルヴィニ『株式トレード 基本と原則』PanRolling)には、「本気で株式投資を始めたい人は、筆記用具とノートを持ってきて話を聞きに来る」と書いてあります。株式投資ではありませんが、興味深いエピソードがあります。私のゼミ生に、私のアドバイスを聞き、A4ノートを持って就職活動をしていた学生がいます。もちろん、相手の話をメモするために持って行っているわけですが、何と、リクルーターや人事部の方がそのノートに色々と重要なことを書いてくれたと言うのです。人によっては、図まで描いて詳細に説明してくれたそうです。株式投資に限らず、何かしら教えてもらうときに大事なことですね。真剣な姿勢で話を聞く態度を示せば、相手はもっと教えてあげたいって気持ちになりますね。真剣に聞くか、とりあえず聞いてみようか、その姿勢の差は株式投資に限らず、あらゆる物事の結果に大きく影響します。その道のプロの人が話す内容は、本や記事の内容では絶対に知れないものですから、素直に聞き入れる姿勢を持つことから始めましょう。合わせて、事前に予備知識を勉強しておけば、相手も何を話せばいいか判断しやすくなりますし、本気度合いも伝わります。自分が理解できたことと、そうではないことが整理されるので、具体的に聞きたいことも出てくるはずです。何の準備もせずに聞きにいってしまうと、相手も何から話せばいいか、混乱させてしまいます。株式投資を続けることは仕事やスポーツと同じ!株式投資を始める第一歩を話してくれましたが、株式投資を続けるために一番必要なことは何でしょうか?物事を進めるプロセスを理解していることが一番大事ですね。仕事やスポーツ、受験勉強など、なんでもいいので何かしら努力してうまくいった経験を持っている人は、株式投資も努力が必要で時間がかかることを理解してくれます。合わせて、何を聞くべきか判断もできるので、こちらとしても教えやすいんです。そうではない人は、手取り足取り教えてもらおうとするので、教える気もなくなります。極端に言えば、事前に予備知識を学んでいなくても、何か物事を身に付けるには時間と努力が必要なことを体感していれば、株式投資を続けるために必要なことも理解できると思います。もし、何か1つのことを続けた経験がない人が本気で株式投資を始めたい場合は、何から始める必要がありますか?私の場合、そもそもの勉強の仕方やノートの取り方を教えて、知識の身に付け方や情報を整理する方法を理解してもらいます。そうでないと、いくら株式投資のことを勉強しても自分の身にならないからです。例えば、何かスポーツを始めた場合、最後まで試合を続けられる能力と体力はどんなスポーツでも必要ですよね。たまに面倒くさがる人がいますが、「株式投資でうまくいきたいなら、まずは学び方を学びなさい」と、何が何でも理解してもらいます。方法論で株式投資が上手くいくとは限らない 対外経済貿易大学の中国語語学研修引率の様子先生のお話を聞いて、株式投資は安易に手を出せるものではないことが理解できました。続けられる投資家になるには、実際どれくらい時間がかかりますか?少なくとも、2〜3年は見越したほうがいいですね。本やインターネットを見ると、「1年で何億円も儲かった」といった情報に目が行きがちですが、ほとんどが偶然なので長続きしないそうです。そういった人は、儲かったお金をすべて失っている人が多いそうです。株式投資の目的はいくら儲けるかではなく、いくら残せるかです。だから、コツコツ地味に続けているほうが、最終的に大きなお金を残せます。そのため、株式投資では最初の心構えと準備がとても重要です。どれだけ真剣な気持ちで、続けるための準備を整えているかで、株式投資の結果は大きく変わってきます。仮に100%儲かる投資手法を教えたとしても、実際に理解して実行できる人は1割もいないと思います。絶対に儲かる投資手法を知ったとしてもですか?はい。これは、株式投資に限らず、何か新しいことを始めて、成果を出すまでの本質的な考え方だと思います。みなさん、どうやったら上手くいくか方法論を知りたがりますが、実際に実行できるかどうかは自分次第です。確実な方法論を知ったから、上手くいくのではありません。例えば受験勉強の場合、有名大学に合格する方法はある程度確立されています。その方法を最後まで実践できる人が少ないから、有名大学に合格する人が限られるんだと思います。何事も、ある程度のレベルまで行く方法は確立されていて、そのハードルもそこまで高くありません。一部の人が上手くいくのは、上手くいく方法を最後までやり続けたからです。だから、仮に絶対儲かる投資手法を知ったとしても、真剣にやる心構えと身に付けるための準備を徹底しないと、続けることは難しいでしょう。どのような方法論を選ぶかが重要ではなく、本気でやり続ける姿勢が大前提と…。あと、道具等にもこだわって欲しいです。100円ショップで売られている包丁よりも、プロが使っている包丁を使ったほうが食材を美味しく切れ、料理が上手くできるように、株式投資でもプロが読んでいる本や記録の付け方を学ぶことにこだわってください。スーパーで売っているテニス・ラケットで試合に出るプロのテニス選手がいるでしょうか。小さなメモ帳を使用して、上手くいくわけがありません。私個人の意見ですが、スマートフォンの画面で見ても株式投資は上手くいかないと思います。プロは大きな画面を使い、しかも複数の画面を準備しています。株式投資はいろんな情報を見て判断することが多いので、画面が小さいと見れる情報が限られて、効率が悪くなるからです。チャート等も小さい画面では、ただ見てるだけで何もわからないともいます。社会人の方でスマートフォンを使用して、まともな仕事はできないことは理解して頂けると思います。スマートフォンは通信手段などごく限られた分野で使うものです。プロのカメラマンがスマートフォンで写真は撮りませんし、我々研究者もスマートフォンで論文は書きません。私の授業である学生がスマートフォンでノートを取っているのを見て、腰を抜かしたことがあります。そのような学生の成績は察して知るべしです。株式投資では、断片的に入ってくる情報を効率よく集めて整理することも求められます。そのため、情報の集め方や整理する方法も、プロの投資家や経験者から学ぶのがおすすめです。もうみなさんおわかりだと思いますが、株式投資で大事な要素は仕事やスポーツなどと共通します。なので、「株式投資」だからと言って変に身構える必要はありません。株式投資を続ける考え方が、何ら特別ではないことがわかって目から鱗でした。むしろ「自分でも株式投資は続けられる!」と、勇気をいただいた気分になっています。株式投資を知るために読みたい本まず株式投資の心構えが学べる「古典」を読むそれでは、続けられる投資家になるために、最初に何をすべきか教えてください。株式投資について本当のこと知りたいなら、まずは株式投資の世界で「古典」と呼ばれる本を読んでください。世に出ている株式投資の本は、そのほとんどが〇〇業界の立場を配慮して書かれているため、私たち個人投資家にとってあまり参考になりません。私が知っている限り、初めて個人投資家のために本を書いたのは、林輝太郎(はやし てるたろう)さんだと思います。現在でも林輝太郎さんの本は、ECサイトはもちろん、大きな本屋さんでも必ず株式投資コーナーに置かれています。 引用:Amazon「林輝太郎相場選集〈1〉相場金言集」何冊も出版されていますがどれか1冊でもいいので、これから株式投資を始めたい方は、ぜひ林輝太郎さんの本を手に取ってみてください。他に先生が最初に読んで欲しい本はありますか?もう1つ絶対読んで欲しいのは、板垣浩(いたがき ひろし)さんの『自立のためにプロが教える株式投資』(同友館)です。初版は1990年ですが、今でも増刷されているほど、多くの投資家から支持を受けています。 引用:Amazon「プロが教える株式投資: 自立のために」この本は株式投資の心構えや姿勢が書かれており、良い意味で株式投資の現実、厳しさを教えてくれます。本当に株式投資で儲けたいなら、アマチュアではなくプロとして株式投資に臨む必要があるというメッセージが込められています。初めて株式投資の本を読む方からすると、知りたいことが書かれていないかもしれません。しかし、ある程度経験している方にとっては、趣味や片手間といった考え方では甘いと痛感し、身が引き締まる思いを抱くでしょう。そのため、林輝太郎さんと板垣浩さんの本を読むだけでも、株式投資に対する心構えが変わると思います。1冊2,000円程度ですが、1万円以上払ってもおかしくないくらい価値がある本なので、ぜひ読んでみてください。先ほども申し上げたように、株式投資は自分の大事なお金を使います。そのため、最初は腰を落ち着けて勉強する時間を作ることが大切です。心構えを理解してから投資売買の原則が学ぶ先ほど紹介していただいた本は、株式投資の心構えが学べるということですが、その後はどうすればいいですか?株式投資を真剣にやる必要があると理解できたら、株式トレードのパフォーマンスを競い合う「USインベスティング・チャンピオンシップ」の優勝者である、ミネルヴィニさんの本がおすすめです。 引用:Amazon「株式トレード 基本と原則 (ウィザードブックシリーズ) 」 引用:Amazon「ミネルヴィニの成長株投資法 ━━高い先導株を買い、より高値で売り抜けろ (ウィザードブックシリーズ) 」日本語に翻訳されているのは4冊あって、その中でも、前に紹介した『株式投資の基本と原則』と『ミネルヴィニの成長株投資』(PanRolling)の2冊は必ず読んでください。投資対象となる銘柄の条件やリスク管理など、どのような投資手法を行なう場合でも必要な知識が書かれています。ちなみに、プロの投資家といえばウォーレン・バフェットが有名ですが、彼の本を読むのはどうなんですか?個人的な意見としては、ウォーレン・バフェットさんの本は個人投資家にとって、必ず読むべきであるとは思っていません。もちろん、株式投資の本質や哲学に関して、学べることは沢山あると思います。ただ、私たち個人投資家の資金は数百万円、多くても数億円程度ですよね。一方、ウォーレン・バフェットさんは、何千億・何兆という巨額のファンドを数十年単位で運用しています。投資金額と期間が違えば、株式投資の考え方も当然変わります。そのため、彼の書いた本は機関投資家や大口投資家には役立っても、個人投資家にはあまり参考にならないと思います。個人投資家でも、数十億・数百億円を運用している方には参考になるでしょう。地元の八百屋さんと全国展開するスーパーマーケットでは、経営手法は異なります。同じことは、投資手法でも当てはまると思います。このような観点からも、株式投資を勉強するときは、個人投資家の視点に合わせて書かれた本を読むのがおすすめです。ここまで教えていただいた事だけでも、投資に対する考え方が大きく変わると感じました。とはいえ、私が紹介した本を読んで理解できたとしても、株式投資の全体の進捗度合いとしては、せいぜい20%~30%程度です。ここから先は、模擬売買をやってみましょう。証券会社が提供している模擬トレードツールを使って、半年〜1年程度は続けてください。スポーツだと、何日ものトレーニングや多くの練習試合を重ねてから、初めて本番の試合に臨みますよね。株式投資も同様で、いきなり自分のお金を使うのではなく、模擬売買を通じて株式投資をする感覚を養いましょう。ここまでのお話だけでも、株式投資に対する考え方がガラッと変わると感じました。模擬売買以降のお話は、後編でお聞きしたいと思います。株式投資の学び方が知りたい方は、ぜひ後編もご一読ください。後編に進む -
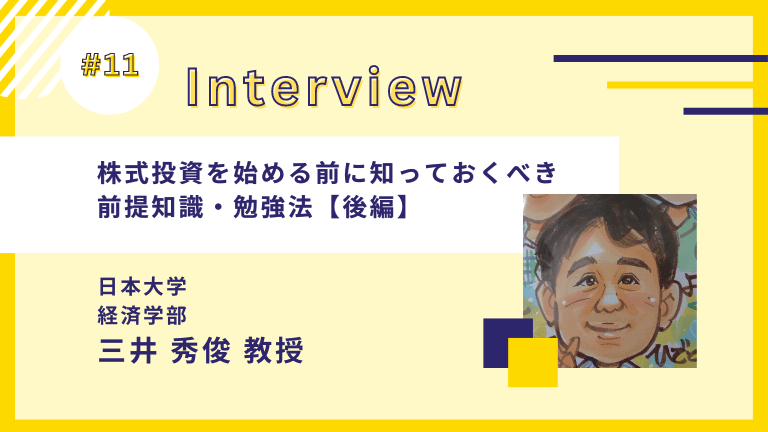
株式投資を始める前に知っておくべき前提知識・勉強法【後編】|日本大学 経済学部 三井秀俊教授
当インタビュー記事は、日本大学で主に金融データ分析を研究されている 三井 秀俊(みつい ひでとし)先生からお聞きした、株式投資の学び方を前編・後編に分けて掲載しています。前編では、株式投資を始める前の心構えや最初に読みたいおすすめの本を解説しています。当記事の後半では、模擬売買や本番の投資で知っておきたいポイント・注意点をまとめています。「これから株式投資を始めたいけど、何から始めたらいいかわからない」という方は、ぜひ前編をお読みになった上で、後編をご一読ください。※前編はこちらへインタビュー日:2023年11月2日模擬売買して投資する感覚を身に付ける 三井秀俊ゼミ:東京証券取引所見学の様子超重要!記録する習慣を身に付けよう模擬売買を始める際、何が一番大事ですか?自分が実行したこと等を記録する習慣を身に付けることです。売買した銘柄はもちろん、日付・売買価格・売買した理由をしっかり「書いて」記録してください。余裕がある方は、日経平均や米ドル・円為替レート等も書いておくと良いと思います。記録する習慣が付くと、自分が上手くいくパターンと失敗するパターンが見分けられ、銘柄の選び方や売買を決める土台になるんです。ほとんどの個人投資家は、この記録の作業をやっていません。株式投資で上手くいっている人が書いた本には、必ず売買を記録していること、また、チャートを手書きで記録していることが書かれています。ミネルヴィニさんの本にも、記録することの重要性が強調して書かれています。私の仮説ではありますが、カルテを書く習慣がある医師は、株式投資が上手くいく傾向があります。患者の身体状況を1人ひとり記録することと、銘柄ごとに重要なことを記録することが共通することから、日々の記録が大事なことをすぐ理解できるからです。習慣化されているので面倒くさいとか言う方はほとんどいません。このような観点からでも、模擬売買を通じて記録する習慣を身に付けることは、株式投資が上手くいくための必須要素だと断言できます。記録を付ければ、自分に合った投資手法は見つけられるのでしょうか?「こういう手法で投資すれば儲かる」と謳っている投資手法を実践したら、確かに上手くいく可能性はあります。ただ、特定の投資手法は、個人の性格が大きく影響することを理解しておいてください。例えば、長期的に運用する投資手法は、短期ですぐに売買する人からすると我慢できないでしょう。逆に、短期的に売買を繰り返す投資手法だと、気長に運用したい人にとっては抵抗を抱くかもしれません。そのため、模擬売買で記録する習慣を身に付けることは、投資における自分自身の性格を理解して、相性の良い投資手法を見つけることにも繋がります。記録は物事を上達させるコツ!有名スポーツ選手も実践している心構えを知ることはあくまで前座で、記録を取ることが投資で一番重要な作業なんですね。記録を取ることは、株式投資に限らず、あらゆる物事に共通して重要な作業です。サッカーの本田圭佑や野球の大谷翔平も、毎回の練習・試合内容をしっかり記録し反省しているそうです。何事もトップレベルに上り詰める人は、何かしら記録する習慣を身に付けています。記録したことを見返すことで、自分が何を考えているのか、何を大事にしているか確認できるからです。自分が積み重ねてきたものを振り返って、失敗しても次はどうするか考えられるから、「もっと続けよう」という粘り強さが芽生えてくるんじゃないでしょうか。ただ、ここまで言っても実際に記録し続けられるのは、10人中1人くらいでしょう。残りの9人は聞いて終わってしまいます。ここが重要です。ほとんどの人が実践しないからこそ、自分はちゃんと記録しながら投資を続けられるかが、株式投資で結果を残せる大きな分かれ目となります。先生も実際に記録を続けてきたからこそ、記録の大事さを確信されているんですね。ちなみに、他にも記録することが大事な理由はありますか?記録することが習慣化すれば、冷静に投資判断しやすくなり、感情的に大きなリスクを取ることも避けられます。感情的になりやすい人は、冷静に判断するための時間を取っていないことがほとんどです。記録することで一旦冷静になり、株価の一時的な値動きに惑わされず、自分がどのような売買戦略にしたがって投資しているか確認できます。個人投資家は、文字通り「個人」で投資する人です。職場の先輩・上司のように、失敗を指摘・修正してくれる人がいません。ということは、自分が実行したことが上手くいったのか失敗したのか、すべて自分自身で判断して修正する「自己管理能力」が必須です。この自己管理能力の大事さって、組織の中で仕事しているとなかなか気付けないと思います。上司や先輩のおかげなのに、「自分が頑張ったから今の自分がいる」と考える人が意外に多いからです。特に、大きな組織に属している人ほどその傾向が強いです。そのため、スポーツや受験勉強、国家試験、個人事業主の経験がある人だと、自己管理の重要さと大変さを理解しやすいでしょう。実際にお金を投じて「土壇場の自分」を知る模擬売買で記録する習慣が出来たら、やっと本場の投資でしょうか?はい。本番の投資ができる準備が整って、株式投資で必要なことの50%まで進んだと言えます。でも、ここからが大変なんです。模擬売買と違って本番の株式投資だと、「違う自分」が出てきます。自分の大切なお金を使っているから、売買する感覚が全然違うからです。模擬売買なら購入した銘柄が50%下落しても気になりませんが、本番だと5%下落しただけでも絶望するでしょう。夜、眠れないこともあるでしょう。人によっては、保有している株が10%下落したら、二度と株式投資はしない、株式投資はギャンブルだと思うかもしれません。ここが、模擬売買との大きな違いであり、越えなければならない壁になります。現実には、一か月で10%以上の上昇・下落は株式市場ではザラにあります。株式投資に関してメンタルに関する本が多く出版されているのもうなずけます。方法論だけでは十分でないことがここからも理解できると思います。ここで、多くの個人投資家は、株式市場から退場することになります。そのため、実際に自分のお金を使った株式投資を始めたら、下落したときの対処方法を身に付けていきましょう。ここがアマチュアとプロの違いです。実を言うと株価の値動きは、一定のパターンの繰り返しが多くみられます。この感覚が体感できれば、下落時の対処方法が見出せて忍耐力が付き、株式投資を続けるモチベーションも保てます。そのためにも、模擬売買で記録する習慣を身に付けることが大事なのです。どの銘柄を選んでいつ売るか、株式投資の醍醐味は最後に控えている 三井秀俊ゼミ:卒業式の様子本番の投資を始めるためにも、どの銘柄に投資するか選ぶ必要がありますが、具体的にどうすればいいでしょうか?ミネルヴィニさん本に、選択する銘柄の最低条件が書かれているので、それらは必ず守って投資してください。株価の値動きは、銘柄によって異なります。一方、人によって投資の仕方も違いますよね。ということは、自分にとって相性が良い値動きをする銘柄があるということです。模擬売買の時点から、自分と相性が良い銘柄を意識しながら銘柄選択をすれば、上手くいく可能性が上がるでしょう。ちなみに、銘柄選定の仕方を身に付ける際の注意点は何でしょうか?いきなり何銘柄も手を出さず、まずは1銘柄だけ選んで売買してください。仕事・スポーツ・料理でも、まずは1つのことをとことん極めた方が、結果的に上手くなりますよね。株式投資も同様で、まずは1銘柄の株価の値動きや事業内容、決算時期など、関連情報を網羅できるまで極めてください。それが出来たら、他の銘柄に手を出しても良いでしょう。「いつ売るか」の見極め、損失を抑え利益を残していく銘柄選定では、自分にとっての得意銘柄を作ることが重要なんですね。あとは、投資した銘柄をどのタイミングで売るかでしょうか?はい。「いつ売るか」とは、ベストな株価で売却できるのはもちろん、損失を抑える「損切り」も含まれます。どれだけ上手くいっている投資家でも、時には失敗します。ということは、損した分を取り戻せないと、株式投資で利益を増やし続けられません。ほとんどの個人投資家は、ちょっと儲かっただけで売ってしまいます。もしくは売るべきタイミングを逃して、そのまま持ち続けて大きな損失を出しています。実際にチャート見たらわかりますが、株価の値動きは一定のパターンを繰り返しているので、長期的に保有しても永遠に上がり続けることはありません。そのため、いつ売るかを見極められて、初めて中・長期的に株式投資を続けられる投資家になります。あとは、別の投資手法を試したり他の銘柄に投資したりして、時には失敗しつつも、少しずつ利益を増やし続けていきましょう。人気を集める投資信託とロボアドバイザー、先生の意見は?ここまで株式投資に関するお話を聞いてきましたが、投資家の中には投資信託を運用したい人もいます。個別銘柄がわからないから投資信託に走る人が多いですが、私からすると投資信託はあまりおすすめしません。長期的に見て、投資信託で利益を得ている人がほとんどいないためです。もし投資信託が気になるなら、リチャード・エリス『敗者のゲーム』(日本経済新聞社)という本を読んでください。この本には、投資信託はどういうものか丁寧に書かれており、投資信託における「古典」に相当します。投資信託に投資するかは、『敗者のゲーム』を読んでから判断することをおすすめします。敗者のゲームというタイトルには、どのような意味があるんですか?敗者のゲームとは、自分のミスを極力減らせば勝てるゲームを指します。例えば、テニスで実力が拮抗している選手同士が試合をすると、相手より素晴らしいショットを打つのではなく、ミスを減らすことが勝利に繋がるということです。下手同士の場合には、ポイントはほとんど相手のミスによるものです。投資信託もテニスと同様で、ファンドマネージャーの実力や得られる情報に大きな差はなく、間違った投資判断を下したファンドが損をする、敗者のゲームとなっています。どうしても購入したければ、株価指数連動型ETFぐらいでしょうか。投資信託を選ぶのも個別銘柄を選ぶのと同じぐらい労力を使うと思います。ちなみに、ロボアドバイザーはいかがでしょうか?一見、ロボアドバイザーやAI投資を利用したら、簡単に儲かるような印象を受けますが、そのようなことはあり得ません。みなさん意外と誤解されていますが、株式市場は売りたい人と買いたい人がいるから成立します。言い換えたら、これから株価が上がると考える人とこれから株価が下がると考える人がいるから、価格が決まって売買できるのです。経済指標が株価を動かしているわけではありません。あくまで株式投資は、商取引の一形態に過ぎません。つまり、ロボアドバイザーやAI投資を利用する人が増えると、同時にそれを逆手に取る投資家が出てきます。それらに使用されているアルゴリズムの戦いになるかもしれません。今はアドバンテージがあっても、いずれは無くなるものも出てきます。また、今度はどのロボアドバイザーやAIを選択するかの問題に直面します。個人投資家にそれらの判断ができるでしょうか。投資信託・ロボアドバイザー・AI投資、いずれにしても利用する際の注意点がありますね。そのため、私が一番お伝えしたいのは、「自分のお金は自分で運用・管理しましょう」ということです。あなたのお金を真剣に増やしてくれる人は、果たしてこの世の中にいるでしょうか?自分で真剣に働いて稼いだお金だからこそ、株式投資も自分で真剣にやらないと増やせません。自分の大切なお金だからこそ、他人に委ねず自分で運用・管理してください。そのためにも、必要なことを正しい手順で学ぶことが大切なのです。株式投資についてお聞きするつもりが、人生で大事なエッセンスをたくさん教えていただきました。投資が上手くいけば、仕事でもスポーツでもうまくいく人になれそうですね。今回はインタビューを受けていただき、本当にありがとうございました!前編を読む -

国のお金の使い方を見極めるには?財政の理解を深めるポイントも解説|京都府立大学 公共政策学部 三宅裕樹准教授
財政は、私たちの生活を良くするために重要な役割を担っており、ニュースでも日々取り上げられています。しかし、財政がどのようにおこなわれているか理解するのが難しく、自分とはあまり関係ないと思う方もいらっしゃるでしょう。そこで、HonNeでは京都府立大学で主に財政学を研究されている、 三宅裕樹(みやけ ひろき)准教授にインタビューを実施。先生の研究テーマに触れつつ、財政を見るためのポイントを解説していただきます。当記事を読めば、財政の見方や自分との接点が理解でき、日々のニュースを読み解く力が身に付けられるでしょう。インタビュー日:2023年10月12日財政を理解するためのコツ財政が持つ3つの役割と3つの見方財政は重要だと理解しているものの、難しい印象もあります。財政にはどのような役割分担があるのですか?大きく3つに分けられます。1つ目は中央政府です。北海道から沖縄まで、47都道府県を統括して財政を管理しています。イメージとしては、いわゆる永田町・霞ヶ関が中央政府に当たります。2つ目は地方自治体です。各都道府県・市町村ごとの財政を管理します。3つ目は、社会保障基金です。年金や医療など特別な基金を積み立てています。これら3つの財政に、私たち国民の税金が行き渡ります。具体的には、所得税であれば中央政府、住民税なら地方自治体、年金は社会保障基金に振り分けられています。私たちが納めている税金がどこに行っているか把握できると、イメージしやすいですね。では、私たちの資産運用という観点からは、財政の動きをどのように見たらいいでしょうか?こちらも3つ挙げられます。1つ目はマーケットを規定する財政です。財政では事前に予算を決めますが、その使い方は日本経済全体の動向に大きな影響を与えます。また、予算の使い方によって、盛り上がる業界もあれば冷え込む業界もあります。2つ目は、投資ライバルとしての財政です。GPIFや大学ファンドなど、私たち個人投資家と同じように、政府自身も大きなお金を運用しています。どのような考え方で投資先を選んでいるか理解しておくと、ご自身の投資判断で役立てられます。3つ目は投資対象としての財政です。中央政府は国債、地方自治体なら地方債、他にも財投機関債など、各部署で借金をしています。そのため、私たちが直接的に投資して財政運営に関わることも可能です。財政が難しいと感じる原因今までは1つ目の見方が強い印象でしたが、投資家として活動するなら2つ目・3つ目の見方も重要ですね。おっしゃる通りです。どの立場で見るかによって、財政の見え方は変わってきます。2つ目は資産運用する主体、3つ目は投資する対象として財政を見るので、金融の側面が強くなっています。なので、投資家としては比較的馴染みやすい見方と言えます。1つ目は、金融というよりも財政学の見方になってきます。政府がどのようにお金を使うのかを決める際には、基本的に金融の発想とは大きく異なります。なぜなら、お金を儲けようという発想で使っていないからです。財政は日本全体を良くするため、困っている人を助けるために運営されています。社会をどうやって安定させるのか、格差を減らすことができるのか、狭い意味での経済とは違う視点で考える必要があります。つまり、全く逆の発想なんですよ。儲けることと社会を良くすることは全然違いますよね。このように財政には2面性があって、場面に応じて考え方を切り替える必要があります。財政は難しい印象がありますが、その原因は金融の視点から関わる要素があるからなんですね。では、投資家として関わる場合、具体的にどこに注目すればいいでしょうか?私たち個人投資家からすると、何百兆円ものお金を動かす中央政府には太刀打ちできないですよね。だから財政の動きに合わせて、「財政がこれからこう動くのなら、世の中はこうなるのでは?じゃぁこの分野に投資しよう。」という発想で投資するのは、1つの考え方として挙げられます。財政の動きがわかれば、1歩進んで自分自身の投資判断が下せます。財政のことを理解するのは、投資する上で大切なことだと私は思います。財政は、どうしても動きが遅いんですよ。学校でも学んだように、国民の税金をどう使うかを決める際には、あらかじめ国会や地方の議会を通す必要があります。通過しても官僚や公務員たちが色んな手続きをおこなって動くので、時間のラグが生じます。この時間のラグを先取りして、どこに投資するか考えることは有力な投資行動になります。国の借金に対する考え方借金が多いことは良くないこと?財政では国債・地方債などを通じて借金をしていますが、よく聞く意見として「日本は1人当たり1,000万円も借金している」という意見があります。この意見に対して、先生はどのような見解を持っていますか?さまざまな意見があるので、正直一概には言えません。しかし、少なくとも1つ知っておいて欲しいのは「ただ借金があるのか?」ということです。現在、日本には約1,000兆円の借金がありますが、そのお金は何に使われているでしょうか?橋や道路などインフラを作ったり、公営施設を運営したりするために使われていますね。つまり、日本には借金があると同時に資産もあるわけです。この話は、私たちの家計にも当てはまります。例えば、住宅ローンも一種の借金ですが、ただ借金している訳ではないですよね。住宅ローンを組むことで、マイホームという資産が手に入っています。したがって、借金だけ見るのではなく、その裏側にどのような資産が作られたか見ることも大切です。確かに、民間企業の貸借対照表も資産と借金を合わせて記載していますよね。ただ、借金と資産を同時に見るには、その資産が売却できる前提があります。じゃあ「橋や道路を転売できるか?」というと、個人や民間企業と同じように考えることはできません。例えば、道路を売却する場合、すべて買い取ってくれるほどの買い手がいるとは限りませんし、外国人投資家に買われると安全保障面での問題を考慮する必要があります。国の資産は国民が使うために作られているため、個人や民間企業のように単純に売却できるものとして見れない側面もあるのです。いわゆる担保の考え方が、財政では当てはまらないということですね。財政だからこそ考えられる、もう1つの考え方実はもう1つ、「そもそも国の借金って大したことないんじゃない?」という考え方があります。例えば、10兆円分の20年国債を発行した場合、本当に20年後に返す必要があるかというと、同じ金額の20年国債を発行して先送りすることが可能です。このような借金の先送りを「借換債」と言いますが、同じことは個人や民間企業ではなかなか政府のようにはできません。個人はいつか必ず死にますし、民間企業も永続性が求められるとしても絶対倒産しないとは限りません。ただ国の場合は、ちょっと不謹慎ですが国民がいる限り返済元である税金は集まります。その気になれば、一気に増税することも可能です。そのため、国債を繰り返し発行して永久に引き継ぐなら、実質的に返す必要がないとも考えられるわけです。このような考え方から、国の借金の大きさは、そこまで大した問題じゃないという意見も見受けられます。国が存在し続けている限り、借金を繰り返せば実質的に存在しないと…。ただ、借換債を何回も続けられるかというと、毎回同じ利子で借りれるとは限りません。例えば、最初は1%で借りれたのに、20年後は日本のマーケットが落ち込み、日本政府の信用度が下がっていると利子が3%に上がるかもしれない。つまり、将来のマーケットや日本政府の信用度がどうなるかわからないので、本当に同じ条件で借換債が発行できるとは限りません。もし出来なかったら、返済するために私たちの税負担が跳ね上がってしまいます。借金の大きさよりも使い方がポイントそもそも、なぜ国債・地方債を発行するのか?国債や地方債は私たち国民の税金で返済されますが、そもそもなぜ国債・地方債を発行する必要があるんでしょうか?時間のラグを埋めるためです。例えば、コロナ渦で日本社会が大きく混乱し、その対策として何十兆円という例年にはないお金が必要になりました。そのお金を増税すれば集められるかと言うと、混乱の最中では現実的ではないですよね。そこで、とりあえず国債・地方債を発行すれば、今困っている人を助けてコロナ渦を乗り越えることが可能です。もちろん返済する必要があるので、混乱が収まれば将来的に税金を増やして徐々に返済していきます。つまり、お金を使うタイミングとお金を集めるタイミングのラグを埋めることが大切で、その手段として国債・地方債が重要なんです。例えば、東日本大震災の復興で必要だったお金は、国民全員で負担しようということで復興増税が実施され、震災の後しばらくしてから少しずつ返しています。なので、コロナ渦で発行した国債・地方債の返済も、何かしらの形で増税されて少しずつ返していく流れになるでしょう。金額の大きさよりも健全な使い道が重要そう考えると、国を運営するために国債や地方債の存在は重要ですね。ただ注意したいのは、発行された国債・地方債で集めたお金が健全に使われるかどうかです。本当にコロナで困った人たちに使われたか、使われたとしても必要以上に使っていないか見る必要があります。お金の使い方と規模が理にかなっていれば、国債を発行する、そして将来私たちが税金で負担することも納得しやすいでしょう。日本の財政には、少子高齢化や安全保障などいろんな課題が挙げられます。そのような課題に対して、約1,000兆円の借金を納得した使い方ができていれば、そこまで大きな問題にはなりません。もし借金が膨らみ続けていることを問題視するなら、歯止めをかける仕組みがしっかり機能していればいいでしょう。つまり、国のお金の使い方に対して国民全員が納得できているかが、大きな問題でないかと考えています。現状、国民がちゃんと理解できないまま一部の偉い人が一方的に予算を決めたり、無駄な使い方が見つかってもなかなか修正しなかったりする部分があると、私は感じています。なので、本当に大事なところに予算を振り分けたり、無駄だった使い方が見つかったら軌道修正したりする議論を、積極的におこなうことが1番の課題だと考えています。借金自体の大きさではなくその使い方、財政運営に対するガバナンスが効いているかが、大きな課題ということですね。とはいえ、選挙や支持率調査の回答だけで、財政運営に変化を促すのは難しいでしょう。だからこそ、投資対象の財政として、投資家目線から財政のガバナンスにプレッシャーを与えることが鍵だと考えています。民間企業が何をしたいのかわからない経営をしていたら、投資家はその企業の株式を買うか迷ってしまいますよね。同じように財政が納得できないお金の使い方をしていると、投資家は財政に投資しにくくなります。となると、資金調達源である国債・地方債の買い手が減るので、金利を上げざるを得ません。当然、金利が上がると借金しにくくなるので、結果として財政のあり方を見直させるプレッシャーを与えられます。したがって、私たちが財政運営に対して影響力を行使することには、いろんな観点から相乗効果を生み出す可能性があると思います。




