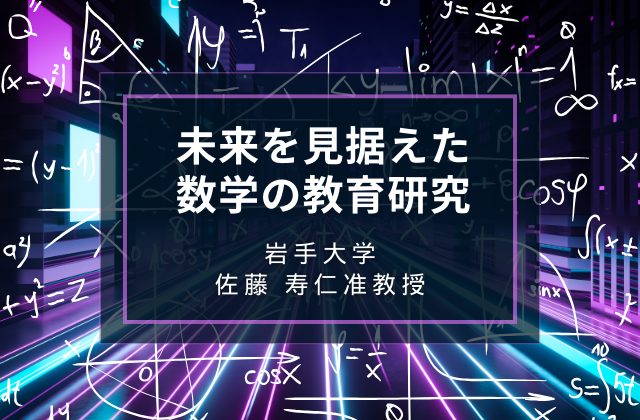ヒトを含めた生物の行動から学べ!「比較心理学」が指し示す超情報化社会をしなやかに生き抜く方法
心理学とは、私たち人間を含めた生物全般の「行動」と「心」の関係を科学的な手法によって研究する学問である。
とはいえ心理学そのものの流れは、ヴィルヘルム・ヴントという人からはじまって、人が幼児期から老年期まで発達していく過程を研究する発達心理学、個人と社会の相互的影響関係を研究する社会心理学などなど、実に裾野が広いのだが、今回、登場していただく大阪大学・人間科学部・行動生理学研究室の松井大助教は、実際の動物を対象にして生物の行動を研究する「比較心理学」を専門にしている。
動物を対象にした実証的心理学というと、生物の条件反射を発見した「パブロフの犬」を連想する人も多いに違いないが、実際に松井先生の話を聞いてみると、「人間とは何か?」という哲学的な大問題への問いかけからはじまって、昨今のSNSや生成AIなどが生み出す超情報化社会を生き抜く方法論にまで行き着いた。
豊富な知識から繰り出されるマシンガントークをどうかお楽しみいただきたい。
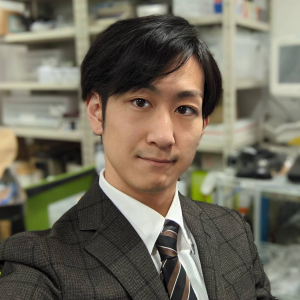
「カラスは黒い」は実は正しくない!?

―――まずは松井先生が研究されていることの概要を説明していただきますか?
僕が研究している比較心理学という学問は(最近では比較認知科学とも呼ばれます)、ひとことで言えば、「ヒトを含めた動物が、なぜそのように行動するのか?」を知るための学問です。
具体的には、カラス、ハト、マーモセット、ラット、イヌなどの動物を対象にして、その動物の身体の形質や環境との接触の仕方などを調べることで、その行動の原因を探ろうとしています。2024年からは、げっ歯類 (マウス・ラット) を用いた行動神経科学的研究を行なっています。
―――そのような研究にたずさわるようになったきっかけは、何でしょう?
そもそも慶應義塾大学に進んだ動機は、哲学を学ぶことだったんです。ただ、いざ入学してみると、情けない話なんですが、同期には僕の能力では刃が立たないほど優秀な人がいて、とても張りあえないなと判断して、哲学とは真逆の科学のほうに進むことにしました。
文学部で科学を専攻するには、心理学と言語学のふたつの道しかなくて、それで仕方なく前者を選択したわけです。
心理学の中でも動物を使った研究をすることになったのは、そのころに読んだユクスキュルの『生物から見た世界』(岩波文庫)という本に影響されたからです。
ユクスキュルは20世紀前半に活躍したドイツの比較解剖学者ですが、この本は彼の生物の神経系の研究から、ダニやウニ、ヒトデなどの生物がどのように世界を見ているのかを解説しています。
例えば人間の目には赤と緑と青の色覚によって周囲の環境の色を識別していますが、鳥は紫外線を見ることができるので人間とはまったく別の世界を見ていることがよく知られています。
人間にとって「カラスは黒い」というのは常識ですが、カラスにとっては種や個体の違いによって別々に見えているはずなんです。
もうひとつ、影響を受けたのは自然人類学の考え方です。この分野では、人間をホモ・サピエンスというひとつの生物としてとらえたとき、どのような進化をたどって現在に至っているのか? 他の生物と比較して、どのような違いがあるのか? といったことを考えていくんですが、人間中心の心理学に対して若干の物足りなさを感じていた当時の僕に「これだな」という手応えを感じさせてくれたのです。
生物としてのヒトはジェネラリストか? それともスペシャリストなのか?

―――松井先生の研究は、他の動物との比較を通じて「人間とは何か?」という問いを解き明かしていくものなのかもしれませんね。
おっしゃる通りです。中でも「人間らしさ」を形づくっているものの本質は何か? ということは、この分野が扱ってきた伝統的なテーマです。
例えば「人間らしさとは、道具を使うことである」と定義したとしましょう。
人間は、道具を手に入れたからこそ、地球上に今のような文明を築くことができたというのは、誰もが納得できる理屈でしょう。
では、ヒト以外で道具を使用する動物は、どのようにしてその能力を獲得したのでしょう?
ニューカレドニア地域に棲息するカレドニアカラスは、倒木の中に潜んでいるカミキリムシの幼虫を捕獲する際、木の葉柄を加工した棒を穴に差し込み、それに噛みついた幼虫を釣り上げるような行動をすることで知られています。
その行動に、人間の道具使用との類似性や連続性は、どれだけあるのか? それを知るために、周囲の環境を調べて生態学的ニーズがどこにあるのかを探ったり、クチバシの形を分析して身体的形質の特徴を分析したり、視覚の仕組みなどを調べてカレドニアカラスの認知機能がどのように形成されているかを見ていくわけです。
―――「人間らしさ」を定義する要素として「道具を使う」というのは説得力のある要素だとは思いますが、それだけではないですよね?
その通りです。
これは学術的な見方というより、僕自身の個人的な観点なんですが、生物を「ジェネラリスト」と「スペシャリスト」という、ふたつの観点からとらえてみるんです。
スペシャリストとして第一に連想されるのがキツツキです。羽軸のかたい尾羽で樹木の幹に垂直に身体を固定し、まっすぐで先のとがった頑丈なくちばしを打ちつけて木の中にいる虫を食べるキツツキは、優秀な捕食者です。森の中などの環境で、彼らに勝てる生物は、そういない。
そう考えてみると、キツツキが全世界に約240種も生息しているのは、彼らの「スペシャリスト」としての能力の結果なのかもしれません。
―――キツツキと比較すると、われわれホモ・サピエンスは「ジェネラリスト」の性質の強い生物ということになりそうですね。
そうですね。ヒマラヤ山脈の高地や、赤道付近の南の島といった極端に異なる環境でも生きられる生物はごく稀なんですが、人間がその数少ない生物のひとつに数えられるのは、得意分野をバランスよく持っていて、環境の変化に順応する能力に長けていたからなのかもしれません。
ちなみにカラスも、地球上のあらゆる環境で生息できる生物のひとつなんですが、人間と違うのは、生息地の環境によって種が異なるところです。どんな環境でも同一種なのは、ホモ・サピエンスくらいでしょう。
言語能力が他の生物と比較して少しだけ優れていて、集団で社会を形成する能力もそこそこ持っている「ジェネラリスト」としての能力が人間を現在に至らしめているというのは、それなりに説得力のある説のような気がします。
では、人間の「スペシャリスト」としての要素はないのか?
僕は、そんなことはないと思っています。他の生物と比較して、突出して優れた人間の能力、それは二足歩行と、その結果として生じた肩の関節の可動域の自由さ、なのではないかと。
―――二足歩行が人間を進化させた重要な要素という話はよく聞きますが、肩の関節という説は聞いたことがありませんでした。
ヒトはもともと四足で歩いていた生物から進化しましたが、四足歩行で犠牲になるのは肩の関節の可動域です。肩を自由に動かすことができないのです。それは、早く走るには、後肢で蹴りだした力を前肢でがっしりと受けとめる必要があるからです。
ただ、人間は二足歩行になることで自由に動かせる肩を手に入れました。人間のように、ものをつかんで遠くに投げられる生物はほかにいないのです。
どちらが先かわからないけれど、手先が器用になったのも、それと関係しています。他の道具を使用生物と比較して、道具を作り、使う能力も突出して高くなった。
もし、宇宙人が地球上の全生物を観察したとして、人間という生物をどう定義するかと考えてみると、おそらく彼らはこんなふうに定義するのではないでしょうか。
「人間は、肩と手を自由に動かすことによって生活史を築きあげた生物である」と。
人間にとって「肩を自由に動かすことができる」という能力は、あまりに当たり前で、それほど重要なものには思えないかもしれないけれど、「ジェネラリストか? スペシャリストか?」という観点から他の生物と比較することで、そのことに気づくことができるわけです。
心理学を学び、安易な自己責任論から開放されよう!
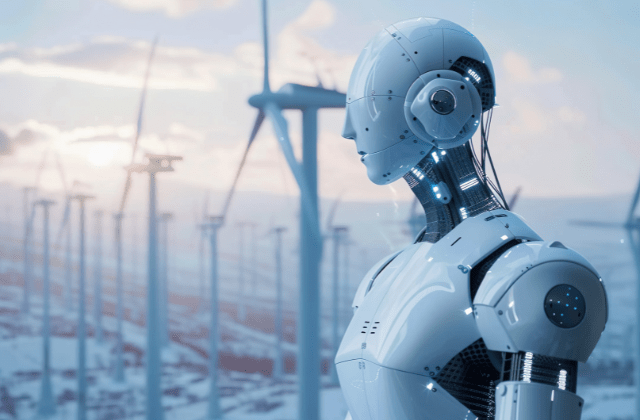
―――松井先生は、動物を対象にした実証的な研究を通じて、「人間とは何か? 生物とは、生命とは何か?」を追及しているという印象がありますが、そうした研究を進めるにあたっての課題は何でしょう?
ひとつ、大きな問題は、比較心理学は生物の「行動」そのものを研究する学問であって、人間が、あるいはその生物が、どのような進化を経て現在に至っているかということはわからないということです。
つまり、異なる生物の行動をどれだけ比較しても、世代間でどんな変化があったかということは見えてこないということ。おそらく、分子生物学や生態学、進化学など、他分野の知見を取り入れていかないと解決できないでしょう。心理学のみで進化を理解することは、不可能に近いことのように思われます。
ただ、僕個人は、そうした比較心理学のジレンマは、弱みであると同時に強みであるとも考えています。
―――「弱みであり、強みでもある」とは、どういうことですか?
心理学は、心のメカニズムを解き明かす学問だからと、心をコンピュータのように解釈して理解しようとする傾向があります。
例えば、外界からのインプットがあって、それが心の内部でどう処理されて、どんなアウトプットとして出てくるかというように。
ところが実際の生物の行動というのは、そんなにスタティック(静的)なものではないんですね。
なぜならすべての生物は、置かれた環境のなかでつねに行動しているからです。インプットがあれば次の瞬間のアウトプットがあり、アウトプットがあればインプットが同時に起こるというのがダイナミック(動的)な生物の世界なんです。
要するに、ChatGPTのように身体を持たない対象は、どれだけ「心がある」ように見えてもそれは錯覚に過ぎず、生物の心をそれと同じようにとらえてはならないということなんです。
―――では、もし今後、生成AIが身体性を持つような技術が開発されたとき、AIが人間に対してどのようなふるまいをするのが適切なのかという問いに答えを出すカギは、比較心理学のアプローチにあると見てよいのかもしれませんね?
まったくその通りだと思うし、僕個人としては、そうあるべきだと思っています。
比較心理学を基礎の1つである行動分析学の言葉に「Organism is always right(生活体はつねに正しい)」というものがあります。
ここで言う「生活体」は、「動物」と同義ととらえてよいでしょう。
動物の行動を分析しようとするとき、正しいか、間違っているかという判断をすべきではないということです。
なぜなら、その動物は自らが置かれている環境に合わせて行動しているのであって、そこに優劣とか差異はなく、行動そのものが解であるはずだからです。
つまり、最初に結論のようなものがあって、「この動物は、この環境の中ではこういう行動をするはずなのに、しないのはおかしい」と判断するのではなく、「この動物の行動は、どのような環境がそうさせたのだろう」と考えるのです。
行動分析学では、こうした考え方を学習児童の問題行動や、学校への不適用、自閉症などの解決に応用しています。
―――「環境」は、「動物の行動」を理解する上で欠かせないファクターなんですね?
ええ、その通りだと思います。
僕は学生に講義をするとき、まず1回目の講義で「心理学を学ぶ3つのご利益」をスライド付きで説明しています。
ひとつめは、「学術的なご利益」。
人間を含めた生物がどのように行動するのかを解き明かすのは、心理学が果たすべき課題なんだということ。
ふたつめは、「社会的なご利益」。
その学術的な成果は、社会問題や臨床での問題を解決するのに大変役立つ可能性があるのだということ。
そしてみっつめに紹介するのが、「個人的なご利益」です。
心理学を学ぶことによって、あなた個人にとっても「安易な自己責任論から開放される」というご利益があるというわけです。
SNSが発達すればするほど、世の中に情報に振りまわされてしまう人が減ることはないでしょう。生成AIがこれだけ注目を浴びていることを考えると、その流れは今後も止まらないと思います。
でも、心理学を学び、生物の行動が環境と密接に結びついているのだということを知れば、そんな世の中でも少しは楽に生きられるようになるのではないでしょうか。
もしかすると、多くの人の心の痛みは、環境を変えるだけで簡単に癒やすことができるかもしれない。
今のような時代だからこそ、ダイナミックな動物の行動に学べ! 身体性をつねに意識して、動物らしさに還れ!
そのことは、学生だけでなく、多くの人に僕から伝えたいメッセージです。
―――興味深いお話、ありがとうございます。

はい
100%
いいえ
0%
はい
100%
いいえ
0%