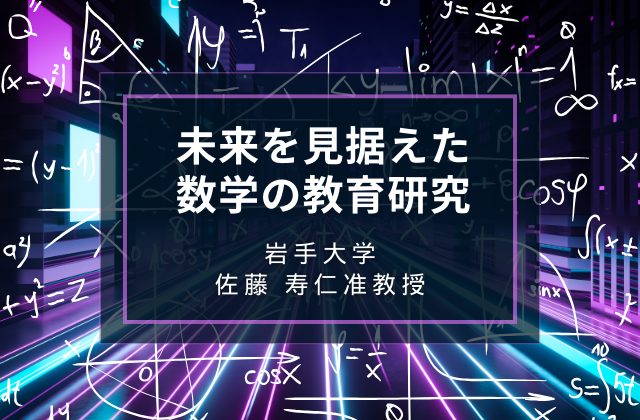子どもたちの世界を広げる鍵:早期英語教育の探究
「英語は世界の共通語」ーグローバル化が進む現代社会において、この言葉を耳にしない日はないだろう。
しかし、日本人の英語力は依然として低迷している。
加速する社会のグローバル化に危機感を抱いた多くの親は、早期英語教育に躍起になっているが、果たして、子どもの頃から英語に触れることは、彼らの未来にどのような影響を与えるのだろうか。
早期英語教育は子どもたちの未来を切り拓く鍵となるのか。
言語教育の第一人者である松本大学教育学部の大石文朗教授と共に、教育学、脳科学、心理言語学、文化論など、多角的な視点から、その可能性を探っていく。

日本人の教育熱心さの秘密!早期英語教育ブームの社会的背景

―――まずは、研究概要と研究テーマについて教えてください。
私の専門は言語文化教育となります。
より具体的には、英語文化教育、異文化コミュニケーション、国際理解教育、異文化理解教育などと表記されることが多い分野です。
大きな枠組みとしては、社会学の一つである言語社会学や社会言語学に含まれる可能性があります。
つまり、社会における文化と英語の関わりを探り、それを教育に生かすことが私の研究テーマです。
特に英語教育の中でも、異文化理解に重点を置いています。
文部科学省は中学校及び高等学校の英語教員免許状の取得に必要な「教科に関する専門的事項」として「英語学」、「英語文学」、「英語コミュニケーション」、「異文化理解」の4分野を指定しているんです。
私が所属する松本大学でも中・高の英語教員免許状の課程認定を受けており、私は「異文化理解」の分野を担当しています。
研究テーマの1つとして、特に北米における日系人に焦点を当てており、日系人の英語習得と異文化理解の視点からも研究を行っているんです。
北米や日系人にフォーカスを当てた理由は、私はハワイ大学マノア校へ進学留学しており経済学を専攻して卒業しました。経済学は広義では、社会のありようを学ぶ学問で、その頃から米国社会に興味があり、また、日系人の方々が身近な存在であったことが大きいと思います。
ハワイ大学マノア校は、人文社会学系の中でも「社会学」、「言語学」、「教育学」の分野で全米トップクラスの実力を持ち、特に日系人研究では世界的にも卓越した評価を受けています。
卒業後日本に帰国し、一時期は留学支援企業に勤務しており、その企業から駐在員として米国へ派遣されました。駐在先がカリフォルニア大学バークレー校の近郊でしたので、駐在員として働きながら、大学院ではバークレー校とも多くのジョイントプログラムを組んでいる、サンフランシスコ州立大学大学院にて教育学修士号を取得しました。
米国駐在を終えて帰国後は大学教員となり、英語教育に携わるとともに、語学研修も担当し、カナダや他の英語圏への海外研修などを実施する機会もありました。 その後、大学に勤務しながら名古屋大学の大学院にて二つ目の修士号を取り、さらに名古屋市立大学の大学院に私の興味のある北米文化に関する領域の先生がいて、その先生の元で博士号を取得しました。
―――英語の早期教育が重要だと感じている親御さんは多いと思います。早期英語教育を推進する社会的背景にはどのようなものがありますか?
英語の早期教育がもてはやされている社会的背景には、いくつかの要因があると考えられますが、大きく分けて二つあると思います。
一つ目は、日本人の教育に対する価値観が他の民族と異なるという点です。
例えば、戦前、日系人は自分が食べることができなくても、子どもの教育を優先し、その結果として日系社会が北米などで大きな勢力になっていきました。
しかし、不幸なことに太平洋戦争が勃発し、多くの日系人が強制収容所に入れられたのです。
ハワイでは当時の日系人口が全体の約3分の1以上を占めていたため、全員を収容することはできませんでしたが、教員や弁護士など、社会の中心になりそうな人物は一時的に収容所に集められ、米国本土に送られました。*
せっかく教育に力を入れていたにもかかわらず、このような悲惨な歴史があったのです。
このように、日本人は昔から教育を非常に重要視する傾向があります。
これは明治時代以降、教育が立身出世や安定した生活を実現する手段として認識されるようになったことが要因です。
明治維新以前は、生まれによって職業が決まる社会でしたが、明治維新による制度改革と文化革命により、教育次第で大きな出世が可能になりました。
そのため、親は自分が我慢してでも子どもの教育を優先するようになったのです。
この傾向は、海外に移住した日本人だけでなく、現在の日本の親御さんにも見られます。
もう一つの要因は、現代社会に対する危機感と不安感だと考えられます。
今の親御さんの多くは、バブル崩壊後の「失われた30年」を経験し、終身雇用の崩壊や大企業の倒産を目の当たりにしてきました。
先の見えない社会に対する不安から、子どもの教育にはより熱心になっているのです。
その中でも特に早期英語教育が注目されているのは、グローバル化が進む日本社会の現状と関係しています。
インターネットで世界中とつながり、国際共通語として英語が使われている現在、トヨタなどの日本の大企業でも、ある役職以上にはTOEICのスコアや英語能力が要求されるようになってきています。
また、国際連合では、6つの公用語が定められていますが、実際の作業言語として使われているのは主に英語とフランス語であり、ほとんどの文章は英語です。
さらに、会議における休憩時間などの立ち話で話し合われたことが発端となって、大きな動きにつながることもあると言われています。
つまり、公式な場だけでなく、プライベートなコミュニケーションにおいても英語力が重要になってくるのです。そういう意味では交渉ごととは、人と人との信頼関係の上に成り立っているので、いくら翻訳機が発達しても機械を介しては信頼関係は成立しにくいものなのです。
国際舞台で活躍するには、英語力が重要であり、ネイティブレベルの英語力があるかどうかで、人脈の形成や国の発展に大きな差が出てくるということになります。
加えて、教育熱心な親にとっては、子どもの教育のゴールは大学受験だと言えるでしょう。
英語は主要な受験科目であるため、早くから取り組んでおくことが有利だと考えられているのです。
他にも様々な要因が考えられますが私としてはこれらのように、「昔からの日本人の教育重視の価値観」と「現代社会に対する危機感・不安感」という主に二つの要因が組み合わさって、早期英語教育への関心が高まっているのだと考えています。
参考: 立命館大学「太平洋戦争中のハワイにおける日系人強制収容」日本の英語教育の変遷ー実用から教養へ、そして受験英語の弊害とは?

―――周囲を見渡すと、なかなか英語を流暢に話せている人は多くないと感じるのですが、これまでの日本の英語教育はどのようなものだったのでしょうか?これまでにも英語の早期教育の重要性は唱えられてきたのですか?
歴史を振り返ると、日本の英語教育にはいくつかの大きな変化のターニングポイントがあったと思います。
幕末から明治前期、特に1899年頃までは、高等教育における学問は主にお雇い外国人によって行われていました。*
当時はまだ教えられる日本人が育っていなかったため、東京帝国大学(現在の東京大学)でも外国語、つまり英語で授業が行われていたのです。
このような状況下では、英語を学ばなければ学問ができないという言語環境にあったのです。
これは中世のヨーロッパでもみられた現象で、大学レベルではラテン語が使われており、専門書を読むにはラテン語の習得が不可欠でした。
明治末期から大正時代になると、日本人教員が育ってきたことで、お雇い外国人に頼る必要がなくなり、日本語で授業を行うことが可能になりました。
また、日本語に翻訳された専門書も多く出回るようになり、英語ができなくても学問ができる環境が整ってきたのです。
その結果、学習者にとって英語の実利的な面が希薄になり、英語の学習目的や意義が問われるようになりました。
ある研究者は、このような社会的要因が英語教育における実用的な英語から教養中心の英文学への転換をもたらしたと述べています。
そして、教養中心の英文学への転換は、人間性や人格形成のための「教養としての英語教育」が重視されるようになりました。
また、この「教養としての英語教育」は、日本語への訳読を中心としており、お雇い外国人教員には不向きだったので、日本人教員が英語を教えることに新たな意義や価値観を付与したのです。
さらに、中等教育への進学率の上昇とともに受験競争の激化につながり、訳読式の英語教育が受験英語として利用され、コミュニケーションの道具としても人格形成のための教養教育としても機能しなくなってしまったのです。
英語は単なる選別のための道具となり、本来問われるべき英語教育の意義や目的が希望校合格という目標にすり替えられてしまいました。
近年では、リスニングなどを取り入れることで是正しようとする動きはありますが、選別の道具としての側面は残っています。
次に、英語の早期教育ブームについてですが、1930年代のブームからが歴史的には顕著だと思います。
1933年に日本が国際連盟を脱退した際、誤解された日本のイメージを是正するために国際交流が盛んになり、英会話ブームが起こったのです。
また、1945年の敗戦後、進駐軍がやってきたことで英語の重要性が再認識されますし、その後、1960年代の東京オリンピック、1970年代の大阪万博などでも国際協力の共通語としての英語学習が促進されました。
特に、1980年代はバブルの時代で、進学留学や語学研修が増加したのです。
1990年代からは、円高の影響を受けて日本企業の海外進出が活発化し、物価や人件費の安い海外に拠点を設けるようになりました。
そして現在では、外国人のインバウンドの増加を目の当たりにして、グローバル化の流れを一般の人々でも肌で感じるレベルになっていると思います。
2022年のJETROの調査によると、日本企業が海外進出する主な理由として、83.1%の企業が市場規模と成長性を挙げています。*
日本国内の市場が縮小傾向にある中、中国やアメリカなどの巨大市場や新興国に販路を拡大することが重要になっているのです。
日本が現在の豊かさを維持するためには海外との関係性が不可欠で、諸外国との協働なしでは、日本は人口減少とともにジリ貧になることは明らかです。
このような経済的な理由からグローバル化や国際化の重要性が叫ばれており、教育に熱心な親は、子どもに国際共通語的役割をはたしている英語教育を受けさせたいと考えているのではないでしょうか。
参考:
1)金井圓 東京大学名誉教授「 著作・記録に見る「お雇い外国人」の足跡」
2)JETRO「 2022年度 海外進出日系企業実態調査」
言語習得の秘密を解明!3人の研究者に学ぶ、発話・語彙・文法の発達

―――早期教育は、英語の習得に実際にどのような効果をもたらすのでしょうか?大石先生の著書にもあった言語習得理論と早期英語教育の関係性を教えてください。
私が書いた「第二言語習得理論の視点からみた早期英語教育に関する研究・・・小学校英語教育に対する提言の試み・・・」では、ペンフィールド、クラッシェン、スタインバーグという3名の研究者の言語習得理論について取り上げています。
ここでは、発話、語彙の拡大、文法という視点からご説明しましょう。

ワイルダー・グレイヴス・ペンフィールドは、言語を習得するための専門的なメカニズムの観点から、4歳から10歳の間が大脳生理学的に言語習得に最適な年齢だと主張しているんです。
年齢とともに、脳に備わっている言語習得に対する特殊な能力が減退していくとしています。第二言語の中枢言語の確立は、母語を介さずに反射的に第二言語を発するために必要不可欠なものだと述べています。
ペンフィールドは脳科学的な見地からこのような主張をしており、元々は失語症の研究から言語習得について研究してきた学者です。
多くの大脳生理学の研究者が彼の説を支持しており、人が言語を操ることができるのは中枢言語が確立されるためであるとしています。
よく知られているように、左脳が損傷を受けると、運動機能がその役割を補うようになります。
これは脳の可塑性が若い時期にはまだ高いからです。
しかし、高齢になると、どちらかの脳が傷ついた場合、その可塑性は失われてしまいます。
この中枢言語が確立されやすい状態である脳の可塑性、つまり柔らかい状態を重視し、第二言語の早期開始に対して肯定的な立場をとっているんです。

スティーブン・クラッシェンは心理言語学者であり、言語能力の向上を「習得」と「学習」という観点から論じています。
「習得」とは、伝達のために言語運用する能力を伸ばすことであり、一方、「学習」とは文法などの規則を知ることで、伝達能力を養うことにはならないと述べています。
つまり、言語運用能力と言語知識という側面から第二言語教育を捉えているのです。
クラッシェンは、第二言語習得における年齢差について、単純に子どもの方が成人より優れているとは言えないと主張しています。
短期的に見れば、成人の方が子どもより第二言語習得は早いと考えており、その理由として、以下の三つの要因を挙げています。
まず第一に、成人は会話の運びや自分たちに向けられたインプットを調整して理解しやすいものにすることができるということです。つまり、成人は相手の目や状況から察することができ、言語がわからなくてもコミュニケーションを取ることができます。
例えば私の経験から説明しますと、学生を語学研修に連れて行き、英会話中心の授業を行うことがよくあるんです。
その際、銀行に行って「スキット」のようなロールプレイを行い、口座開設などの場面を設定して練習させることがあります。
興味深いことに、英語のできない学生でも、授業は簡単だと言うことが多いのです。
しかし、実際に試験をしてみると、全くできないことが明らかになります。
スキットでは、動作も含めて練習するため、学生は銀行に行ったらどのようなことをするのかを大まかに理解してしまいます。
つまり、言葉そのものを理解しているのではなく、状況を理解しているのです。
これはジグソーパズルに例えることができます。
例えば、モナ・リザのジグソーパズルを考えてみてください。パズルが半分ぐらい完成していれば、これがモナ・リザの絵だと全体像を把握できます。
頭の中で補完することができるのです。しかし、見たこともない絵に関しては、8割ぐらい完成していてもどういったものかわかりません。
つまり、成人の学習者は、言語ではなく、他の要因を使って状況を調整し、理解してしまうのです。
第二に、成人は第一言語とモニタリングを使って初期段階の発話を促進し、それがさらなるインプットを呼び込みます。
母語の知識を活用して、正しい表現や間違いを判断することができるのです。
年齢の小さい子は、何が正しい、何が間違っているという判断はできません。
最後に、成人は一般的な知識を多く持っているため、コミュニケーションの内容を様々な観点から判断できるということです。
このように、成人は子どもには備わっていない様々な能力を活用できるため、特に教室という特殊な環境下では、第二言語習得に関する年齢差はほとんどないとクラッシェンは主張してるんです。
心理言語学的見地から、第二言語の習得効率を決定づける要因は、年齢差における身体的要因ではなく、情意的な要因であるとクラッシェンは仮定しています。
学習者が不安感、不信感、挫折感といった否定的な感情を抱いて学習している場合、まるでフィルターがかかったかのように学習内容が吸収されず、表出もしないとして、そのフィルターを「情意フィルター」と名付けています。

ダニー・D・スタインバーグは心理言語学者ですが、運動技能の視点から第二言語における母語話者並みの発音習得については、子どもの方が成人よりも概して長けていると述べています。
スタインバーグはクラッシェンとは異なり、特に発話における発音について子どもの優位性を指摘しているのです。
スタインバーグによると、発音は脳に制御された発話機関の運動によって成立しています。
加齢とともに脳の中枢機能が変化し、9歳から12歳あたりで新たな運動技能を獲得する能力は衰退し始めるとしています。
つまり、発話は運動技能であり、声帯、舌、口などの発話器官の筋肉によって制御されるのです。
スタインバーグは体操やピアノを例に挙げ、7歳で始める方が27歳で始めるよりも上達すると述べています。
これは運動機能が関係しており、若いうちは筋肉が柔らかく適応するからだと説明しています。
次に、語彙力に関して、ご説明しましょう。
語彙の拡大に関しては、ペンフィールドは記憶力が重要だと言っています。
記憶力は加齢とともに衰えていくとし、これを白地の言語板に例えているんです。
人間はこの世に生まれるときに白地の言語板を持ってきますが、まもなくいろんな単位で埋め尽くされていきます。
白いノートに書き込むスペースがなくなるように、経年によってだんだんと書き込むのが困難になってきます。子どもが成年になるまで1カ国語しか用いないなら、第二言語を学ぶ際にはすでに書かれている母国語のシンボルを用いてしまい、新しく覚える第二言語の発話の音を模倣する代わりに、母語に似通ったアクセントをつけてしまったり、間違った構文に再配列させようとさえしてしまうと主張しています。
一方、クラッシェンは語彙の拡大については、年齢による差はないとしています。
加齢とともに衰えていく記憶能力が語彙の拡大を決定付けるのではなく、学習者がどのように何を学ぶかという学習の質が重要だと考えているんです。
インプットが極めて重要であり、現在の学習能力よりも少し高いレベルのインプットが与えられるべきだと主張しています。
適切なレベルのインプットを理解することによって言語は習得されるのです。
また、語彙の拡大には学習者が自ら進んでインプットを理解しようとするコミュニケーションの願望が不可欠であり、教師が学習者の興味を引く題材を提供することが重要だとしています。第二言語における母語の干渉は、単に第二言語が未熟であるがために生じるものだと言っています。
スタインバーグはペンフィールドと同様に、言語習得の基本は記憶力だと考えているようです。
特に第二言語の語彙学習では棒暗記つまり単純連合学習が不可欠だと主張しており、この棒暗記は加齢とともに衰退していきます。
8歳頃から衰退が始まり、12歳頃からさらに加速されるため、早期英語教育を支持しているのです。
最後に、文法に関する発達の差異をご説明しましょう。
ペンフィールドは十分に幼い時から第二言語に触れていれば、文法を教わらなくとも語の配列の規則を習得していくと述べています。
そもそも言語とは目的を達成するための手段であり、言語そのものを学習すべきではないことを強調しています。
ペンフィールドによれば、文法を含めた言語そのものの活動は脳内に形成されるニューロンのパターンであり、諸々の反射によって可能になるのです。
文法などの語の配列に関するパターンは全て脳内にある中枢言語に保存されており、無意識的に中枢言語に規則性が反射的に蓄積されています。
クラッシェンは前に述べたように、成人の第二言語習得の方法を「習得」と「学習」の二つに分けて論じていますが、「習得」とは言語の力を伸ばす自然な方法であり、無意識の過程だと述べているのです。
子どもが言語能力を身につける過程はこの「習得」であり、言語そのものを意識せず意思を伝え合っているため、子どもには言語能力を獲得しているという自覚はなく、身に付いた文法は直感的なものだと述べています。
他方、「学習」とは言語について知ることであり、言語の形式的知識を得ることだとしています。
「習得」は無意識的ですが、「学習」は意識的であり、言語の規則について意識的に知識を身につけることなので、成人にとっても可能だとしています。
スタインバーグは学習環境に着目し、自然的場面と教室的場面では子どもと成人の学習効率が異なると述べているんです。
自然的場面とは社会活動を行う中での言語運用を意味し、そのような場面では子どもに有利に作用しますが、社会の状況によっては成人外国人に対して敵対的な環境の場面さえあると指摘しています。
例えば、子どもなら無邪気で許されることでも、大人なら相手も一定の語学力を期待し、その程度しか話せないのか、と上から目線で馬鹿にしてくることがあるでしょう。
つまり、学習環境によって言語習得の難易度が変わってくるのです。
しかし、自然環境では子どもの方が有利ですが、教室の場面では成人が子供よりも優位な立場にあると指摘しています。
成人は教室という学習環境を十分に心得ており、注意を払い集中すること、長時間静かに座っていることができるのです。
スタインバーグの主張は、開始年齢の違いによる文法力の到達度の差はないとしています。
成人の中には、文法に関しては母国語話者と判定される人々がいるため、第二言語の文法学習には臨界期が存在しないと断定して間違いないと述べています。
実際に、受験の文法に長けた日本人の中には、ネイティブよりも文法に精通している人も少なくありません。
以上が、ペンフィールド、クラッシェン、スタインバーグの3名が唱えている言語習得理論と早期英語教育の関係性の概要となります。
心の教育なくして英語習得なし?異文化理解と愛情が言語学習の鍵を握る!

―――実際のところ、早期英語教育には効果があるのでしょうか?子どもが英語を話せるようになるためには、小さい頃からきちんと教育を施していくことが必要となるのでしょうか?
バイリンガル教育の先駆けとして、カナダが現在イマージョン教育を行っており、英語とフランス語を公用語としています。
トータルイマージョン教育の場合、約5,000時間の言語接触が一般的だとされているのです。
しかし、5,000時間も強制的に学習させられると、英語嫌いになってしまう可能性があります。
まずは子どもの性質を見極め、いかに英語学習に関心を向けさせるかという環境作りが大切なのです。
教育学では、認知能力と非認知能力という概念が言われています。
認知能力はIQなどの測定可能な知能を指し、非認知能力は測定できない能力、つまり「やる気」、「忍耐力」、「協調性」、「自制心」など、社会性に結び付く能力を指すのです。
最近の脳科学では、認知能力と非認知能力は密接に関係し合っていると主張されています。
あまりにも過度な知識の詰め込みに特化した早期英語教育は、子どもの人格形成に悪影響を及ぼすことが明らかになっているそうです。
知識の詰め込みは大脳皮質に情報という刺激を与えますが、大脳皮質よりも内側にある大脳辺縁系という、喜怒哀楽の感情をつかさどる脳の部分と連携がとれていないと、短期的な記憶にしかなりません。
逆に、トラウマのように強い恐怖という感情を覚えた時は、その内容が記憶として長く残ってしまいます。
つまり、喜怒哀楽が伴わないと知識は定着しにくいのです。
大脳辺縁系は、小さい頃に親の愛情と信頼を受けることで育つと言われています。
知識を詰め込むだけの早期教育では、大脳皮質と大脳辺縁系の連携がうまくいかず、人格形成に問題が生じる可能性があります。
したがって、小さいうちから単語を覚えさせるような詰め込みの英語教育ではなく、温かい心を養うことこそが認知能力の発達につながるのです。
感情をつかさどる大脳辺縁系が発達してこそ、大脳の連携がうまくいきます。
極論を言えば、小さい子どもにとって最も大切なのは、親がたくさん愛情を注ぎ、まずは温かい心を育むことです。
そして、ある程度言葉が分かるようになってから知識を詰め込むのではなく、親が愛情を注ぎながら互いの信頼関係のもと、早期英語教育などに取り組むべきなのです。 そうでないと、英語嫌いを増やしてしまう可能性もあります。
一部の教育熱心な親にみられる点数という結果を追い求める風潮は、偏差値主義の現在の受験競争にも原因があるのかもしれません。日本の一般入試は、ある意味椅子取りゲームなので、他人のことを考えていては希望校に受かりません。合格という椅子のみを見据えて、直線的に取りに行くことが求められ、合否という結果でしか評価されないという現実があります。
ただ、受験も徐々に変わってきており、総合型選抜入試、いわゆるかつてのAO入試が多くなってきています。これは、アメリカの入試制度を参考にしたもので、学力以外の高校時代の活動等など社会性を評価するものです。
今まであまりにも認知能力の評価に偏っていましたが、非認知能力が受験でも評価されるということは、ますます家庭での小さい頃からの「心の教育」が重要になると思います。
―――土台である心の教育ができていないまま、競争社会に晒される子どもたちが少なくないのですね。そのような中でも、今後も日本では早期英語教育は重要視されていくのではないかと思います。早期英語教育を受けている子どもたちへの将来の展望や現在子育てに励まれている読者の皆様にメッセージがあれば、教えてください。
英語習得と異文化理解は表裏一体のものであると言えます。
私の専門である言語文化教育の分野では、1960年代からノンバーバルコミュニケーション、つまり非言語コミュニケーションの重要性が指摘されてきました。
アルバート・メラビアンという心理学者が提唱した「メラビアンの法則」によると、コミュニケーションにおける言語の役割は7%程度で、残りの93%は表情や身振り、声のトーンなどの非言語情報から相手を理解しているとされています。
つまり、コミュニケーションの本質は言葉だけでなく、相手の意図を察することにあるのです。
認知言語学の観点からも、人間は言語を単なるきっかけとして、自分の心の中にある風景を見ているに過ぎないと言われています。
したがって、外国の価値観や文化を学ばない限り、真の意味での言語コミュニケーションはできないと言えるでしょう。
異文化理解とは、自分とは異なるものを認めることから始まります。
しかし、人間には往々にして同質性を求め、異質なものを排除したいという本能があります。
特に日本は、移民で成り立った米国などと比べるともともと同質性が高いので、村社会的な性質が強くなりやすく、異質排除に陥りやすい一面があります。
この傾向は大なり小なりどのような社会にもあります。異質という未知なものは不安を引き起こすため、馴染んだものに心が落ち着き、ひいては自分の身の安全を確保することにつながると捉えるのは人間の本能なのかもしれません。
その一方で、人間には矛盾した性質もあります。
異質なものを排除する反面、違うものに憧れを抱くのです。
外国に行きたいと思ったり、新しい食べ物を試してみたいと感じたりするのは、この性質の表れと言えるでしょう。
多様性に対する理解を深めるためには、同質主義や異質排除の傾向ではなく、「違うものへの憧れ」に考え方の方向性をもっていく必要があります。何事も先ずは、興味や関心に基づく、「憧れ」が原動力になると思います。
加えて、日本社会が諸外国と良好な関係を維持していくためには、多様性を認め、それらを受け入れざるを得ません。
そのためには、幼少期から「違い」に対する寛容性を養うことが重要です。
そのためには、幼い頃から継続して家庭教育と公教育によって社会全体で長期的視野に立って取り組む必要があると私は考えています。
英語教育とは単に言語スキルを身につけるだけではなく、異文化理解教育が目指すところの多様性を認め、寛容性を養う、いうなれば心の教育も包括していると私は捉えています。

はい
0%
いいえ
0%
はい
0%
いいえ
0%